
尾瀬ヶ原 〜尾瀬の野山に深まる秋(前編)〜
 |
(前編) |
【福島県 檜枝岐村・群馬県 片品村 令和5年9月15日(金)】
4年ぶりに訪れた尾瀬。その間巷では様々なことが起こりましたが、何一つ変わらず雄大な自然が当たり前にそこにありました。
今回の尾瀬歩きは昨日から。まず鳩待峠をスタートしてアヤメ平へ。そこから富士見峠を経て八木沢道で見晴に下り、昨夜は見晴の尾瀬小屋で一泊しました。(昨日の様子はこちらとこちら)
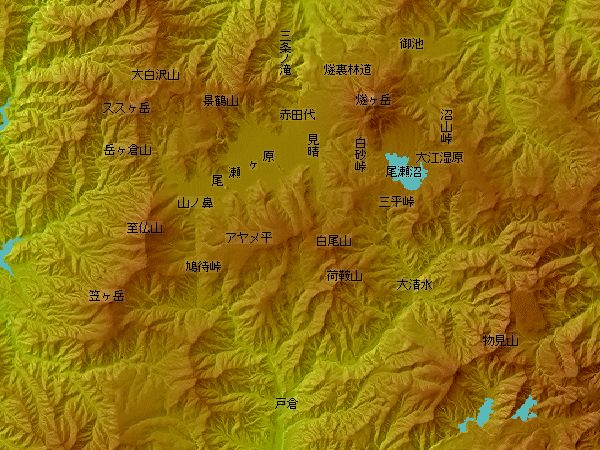 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
|
| 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
今日は尾瀬ヶ原を歩きます。見晴から下田代、中田代、上田代と尾瀬ヶ原を縦断し、山ノ鼻を経て鳩待峠に戻るというルートです。いわば尾瀬の銀座通りを歩くようなものですね。
昨夜は20時消灯でしたが、歩き疲れていたこともあってすぐに寝入ってしまいました。そして、夜中、時刻は分かりませんが、眠りが浅くなったタイミングで結構強めの雨音を聞きました。半分寝たまま、ぼんやりと
”ああ、明日は雨の中の歩きか” と考えたことを覚えています。
朝、起きてみると雨は小雨になっていました。若干気持ちが軽くなりましたが、でもこの分ではレインウエアの着用は必至です。
6時朝食。身支度を調えて7時に尾瀬小屋を出発です。
| いざ出発 |
レインウエアをしっかり着込んで尾瀬小屋の玄関を出ると、雨は更に弱まり霧雨くらいになっていました。いいぞいいぞ。
| 下田代 |
まずは下田代を歩いて行きます。視界は1、2kmといったところでしょうか。
| エゾリンドウ |
尾瀬の湿原で見かけるリンドウは概ねエゾリンドウ。逆に森の中で見かけるのはオヤマリンドウであることが多いです。花の付き方や葉の形などが見分けポイント。
木道は正面の拠水林に向かって伸びています。おや、雲の切れ間に青空が覗いていますね。
| アブラガヤ |
尾瀬の湿原を代表する植物の一つ、アブラガヤです。人の背丈ほどの高さになります。
| 六兵衛掘 |
さっき見えていた拠水林までやって来ました。これは六兵衛掘と呼ばれる川に沿ってできた林です。
拠水林とは川の両側にできた自然堤防を土台として繁る林のこと。湿原の外から流れ込む川は土砂を運んできて流れの両側に堆積させるので自然堤防ができるのです。そこは土壌が安定していて根が張りやすいので樹木が育つという理屈。自然堤防なので必然的に拠水林の幅は薄いのです。
| ゴマナ |
拠水林の中で見かけたゴマナ。雨に打たれて少しやつれたように見えます。
| 六兵衛掘 |
この六兵衛掘は見晴の東側の山中から流れ出し、下田代を二分するように蛇行して、最終的には沼尻川に合流します。「二分する」とはどういうことかというと、下田代は俯瞰すると概ね正方形をしていて、沼尻川はその外周を匚のように流れています(右下から右上へ)。六兵衛掘は右下から左上への対角線のように流れて下田代を二分しているということです。(ただそれだけの情報)
| トモエソウ |
これは花が終わった後の花序ですね。トモエソウでしょうか。
| オゼミズギク |
オゼミズギク。昨日も見晴で出会いました。花の季節の終わり際を飾る花の一つです。
| 沼尻川の拠水林 |
またまた正面に拠水林が見えてきました。あれこそは沼尻川の拠水林。下田代と中田代を分ける境界線です。
さっき青空を見て天気の回復を期待しましたが、また霧雨が降ってきました。なかなか思うようにはいきませんな。
さすがは沼尻川。川が大きい分、拠水林も規模が大きいです。
川べりの様子。ここだけ見ると深い森の中のようです。
| 竜宮小屋 |
拠水林を抜けるとすぐに竜宮小屋があります。暑くなってきたのでここでレインウエアのズボンを脱ぎました。それだけでもずいぶん身軽になって歩きやすいです。さあここからは中田代です。
| 竜宮交差点 |
竜宮小屋を過ぎてほどなく、木道の交差点が現れました。竜宮交差点です。右へ折れるとヨッピ橋へ、左に行けば長沢新道を経てアヤメ平へ、直進すると山ノ鼻へ。
時刻は8時。見晴からここまでで1時間というスローペースですが、yamanekoとしてはこれで通常運転です。
| イワショウブ |
イワショウブ。花が終わり実を付ける段階です。
| イワオトギリ |
これはイワオトギリでしょうか。葉を裏返してみると黒点が多数ありました。赤褐色のものは果実。
| ミツガシワ |
ミツガシワの花期は5月から8月ですが、この場所では毎年この時期まで咲いています。
この花を初めて見たのは島根県の赤名湿地でのこと。浅い沼一面に群生していました。静かな森の中のことで鳥肌が立ったことを覚えています。もう20年以上前のことです。
| オオバセンキュウ? |
難しい植物が続きますね。これはオオバセンキュウか。
| ゴマナ |
天気はいまいちですが、次々と花が出迎えてくれるので楽しいです。これはゴマナですね。
| ハンゴンソウ |
どちらかというと林の中で出会うイメージのあるハンゴンソウ。開けた湿地にも元気に生えていました。
| 竜宮 |
木道が「Φ」文字のようになっている場所にやって来ました。直進する道を左右にそれるように木道が延び、やがて元の道に合流します。それた先に何があるのかというと、写真のとおり小さな池(?)。今は特段何事も起こっていませんが、水量の多い時期には左の池に水がどんどん流れ込み、吸い込んだその水が約30m離れた右の池から滔々と湧き出すという不思議な現象が見られます(水の多いとき)。このような現象が起きるところを「竜宮」というのだそうです。
| オオマルバノホロシ |
この赤い実はオオマルバノホロシのもの。ナス科に特有の形状をしています。漢字では「大丸葉白英」と書き、「白英」とは同じナス科のヒヨドリジョウゴのことだそうです。ヒヨドリジョウゴも似たような朱い実を付けますが、ほぼ球形であるところがオオマルバノホロシと違うところ。
| 牛首遠望 |
木道の先にこんもりとした小山。湿原に半島のように突き出した起伏で、「牛首」と呼ばれています。牛首のところに流れる上ノ大堀川までが中田代。そこから先が上田代になります。
| ヒツジグサ |
池塘に浮かぶヒツジグサの葉。もう紅葉が始まっていますね。
| 下の大堀川橋 |
下ノ大堀川にかかる下の大堀川橋。橋の名前は「ノ」ではなく平仮名の「の」でした。この辺りが中田代のちょうど真ん中くらいになります。
| 下ノ大堀川 |
下ノ大堀川は湿原内に水源を持つ川なので、拠水林はありません。
| 夢の中の彷徨 |
「ここはいったいどこなんだ」と歩きながら呟いてしまいそうな、そんな風景の中を行きます。
| サワギキョウ |
サワギキョウはその名のとおりキキョウの仲間。ただ、キキョウの花冠は筒状ですが、サワギキョウは唇形と、ずいぶん見た目は違います。大きさは大きいものでは1mくらいに成長しますが、ここは低栄養だからか、ずいぶんと小振りです。
| 牛首分岐 |
8時55分、牛首分岐までやって来ました、ここを右手に折れるとヨッピ橋に至ります。
牛首分岐を直進ししばらくするとまた拠水林が見えてきました。上ノ大堀川が作った拠水林で、中田代と上田代を分かつ林です。
| 上の大堀川橋 |
その上ノ大堀川を渡ります。ちょっと年季の入った橋ですね。
| 至仏山現る |
上田代に入ると尾瀬の雄、至仏山が姿を現しました。圧倒的な存在感に「おおーっ」と声が出てしまいます。
さあ、上田代に入りいよいよ尾瀬ヶ原も終盤。これから至仏山の麓の山ノ鼻に向かいます。(後編に続く)