
燧ヶ岳 ~秋澄む峰に遊ぶ幸せ(後編)~
 |
(後編) |
【福島県 檜枝岐村 平成24年9月15日(土)】
「秋澄む峰に遊ぶ」 今回の燧ヶ岳登山はまさにそんな感じです。(前編はこちら)
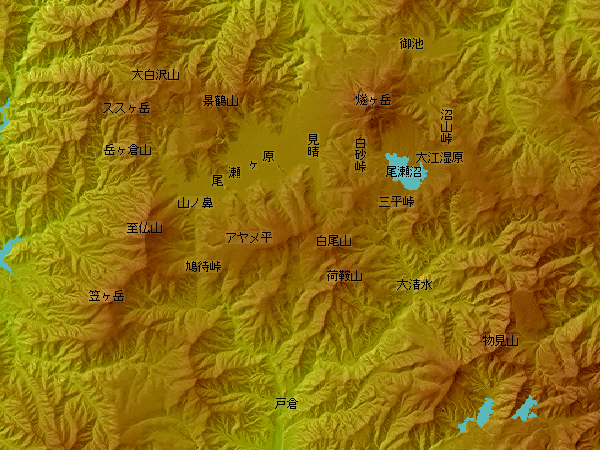 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
|
| 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
尾瀬沼東岸の尾瀬沼ヒュッテを発ってから4時間。静かな森の中をのんびりと登って、ここ俎嵓(まないたぐら)に到着しました。これから西側にある双耳峰の片割れ、柴安嵓に向かいます。
| 柴安嵓 |
むう、なかなかの面構えです。ここから下ること50mで鞍部に至り、そこから一気に60m登ると燧ヶ岳の最高峰に到達します。そしてその頂に立つと眼下には尾瀬ヶ原が広がっているはずです。
柴安嵓山頂の北側は深く削れた谷になっています。この激しく荒々しい崩壊地も燧ヶ岳が持つ表情のうちの一つですが、なかなかこの面をとらえた写真は見ることはないと思います。
山々を削る深い谷は只見川の源流部。もともとは尾瀬ヶ原から流れ出したものです。写真最奥の山並みは越後山脈。正面は荒沢岳です。その左手には雲の中に越後駒ヶ岳や八海山などもあるはずです。
| 鞍部 |
岩場を用心しながら下って鞍部に到着。俎嵓からは遙か下に見えていましたが、下ってみると思ったより早かったです。
| |
|||
| 柴安嵓山頂 |
柴安嵓の急斜面にとりついて黙々と登ること10分、ついに燧ヶ岳の最高地点に立つことができました。時刻は11時30分です。
山頂は尾瀬ヶ原側に緩く傾斜していて、案外広かったです。多くのグループが腰を下ろして昼食をとっていました。
| 尾瀬ヶ原 |
そしてこれが2年間思い描いていた燧ヶ岳からの尾瀬ヶ原です。そう、2年前に至仏山から、そして尾瀬ヶ原から燧ヶ岳を眺めて、あの頂からこっちを見たらどんなだろうと思っていたのです。やっと叶いました。
手前の広大な森は燧ヶ岳の山麓。その森が切れるところ、小さな白い点のように見えているところが見晴という場所で、そこには山小屋が5、6軒あります。yamanekoもそこにある第二長蔵小屋に泊まったことがあります。その見晴からまっすぐ木道が延びているのが分かりますね。拠水林でいくつかに分割されたような尾瀬ヶ原を木道が貫いています。そしてその先には堂々たる山容の至仏山。…しみじみ、幸せです。
しばしの間立ち尽くした後、腰のホルスターからカメラを取り出し、めまぐるしく流れていく雲の一瞬の隙間をとらえてこの写真を撮りました。
| 昼食 |
昼食はおにぎりです。前日に宿に注文しておくと、翌朝受け取ることができます。おかずは煮込んだゆで卵と魚肉ソーセージ。あと、のり佃煮と漬け物がそれぞれビニールパックに入っています。汗をかいた後の食事になるので塩分は濃いめです。
| 俎嵓 |
柴安嵓山頂では40分ほど休憩をとりました。さて、これからまた俎嵓に戻ります。上の写真は柴安嵓から眺めた俎嵓。午前中、あの右側の稜線の登ってきたのです。俎嵓の背後、遠くに見えるのは帝釈山。尾瀬エリアの東側の辺縁に位置する山で、オサバグサの群生地があることで知られています。ここからは直線距離で15㎞ほどです。
12時10分、スタートです。
ほぼ目の高さに見える俎倉の頂上。平坦なところがないので、立っている人が多いですね。
| 越後の山々 |
柴安嵓から下る途中、北西方向を眺めたところです。左手前に見えるやや台形の大きな山は平ヶ岳(2141m)。この山はアプローチが長いので、日帰りするには熟達者のレベルが必要とのこと(ガイドブック記載で片道7時間!)。平ヶ岳の一列後の山並み、写真右手にある山が荒沢岳(1969m)。名前のとおりギザギザです。そして最後列、写真中央にやや薄く見えているのが越後三山の中ノ岳(2085m)(左)と越後駒ヶ岳(2003m)(右)です。直線距離で約25㎞。奥行きのある風景です。
| 俎嵓山頂 |
12時40分、再び俎嵓に戻ってきました。山頂はこんな感じです。
俎嵓山頂はスルーして、そのまま北側の登山道へ。こっちは御池に下る道です。
| 熊沢田代と会津駒ヶ岳 |
下り始めてすぐ、眼前にこんな風景が広がります。会津駒ヶ岳の安定感、正面から向き合っているとなんか素直な気持ちになってくるのが不思議です。
ずいぶん下の方にテーブル状の平坦な地形がありますね。あれは標高1950mに広がる熊沢田代。ここから400mも低いところにあります。ちなみに田代とは湿原のこと。ここからは見えませんが、その下にも東田代、広沢田代と、大きな湿原が何段か連なっています。
急な道を下っていきます。たまに追い越されることはあっても、この時間、このルートを上ってくる人と行き違うことはほとんどありません。
| ガレ場 |
俎嵓山頂直下から熊沢田代まではガレ場と幾筋かの涸れ沢を下っていくルートとなっていて、ちょっと足元に気を遣います。中でも長い涸れ沢を下る箇所では、その沢に入る箇所とそこから脱する箇所で道に迷いやすいようで、雪が残る時期には特に注意が必要とのこと。登山者に警告する看板も設置されていました。
上の写真のガレ場も結構な斜度。足を滑らせると百mくらいは転がっていきます。
この辺りの土は妙に赤いです。約10万年前に燧ヶ岳の円錐山体ができたときの噴出物と考えられていています。赤いのは鉄分が酸化したものでしょうか。
| |
1時10分、道に迷いやすいとされる涸れ沢に入りました。この沢に入る地点にはロープやビニールテープで間違わないように案内されていました。確かに登山道なのかただの沢筋なのか紛らわしいです。
| 涸れ沢を下る |
やがて涸れ沢の幅が広がってきました。視界が開けた分心は軽くなっていきます。でも延々と沢を行くルートになっていて(250mも降下!)、事前に情報を得ていなければ本当にまだ沢を歩いていて間違いないのかちょっと不安になるくらいです。あと、とにかく歩きにくく、かなり体力を奪われました。
| ジョウシュウオニアザミ |
そんな中でも登山道脇には様々な植物が微笑んでいます。これはジョウシュウオニアザミ。厳つい葉をもっていますが、花はうつむいて付くというツンデレ(?)具合。「アザミの花も一盛り」(刺のあるアザミでも花の咲く美しい時期がある→どんな娘でも年頃には魅力が出てくるものだ)という諺があるそうですが、どうしてなかなか美しいと思いますよ。
| ヒメウメバチソウ |
おお、これはヒメウメバチソウでは。ちょっと盛りは過ぎているでしょうか。分布はかなり限られているそうで、燧ヶ岳のこのルートには分布することが知られています。ウメバチソウとは印象がかなり異なりますが、近縁種だそうです。
| ハリブキ |
ハリブキの赤い実が午後の陽に照らされて輝いています。その鮮やかさにつられて手を触れようものなら相当痛い目に遭うことに。なにしろ葉や茎に強烈な刺が密生していますから。
| 夏の名残 |
背の高い木も多くなってきました。他愛もない話をしながらひたすら下っていきます。遠く会津駒ヶ岳の上に入道雲が立ち上がっていますね。季節が入れ替わりつつあります。
| ツツジ科の果実二種 |
同じような大きさの紅白の実がありました。白いのがシラタマノキ、赤いのがアカモノです。いずれもツツジ科の植物です。シラタマノキは下を向き、アカモノは上を向くのも対照的ですね。
| 熊沢田代 |
森が開け、目の前に熊沢田代が現れました。標高1980m、天空に張り出した広大なテラスに広がる別世界です。湿原の中程に二つの池塘があり、その間を木道が貫いて丘の向こうに続いています。それにしても、なんと静かなことか。人工的な音はまったくしません。この風景を前に足が止まってしまって、しばらく動けませんでした。
| 池塘 |
2時5分、熊沢田代の中央部にやって来ました。ここで小休止です。もう草紅葉が始まっていますね。この黄葉は主にキンコウカの葉。これからもっと鮮やかな黄色に変わっていくはずです。
| ヒメシャクナゲ |
湿原にはヒメシャクナゲが実を付けていました。ミズゴケが広がっているところに生えています。花は小さな壺型でシャンデリアのように吊り下がって咲きますが、実は写真のように上を向いて付いています。ちょっと美味しそうですね。高さ10㎝程度と小さいものの、これでも立派な樹木です。
| 映り込む秋 |
木道脇の休憩スペースに腰を下ろして涼やかな風に吹かれます。上空高くには秋の雲。そしてそれが池塘の中に映り込んでいます。耳を澄ましてようやく頭の中のシーンという音を感じ取れるくらいの静寂に、ある意味ぼーっとしてしまいます。あれ、自分は今どこにいるんだっけ、という短い時空喪失にみまわれ、すぐに我を取り戻す感覚といったらいいでしょうか。
至福の時間を過ごした後、再び歩き始めました。正面の丘を越えるとそこからはまた急降下が始まります。
| 急降下 |
だんだん膝がガクガクしてきました。こんな階段と、あと同じような斜度の岩の道とが交互に現れて大腿四頭筋を痛めつけてきます。
梢の間から広沢田代が見えました。標高は1770mです。湿原が黄色く輝き、天からのスポットライトを受けているようです。
そして3時15分、広沢田代に到着しました。ここでも小休止です。ここには池唐がたくさんあって、熊沢田代とはまた少し違った雰囲気です。周囲の風景が水面に映って、池塘の中にパラレルワールドがあるみたいです。
| 振り返ると |
振り返ると山がのしかかってくるような感じですが、あの上の向こうに熊沢田代が広がっているのです。
| オゼミズギク |
湿原にはまだ花もあります。これはオゼミズギク。葉の裏に腺点がたくさんあるのがミズギクとの相違点だそうです。腺点とは、分泌物質を出す腺で(イメージ的には人間の汗腺みたいなもの)、通常は黒点や透明の点のことが多いです。
さあ、体がカチカチに固まる前にまた動き出しましょう。御池までの標高差は250m(まだ250mもあるのか…。)。
| どこから下りようか… |
再び、いや三たび急降下の始まりです。もう筋肉はパンパンです。
今回、尾瀬沼から登って御池に下りるルートを選んだのは標高差に違いがあるから。このルートだと、上りは670m、下りは830mで、逆を行くより体力的に楽だろうという計算のもとです。ところが延々と下るというのもなかなかハードなのもだと思い知らされました。多少上りが長くても、体力のあるうちにこなしておいて、下りを楽にするという方法もあるんですね。勉強、勉強。
午後4時を過ぎました。だんだん傾斜が緩やかになってきましたが、これはひょっとして御池が近いということか。
人影のない森の中を歩いて行きます。朝、尾瀬沼の畔を出発して、山頂で遮るもののない眺望を楽しみ、下山路では光り輝く湿原を歩いたここまでの楽しい行程を思い返します。まだ終わってはいませんが、尾瀬はまた忘れ得ない思い出を作ってくれました。
4時15分、分岐が現れました。御池の駐車場は右に折れて100mほど行ったところにあるはずです。ちなみに左に折れると、燧ヶ岳の北麓を回って尾瀬ヶ原に至る道になります。
| オクトリカブト |
この期に及んでまだ花の写真を撮るyamaneko。これはオクトリカブトです。トリカブト界の猛毒銀メダリストです。
| 御池駐車場 |
4時20分、ついにゴールに到着しました。御池駐車場です。トータル9時間20分の山歩きでした。まずはケガもなく下りてこられたことに感謝。そして好天に恵まれたことにも感謝です。
広い駐車場を突っ切って、入口近くに停めておいたドリーム号のもとに向かいます。リュックを下ろし、靴を履き替えてから、軽くストレッチ。夫婦そろってロボコップみたいな動きになっていました。そして片付けが終わったら車に乗り込んで、ブナ平を下ったところにある七沢山荘まで移動。今日はそこに泊まって疲れを癒すことになっています。本当に楽しい山歩きでした。
何気なく野山を歩くそのかけがえのなさ。 - 今年6月に亡くなった俳優の地井武男さんが遺した闘病日記が、その死後に見つかったというネットニュースを一月ほど前に読みました。そのある日の日記に「あきらめない」と題された一節があったそうです。静かな森の中で木や太陽や空気に感謝し、愛しみ、自分がその中にその一部としていられることに感動する、そんな日々を送りたい(大略)。病床で書かれたであろうその一節を読んだたとき、深い共感が胸を静かに満たしていくような感覚を覚えました。そして心からそれを渇望したんだろうなと痛ましくもありました。
これから静かな森を歩くとき、その一節を思い返すことがあるかもしれません。そういう思いであらためて見渡す森はどんな風に見えるのか。これから少しでも多くそういう山歩きをしたいと思いました。