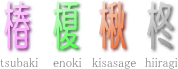2025年4月5日(土) その1

①
東京のソメイヨシノ満開宣言から1週間。多摩丘陵でも桜の盛りを迎えようとしています。これは尾根道のヤマザクラ。もう老いを迎えつつある大木で、おそらく戦前にここが戦車道だった頃に植えられたものではないでしょうか。

②
野草見本園へ。ムサシアブミです。先週、ロケットのようなシュッとした芽を出したと思ったら、あっという間にこの状態に展開しました。成長の早さにびっくりです。

③
イカリソウ。名板にはシロバナイカリソウとありました。名前は花冠が和船の碇に似ているからだそう。細く突き出ている部分は距という器官です。イカリソウの母種はヤチマタイカリソウというものだそうで、漢字では「八街碇草」。なぜ八街?八街は千葉県北部にある落花生栽培で有名なところですが、ヤチマタイカリソウの主な分布は西日本のしかも石灰岩地だそうです。益々??。その関係性に興味あり、です。
 |
④
パークセンターのフェンスにミツバアケビが絡みついていました。今ちょうど開花の状態です。一見花のような姿をしているのが雌花、つぶつぶのようなものが雄花で、いずれも花弁はありません。毎年秋には美味しそうな実を付けます。でもこの前を通りすぎる人の中でそれが食べられるものだと知っている人は少ないでしょうね。

⑤
垣根をレモンイエローに染めていたヒュウガミズキ。この時期、まだ葉は展開していなくて、花と入れ替わりで緑の垣根になっていきます。

⑥
イロハモミジといえば秋の紅葉ですが、花の様子はこんな感じ。花冠の大きさは5mmほどです。花序には10数個の花が付き、雄花と両性花が混在するのだそうです。雄しべが花冠から飛び出しているのが雄花です。

⑦
この濡れ髪のようなものはアラカシの若葉。まさに葉芽から展開し始めたところで、葉はまだ折りたたまれた状態。テカテカした軟毛に覆われています。なんとなくセミの羽化を連想させます。

⑧
ヌカボシソウです。ここでこの花に目がとまる人はほぼいないのではないでしょうか。yamanekoも教えてもらって初めて存在を知りました。花冠は6mmほどで、まったく目立ちません。漢字では「糠星草」と書き、糠星とは夜空に散らばる無数の星のことだそうです。

⑨
冬を迎えても枯葉を落とさないヤマコウバシですが、冬芽が膨らみ始めるこの時期になってようやく枝から葉を落とし始めました。冬芽はクロモジ属の中で唯一混芽(葉と花が一緒に入っている)だそうです。雌雄異株ですが雄株が未発見という不思議な植物。でも雄株なしで結実するのだそうです。

⑩
イヌザクラは葉を展開し終え、花序を伸ばし始めました。開花した姿は日本人がイメージする桜とは程遠いですが、この木の標準和名を付ける際には、これが桜の仲間だと分かっていたということでしょう。それまでは地域ごとに、桜とは無縁の様々な名前で呼ばれていたでしょうね。

⑪
さっき見たミツバアケビより淡い色合いのアケビの花。基本的な構造は同じで、花冠のように見えるのは雌花、つぶつぶのようなものが雄花です。

⑫
これはツルウメモドキの若葉です。五線譜の上の音符みたいに並んでいました。

⑬
カマツカの葉。展開したてで、まだしなやかです。やがて縁の赤味が取れ、葉全体が濃い緑色になる頃には、質もしっかりと硬くなります。

|
|
|
|
2025年4月5日(土) その2

①
サルトリイバラの花は葉腋からぶら下がるように付きます。雌雄異株でこれは雄花でした。葉は展開途中。最終的にはリンゴを縦に切ったときの断面のような形になります。

②
地面を這うように咲いていたミツバツチグリ。バラの仲間です。葉は3つの小葉からなっていて、これが奇数羽状複葉だとキジムシロ。両者の花はそっくりなので、葉が分かりやすい見分けポイントです。

③
オオシマザクラ。緑の若葉と白い花冠の取り合わせがすがすがしいです。これもミツバツチグリと同じバラ科。さっきのカマツカもバラ科です。バラ科の懐の深さを感じさせます。

④
コナラの若葉は淡い緑色で、遠目には銀色の輝きを放っています。コナラは、クヌギとともに、多摩丘陵でも最もポピュラーな樹木です。もちろんここ小山内裏公園でも主役といっていいです。

⑤
ニガイチゴの白い花。これもバラ科です。名前に反して果実は甘いです。

⑥
ヤマモモの雄花序。まだ葯が開く前です。ヤマモモは雌雄異株で、この株は雄株。なので実は付きません。ヤマモモの果実は甘酸っぱくて美味しいんですよね。子供の頃、遊びの途中で口の周りを真っ赤にして食べていたことを思い出します。

⑦
大田切池の西側、鮎道沿いの雑木林を見ると木々が芽吹きを迎えていることが分かります。写真中央の白いコブシの右側がコナラ、左側がクヌギです。コナラは白っぽい黄緑色ですが、クヌギの方はやや褐色がかっているので、遠目でも区別がつきます。

⑧
コバノガマズミはこの公園ではあまり見かけません。この株も、園の片隅にひっそりと生えていました。今若葉の展開が概ね終わったところです。
⑨
石垣の隙間で逞しく生きるオニタビラコ。長い花茎を伸ばし、高さは30cmほどになります。頭花の大きさは約1cmで、それが数個集まって付きます。

⑩
クロモジの花序。巾着というか羽根突きの羽根というか、ユーモラスな姿をしています。

⑪
モミジイチゴの花は下向きに付くのが一般的。ニガイチゴ同様、モミジイチゴの果実も甘くジューシーです。yamanekoにとって野遊びのおやつでした。
⑫
武者のような堂々とした立ち姿。ミミガタテンナンショウです。高さは80cmほど。テンナンショウ属はふつう雌雄異株ですが、雌雄は蓄えた栄養の量で決まるのだそうです。栄養は地下の球茎に蓄えられるので、ここが大きいと雌株、小さいと雄株になるということです。

|
|
|
|
2025年4月5日(土) その3

①
ヤマツツジの若葉。この時期、こんなにしなやかな姿をしています。花はあと半月後か。

②
以前、クズの除去などの保護活動をしたカジイチゴ。今年もたくさんの花を付けました。ニガイチゴ、モミジイチゴに次いで今日3つ目のイチゴです。

③
この辺りではまだカントウタンポポをよく見かけます。もう少し市街地だと外来種のセイヨウタンポポが優勢になるようです。見分けるポイントは、花冠を裏返したところにある総苞片の状態。花冠の基部に張り付いているとカントウタンポポ、反り返っているとセイヨウタンポポです。ただ中間的な形状のものも多いそうです。

④
尾根道を彩るソメイヨシノ。七部咲きといったところか。

⑤
マユミ。葉が展開すると次は花序が伸び始めます。雌雄異株で、今の様子からは判別できませんが、この株は雄株です。雄花は雄しべが長くて柱頭が短く、雌花はその逆です。

⑥
イタドリが伸び始めています。この時期はまだ可愛い姿で、茎は柔らかく山菜として好まれますが、あっという間に成長し、晩秋には固く木質化します。中国では古来それを杖としたほど。茎の模様が虎のようだということもあり、イタドリは漢字では「虎杖」と書きます。

⑦
オオアラセイトウの群落。なかなか見事です。

⑧
ニワトコの花序です。形は円錐状で、これで開花状態。花序の中にある黒っぽく点々としたものは雌しべの柱頭です。別名のセッコツボク(接骨木)はポピュラーですが、写真のような葉の姿をツルの翼に見立てて、「やまたづ」(山鶴)とか「たづのき」(鶴の木)と呼ぶ地方もあったそうです。そういわれればツルの羽ばたく様子に似ていないこともないですね。

⑨
クヌギの芽吹き。葉の展開に先駆けて花序が伸びてきています。コナラに比べると全体に褐色がかっていることが分かります。クヌギも多摩丘陵にはたくさんあります。

⑩
マルバアオダモは葉が展開したらすぐに花期です。去年はうかうかしていて花を見逃してしまったので、今年は注意していました。こうやって花に出会えて嬉しいです。

⑪
キランソウが出始めると春も本番だなと感じます。花をアップで見るとなかなか優美な姿をしています。シソの仲間。

⑫
保護活動をしたヤブサンザシ。一番大きな株に花が付きました。雌雄異株で、これは雄花。すなわち雄株に付く花です。小さな株での花は来年以降に期待。

|
|
|
|
2025年4月9日(水)

①
クサボケ。このサイズだと名前のとおり草本のように思えますが、これでも樹木です。なかなか愛嬌があり、藪の中で見かけたりするとちょっと嬉しいです。

②
サンクチュアリ内の整備の際に見かけたイチリンンソウ。春の陽をいっぱいに受けていました。草丈に比して花冠が大きめなのが特徴で、頭でっかちな印象。ニリンソウが清楚な印象なのとの違いはこのスタイルにあるのかもしれません。

③
尾根道のソメイヨシノ。花の時期に葉がないため、全体として白く輝いているように見えます。

④
イタヤカエデの若葉。展開したての頃は赤味を帯びています。
⑤
これはキハダの葉が展開し始めたところ。ここから奇数羽状複葉の花序が伸びていくんですから、生き物って不思議です。
この写真を見て、昔マジックハンドというおもちゃがあったことを思い出しました。長さ50cmほどのアームの先に物を掴む部分があって、手元のレバーを握ると先端部が開いたり閉じたりするもの。懐かしいです。

⑥
こちらはヤマザクラ。花と同時に葉も展開するので、ソメイヨシノにはない野趣を感じます。自然の野山にはこちらの合いますね。

⑦
この時期、カツラの葉も展開し始めます。ハート形の葉が枝に沿って行儀よく並んでいて、それらが春風に揺られる様子はなかなか愛らしいです。

⑧
野草見本園へ。こちらはニリンソウです。やっぱりイチリンソウよりも清楚な感じがします。葉の切れ込みも、イチリンソウが深く細かいのに対し、ニリンソウは浅く丸っこいです。これも全体の印象に影響を及ぼしているかも。

⑨
シャガは暗い背景によく映えますね。花冠は優美で絢爛。ヨーロッパの王朝風(?)です。ただ、華やかさの中にどこか愁いをたたえているようにも見えるのはyamanekoだけか。

|
|
|
|
2025年4月16日(水)

①
津島谷戸入口付近に生えるツルカノコソウ。元はサンクチュアリ内で多く見られたものですが、数年前に木々が皆伐されてからこちらのやや暗い環境の場所に新天地を求めたようです。ただ、ここもナラ枯れが進みつつあり、それが伐採されると、ここではもう生きていけないということになるのだと思います。

②
フデリンドウ。まるで歯車のような整った形をしています。日当たりの良い場所を好み、毎年ここの歩道脇に咲いてくれます。

③
ヤマブキもこれからが見ごろ。どの株も写真のように枝にたくさんの花を付けていました。山中に生えるヤマブキの枝が風に揺られる様子から、古くは「山振り」と呼ばれたそうです。

④
九反甫谷戸へ。マルバスミレが咲いていました。薄紫色のタチツボスミレが多い中、純白の花弁が目立っていました。全国に分布する種で、珍しいものではありません。

⑤
これはタマノカンアオイの花。ちょっと失礼して、写真を撮る間だけ覆いかぶさっていた葉を上げさせてもらいました。萼筒の入口にある環状の斑紋が目立っています。多摩丘陵で発見されたもので、分布は関東地方南西部に限られるそうです。

⑥
アオハダの若葉。葉は短枝の先端に集まって付いています。1か月前の短枝の様子はこちら。

⑦
多目的広場のベンチに腰を下して木々の樹冠を見上げました。この時期、様々ない色合いの緑色で彩られ、瑞々しく、かつ、鮮やかです。

⑧
ヤマコウバシ。この木が目立つのは他の木々が葉を落としてから。この木自体の葉も薄茶色になってからです。なので、若葉の展開をじっくり見ることは少ないです。同時に葉腋に小さな雌花序を付けます。ヤマコウバシは雄花がなくても結実しますが(雄株自体が未発見)、花がごくシンプルなのはそのことと関係しているのでしょうか。

⑨
南広場に植栽されているイチョウ。短枝から葉が噴き出したような感じに見えます。淡い色合いで瑞々しいです。
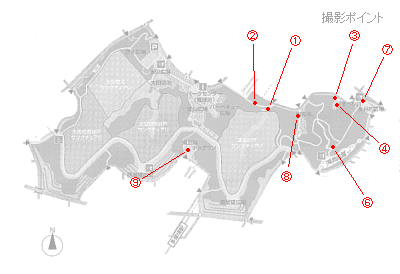
|
|
|
|
2025年4月17日(木)

①
カキドオシ。花に目が行きがちですが、葉も様子も可愛いです。絵に書いたような葉の形をしています。
②
これはなにかの妖精か? いや、これはゼンマイの栄養葉。ぎゅっと球状にまとまっていたものがほぐれていく過程ですね。80年代頃、音に反応して踊るダンシングフラワーというおもちゃがありましたが、それに雰囲気が似ています。

③
ズミには「北国に春を告げる花」というイメージがありますが、北海道から九州までの内陸部に分布しているようです。yamanekoが自然観察を始めた頃に広島県の山間部にあるクロカンパークで見たズミが印象に残っています。山里に訪れた春の風景の中でした。
④
カスミザクラ。遠目に見て山肌に霞がかかったように群れ咲くことから付いた名前だそうです。ヤマザクラに似ていますが、花柄に毛があることで区別がつきます。花弁の先端が切れ込むのも特徴の一つ。

⑤
トウグミの花が満開です。トウグミはナツグミの変種とされていて、葉の裏に星状毛が密生していたらトウグミ、輪状毛が密生していたらナツグミだそうです。ただし、ルーペがないとよく分かりません。

|
|
|
|
2025年4月19日(土)

①
マルバアオダモの花期はもうそろそろ終わりか。雌雄異株で、雄花が付く株と両性花が付く株があります。ただ、両性花は自分の花粉では受粉できないので、結実するためには雄花の花粉が必要となるのだそうです。

②
マジックハンドの先端みたいだったキハダの若葉がずいぶん広がってきました。この木は、yamanekoが多摩に引っ越してきてすぐ、この公園で最初に興味を持った木です。その時は花期の終わりの頃で、枝下にたくさんの花を散らしていました。

③
イタヤカエデの花序。カエデの仲間には、このイタヤカエデののように花が上を向いて付くものと、イロハモミジやウリハダカエデのように垂れ下がるものがあります。
④
シロダモにも若い葉が展開しつつあります。展開直後は黄金色の軟毛に覆われていて、触るとビロードのように気持ちいいです。葉が成長するとともに軟毛はきれいに抜け落ち、固く光沢のある頑丈な葉になっていきます。
⑤
おお、ウワミズザクラの花序が。これがサクラの仲間といわれてもなかなかピンときませんよね。同じような花の付き方をするイヌザクラとの見分けは、花序と枝の間に葉が付いているか否か。あと、花の付き方もウワミズザクラはびっしりですが、イヌザクラはやや疎な感じです。

⑥
ミツデカエデ。葉が展開したばかりで、まだ花序は伸ばしていない様子。もうしばらく経ってからあらためて確認に来たいと思います。このミツデカエデの花序はぶら下がるタイプです。

⑦
現代アートと見まがうホオノキの芽吹き。まず葉が、その後に花が展開します。ただ、かなりでかいので(写真のもので直径30cmくらい)、芽吹きという言葉が似あいません。

⑧
これがイヌザクラの花序。花序と枝の間に葉が付いていないのが分かります。花と花の間にも隙間がありますね。
⑨
トチノキの芽吹き。トチノキもホオノキと同じように大きな葉になりますが、芽吹きの様子はやや控え目です。

⑩
今、林縁では満開のジュウニヒトエがあちこちに見られます。冬の間どこに隠れていたんだというくらい、何もないところから伸びています。花序にはシソ科に特有の唇形花がびっしり。

⑪
垣根に植栽されているトキワマンサク。てっきり外来のものかと思っていましたが、国内にも自生地があるとのことです(三重県、熊本県など)。

|
|
|
|
2025年4月24日(木) その1
①
コナラの幹を這い上がろうとしているツタウルシ。小葉の葉脈があばら骨みたいに見えます。人にもよりますが、ウルシの仲間の中では強いかぶれ症状が出る種です。

②
ホウチャクソウ。葉腋から磁器のような質感の花冠がぶら下がり、先端がわずかに開きます。遠目にもどこかスマートな印象を受ける花です。

③
ヤマグワの実が育ちつつありました。熟すと赤色から黒紫色になり、甘くジューシーになります。野山で熟した実を見つけるとついい食べてしまうのですが、指先や口の周りが紫色になってしまうのが難点です(子供の頃から何ら進歩していません)。
④
カジイチゴの花はそろそろ盛りを過ぎます。次は実の付く頃が観察チャンスです。

⑤
ウシハコベの花冠をアップで。よく似るハコベやコハコベは柱頭が3つに分かれていますが、このウシハコベは5つです。そこが一番の見分けポイント。
ハコベに比べて大きいことから名前にウシと付けたようですが、大きさにそこまでの違いはなく、過大な表現だと思います。

⑥
これはツボスミレ。漢字では「坪菫」と書き、坪は庭のことです。すなわち庭に咲いているスミレということですね。丈は10cmほど。写真はローアングルで撮ります。

⑦
ユズリハに若葉が展開しています。薄日を受けて自ら発光しているかのように浮きたって見えました。名前のとおり、葉が成長すると下の古い葉が落ち、代替わりします。これを家が代々続くとことに例えて、おめでたい木とされています。

⑧
ダンコウバイの葉の展開は概ね完了したようです。先割れスプーンみたいな形が特徴的です。そういえば、先割れスプーンって今でも給食で使われているのでしょうか。
⑨
カマツカの花が満開です。清楚な花が散集状に付きます。秋の黄葉も和テイストでいい色合い。珍しいものではないですが、yamanekoにとって気になる木のひとつです。

⑩
鮎道にヤマツツジが群生しているエリアがあります。もしかしたら植栽かもしれません。今年も元気に咲き始めました。yamanekoが所属しているボランティア団体で冬にササ刈りや下草刈りをして整備しているので、きれいに咲き揃うと嬉しいです。
⑪
春本番になり、林床ではキンランが咲き始めました。野生ランの中では容姿が派手な方だと思います。多摩丘陵では普通に生えるものですが、これを盗掘する輩がいるのが残念です。
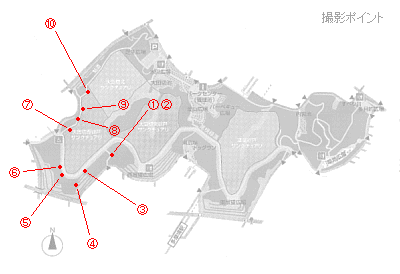
|
|
|
|
2025年4月24日(木) その2

①
チゴユリの「チゴ」とは稚児のこと。すなわち小さく可愛いユリという意味です。確かに丈はせいぜい15cmほど。俯き気味に花を付ける姿はやっぱり可愛いです。名前に偽りなしですね。
②
コナラの根元に着生しているノキシノブ。ウラボシ科のシダの一種です。ノキシノブの「ノキ」は家の軒崎のことで、茅葺き屋根の上や軒崎で茂っていたことによるネーミングだそうです。近年、茅葺き屋根自体見かけませんね。

③
ハナイカダの花は葉身の中央に付きます。まるで花が筏に乗っているようとのネーミングです。通常、花は葉腋から花柄を伸ばしてその先に付くもの。ハナイカダではその葉柄が表脈に重なるように合着して、その結果花の位置が葉の中央にきているのです。葉の主脈のうち花から基部側の部分が白く太くなっているのは花柄の名残。

④
オニタビラコの頭花。ミニタンポポのような頭花が数個集まって付きます。一つの頭花には30個くらい舌状花があり、その一つ一つが1個の花です。丈は30cmくらいあるスマートな姿で、基部で根生葉を広げています。

⑤
尾根道沿いにガマズミはたくさん植栽されていますが、このコバノガマズミはほとんど見かけません。生えている環境からこれは自生のものと思います。ここからわずか数km離れた長沼公園では自生のコバノガマズミを多く見ましたが、この違いは何だろう。小山内裏公園では公園造成時に切られたか?

⑥
ヤマフジが高木に登り、立派な花序をたくさん垂らしていました。天然のプロジェクションマッピングです。
ヤマフジとフジ(ノダフジ)の見分け方としてツルの巻き方があります。両手でハンドルを握る格好をし、それぞれの手の親指の向きに蔓が巻き登ると仮定して、左手の親指の向きならヤマフジ、右手の親指の向きならフジ(ノダフジ)です。
なお、「右巻き」、「左巻き」といった表現は、蔓や渦、ネジなどものによって定義が異なるので、誤解の元です。

⑦
ホタルカズラは斜面で見かけることがほとんどで、平らな地面に生えているところは見たことがありません。カズラの名が付いているとおり、蔓で斜上する性質があるのでしょうか。花は5百円玉ほどの大きさで、鮮やかな色と相まって、よく目立ちます。
 |
⑧
野草見本園へ。これはエビネ。同じエビネでも色合いなど変異が多いのが特徴です。これも野生ランの一種。

⑨
これは畑で栽培されているエンドウ。マメ科に特有の蝶形花で、花はきれいだし実は美味しいし、いいとこだらけです(品種改良されていますからね)。張られた糸は鳥よけ。

⑩
アカマツの雄花序です。今はまだ開花前。新しい枝の基部に付き、これから先端が伸びてその先に雌花が付きます。アカマツは雌雄同株です。

⑪
今月はじめ、赤く小さな花を付けていたイロハモミジですが、3週間経って若い果実ができていました。タケコプターみたいです。(花の様子はこちら)
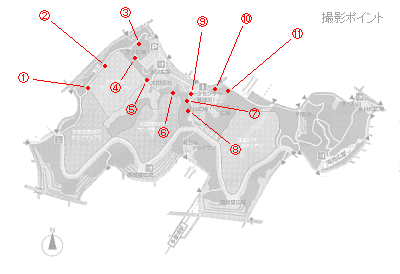
|
|
|
|
2025年4月24日(木) その3
①
セイヨウジュウニヒトエ。もともと海外から移入されたものが各地で野生化しているようです。姿はジュウニヒトエ、花の色はキランソウという変わり種です。

②
在来のジュウニヒトエと隣接して生えていました。誰かが植えたのか?

③
ドウダンツツジの花は壺型。受粉を手伝う虫が入りにくい形なのではと心配しますが、自然界の造形はちゃんと考えられているんでしょうね。
ところで、ドウダンツツジは漢字では「満天星躑躅」と書きますが、かなり無理筋です。調べてみると、この花序の付き方が燭台の足みたいということで、ショクダイがドウダンに転訛したものだそう。それもかなりの無理筋ですが。一方、「満点星」は中国での表記で、それをそのまま用いているということです。

④
九反甫谷戸へ。イチリンソウがその名のとおり1輪だけ咲いていました。ここでは少しずつ増えているように思います。

⑤
マユミの花。マユミは雌雄異株としている図鑑もあれば、雌雄異株と明言せず「雌しべが長く雄しべが短いタイプと、その逆のタイプがある」とする図鑑もあります。写真のもの雄花(雄しべが長くめしべが短いタイプ)です。

⑥
散策していてこの花に気が付く人は少ないのでは。これはツルウメモドキの花(雄花)。大きさはわずか8mmほどです。秋になってオレンジ色の実ができるとよく目立ち、花材やリースのパーツに用いたりする人もいます。
⑦
現代アートのようなヒメコウゾの花序。先端の白っぽいウイルス細胞みたいなものが雄花。その上に連なって付いているエネルギーボールみたいなものが雌花です。

⑧
東展望台の近くにやって来ました。何かの綿毛が吹雪のように風に飛ばされていたので、その元をたどってみるとヤマナラシでした。ヤナギも柳絮(りゅうじょ)と呼ばれる種子付きの綿毛を飛ばしますが、ヤマナラシも同じヤナギ科です。なるほど納得。

⑨
エノキに若い実ができていました。今年も花の観察時期を逃してしまったということになります。残念。花は来年に持ち越すとして、秋になったら熟した実を味わってみたいと思います。
⑩
花はツリガネニンジンに似ていてい、葉はスイセンににている、その名もツリガネズイセン。南欧原産の外来種だそうです。

⑪
アカメガシワの名を体現する若い葉。展開し始めの頃は葉の表面に赤い星状毛が密生していますが、成長するにつれて取れていきます。ただ、取れてつるつるになるのではなく、成長した葉は緑色の星状毛に覆われます。生え変わる感じでしょうか。ちなみに、この赤い毛には若い葉を守る役割があるとのことです。

⑫
自生のエビネの群落。今年も元気に咲いてくれました。
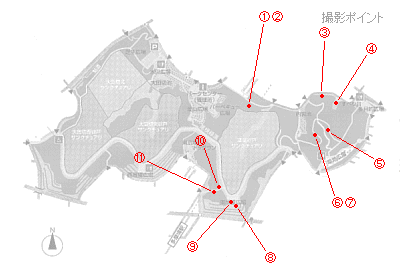
|
|
|
|
| |