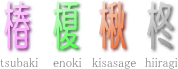2017年4月2日(日)

①
尾根道から里山広場への下り口にあるヤブザクラが咲き始めました。今年は去年より1週間ちょっと遅めの開花です。

②
萼の形がタマノホシザクラに似ていますが、萼片の基部が若干くびれていて、やや粗めの鋸歯があるのが相違点です。いずれもマメザクラのエドヒガンとの交雑種と考えられているそうです。

③
アカバナミツマタ。この花もやっぱり去年より1週間ちょっと遅れています。

④
シナレンギョウ。園路の脇に植栽されています。

⑤
内裏池で。カルガモ(雌)が水遊びをしていました。
⑥
ミチタネツケバナはユーラシア大陸原産の帰化植物。高さは10cmほどで、在来のタネツケバナに比べるとずいぶん小さいです。

|
|
|
|
2017年4月5日(水)

①
クヌギの若葉。この時期、コナラとよく似た姿をしていますが、葉の先の部分がやや褐色を帯びているのが見分けポイント。木全体を遠目に見ると少しベージュがかって見えます。
②
タンキリマメ(か、トキリマメ)。冬の名残ですね。

③
野草見本園で。これはタマノカンアオイ。地面に埋まるようにして花を付けています。
④
タンチョウソウだそうです。ここで初めて見ました。東アジア原産の植物のようです。
⑤
バイモ。たしかこれも帰化植物のはず。

⑥
ニリンソウも咲き始めました。そろそろ春本番です。(サクラはまだこれからですが。)

⑦
谷戸山の会での活動の一環で大田切西谷戸へ。普段は立入が制限されているところです。

⑧
ノカンゾウの若葉。

⑨
キジに遭遇。1週間前に出逢ったやつでは。

⑩
シュンランはまだ生き生きとしていました。
⑪
ミツバアケビの花。上の3萼片のが雌花で、その下の小さいのが雄花。雄花にも萼片がありますが、小さく目立ちません。そのかわり雄しべが球状に集まっているのがよく目立ちます。

⑫
コブシの花の中心部はよく見ると豪華な感じです。

⑬
シャガが咲き始めました。冬の緑の少ない季節に、ずっと元気に緑色の葉を見せてくれていました。

|
|
|
|
2017年4月8日(土)
①
暖かい春の雨がどうにか上がって、今日は小山内裏公園のガイドウォークに参加。まずパークセンターに向かう道すがら、満開のキブシを観察。

②
一週間前のさくら祭りのときにはほとんど咲いていなかったヤマザクラの大木。今日はもう満開でした。

③
天気のせいか今日の参加者は数えるほど。
路傍のカントウタンポポ。総苞片が反り返らないことで外来のセイヨウタンポポと見分けることができます。

④
白花のヤブツバキ。公園内にあるとは今まで気がつきませんでした。図鑑を見るとヤブツバキには淡紅色や白色のものも希にあるとのこと。

⑤
タマノホシザクラです。内裏池の奥にある大木は数えるほどしか花を付けていませんでした。時期的にはもう盛りを過ぎる頃とのことで、今年はこのまま終わってしまいそうです。

⑥
ミツバウツギの若葉。ガイドウォークで教えてもらって、はじめてこの公園にミツバウツギがあることを知りました。花の時期が楽しみです。

⑦
イヌザクラの花序。ムスカリみたいですね。これから延びていきます。

⑧
コナラの若葉は輝くような白色です。これがしばらくすると鮮やかな緑色になるんです。

⑨
もうハンショウヅルに花芽が付いていました。こんなに早くから準備をしていたとは。

⑩
ガイドウォーク終了後、一人で公園の西側を散策。
大田切池ではコガモのつがいが休んでいました。顔を背中の羽毛に突っ込んでいます。

⑪
クサボケの開花。丈は低くても草ではなく立派な木です。鮎道で。
⑫
カタクリの自生地に行ってみるともうほとんど花は終わっていました。そして実を付け、その後は地上から姿を消します。

⑬
クロモジの花も満開です。目立つ花も地味な花も、みな一生懸命に咲いています。

|
|
|
|
2017年4月12日(水)

①
夜半まで降った雨が上がり、瑞々しく晴れた朝です。
南広場から上がった先の尾根道。ヤマザクラが満開です。
②
これはゼンマイ。背が高く、先端がボール状になっているのは胞子葉で、「雄ゼンマイ」と呼ばれています。一方、根元にある先端が円盤状のものは栄養葉で、「雌ゼンマイ」と呼ばれ、こちらが食用。いずれも葉が展開する前の状態です。

③
シロダモの若葉。この時期、黄金の軟毛に覆われていて、ビロードの手触りです。これが隣にあるような固くて光沢のある葉に変わるのです。

④
ミズキの若葉。「萌える」という言葉がぴったりと当てはまるような姿です。

⑤
野草見本園で。ムラサキヤシオのように見えますが、何でしょうか。
⑥
バイモ。花冠の内側に網目模様があります。江戸時代、倹約を求められた庶民が着物の裏地でお洒落をしたという話を思い出しました。

⑦
カツラも若葉を展開させています。可愛いハート型です。

|
|
|
|
2017年4月16日(日)

①
イロハモミジの花です。小さくてあまり注目されません。

②
クスノキの若葉。しなやかそうですね。草地広場にて。

③
こちらはサルトリイバラの若葉と、その下に咲く花。とてもユリ科とは思えない風情をしています。

④
ジュウニヒトエがちょうど見頃。明るい林の縁でよく見かけます。

⑤
まだ林には光が十分に射し込んでいます。この時期は歩いていても気持ちがいいです。

⑥
オオシマザクラ。白色の花と同時に緑の葉が展開するので、全体に涼しげな印象を受けます。

⑦
ニワトコも開花しました、ごく小さな花が、まるで泡を吹いたように咲いています。

⑧
カキドオシ。丈は低く小さな花ですが、垣根を突き抜けてまで広がるという意味の名が示すように、旺盛な繁殖力を持っています。

⑨
キランソウは鮮やかな紫色。カキドオシより更に丈は低く、地面に貼り付くようにして咲いています。ジュウニヒトエもカキドオシもキランソウも同じシソ科の植物です。よく見ると花の構造が似ています。

⑩
カントウタンポポです。花が咲くときには虫が来やすいように背を起こし、花期が終わると茎を倒します。そして、種を付けると再び背を起こし、少しでも高い位置から種を飛ばそうとするのです。

⑪
トサミズキの若葉。じゃばらに折りたたまれていたのがよく分かります。

⑫
ツルカノコソウ。この公園では初めて見ました。ツルと名が付きますが、特にツル性の植物というわけではありません。
⑬
カラスノエンドウの花。マメの鞘を笛にして、子どもの頃よく遊んでいました。仲間内でも作るのが上手かった記憶があります。

⑭
揉むとキュウリのような匂いがすることから名が付いたというキュウリグサ。花冠の大きさは5mmにも満たないほどです。水色とレモン色のパステルカラーで、子どもが絵に描く「the
お花」の形をしています。

⑮
アラカシの若葉です。なんか妙な迫力がありますね。

⑯
さっきのトサミズキに似ていますが、こちらはヒュウガミズキの若葉。こちらの方が二回りくらい小さいです。

⑰
野草見本園にやって来ました。イチリンソウが端正な姿を見せていました。
⑱
4日前にみたゼンマイ
。胞子葉も栄養葉もずいぶんほどけてきました。こんな過程を経て葉を広げるんですね。

⑲
アオキの雌花。十字の花弁の中央に黄緑色をした雌しべの柱頭が一つあるのが分かります。

⑳
こちらはアオキの雄花。十字の花弁の中央に四つの黄色い点。これは雄しべの葯です。

|
|
|
|
2017年4月19日(水)

①
朝の散策。寒さも緩み、より楽しくなりました。
これはキハダの若葉。冬芽はこんなだったんですよね。

②
ヌルデの芽吹きです。去年の果穂がドライフラワーになって残っています。
それにしても若葉はみんなしっとりとしなやかそうですね。

③
イタヤカエデも若葉を展開しています。瑞々しい。

④
蕾の状態のウワミズザクラ。ソメイヨシノが終わり、ヤマザクラもそろそろ終わりそうになるtp、今度はウワミズザクラが咲く番です。

⑤
トウグミが咲き始めました。葉にも花にも細かい斑点(星状毛)が散りばめられています。

⑥
コナラの花が満開です。一般的な花のイメージからはかけ離れていますね。

⑦
マルバアオダモも咲きはじめる季節。なんだかごちゃごちゃしていますが、これは細長い4弁の花が寄り集まった姿です。

⑧
今月初めから咲き始めたシャガ。そろそろ満開を迎えそうです。

|
|
|
|
2017年4月22日(土) その1

①
アカメガシワの若葉。その名のとおり表面が赤い細毛に覆われています。展開するにつれてとれて、本来の緑色に。

②
タチツボスミレとカントウタンポポとの寄せ植え、的な株。ヤマザクラの根元で。

③
ウワミズザクラ、満開ですね。
④
ミツバアケビの雄花。雄しべの葯が目立っていますが、その付け根に花被片が反り返って付いているのが分かります。

⑤
これはスミレサイシンか。

⑥
ホオノキの冬芽も展開しました。
⑦
10日前から観察しているゼンマイ。胞子葉、栄養葉ともに馴染みのある姿になってきました。
⑧
野草見本園へ。エビネが咲いていました。
⑨
バーベキュー広場内にあるメタセコイアの若葉。この時期の葉を観察するのははじめてかも。こんなに垂れ下がるものだとは知りませんでした。

⑩
小山内裏公園の北側の道路沿いに植栽されているグミ。トウグミで合ってるでしょうか。満開でした。

⑪
まだヤマザクラが咲き残ってくれていました。桜の季節、あっという間でした。また来年!

|
|
|
|
2017年4月22日(土) その2

①
今日はネタが多いので二部構成で。
これはアカマツの若い花。トウモロコシみたいな丸いものは雄花で、雌花は先端に付きます。これからもっと伸びるはず。

②
チガヤです。なんかボロボロに見えますが、たくさんの葯がぶら下がっているのです。
③
ヘラオオバコの花。アンテナのように飛び出ているのは雄しべです。

④
フデリンドウが咲いていました。不思議と斜面で見かけることが多いです。

⑤
ヤブレガサ。といえば「刀舟」で「悪人狩り」

⑥
チゴユリもずいぶん咲いていました。皆が一気に咲き始めるので、もったいないような気がします。

⑦
ハナイカダの小さな花。花茎が葉の主脈上に合着したような構造です。

⑧
去年の秋に生まれたキイロスズメバチの新女王。越冬を終え、出てきたばかりでしょう。これから適当な場所を見つけて巣を作り始めるはずです。

⑨
ニガイチゴ。実は苦くなく、むしろ美味しいです。

⑩
小山内裏公園のヤマツツジはほとんど植栽のような気がします。野生のものもあるのか?
⑪
久しぶりに尾根緑道を東へ。ムラサキケマンはもう終わりかけ。

⑫
元気いっぱいのキランソウ。普通、地面に貼り付くように生えているのですが、この辺りのものは茎が立っていました。高さ10cmくらいにまで。

|
|
|
|
2017年4月26日(水)

①
ホタルカズラ。花冠は500円硬貨ほどの大きさで、けっこう華やかです。
②
イヌコリヤナギが早くも実を付けています。種子が白い綿毛に包まれて、やがて風に飛ばされていきます。今年は開花の状態は見逃してしまいました。

③
大田切池のコガモのつがい。のんびりしていますね。

④
芝生広場に移動。こちらではウワミズザクラが満開です。

⑤
早春にいち早く花を見せてくれたウメが可愛い実を付けていました。カリカリ梅を一回り大きくしたサイズです。(この木が紅梅だったか白梅だったか忘れてしまいました。)

⑥
涼やかな色合いのチョウジソウ。花冠を真横から見ると「丁」字形をしています。野草見本園で。

|
|
|
|
2017年4月29日(土)

①
今日は尾根道を東へ。植栽のアセビのしなやかな若葉です。まだ葉にクロロフィルが十分できていないのか、若干褐色がかった色をしています。

②
ヤブツバキの紅葉。こちらは逆にクロロフィルが壊れてきているもので、落葉間近です。

③
ヤマグワはもう実を付けていました。黒紫色に熟すのは5月下旬か。

④
カマツカの花。バラの仲間です。花期が短くあっという間に散ってしまいます。

⑤
ツリバナはその名のとおりの姿。自然のモビールです。

⑥
イヌザクラ。ウワミズザクラの花に似ていますが、一回り小さく、また、花穂の付け根に葉が付くか否かで見分けられます。イヌザクラには葉が付きません。

⑦
九反甫谷戸へ。園内には植栽のヤマブキも多くありますが、これは自生ではないかと思います。

⑧
やとの奥にはイチリンソウの小群落が。やや薄暗い中で静かに咲いていました。

⑨
フサザクラの若葉。小さくても先端が細く突き出る特徴的な姿は同じです。

⑩
小山内裏公園でミツバウツギの花を見るのは初めてです。20日前に行われたガイドウォークでここにあるのを教えてもらいました。
⑪
ズミの花。純白です。これもバラの仲間です。

⑫
満開のイヌザクラ。この写真だと花穂の基部に葉が付いていないのがよく分かります。

⑬
クサイチゴの花の時期はもう終わりかけ。かろうじて残っていました。
⑭
オニタビラコ。なんともあっさりとした姿です。丈は50cmほどになります。

|
|
|
|
| |