
大江湿原・尾瀬沼 〜遥かなる花の別天地へ(中編)〜
 |
(中編) |
【福島県 檜枝岐村 令和7年6月17日(火)】
遥かなる花の別天地「尾瀬」での野山歩き。中編です。(前編はこちら)
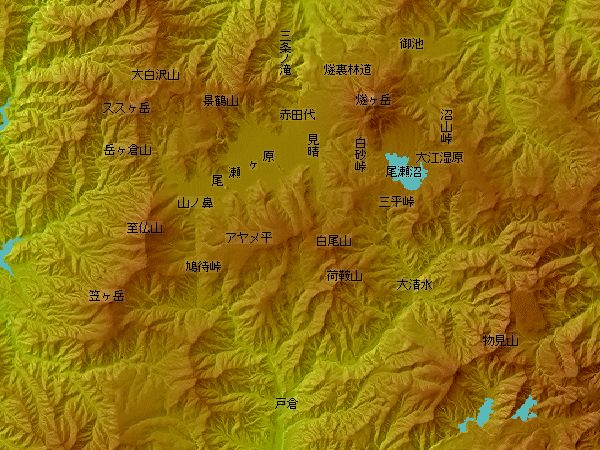 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
|
| 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
いろいろすったもんだがあって、沼山峠の登山口を出発したのは9時30分。花に出会うたびに歩みを止め、大江湿原に出たのは10時35分でした。そこから尾瀬沼に向かいます。
| タテヤマリンドウ |
この日、大江湿原にはタテヤマリンドウが咲き乱れていました。どの株も初夏の日差しを受けて輝いています。
| ツボスミレ |
これはツボスミレ。尾瀬では林間ではなく湿原に多く見られるそうです。
| 大江湿原 |
湿原の回廊を行くかのような大江湿原。木立の切れたその先に尾瀬沼が広がっているはずです。
この道は、いにしえの会津沼田街道の一部。福島県檜枝岐村の七入から沼山峠、大江湿原、尾瀬沼東岸を通って、群馬県片品村大清水に下るルートで、江戸時代、会津と上州を結ぶ唯一の交易路として使われていた道だそうです。ただ、そのときもこうやって湿原のど真ん中を通っていたのでしょうか。歩きやすさからするとおそらく森の際を通っていたのでは。
| ショウジョウバカマ |
木道脇にショウジョウバカマが生えていました。こんなところでも生きていけるんですね。森の中で出会う花という認識でしたが。普通、葉はロゼット状に地面に広がるのですが、これはチューリップの葉のように立ち上がっています。雪解けの水から葉を守るためか。
| 視界開ける |
おお、遠くに尾瀬沼の湖水が見えました(写真はズーム)。新しい世界が開けたような気分です。会津沼田街道を歩いてきた昔の商人たちもこの風景に心癒されたかもしれませんね。
メインの木道から右手に入る分岐がありました。こちらを訪れる人はほとんどいません。なぜならこの先は「ヤナギランの丘」と呼ばれる小高い丘になっていて、そこには尾瀬の自然保護に生涯を懸けた平野長蔵氏、息子の長英氏、孫の長靖氏とそのご家族の方の墓所となっているからです。
| ヤナギランの丘 |
ここは尾瀬の散策マップにも掲載されている有名な場所ですが、とはいえよその家の墓所なわけなので、丘の手前で手を合わせ引き返しました。日本の自然保護の礎を築いた平野三代の生涯を記した書物は多くあります。yamanekoはこれまでそのごく一部を目にしたに過ぎませんが、確固とした信念は人間を驚くほど強くするものだと感じたのを覚えています。三人とも自分が人生をかけて守った場所で今はきっと穏やかに眠っているでしょう。
| キジムシロ |
キジムシロは多摩丘陵でも普通に見かける花です。湿地でも生きられるんですね。尾瀬の湿原は大部分が高層湿原で、ミズゴケが水面よりも高く盛り上がっているので、その上で生きる分には良いのでしょうが、一方で栄養が溶け込んだ土も水も届かないわけで、なかなか過酷な環境なのではないでしょうか。根が深く入り込んでいるのかも。
| シナノキンバイ |
シナノキンバイは湿った環境を好む植物。尾瀬ではここ大江湿原の他に至仏山でも目にすることができます。キンポウゲ科なので、例のごとく花弁状のものは萼片です。
| サンリンソウ |
ニリンソウかなと思いましたが、よく見るとサンリンそうでした。茎葉に葉柄があるのがニリンソウとの相違点です(ニリンソウは無柄)。名前に反し、一つの株に花が3個付くことはほとんどないとのことです。であれば別の名前を付ければよかっただろう、と思うのはyamanekoだけか。
| オオバタチツボスミレ |
オオバタチツボスミレは北方系の植物。北海道に多く、本州では尾瀬が分布のほぼ南限だそうです。似た名前のスミレにオオタチツボスミレというものがありますが、名前からするとこれは大きいタチツボスミレということでしょう。オオバタチツボスミレは葉が大きいタチツボスミレということになるのだと思います。残念ながら上の写真には葉がはっきりとは映っていませんが。
細長い大江湿原の真ん中を流れる大江川。
尾瀬の湿原には多くの川が流れています。そのうち周囲の山から流れ下っている川の場合、山から土砂を運んできて湿原内の流れの両岸に堆積させ自然堤防を作るため、そこに林(拠水林)ができることがあります。当然、川の流れ出しが湿原内にある場合は自然堤防はできません。ここ大江湿原には拠水林は見られず、後者のパターンです。
| 分岐 |
11時10分、木道に分岐が現れました。ここから右手に伸びる道は尾瀬沼西岸の沼尻まで続いています。沼尻は尾瀬沼の水が尾瀬ヶ原に向けて流れ下る(標高差250m)水口に当たる場所です。yamanekoはとりあえず直進し、ビジターセンターや山小屋のあるところまで行き、引き返してこの分岐を分かれて沼尻に向かいます。
| リュウキンカ |
リュウキンカ。遮るもののない湿原に生きる植物は、このように日の光を存分に浴びられる反面、風雨にもそのまま晒されるということですね。そんな中で数千年にわたって命を繋ぎ続けてきたその強さに感服します。
| 尾瀬沼と燧ケ岳 |
右手には尾瀬沼と燧ケ岳の大パノラマが広がっています。燧ケ岳にはまだ雪渓が残っていますね。当然ですが尾瀬沼の水際に護岸はありません。地面から連続的に湖水に繋がっている、下界ではありそうでない水辺の風景です。所説あるようですが、大江湿原は尾瀬沼が徐々に湿原化していったものと考えられていて、この水辺はまさにその移行過程の現場ということのようです。
| 長蔵小屋 |
ほどなく尾瀬沼東岸に到着しました。ここには環境省のビジターセンターのほか、長蔵小屋、尾瀬沼ヒュッテといった山小屋、売店もあります。
江戸時代、ここに交易の場が設けられていて、会津から来た人と上州から来た人が、お互いに交易品を置いておく形で取引がなされていたとのことです。相当な信頼関係がなければ成立しないやり方ですね。明治中期まで続いていたそうです。
| ミツガシワ |
休憩後、来た道を戻ります。これはミツガシワ。氷期からの生き残りといわれています。どちらかというとヒタヒタと水に浸かるような環境を好む植物です。
| 沼尻へ |
そして分岐を西へ。正面に見える丘の中に入っていきます。
| 大江川 |
大江湿原を流れてきた大江川を渡ります。水深は3mくらいありますが、水が澄んでいて底まで見えるのは貧栄養の証か。
| 森の中へ |
久しぶりに林間を歩きます。木陰が有難いです。
| 長英新道分岐 |
しばらく行くと長英新道との分岐が現れました。長英新道とは平野長英氏が拓いた燧ケ岳への登山道で、yamanekoも歩いたことがあります。今日はここは直進です。、
| 浅湖湿原 |
ここから沼尻までの間には小さな湿原をいくつか横断していきます。ここは浅湖湿原という名が付けられている湿原で、比較的大きめな湿原でした。
| ミズバショウ |
ミズバショウ。尾瀬に来ている実感が湧きますね。
浅湖湿原を抜けると再び林間へ。
| コミヤマカタバミ |
コミヤマカタバミ。花もさることながら、ハート形の小葉に目が行きますね。ハート3個で一つの葉です。
梢越しの尾瀬沼。正面に見える山は、地図上での特定はできるのですが、名前はどこを調べても分かりませんでした。標高1885mなのでとりあえず「1885ピーク」と呼ぶことにしました。
木漏れ日の下を歩く。日々の小さなストレスさえも悉く霧散させてしまうほど、清々しいです。
| ダケカンバ |
新緑のダケカンバ。なんだか木全体が輝いていませんか。
また小さな湿原を渡ります。ここまでも森歩きと湿原歩きを何回か繰り返しました。
少し開けたところに出ました。2万5千分の1の地図上では「オンダシ」と記されている辺りです。静かな湖水ですね。写真左奥の山はさっきの1885ピークで、写真右の平たい山は皿伏山です。
またしばらく歩いていくと、木立の向こうに建物が見えてきました。あそこが沼尻の休憩所になります。
| 沼尻平 |
開けてきました。ここからが沼尻平。「平」と名が付いていますが、平原ではなく湿原です。
沼尻平に出てから振り返ると、燧ケ岳の山頂が望めました。近すぎてのしかかるように見えています。
沼尻の休憩所を目指して歩いていきます。
ん? 正面の木立の奥に見えるのは…、至仏山!
| 至仏山 |
アップで見ると、おお、やはり至仏山です。ここからの距離は約11kmほど。尾瀬ヶ原の西側に聳える、尾瀬を代表する山の一つです。
| 分岐 |
この分岐を直進すると尾瀬ヶ原に至ります。ここは左手へ。
| 沼尻休憩所 |
するとすぐそこに沼尻休憩所があります。まだ新しいです。というのは、以前ここにあった沼尻休憩所は10年前に失火で焼失してしまい、yamanekoがその翌年に訪れた時には更地になっていました。かろうじて建物の基礎部分の痕跡が見られる程度でしたが、どうやら2年前に再建されたようです。
休憩所の前からの眺望です。静かに広がる尾瀬沼。正面奥には檜高山、右手には1885ピークがその湖水を見下ろしています。
| 昼食 |
時刻は12時10分。休憩所に入り昼食をとることに。七入山荘で用意してもらったおにぎり弁当です。これを食べて復路のエネルギーを補給します。
今日の野山歩きはちょうどここが折り返し地点。食後、ちょっと休んでまた歩き出します。(後編に続く)