
大江湿原・尾瀬沼 ~遥かなる花の別天地へ(後編)~
 |
(後編) |
【福島県 檜枝岐村 令和7年6月17日(火)】
♪夏が来~れば思い出す~。遥かなる花の別天地「尾瀬」での野山歩き。後編です。(中編はこちら)
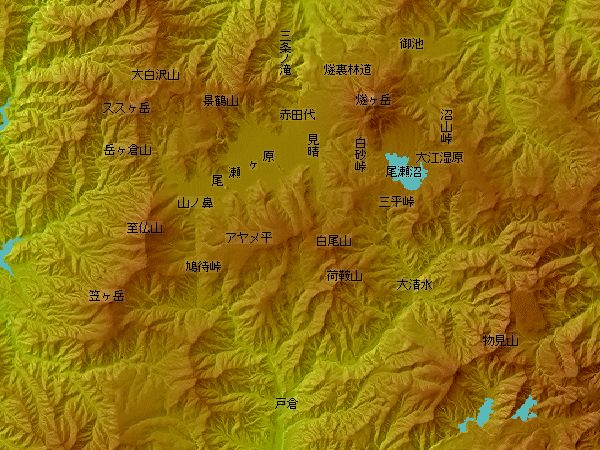 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
|
| 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
沼山峠の登山口を9時30分に出発し、11時30分に尾瀬沼東岸に到着。そこで一休みして西岸の沼尻まっでやって来ました。新しくなった休憩所で昼食をとって、ここから来た道を戻ります。時刻は12時25分です。
広々とした休憩所のデッキ。この日は日差しが強かったので他の登山者もみんな建物の中で休んでいました。
| 沼尻平 |
沼尻平を歩いていきます。平日とはいえ誰もいないという贅沢な空間です。
| アサノハカエデ |
森に入って頭上を見上げると、アサノハカエデの葉が風に揺れていました。新緑のように輝いています。もう6月下旬になろうかという時期ではありますが。
鳥の声しか聞こえない湖畔の道をトコトコ歩いていきます。
| ミズバショウ |
ミズバショウの花は棒状の花序の表面を覆うようにびっしりと付いていて、今ちょうどそれぞれの花が花粉を出しています。白い花弁のように見えるものは仏炎苞。葉が変化したものです。
| エンレイソウ |
エンレイソウ。茎の先端に大きな葉を3個付け、その中央に花を付けます。
おや、往きには気が付きませんでしたが、桜が咲いているじゃないですか。
| タカネザクラ |
これはタカネザクラですね。図鑑によると標高1000mから2800mまでの高地に生え、桜の仲間では最も標高の高いところで生きている種なのだそうです。尾瀬沼湖畔の標高は1660m。標高的にど真ん中ですね。
| サンショウウオの卵嚢 |
水の中に白くふわふわした感じの物が。これはサンショウウオの卵嚢ですね。尾瀬ではクロサンショウウオ、トウホクサンショウウオ、ハコネサンショウウオの3種が確認されているそうです。これはハコネサンショウウオのものでは。
木立の向こうに浅湖湿原が見えてきました。
| 浅湖湿原 |
まさに非日常の風景。「この先には何が待っているのか」って、冒険物語の主人公になったような気持ちになります。
| 長英新道分岐 |
1時10分、長英新道との分岐まで戻ってきました。大江湿原まではあとちょっとです。
| コミヤマカタバミ |
半日陰に咲いているイメージのあるコミヤマカタバミですが、こうやって陽射しに輝いている様子もきれいです。この季節を謳歌しているんでしょう。
| ハリブキ |
これはハリブキの若い株。今は20cmほどですが、成長すると高さ1mくらいになります。幹や枝に長く鋭い刺が密生していて、過剰防衛と言っていいほど針だらけです。葉も葉脈上に針が並ぶなど例外ではありません。しかも冬芽の段階から針に守られているという徹底ぶり。
おお、大江湿原が見えてきました。尾瀬沼沿いの道はここまでです。
| 三本カラマツ |
大江湿原が尾瀬沼に接する辺りに小さな塚のような場所があり、そこに3本のカラマツが立っています。その名も「三本カラマツ」。大江湿原のシンボルツリーのようでもあります。
言い伝えによると、平安時代末期、平清盛と対立し敗れた以仁王が落ち延びて行く際に、この地でお供の尾瀬中納言藤原頼実が病死したことから、その墓所として塚が築かれたとのこと。その後、この墓を守るために兄の尾瀬大納言藤原頼国が檜枝岐に定住し、牛に乗って幾度となく弟の墓に参ったのだそうです。そしてその頼国が亡くなった後、今度は共にこの塚に通った牛がこの場を訪れ、塚の周りを三度巡ってから沼に向かい、静かに水の中に隠れたのだそうです。なんとも不思議な話です。ただ、カラマツ自体は比較的新しい時代に植えられたもののようです。
| 丁字路 |
3本カラマツを過ぎるとすぐに丁字路の分岐が現れます。右に行くと尾瀬沼東岸地区、左は沼山峠に至ります。ここは一旦右に向かい、東岸で小休止した後沼山峠に戻ります。
| コバイケイソウ |
コバイケイソウの花序が伸び始めています。夏の高山を代表する花ですね。
| オオバタネツケバナ |
これはオオバタネツケバナですね。タネツケバナを漢字で書くと「種漬花」で、稲作で種籾を水に漬ける頃に花が咲くことから名づけられたものだそう。
| ミツガシワ |
ミツガシワ。カシワの葉に似た3個の小葉持つことからの名前だそうです。どう見てもカシワの葉に似ているとは思えませんが。花には雌しべが長いタイプと短いタイプの2種があり、長いタイプの花しか結実しないのだそうです。写真のものは長いタイプでした。
| 尾瀬沼ビジターセンター |
尾瀬沼東岸にある環境省のビジターセンターに立ち寄りました。時刻は1時30分です。尾瀬にはビジターセンターが2か所あり、ここの他に尾瀬ヶ原西端の山ノ鼻にあります。レンジャーさんが常駐しています。
| サンカヨウ |
深山で出会うことの多いサンカヨウ。山に来たことを実感させる花です。果実は濃いコバルトブルーで、表面は白い粉を吹いたようになっています。サンカヨウは漢字では「山荷葉」と書き、荷葉とはフキの葉のこと。確かにフキの葉に似ています。若干切れ込みはありますが。
| 燧ケ岳 |
尾瀬沼東岸から望む燧ケ岳。この山の雪解け時に現れる雪形に、鍛冶屋さんが使う火打ち鋏に似たものがあることから名付けられた名前だそうです。雪の多い地方では雪形に着目したネーミングの山はありがちですね。
さて、燧ケ岳に挨拶をして、そろそろ沼山峠に戻りましょう。
大江湿原に向かって歩き出します。ああ、次に来られるのはいつだろうか。名残惜しいです。
| シナノキンバイ |
シナノキンバイにもお別れを。
| イワカガミ |
おっと、こちらは今日初めて見たイワカガミ。湿原の中にあるとなかなか見つけられません。「忘れないでよー」と声をかけられたような気がしました。笑
| 大江湿原 |
あー、また慌ただしいところに戻っていくのか、なんてことが瞬間脳裏をかすめますが、いやいや、尾瀬を離れるまではこの状況を楽しむべし、などと考えながら木道を歩きました。
| ワタスゲ |
おお、こちらも尾瀬の湿原を代表する植物。ワタスゲです。見てのとおりの名前ですね。
| ショウジョウバカマ |
ショウジョウバカマの花色にはバリエーションがあります。写真のようにオレンジ色のものから紅色、赤紫色のものまで。
大江湿原を過ぎ、木道が森の中に入っていきます。
ここから標高差110mを登っていきます。
| イワナシ |
こうやってじっくり見るとイワナシの花は可憐ですね。花冠は釣鐘型で、白色から薄桃色に至るグラデーションがいい感じです。
峠に向かう直線。向こうからクマが走って来たら逃げ場がありませんね。尾瀬はクマの影の濃いところですが、近年ニュースで巷を騒がせているアーバンベアとは異なり、そこに棲んでいるのは分別のある昔ながらのクマという印象です。yamanekoもニアミスの経験がありますが、それもむしろ先方から避けてくれたような気がしています。
| 沼山峠 |
ここが沼山峠のピークです。峠感はほぼありません。
沼山峠から下ることしばし。木立の向こうに沼山峠バス停の建物が見えてきました。ここまで特にケガも体調不良もなく戻ってこられました。もしかしたらトレッキングシューズの効果もあったかもしれません。そういうことにしておきましょう。安心して歩けましたし。
| 沼山峠バス停 |
2時35分、沼山峠バス停に戻ってきました。とりあえず整理体操をしておきましょう。
| 尾瀬口船着き場行き |
バスの発車は15時ちょうど。このバスは御池を過ぎて奥只見湖の尾瀬口船着き場に向かうようでした。その終点のバス停はダム湖の最奥にあり、こんなところに取り残されたりしたら絶望しかないというような場所。国道こそ通ってはいるものの、新潟側からその”尾瀬口”に来るにはくねくねの山道を車でやってくる必要があり、わざわざそこでバスに乗り換えて尾瀬に向かう人はいるのだろうかとずっと疑問でした。今回ふと思いついたのは、もっぱら御池から平ヶ岳の登山口(終点の船着き場までの途中にある)に行く人がこのバスを利用するのではないかということ。平ヶ岳は日本百名山の一つなので、そこそこの利用者があるのだと思います。ついでにその先の船着き場(奥只見ダムのダムサイトとの間を運航している模様)まで路線を延ばしているということでしょう。
| 御池 |
yamanekoは寝過ごすことなく御池で下車。忘れ物とかないよう今度は落ち着いて帰り支度をしました。そして、妻へのお土産(お菓子とTシャツ)を買って、3時30分、ドリーム号Ⅲとともに東京を目指して走り出しました。
今回の尾瀬行きは約2年ぶり。片道6時間の遠路を走ってきたyamanekoの期待を裏切らない楽しいものでした。にもかかわらず、また来月にでも訪れたいなと思わせる、尾瀬にはそんな不思議な魅力が確かにありますね。