
大江湿原・尾瀬沼 ~遥かなる花の別天地へ(前編)~
 |
(前編) |
【福島県 檜枝岐村 令和7年6月17日(火)】
今年も早、6月中旬。梅雨入り後も連日の猛暑です。梅雨って毎年こんなに暑かったっけ? と天気予報を見るたびについ口にしてしまう毎日。どっか気持ちいいところに行きたいなとボンヤリ考えるyamanekoでしたが、ふと「!」マークとともに尾瀬の風景が頭に浮かびました。おお、尾瀬か、尾瀬があったな。ふむ、尾瀬に行くなら久しぶりに尾瀬沼がいいな。
急に活力を取り戻した感じで、直近の尾瀬の天気予報を確認してみると、なんとしばらく晴れ模様。梅雨のこの時期に数日晴れるとは僥倖と言えるでしょう。そうでなくても尾瀬は天気が崩れやすい場所なのです。で、これは行くしかないかということになりました。
尾瀬沼へは、群馬県側の片品村大清水から三平峠を越えて行くルートがありますが、車を停めてから標高差550mを登らなければいけません。一方、福島県側の檜枝岐村御池から向かえば、沼山峠までシャトルバスがあるので、実質標高差は100m弱。圧倒的にこちらの方が楽です。ただ、福島県側に回り込む分、東京からだと数時間余計に時間がかかってしまいますが。なので、前日のうちに檜枝岐に入り、そこで一泊して尾瀬にアプローチすることにしました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前10時、ドリーム号Ⅲで出発。この日は移動だけなのでゆったりと走ればOKです。圏央道外回りから久喜白岡JCTで東北道に入り、途中上河内SAで昼食をとって、宇都宮の先、西那須野塩原ICで一般道へ。さて、ここまでも長かったですが、ここからも長い長い。塩原温泉を越えて会津西街道に入り、福島県に入ったら国道352号線をひたすら西へ。檜枝岐村の中心部を通り過ぎて宿のある七入に着いたのは午後3時半になっていました。泊まるのは七入山荘。今から13年前に一度泊まったことがある宿です。さっそくひとっ風呂浴びて長距離運転の疲れを癒しました。
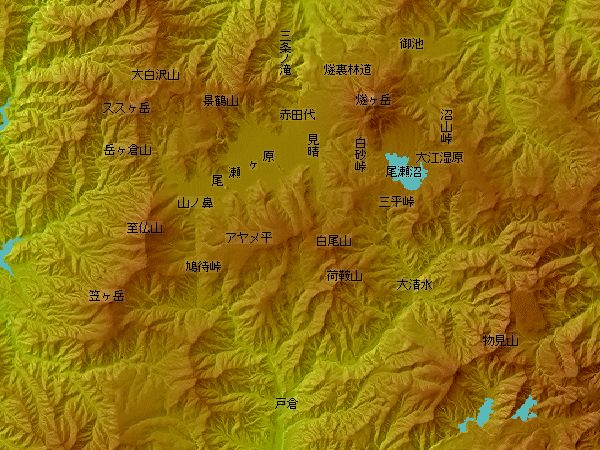 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
|
| 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
今回のルートは、尾瀬エリアの東側、沼山峠から大江湿原に入り、尾瀬沼東端に出てそこから沼の北岸を西進。西端の沼尻で折り返して、来た道を戻るというものです。
| 御池駐車場 |
翌朝、7時半にチェックアウトし、尾瀬散策のベースとなる御池へ。実際の登山口は御池から5kmほどの沼山峠にあり、御池-沼山峠間はシャトルバスで移動することになります(一般車両通行禁止)。まずは御池の駐車場にドリーム号Ⅲを停めて、出発の準備を始めました。
| バスターミナル |
ほどなく8時ちょうど発のシャトルバスがやって来ました。なかなかナイスなタイミングです。急いで往復チケットを買ってバスに乗り込みました。乗客はyamanekoの他にご夫婦が1組。そして沼山峠に向けて定刻に出発しました。
| 橅平 |
沼山峠までの所要時間は20分ほど。標高差にして約200mを上っていきます。途中、橅平(ぶなだいら)を見下ろせるところでバスが一時停車。運転手さんがその地形の成り立ちを簡単に解説してくれます。ブナやオオシラビソなどのもこもことした樹冠が広がっているのがよく分かりますね。
橅平は、太古(16万年前とも35万年前とも)に檜枝岐川の最上流部で噴出、堆積した溶結凝灰岩からなるテーブル状の平坦面で、深い谷を埋め尽くす形でできています。写真奥の深い切れ込みが檜枝岐川の谷で、そこから一気に400mの壁を登りきると、標高1400mに広がる橅平の上面に出ます(つまり400mの厚さ堆積した!)。昨晩泊まった七入山荘はその壁面の直下に位置しています。ちなみにこの台地は後に形成された燧ケ岳の土台となっているのだそうです。
ここでyamanekoは重大なことに気が付きました。なんと靴がスニーカーのまま。トレッキングシューズに履き替えるのを忘れていたのです。さっきバスがいいタイミングで来たので、履き替える前にそのまま乗り込んでしまったようです。あちゃー、となり、次に頭の中で葛藤が。「今日歩くのはほとんど木道だし、スニーカーでもいけるだろう」、「履き替えに戻ると1時間のロスになるし、往復のチケット代(1600円なり)も無駄になる」、「いや、尾瀬での事故で最も多いのは木道での転倒だよな」、「仮に事故でも起こしたら、やっぱりやったかと後悔するだろう」、「そもそも山で安易な選択をし万全を期さないというのはだめだろう、仮に何も起こらなかったとしても」…、結局、履き替えに戻ることに決めました。(そこから終点の沼山峠までの時間が空しかったこと。)
| 沼山峠口 |
8時20分、バスは沼山峠口に到着。いつの間にか素晴らしい晴天になっていました。同乗のご夫婦はほどなく登山口に向かったようです。本来ならyamanekoもストレッチを済ませて出発するはずだったのですが…。
乗ってきたバスで折り返すまで10分間の空き時間があります。せめて周辺の観察でも。
| ウワミズザクラ |
ウワミズザクラです。多摩丘陵では4月中旬に開花していましたが、ここでは2か月遅れなんですね。
| キセキレイ |
軽やかな鳴き声を聞かせてくれるのはキセキレイ。雌のようです。渓流の鳥といったイメージでしたが、こんな高いところで見かけるなんて。図鑑で調べてみたところ、平地から標高2000m以上の高地にまでいるとのことでした。
運転手さんの合図で再びバスに乗り込み、乗客一人で御池に戻りました。そして靴を履き替え、チケットを買いなおして、あらためて沼山峠行のシャトルバスへ。今度は大型の観光バスです。しかもほぼ満席。どうやら某旅行社のツアー客の皆さんが乗り込んでいるらしかったのですが、一応乗合のシャトルバスといった位置づけなので、yamanekoもわずかに空いていた席の一つに座りました。
そして9時ちょうどに出発です。ツアー客の皆さんは全国各地から集まっているようで、隣に座っていた女性は一人で長崎から来たと言っていました。今日、沼山峠から尾瀬沼に向かい、そこから尾瀬ヶ原東端の見晴まで下って山小屋に一泊。翌日は尾瀬ヶ原を縦断して山ノ鼻から鳩待峠に出るといった行程だそうです。その女性は初めての尾瀬ということで、とても楽しみにしていたようでした。
9時20分、沼山峠に到着しました。1時間前に見た風景です。ツアーの皆さんは10人程度×3グループに分かれストレッチを始めました。
| 登山口 |
そして、そのグループがみんな出発した後、おもむろにyamanekoもスタートしました。時刻は9時30分になっていました。
ちなみにこの場所はバスの停車場としての「沼山峠」ですが、地理上の沼山峠はここから山道を登ったところにあります。
登山口から沼山峠までの標高差は約90m。その間は階段状の木道になっていて、傾斜は緩やかです。
| ムシカ |
森の中で最初に出迎えてくれたのはムシカリでした。葉がよく虫に喰われるので「虫喰われ」が転訛した名前だそうです。確かに丸い大きな葉全体がレース状に喰われ尽くされているのをよく見ます。
| コミヤマカタバミ |
小型のミヤマカタバミでコミヤマカタバミ.。ハート形の小葉が3個付き、ミヤマカタバミの小葉が角張っているのに対し、コミヤマカタバミの小葉は角が丸っこく、より典型的なハート形をしています。
| オクノカンスゲ |
木道の脇に生えているこれはオクノカンスゲか。
小穂をアップで。雄小穂の葯が水平に伸びだして、試験管ブラシのようになっています。一般的にスゲの雄小穂の葯はみな垂れ下がって付いているイメージですが。たまたまか。雄小穂の下にある爪楊枝のように細いのが雌小穂。飛んできた花粉をキャッチできるようヒゲが生えています。
| コミヤマカタバミ |
コミヤマカタバミ。林間の潤った地表に生えているせいか、瑞々しいです。
林床にはまだ雪が残っているところも。
オオシラビソの幹のくぼみで生きているコケ。そのコケをベースに芽吹いている植物。さすがは尾瀬の自然林。命が濃いです。
木道がなだらかに伸びています。気持ちいい。(もう靴を履き替えに戻ったことなど忘れてしまっています。)
| スギゴケ |
切り株を覆うモフモフのスギゴケ。
| ダケカンバの林 |
頭上には青空。ダケカンバの若葉が輝いています。ここでは今まさに新緑の季節なんですね。
| ムシカリ |
ムシカリの花。アジサイと同じように、花弁が開いているように見えるものは装飾花。結実する機能は持ち合わせていなくて、もっぱら客寄せ用の飾りです。その装飾花に取り囲まれるようにある粒々が両性花の蕾です。ところで、葉が既に虫に喰われて点々と穴が開いていますね。一面レース状になることも珍しくないです。
| コミヤマカタバミ(ピンクver) |
こんなものもありました。コミヤマカタバミですが花弁がピンク色をしています。yamanekoは初めて見ましたが、調べてみると稀にあるようです。土壌の性質の影響を受けてこうなるのでしょうか。
| 峠 |
9時55分、峠のピークにやって来ました。写真でも分かるとおり、超緩やかに尾根を越えていきます。
峠を越えると、当たり前ですが道は下っていきます。(片峠という場合もありますが) 登山口から尾瀬沼畔の大江湿原までは、90m上って110m下るといった関係になります。
| ゴゼンタチバナ |
これはゴゼンタチバナの葉ですね。行儀よく並んで生えていました。
| 休憩スペース |
しばらく下ると雛壇状の休憩スペースがありました。さっきのツアーの人たちが休んでいましたが、休憩を終えて出発した後の状況です。
そこのベンチからの眺望。森が開けて、奥の方に檜高山のピークが見えていました。檜高山は尾瀬沼東岸にある山です。
| イワナシ |
足元にイワナシが咲いていました、背丈はごく低く、地面を這うように生えていますが、これでもツツジ科の樹木です。この花に初めて出会ったのは岡山県北部にある森林公園でした。ただ、そのときのものは花冠が全体に朱色だったように記憶しています。地域的な変異か。
| ナナカマド |
頭上ではナナカマドの若葉が風に揺れていました。爽やかです。こういうのを眺めるだけでも遠くまでやって来た甲斐があるというものです。
| 森を抜けると… |
おっ、森が途切れ、その先に湿原が見えてきました。いよいよ大江湿原です。
| サンカヨウ |
サンカヨウ。花は白いですが、雨に濡れると花弁が透明になるという変わり者。乾くとまた白色に戻ります。
| エンレイソウ |
こちらはエンレイソウ。漢字では「延齢草」と書き、なんか薬効がありそうな名前です。まだ森から出ていませんが、湿原が近いというだけで花が多くなってきた気がします。
| コバイケイソウ |
コバイケイソウの若葉が伸び始めています。この状態のときが山菜のウルイ(オオバギボウシの若葉)とよく似ていて、誤食による中毒事故の報道をときどき目にします。よっぽど自信がなければ野生の植物は食べない方がいいです。
| 大江湿原 |
10時35分、大江湿原に出ました。解放感満点です。
| リュウキンカ |
これはリュウキンカですね。尾瀬の湿原の代表的な花です。黄色い花弁のように見えるのは萼片で、リュウキンカに花弁はありません。キンポウゲ科の植物によくあるパターンです。
| ミズバショウ |
おお、尾瀬といえばミズバショウ。運よく出会えました。花期は5月中旬から6月下旬までですが、年によりピークに結構ずれがあり、6月初旬に行っても既にほとんど終わっていたり、また、直前に開花を確認して訪れても急に霜が降りて一気に傷んでしまったりと、yamanekoも残念な思いをしたことがあります。今回は急に決めた尾瀬行きにも関わらずラッキーでした。
| ミツバオウレン |
ミツバオウレンは名前のとおり3つの小葉が特徴。こちらもキンポウゲ科で、白い花弁状のものは萼片です。萼片の幅は、セリバオウレンよりも太く、バイカオウレンよりも細いです。
| 木道の間から |
木道は複線。その間から顔を出しているミズバショウです。可愛いですね。
| タテヤマリンドウ |
この涼やかな花はタテヤマリンドウ。多年草ではないので、秋に実を結ぶと地上部も根も枯れてしまいます。普通の一年草であればできた種子が地面に落ち、翌春に芽吹くのですが、タテヤマリンドウの場合は秋のうちに芽吹いてその状態で越冬し、翌春に花を付けるという変わったパターンです。
| 大江湿原 |
ああ、とつい声が出そうなほど伸びやかな気持ちになれるこの風景。この空間にyamanekoただ一人なんて、人口密度低すぎです。(正確にはさっきのツアーのグループがずっと向こうに見えていますが。)
大江湿原は細長く、この先に尾瀬沼が広がっています。そこまでの間にもたくさんの花に出会うでしょうね。楽しみです。(中編へ続く)