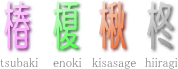2025年10月6日(月)
①
この時期、藪を覆い尽くしているのがこのカナムグラ。これは雄花序で成熟すると花粉をサラサラと散布します。秋の花粉症に困っている人にはありがたくない存在。

②
こちらはカナムグラの雌花序。花粉の受け手ですね。まるで鎧のようです。カナムグラの茎(蔓)には硬く短い刺が下向きに密生していて、指でなぞることもできないほど。これを他の植物に絡めて四方八方に伸びて行くという手法です。

③
野草見本園へ。コバノカモメヅルがまだ咲いていました。ササのような葉の付け根(葉腋)から花茎を伸ばしているのが分かります。
④
これはレモンエゴマの花序。見るからにシソの仲間ですね。エゴマに似ていてレモンのような香りがすることが名の由来だそうです。日本に自生する種ですが、少なくともレモンが渡来した明治初期以降に命名されたものですね。

⑤
コブシの集合果。手前のものは成熟しきって個々の果実があらわになり、更にそれが裂けて朱色の種子が顔をのぞかせています。奥のものは熟す前の状態。

⑥
大田切池の畔に立つクヌギ。もふもふのマフラーを巻いているように見えます。

⑦
フェンスに絡みつくヘクソカズラ。丸いのは果実です。完熟までもう少しといったところでしょう。リースの部材に使えそうですが、すぐにバラけてしまってなかなか上手くいきません。
⑧
ドッグランの近くに植栽されているシュウメイギクの園芸品種。見た目もキクに似ていますがキクの仲間ではありません。自生のものは古い時代に中国から渡来。萼片(花弁のようにみえるもの)の数は30個程度あるそうです。ダリアみたい。
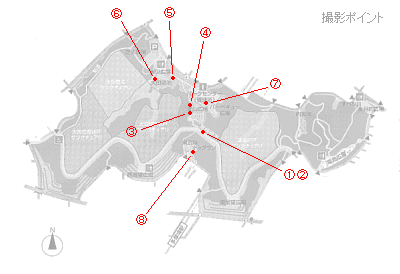
|
|
|
|
2025年10月8日(水)
①
今回は野草見本園内で完結。
これはイヌショウマです。花序の下の方から咲き上がっていくパターン。
②
クサボタンの花序。くるっと丸まった萼がアンティーク調です。これでセンニンソウの仲間と言われてもピンときませんが、果実を見るとそっくりなので、納得です。(センニンソウの果実)

③
ホトトギスが咲き始めました。もしかしたら園芸的に手が加えられたものかもしれません。弾丸のようなものは蕾です。

④
フジカンゾウの花序です。ヌスビトハギに近い仲間ですが、こちらの方が花が華やかです。名前の「藤甘草」の「藤」はフジのような花という意味。「甘草」は山菜として親しまれているノカンゾウではなく、マメ科のカンゾウのこと。生薬や甘味料として利用されている植物だそうです。

|
|
|
|
2025年10月15日(水)

①
秋らしい気温になってきました。
これはアキニレの若い果実。2枚の果皮に挟まれて種子がある真ん中の部分がぷくっと膨らんでいます。生八ツ橋みたいです。

②
ガマズミの実が色づきました。写真のように深い紅色になるものと、次の写真のように朱色になるものがあります。両者は同じものなのか、単なる株ごとの個性なのか。それとも熟していく過程の異なる姿?

③
こちらが朱色のもの。深紅色のものがやや扁平な形なのに対し、こちらは球形です。それぞれの株元をたどってみると、少なくとも同じ株の枝で両者が混在しているものは見つけられませんでした。まったく別の株か、あるいは株本が隣接しているものはありました。

④
ハリブキの若い果実です。高木になるものが多く、いつも見上げるアングルになってしまい、観察に苦労します。実の付き方がなんとなくヤツデに似ていますね。同じウコギ科に属しています。

⑤
こちらはミズキの果実。全体に円錐形の果序となっていて、どの果序も葉の上に頭を出すように付いています。鳥たちに食べてもらいたいんでしょうね。
⑥
アカネの花序。ぱっと見、カナムグラの雄花序に似ています。咲いている時期も同じなのでややこしい。でも、カナムグラは風媒花で、雄花はぶら下がるように付いていて、風に揺られて花粉を漂わせますが、このアカネは虫媒花で、花粉を飛ばすようなことはありません。ゆすってみると一発で見分けられるということですね。

⑦
イヌホオズキ。よく似たものに外来のアメリカイヌホオズキというものがあり、両者は葉の幅の細さ、果実の光沢の有無などで見分けられるそうです。イヌホオズキの花は薄紫色ですが中には白花もあるとのことで、決め手にはならないようです。
⑧
今年もコシオガマが咲き始めました。ロープで囲って保護していたエリアです。ただ、一年草なので、翌年も咲いてくれるとは限りません。なるべく周辺環境が攪乱されないようにするだけです。

⑨
クマノミズキの花序。枝先がサンゴのように見えます。ミズキの果序が円錐状だったのに対し、クマノミズキは盃状になった枝の上面に実を付ける形をしています。

⑩
南広場の明るい林床にポツンと一株、マルバフジバカマが。唐突感がありました。北アメリカ原産で、昭和初期に見つかったものだそうです。誰かが植えたとも思えないし、なんでここに?去年もあったのかな。

⑪
頭花をアップで。15個から25個の筒状花が寄り集まって一つの頭花を形作っているのだそうです。繊細な工芸品みたいですね。
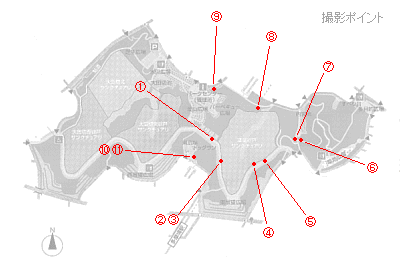
|
|
|
|
2025年10月18日(土)

①
野草見本園にもキバナアキギリがありました。九反甫谷戸の群生地ではあらかた花期が終わっていると思います。
②
息が長いカリガネソウの花。なかなかスタイリッシュですね。もうこの時期には果実ができ始めています。写真下部の4つ寄り集まっている球形のものが果実です。

③
ヤクシソウ。漢字では「薬師草」と書きます。その謂れは不明とするものもありますが、普通に考えたら薬効があるからじゃないかと。実際に皮膚の腫物の民間薬として使われていたそうです。ちなみに薬師といえば薬師如来。他の如来(釈迦、大日、阿弥陀)の名前を持つ植物はあるかと調べてみましたが、少なくとも標準和名としてその言葉を冠している植物はありませんでした。

④
チャノキの花です。たくさんの雄しべが特徴で、必ず俯いて咲きます。

⑤
この毒々しいものはゴンズイの果実、実の部分(果皮が肥大したもの)が開裂して、黒い種子が露出しています。これが完熟の状態。この種子、落ちそうで落ちないんですよね。

⑥
風に揺れるススキとセイタカアワダチソウ。モズの声も聞こえてきます。秋ですな。

⑦
キンミズヒキの花序。花は根元側から咲いていくようです。花が終わった後にできる果実は、お馴染みのひっつき虫。気が付くと運動靴の紐の部分にびっしり付いていたりします。
⑧
カラスウリの果実。形といい色といい、見るからに美味しそうに実っていますが、実はスカスカで、なにより不味い(苦い)とのこと。こんなに見かけ倒しの果実もちょっと他にないでしょう。
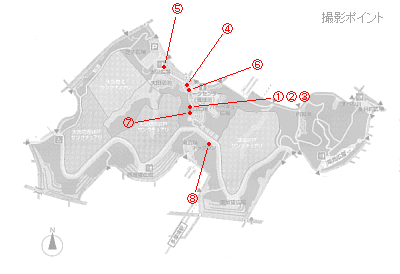
|
|
|
|
2025年10月28日(火) その1

①
尾根道から里山広場に下りていくと甘い香りが漂っていました。カツラの落ち葉から放たれる香りです。カツラと言えば葉はハート形ですが、落ち葉を見るとそうでないものも多いようです。

②
カツラ本体の方はこの黄葉。秋が深まりつつあります。あの猛暑が嘘のよう。
③
野草見本園へ。ニシキギの実が熟して開裂し、種子が露出しています。枝に板のような翼があるのが分かりますが、この翼がないものをコマユミと言います。昔、コマユミの園芸品種がニシキギだと思っていましたが、それは誤り。

④
クサボタンの果実。センニンソウやハンショウヅルの果実にそっくりです。調べて見るといずれもキンポウゲ科センニンソウ属でした。

⑤
シロダモ。赤く熟しているのは去年結実した果実。シロダモの果実は翌年の秋に成熟します。同じ枝に付いている粒々は今年の花芽。もうじき開花です。

⑥
クサギの実もそろそろ終わりですね。哀愁を感じます。

⑦
代わってムラサキシキブが実を結ぶ時期になりました。民家の庭先などでよく見かける実がびっしりと付くものは、園芸用に手を加えられたコムラサキです。ムラサキシキブの疎らな実の付き方も、虫喰いの葉と相まって、野趣があって良いものです。

⑧
径1cmほどの頭花をたくさん散らしたように付けるヤクシソウ。野辺の菊です。

|
|
|
|
2025年10月28日(火) その2

①
シロヨメナ。白菊としては最もポピュラーな野菊ですが、イナカギクと生えている場所も含めてよく似ているので、葉の形や総苞(頭花の付け根部分)の様子を確かめてみる必要があります。

②
チゴユリの黄葉って和テイストで趣がありますね。yamanekoの好きな色合いです。

③
こちらはチゴユリの実。茎頂に黒く熟す実を1個付けます。

④
薄い紫色の舌状花をもつノコンギク。紫色の菊ではこちらが最もポピュラーです。

⑤
秋晴れをバックにした桜の紅葉。清々しいです。

⑥
ハリエンジュの果実がぶら下がっていました。枯れているようにも見えますが、これが熟した状態。鞘の中に扁平な種子が数個入っています。

⑦
シャクチリソバの花が満開です。尾根道の脇に毎年群生する場所があり、草刈りで刈られないよう保護しています。果実は普通のソバより一回り大きいですが、食用には向かないと聞いたことがあります。

|
|
|
|
2025年10月29日(水)
①
小山内裏公園の正面入口にあるシンボルツリー。ケヤキです。今年も紅葉が始まりました。もう少し葉の量が減ってくるとより風情が増します。

②
尾根道沿いに植栽されているヒイラギモクセイ。花はヒイラギにそっくりです。見分け方は葉の棘の数。ヒイラギは棘が2~5対ありますが、ヒイラギモクセイの場合は8~10対です。

③
尾根道沿いにはサザンカも多く植栽されています。散る際には花弁がバラバラに落ちるので、株の下は花弁の絨毯ができます。
④
野草見本園にやって来ました。ヤマハッカがひっそりと花を付けていました。小さいですがシソ科に特有の唇形花です。名前にはハッカと付きますが、香気はほとんどありません。

⑤
今や野生ではほとんど見ることのなくなったフジバカマ。葉を摘んだ後、生乾きのときには桜餅の匂いがするそうです。感じたことはありませんが。桜餅に用いられるのはオオシマザクラの葉で、それと同じクマリンという香り成分を持っているようです。
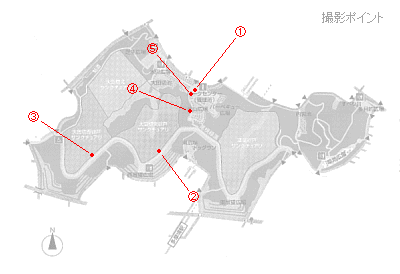
|
|
|
|
2025年10月30日(木)

①
調整池の近くのハリギリが花を付けていました。本来なら8月から9月に咲くものです。このすぐ近くの尾根道沿いにある株では既に実が熟しつつあるので、水辺に近いといった環境の違いで花の時期がずれているのかもしれません。

②
ヤマコウバシの果実。葉の様子といいこの果実といい、クスノキの仲間であることがよく分かります。
ヤマコウバシは落葉樹ですが、春が訪れるまでは枯れた葉が枝に残ったままです。その意味は何なんだろう。常緑樹とされるクスノキは、翌春に新しい葉と入れ替わる形で落葉しますが(全部ではなく半分程度)、それの変化形でしょうか。
③
この時期、野辺で地味に咲き誇っているイヌタデ。花の後も赤い花被は残って果実を包むのだそうです。大事な果実を守っているんですね。小さくてよく見えにくいですが。
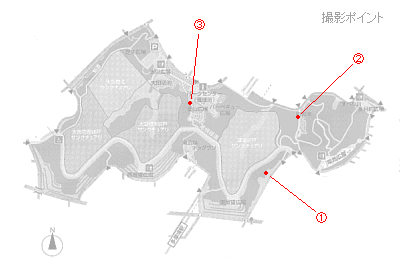
|
|
|
|
| |