2025年9月3日(水)

①
9月になりましたが真夏継続中です。
野草見本園のヤマホトトギス。見慣れた花ですが、よく考えるとかなり突飛な姿をしていますね。虫へのアピールでしょうね。
②
クズの開花時期になりました。花序の下の方から順に咲いていきます。花序の中ほどでは蕾が膨らみつつありますが、この状態に擬態して花序に紛れ込んでいるのはウラギンシジミの幼虫。花序をよーく見ると時々見つけることができます。

③
外来種のアカボシゴマダラです。30年前に埼玉県の秋ヶ瀬公園で発見され、その後南関東の各地で見られるようになったそう。現在も関西や東北地方に分布域が拡大中だそうです。在来生態系の保護のため駆除の対象となっています。人為的に放蝶されたものが広がった、または、各地で放蝶された、というのが定説のようです。

④
ガガイモ。花冠は5裂していて、内側に長い毛が密生しています。この時期には暑苦しい見た目です。

|
|
|
|
2025年9月4日(木)

①
野草見本園で。
これはカラワケツメイ。マメ科に属していますが、マメ科の花に特徴の蝶形花ではありません。蝶形花はマメ科の主流派閥であるマメ亜科の特徴で、ジャケツイバラ亜科のカワラケツメイにはその特徴はないのだそうです。

②
早くもオトコエシが開花し始めました。オトコエシは丈が高く、がっしりとした花茎を持っていて、そこが「男郎花」の名の由来。オミナエシ(女郎花)の姿と比べてということです。
③
ヤブランもあちこちで花序を伸ばし始めています。この花の撮影はいつも蚊との戦い。アングル、露出、絞りをぱっぱとセットして(ピントはオートで)シャッターを切ります。

④
一部開花しています。特段、花序の下から咲くとか上から咲くとかないようですね。
⑤
ツリガネニンジンです。花茎が伸びると一旦倒れてそこからまた上に向かって花茎を伸ばしたりします。なかなか姿勢の良いものに出会えません。
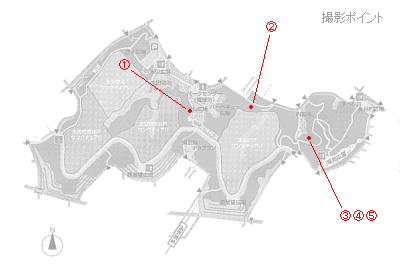
|
|
|
|
2025年9月10日(水)

①
野草見本園のカリガネソウ。9月に入ってからチラホラ開花し始めましたが、今年は例年より半月ほど遅めのようです。去年は逆に早かったですが。名前の由来は雁(かり、かりがね)が飛ぶ姿に似ていることだそう。どこがどう似ているのか、疑問です。

②
オミナエシ。秋の七草の一つで、穏やかな里の秋を彷彿とさせますが、顔を寄せると若干腐敗臭がします。
オミナエシを漢字で書くと「女郎花」。なぜこの字が当てられているのかははっきりしないのだそう。平安時代中期には既にこの字の記述があるとのことなので、当時の世相や風俗に由来するのでしょうね。

③
こちらも秋の七草の一つ、というとちょっと驚きますが、これはキキョウの果実です。蒴果と言われるタイプの果実で、先端部の隙間から乾いた種子を溢すように散布します。地味な、というより寂れた姿に、瀟洒な花の姿とのギャップを感じます。種子の散布を鳥や動物などに頼らないので目立つ必要がないからと解説するものも見られますが、ただ普通に枯れつつあるだけのような気もします。

④
これはナギナタコウジュの花穂。花茎が若干反っていて、その片側だけに花が並ぶ姿を薙刀の刃に例えた名だそう。シソ科特有に香りを持っています。コウジュ(香薷)は、この花を乾燥させて作る生薬の名前。利尿、血行促進などに薬効があるそうです。
⑤
このポップは花はアレチヌスビトハギ。北アメリカ原産の帰化植物で、主に関東以西に根付いているそうです。比較的新しい移入者とのこと。

⑥
ガガイモの花序です。障害物がないとこんな風に球状に花を付けるんですね。花冠から伸びる柱頭が波平さんの頭の毛みたいで面白いです。
⑦
エノキの果実を見上げたところ。そろそろ熟してきているようで、果実の表面がへこんでいるのが分かります。これは中の水分が少なくなってきたから。干し柿みたいな味がします。
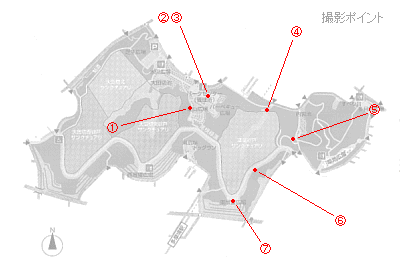
|
|
|
|
2025年9月17日(水)

①
コバノカモメヅル。水不足なのか、それともこれから開くところなのか、花冠の裂片が丸まっていますね。中央に蕾が見えているので、後者なのかもしれません。本来は星型に開きます。今年保護した場所では他の植物に負けてほとんど開花していませんが、ここ野草見本園のものはかろうじて育っているようです。

②
ツリフネソウの花が咲き始めました。猛暑のせいか傷みが目に付きます。
名の由来は、舟を吊るしたような花の付き方からと思っていましたが、そもそも舟を吊るすというシチュエーションはそんなにあるものなのかと疑問が。生け花の花器に舟形でそれを吊るして使うその名も「釣り舟」というものがあり、そっちから来たのではと密かに思っています。

③
これはラッカセイの花です。片仮名だと違和感がありますが、ピーナッツができる落花生です。花はあまり見たことないですよね。普通植物の実は花の付け根辺りにある子房が膨らんでできますが、このラッカセイは子房に柄が付いていてそれがにゅーっと伸びて地面に突き刺さり、地中に潜ってそこで膨らんで実になります。
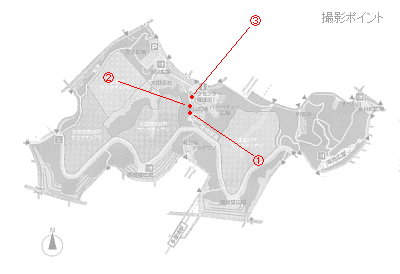
|
|
|
|
2025年9月22日(月)

①
ヤマホトトギスです。開花すると花被片が反り返るのが特徴。この仲間のヤマジノホトトギスは水平に開くのが一般的で、ホトトギスは逆に盃状に上向きに開きます。メリーゴーランドのような器官は雌しべと雄しべです。

②
クリが実りつつありました。木全体として実の付きはそこそこでしたが、何故だか手に届く範囲には皆無でした。
③
毎年計ったように彼岸に咲くヒガンバナ。彼岸の期間は中日(今年は23日)を挟んだ前後3日で、毎年その前半を狙って開花しているように思います(yamanekoの観察による)。今年のような異常な猛暑であってもぶれないのは、気温ではなく日照時間で開花しているということでは。

④
クサギの果実。ホオズキのように袋状に閉じていた萼片が開いて、最終的には星型に平開します。果実は黒く見えますが実際には濃い藍色をしています。

⑤
普段あまりじっくりと見ることのないイタドリの花。ごく小さく5mmほどの大きさです。雌雄異株で、これは雄花。雄しべが多数(通常8個)あることが分かります。雌しべもあることはあるのですが、小さくて本来の機能は備えていないそうです。
⑥
このミズヒキの花も極小。イタドリよりもワンサイズ小さいです。花被片は4つに裂けていて、上3つは紅く、下1つは白いです。ミズヒキはイタドリと同じタデ科で、この科の花は小さいものが多いです。

⑦
九反甫谷戸にやって来ました。キバナアキギリが咲く時期です。今年は株の数が減っているような。左の花は横を向いているので観察に好都合。上の花被片は袋状になっていて先端から長い雌しべが突き出ています。その根元辺りから顔を出しているものは雄しべ。本来は袋の中に格納されています。それがハナバチが花筒に入ったタイミングでスリットのように開いた隙間から出てきて、ハチの背中に花粉を付けるという芸の細かいことをやります。

⑧
数日前に雨が降ったので公園内のあちこちにキノコが顔を出していました。これはテングタケ? 似たものにテングタケダマシとかテングタケモドキとかイボテングタケとかあるようで、yamanekoのような素人には判別不能です。

⑨
ヤマハギ。最もポピュラーな萩で、秋の七草の萩はこれかもしれません。この公園には秋の七草のうち、萩、尾花(ススキ)、葛、女郎花(オミナエシ)、桔梗(キキョウ)は生えていますが、撫子(ナデシコ)と藤袴(フジバカマ)は自生では見たことがありません。
⑩
野草見本園にやって来ました。これはタヌキマメ。ラグビーボール状のものは果実ではなく蕾。これから開花していきます。この蕾の表面(萼片)が毛深いのでタヌキの名が付けられたとのことです。この花は昼に咲いて夕方に閉じるという朝寝坊型。花には朝に咲いて昼に閉じるもの(ハスなど)とか、夜に咲いて朝に萎むもの(カラスウリなど)とか様々ありますね。

⑪
これはセンニンソウの果実。「果実群」と言った方が良いかもしれません。長い髭(花柱の名残)を持つ痩果が星状に5個付いていて、これで一つの花の果実です。これらが絡み合っている状態ですね。
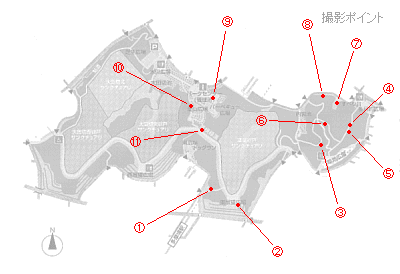
|
|
|
|
2025年9月23日(火)

①
ヤブツルアズキ。アズキ(小豆)の原種とされています。いちおう、マメ科の特徴でもある蝶形花ですが、左右対称ではなく、カタツムリのような、はたまたキャッチャーミットのような特殊な形をしています。
②
これはクワクサですね。葉が樹木のクワに似ているからその名が付いたとのことです。特段そうとも思えませんが。
③
クワクサの花をアップで。葉腋に尾花と雌花が混在した丸い花序を付けていますね。4個の雄しべが飛び出しているのが雄花。初めは内側に折れ曲がっていて、それがピンと伸びた状態です。雌花は暗紅色の花柱を出すのですが、まだその状態になっているものはないようです。

④
アキノノゲシは背が高いです。茎頂に花序を付けるので背伸びして見ることもあります。この淡いクリーム色が優しい感じでいいですね。

⑤
芝生の上を這うハイメドハギ。メドハギの変種だそうです。その名のとおり茎の基部が地を這うように伸びています。花をアップで見ると紫色の斑紋が綺麗ですね。普段は気付かずに踏みつけて歩いたりしていて、申し訳ないです。

⑥
こちらもこれまで散々踏みつけてきたであろうネコハギ。葉が軟毛に覆われ、その手触りがネコの耳に似ているからこの名になったとも聞きましたが、図鑑によると牧野富太郎がイヌハギに対する形で命名したとありました。どっちもふーんって感じです。
⑦
水辺で咲いていたボンドクタデ。昨日見たイタドリといいミズヒキといい、タデ科の花は小さいです。ボントクとは「凡篤」と書き、愚かなといった意味だそう。見た目はヤナギタデに似ているものの辛味がないので、役に立たないということから名付けられたのだそうです。本人にしてみれば迷惑な話です。ちなみに辛味を持つヤナギタデは薬味として用いられ、特に焼き鮎に添えられる蓼酢となることから有用なのだとか。所詮、有用無用は人間目線です。
⑧
交尾前のキイトトンボ。前がオスで後ろがメスです。オスの尻尾(腹部)の先には把握器という器官があって、これでメスの首根っこを掴んでいる状態です。この後、メスが尻尾を丸めてその先端にある生殖器をオスの胸近くにある生殖器に結合させて交尾成功。2匹のこの状態がハートマークに見えほのぼの感があるのですが、オスがメスを掴んでいるのは自分が交尾したメスを他のオスに盗られないようにするためなのだとか。うーむ…。
⑨
これはヤマノイモの蔓。先端にムカゴが付いていますね。葉が対生に付いているのもヤマノイモの特徴です。(よく似るタチドコロなどは互生)

⑩
湿った場所を好むイボクサ。地面に這いつくばるようにして生えています。花の大きさは大きいものでも1cm弱。花弁の先端は赤紫色、雄しべの葯は青紫色とパステルカラーで、ファンシー(死語)です。なのに名前がイボとは。これは葉の汁を付けるとイボが取れるという言い伝えから付けられたのだそうです。
⑪
イボクサと同じような環境に生えるコケオトギリ。休耕田などで時々見かけます。コケオトギリは(よく似るヒメオトギリも)他のオトギリソウ属とは違って葉に黒点が全くないのだそうです。一方、陽に透かすと明点があるのが分かるそうですが、いずれにしても葉自体がごく小さいので、老眼のyamanekoには判別できません。

⑫
ツルニンジン。多摩丘陵にもあるところには普通にあるのですが、ここ小山内裏公園では稀にしか見かけません。「去年ここで見かけたのにな…」ということもしばしば。多年草なので前年に見かけた場所では翌年あっても良さそうなものですが、公園という環境下では撹乱要因が大きいのかもしれません。
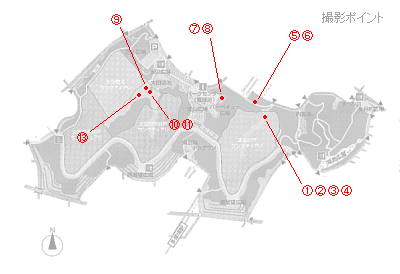
|
|
|
|
2025年9月24日(水)
①
鮎道沿いにはツリガネニンジンの保護エリアがありますが、同じような環境を好むツルボも多数生えていて、むしろこちらが優勢になってきています。ツルボは別名をサンダイガサ(参内傘)といい、これは公家が参内する際に従者が後ろから差し掛ける傘をつぼめた姿に似ているからだそうです。ふーん。ただ、標準和名であるツルボの由来は不明なのだそう。

②
鑓水口の近く、ちょっと分かりにくいところにあるミツデカエデです。yamanekoもここにあることを1年前に初めて知りました。葉は三出複葉(3個の小葉で一つの葉)で、一般的なカエデの葉とは様子が異なります。
③
ママコノシリヌグイです。茎や葉に鋭い棘が多数あり、これで憎い継子の尻を拭いてやるというなかなかのネーミング。今の世の中、コンプラ的にどうなのか、という話です。ちなみに花はごく小さく、これはタデ科の特徴ですね。

④
これはキクイモですかね。イヌキクイモかも。掘って地下茎を見てみなければ判別困難です。キクイモの方は飼料用などとして戦時中によく栽培されていたそうです。イヌキクイモは根茎が痩せていて役に立たないので「イヌ」の名を冠したというよくあるパターン。本当はイヌは人間の良きパートナーとして役に立つのに、随分な扱いですね。

⑤
シロバナヒガンバナ。植物の花の中には本来の色ではなく稀に白い花を付けるものが少なからずあります。yamanekoもカワラナデシコやカタクリ、キキョウなど数多く出会いました。ただ、シロバナヒガンバナはヒガンバナとショウキズイセンが自然交雑したものだそうで、そのせいか花は純白ではなく、ややピンク色を帯びています。
それにしてもヒガンバナは種子を作らず今ある球根の横に新しい球根を作って増えていきます。すなわち分布の拡大スピードは極めて遅いはずなのですが、急にここに現れたのは誰かが植えたということか。(確か去年までは
なかったような)
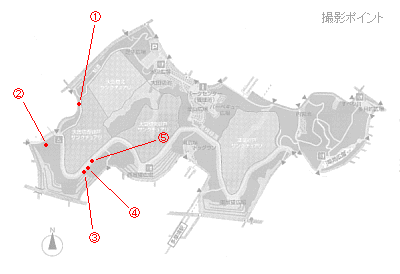
|
|
|
|
| |

