
筑波山 〜東の秀峰に久々に(後編)〜
 |
(後編) |
【茨城県 つくば市 令和6年6月20日(木)】
久々に訪れた筑波山。梅雨入り前で大汗をかいています。その後編です。(前編はこちら)
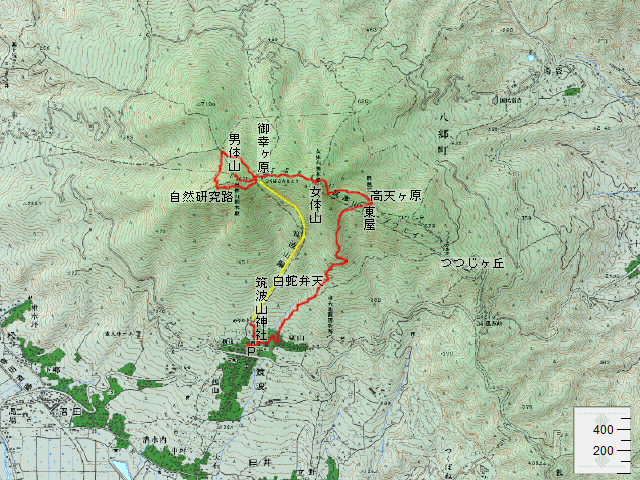 |
Kashmir3D |
麓の駐車場を10時20分に出発。白雲橋コースを登って12時50分に女体山の山頂に到着しました。女体山は双耳峰をなす筑波山のピークの一つです。
とりあえず岩峰の先端まで行ってみましょう。
まるで空を飛んでいるかのような眺め。正面を向いていると足元が視界に入ってこないのでそう感じるのです。
写真に捉えている範囲は北東から南西までのおよそ180度で、実際に見えている範囲は更に広かったです。上の写真はその半分の北東から南東までの範囲。眼下の山上にある施設はロープウエイのつつじヶ丘駅です。その遥か先には霞ヶ浦が。左側の田園地帯の先に石岡市街があり、その左側(写真左端)に3年前に登った難台山が見えています。
右にパンして、こちらは南東から南西までの範囲。筑波研究学園都市がある方で、今日やって来たのもこの方角からです。ここから約70km先に東京があるはずです。眼下の緑の中に筑波山神社を中心とした門前町が見えていますが、そこから田園を突っ切る道が伸びているのが分かります。これは「つくば道」と呼ばれる参詣道で、徳川家光(三代将軍)の時代に設けられたものだそうです。
ひとしきり眺望を楽しんだ後、女体山の神社に参拝します。
| 筑波女大神 |
筑波山神社の御祭神は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冊尊(いざなみのみこと)の二神だそうで、社殿も2つに分かれていて、女体山の山頂に伊弉冊尊を祀る社殿があります。人々は、敬う山に2つのピークがあれば、やはり男女の神を祀りたくなるものなんでしょうね。ただ、古事記によると伊弉諾、伊弉冊の前にも4組の男女の神がいるとのことですが、伊弉諾、伊弉冊がメジャーなのはやっぱり国造りの神話が影響しているのかもしれません。その功績や大、ということでしょうか。
ところで、ネットでは縁結びのパワースポットとか書かれているものもありましたが、2人が最後どうなったかご存知か?
ちなみに、両社殿はお互いに向き合っていたりするのか、グーグルアースで調べてみましたが、男体山の社殿の向きは南南西方向、女体山の社殿は西北西方向と、特段見つめ合っているといった関係にはありませんでした。
参拝後、男体山との鞍部に向かってゆっくりと下っていきます。この道は2つの山頂を結んでいるので「山頂連絡路」というのだそうです。
| ガマ岩 |
途中にあったガマ岩。口を開けた筑波のガマを見上げている構図です。見る角度によってはそう見えないこともないような(二重否定)。
| コアジサイ |
このコアジサイはまだ開花状態でした。アジサイにお馴染みの装飾花がないのがコアジサイの特徴です。
途中に広場があったので、ここでザックを下ろして昼食を取ることにしました。コンビニおにぎりです。
| 御幸ヶ原 |
さっさと昼食を終えて再出発。やがて梢の向こうに鞍部が見えてきました。御幸ヶ原というのだそうです。地形的にどうみても原ではないですが。
1時20分、御幸ヶ原に到着しました。ここへは筑波山神社の裏手からケーブルカーで上がってこられるので、登山装備でない観光客の方もたくさんいます。
| 北側 |
御幸ヶ原からは、筑波山の裏側といったら失礼ですが、東京方面からは山の陰になって見られない北側の眺望が広がっています。写真右手に伸びる山々は、ここ筑波山から峰続きの山塊で、加波山とか雨引山とかが並んでいます。その左手に広がる田園地帯は、真壁石で有名な旧真壁町。今は桜川市真壁町になっています。
| 男体山へ |
さて、ここから男体山へ向かいます。女体山は、ロープウエイ駅が近くにあるということもあってか、比較的多くの人で賑わっていますが、男体山の方はいつ来てもひっそりとしています。
男体山への道はやや傾斜がきつめです(道はしっかりしています。)。地図上での計算ですが、御幸ケ原からだと、女体山へは概ね14%の勾配(比高80m/距離580m)、男体山の方は概ね42%(80m/190m)となっています。
疲れが出てきた大腿四頭筋にギシギシ負荷がかかる登山道。
| ヤマユリ |
これはヤマユリか。先端にまだ蕾が出ていませんが。
| シモツケ |
ここのシモツケは女体山で見たものより色合いが鮮やかでした。
| ブナ |
これはブナの若い実ですね。まだ殻斗に覆われています。全体に毛むくじゃらみたいですが、これはクリでいうところのイガに当たるもの。毛というよりは柔らかめの棘といった方が当たっているかも。熟すとクリ同様に殻斗が裂け、中から硬い実が出てきます。これがクマの大好物なんですよね。
1時35分、御幸ケ原から10分ちょっとで男体山の山頂に到着しました。山頂には社殿があります。案の定誰もいません。ここは社殿の裏側。早速表側に回ってみましょう。
| 筑波男体神 |
こちらが伊弉諾尊を祀った社殿です。大きさや全体的な形は一見して女体山の社殿と同じように見えますが、よく見ると千木と鰹木に違いがありました。千木(ちぎ)とは社殿の屋根の両端でX形に交叉している部材で、鰹木(かつおぎ)は屋根の棟に直交する向きに置かれている丸太のような形のものです。女体山の社殿では千木の先端は水平にカット(内削ぎ)されていて鰹木は2本、男体山の社殿では千木の先端は垂直にカット(外削ぎ)されていて鰹木は3本ありました。
千木の形は、祭神が男の神様の場合は外削ぎ、女の神様の場合は内削ぎであり、また、鰹木は、男の場合は奇数、女の場合は偶数とされているといった話もあるようですが、これらは全くの俗説とのことです(Wiki情報)。ふーん。ただ、全国的にそのような統一ルールはないとしても、男女の神を祀るここ筑波山の両社殿にそのような意味が持たせてあってもおかしくはないですよね。というのは、千木や鰹木以外の部分が非常によく似ているので、あえてその部分に違いを持たせているように見えるのです。
そしてこちらが男体山からの眺望。関東平野を一望できました。
男体山の標高は871m。女体山が877mなので、こちらが6mほど低いことになります。今でこそ測量技術によりその僅かな差を理解できていますが、2千数百年前、ここ筑波山の2つのピークに祭神を祀るに当たってこの標高差を意識していたのでしょうか。遠目に見てなだらかなピークが女体山、急峻なピークが男体山となったようにも思えますが、仮に、山容の険しさとかではなくより高いほうが女体山としていたとすると、太古の時代の男女観がなんとなく伺い知れる気がします。
| ツルマサキ |
さて、山頂では眺望を楽しんだら他にすることはないので、すぐに下山することに。
これはツルマサキですね、ちょうど花が咲いていました。マサキにそっくりですが、ツル性である点が異なります。
| ガマズミ |
ガマズミの開花時期も多摩丘陵とはかなりずれているようです。
つんのめりそうな急傾斜。一歩一歩確実に足を運びます。
それでもあっという間に下りてきました。
御幸ヶ原に戻ってくると上空を軽飛行機が飛んでいきました。プロペラが見えたのでグライダーではないようでした。上から見ると気持ちいいでしょうね。この付近では龍ケ崎に飛行場があるようなので、そこから飛んできたものなのかもしれません。
| 自然研究路へ |
ここからは男体山の中腹をぐるっと一周する自然研究路を反時計回りに歩きます。以前にも歩いたことがあって、散歩気分で一周したような記憶が残っていたのですが…。
歩き始めるとどんどん坂道を下るではないですか。下るということは後でその分登るということ。こんな道だったかな。
| チドリノキ |
そう思いつつも、何か面白いものはないかと探してしまいます。
これはチドリノキ。翼果を見ると明らかにカエデの仲間ですが、葉はカエデっぽくはありません。カエデの仲間の葉はほとんどが紅葉(もみじ)のような深く裂けた形をしていますが、このチドリノキやヒトツバカエデなどは全く裂けないいわゆる「普通の」葉の形をしています。
| ヤマアジサイ |
これはヤマアジサイですね。花序の縁に装飾花が並び、中程には両性花(まだ蕾)が集まっています。
| 最低地点 |
自然研究路を歩き始めて10分ほどでコース中の最も低い地点にやって来ました。地図を見ると標高差にして60mほど下ってきたことになります。ここから折り返すようにして男体山の西面、南面を登り返していきます。
まあ道はしっかりしているようです。
| ユキザサ |
ユキザサが実をつけていました。秋には透明感のある深い紅色になります。
斜面に架けられた板橋。右にかしいでして、雨の後などは滑り落ちそうで怖いです。
装飾花の付き方が面白いですが、葉の形からも、これもヤマアジサイでしょう。
| ツクバネソウ |
これはツクバネソウ。茎の先端に4個の葉を広げ、そこから花茎を伸ばして緑色の花を付けています。中央にはもう実ができかかっていますね。
ところどころに急傾斜な場所もあり、変化が楽しめる道でした。一部木道が壊れかかっているところも。小さな子供にはちょっと注意が必要です。
| オカタツナミソウ |
木道の段差のところにオカタツナミソウが咲いていました。つい見逃してしまいそうなところでひっそりと。
| 東屋 |
東屋で小休止。男体山往復の際もほとんど人に出会いませんでしたが、ここ自然研究路でも数人としかすれ違いませんでした。観光客は基本立ち入らないエリアなんですかね。(いや、よく考えたら平日だからか!)
| 分岐 |
自然研究路を8割方回った辺りで分岐が現れました。ここを左に折れると男体山の山頂に至るよう。yamanekoは右に折れて御幸ヶ原に向かいます。
| 解説板 |
自然研究路にはところどころに写真のような解説板が設置されていました。地質や植生、生息動物など自然科学に関するものが全部で19か所ありました。ただ漫然と歩くよりもこのような解説板があると楽しいですね。
そろろろ自然研究路も終わりのようです。そこそこアップダウンがあり、いい運動になりました(と、無理して余裕を見せる。)。
| 御幸ヶ原 |
2時30分、御幸ヶ原に戻ってきました。40分かけて自然研究路を一周してきたことになります。とりあえず休憩です。持参したお菓子と飲み物をここできれいに消費しました。
下山はケーブルカーで。ここのケーブルカーは大正時代の創業とのこと。当時は筑波山観光の目玉だったでしょうね。現在でも全国で3番目に長いという微妙なアピールポイントを有しています。
| 筑波山頂駅 |
チケットを買いに行くと2時40分発の便がもうじき出発とのこと。慌てれば間に合いそうでもありましたが、次の3時発の便で下ることにしました。その20分間で入念にストレッチを。時間の有効活用です。
| 宮脇駅 |
乗車時間7分ほどで筑波山神社の裏手にある宮脇駅に到着しました。無事に下山できてやれやれです。
ここから神社に向かい、お礼のお参りをして、それから帰途につくことに。
登りの際に出会った水戸からの3人組も同じケーブルカーだったのか、参拝を終えて駐車場に向かう際にすれ違ったので、会釈しておきました。向こうも気がついてくれたようでした。無事に下山できたようで何よりです。
3時20分、駐車場に戻ってきました。さて、ここから3時間の長旅が待っています。帰りは圏央道で。都心を経由しないので、おそらくひどい渋滞はないでしょう。(実際にありませんでした。)
今回の筑波山行き。実は3月に予定していたものでした。全て準備を終えていた登山前日、筑波山付近を震源とする地震が発生したので、急遽場所を替えたのです。その後、特段この辺りで地震が続いているということもないようなので、きっとあの日は来るなという知らせだったのではないかと思っています。
山には、人間を謙虚にするというか、なんとなくそんなふうに考えさせる力がありますよね。