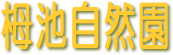
栂池自然園 ~北アルプスの花々(栂池・前編)~
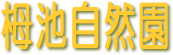 |
(前編) |
【長野県 小谷村 平成24年7月29日(日)】
昨日は八方山で夏の高山植物を堪能しました(八方山の様子はこちら)。下山後、北隣の小谷村に移動し、栂池高原で宿泊。宿の温泉で疲れをとって、今日もまた高山植物を見に行く計画です。
栂池高原の旅館街があるのは標高830m付近。そこからゴンドラとロープウエイを乗り継いで1850mまで上がると、栂池自然園という高山植物の楽園があります。園内には尾瀬ヶ原のように木道が整備されていて、その延長は約5.5㎞、所要時間は4時間(yamanekoペースではその1.5倍か)と、広大です。
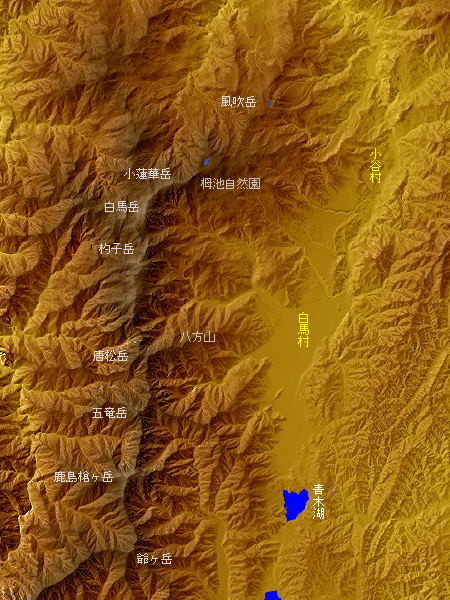 |
Kashmir 3D |
小谷村といえば平成7年7月の集中豪雨が思い出されます。土石流とともに巨大な岩がゴロゴロ転がってきた防災用カメラの映像が強烈で、いまだに鮮明に記憶しています。小谷村を「おたりむら」と読むこともこのときのニュースで知りました。
| ゴンドラ |
朝、カーテンを開けて山を見ると、今日も雲がかかっていて山頂は見えません。いや、むしろ昨日より雲は低く、今日はゴンドラですぐに雲に突入するような感じです。
午前8時20分、栂池高原駅からゴンドラに乗り込みました。するとほどなくあたりは乳白色の世界に。視界は5mほどしかなく、前を行くゴンドラも見えません。対向してくるゴンドラは白い世界から突然ぬっと現れ、まるで黄泉の国から戻ってきたような感じでした。
ところが、ある程度高度が上がると視界が戻ってきました。どうやら雲の層を突き抜けて、その上に出たようです。上の写真はゴンドラの終点、栂の森駅の手前。正面奥に小蓮華山(2776m)が望めます。あとは頭上高くにある雲が取れてくれれば夏山の美しい姿を楽しめるのですが。
| ビジターセンター |
栂の森駅でゴンドラを下り、木立の中を200mほど歩いて、今度はロープウエイに乗り換えました。麓の駅を出てなんだかんだで約40分、栂池自然園のビジターセンターに到着しました。
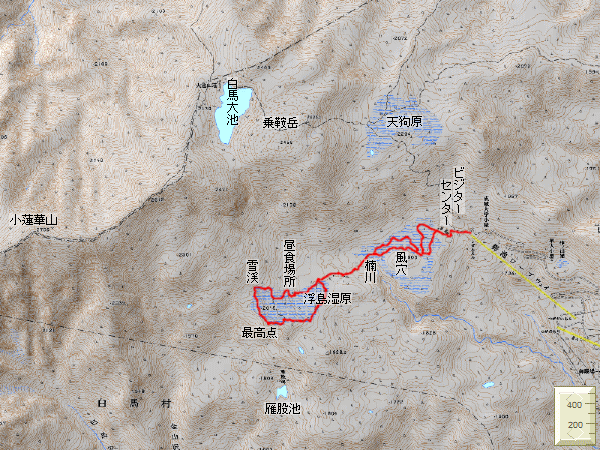 Kashmir 3D |
栂池自然園は2段のひな壇状になっていて、標高1850mに広がる高層湿原と、その奥にある1900mから2000mに広がる高層湿原とで構成されています。これらのひな壇状の地形は白馬乗鞍岳の噴火活動で生じた断層により造られたと考えられています。ひな壇状になった平坦面の窪地に水が溜まり、そこに育ったミズゴケなどは冷涼な気候のため枯れても腐ることなく泥炭化して、国内有数の高層湿原が造られたのだそうです。標高2200mに広がる天狗原も同じように造られたひな壇です。
ビジターセンターから歩き始めるとまずミズバショウ湿原と呼ばれるエリアがあり、その奥に風穴のある小山があって、さらにその先にワタスゲ湿原と呼ばれるエリアがあります。楠川を渡ると標高差50mほどの斜面があり、その先には浮島湿原があります。その奥は支尾根に向かって小さな湿原が続く上りになって、最高地点に至ります。
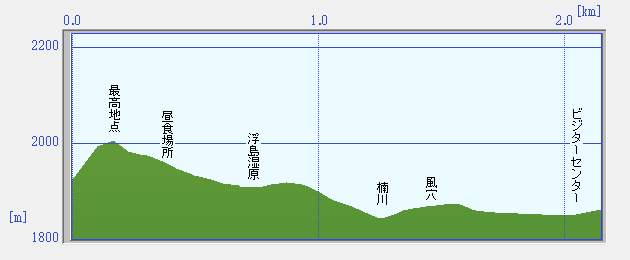 Kashmir 3D |
|
上の図は、ビジターセンターと園内最高地点とを結ぶ直線上での断面図。標高的には昨日の八方山とほぼ同じです。
| |
9時15分、園内の散策開始。ときおり日射しがあります。
| カラマツソウ |
最初に現れたのはカラマツソウ。線香花火のような花です。この花に花弁はなく、白く細長いのは雄しべです。
| |
湿原の中には小さなせせらぎが雪解け水を集めています。
| ミヤマキンポウゲ |
ミヤマキンポウゲは亜高山帯に咲くキンポウゲ。低山や野山で見られるものはウマノアシガタという名が標準和名になっています(別名をキンポウゲというのだとか。)。一方でキンポウゲはウマノアシガタの八重咲きになったものを指すとする解説もあります。
| イワナ |
湿原を流れる小川を覗いてみるとイワナが数匹流れの中にとどまっていました。この湿原で生まれここで一生を終えるのでしょうね。自分がこんなに標高の高いところにいるなんて、一生知らないままでしょう。
| ミズバショウ湿原 |
標高2000m近くでありながらこの大地の広がり。ここは尾瀬ヶ原や戦場ヶ原より500mも高いところにあるのです。
| クルマユリ |
クルマユリで間違いないと思いますが、ちょっと印象が違うような。よく見るクルマユリは葉が線形ですが、写真のものは葉の幅が広く卵形といってもいいくらい。また、花被片の反り返りも先端のとがり具合も緩いようです。単なる個体差でしょうか。
| オタカラコウ |
大型のフキといった風情のオタカラコウ。「雄宝香」と書き、別種でメタカラコウ(雌宝香)というのもあります。オタカラコウの方が全体にがっしりとした印象を受けます。この花を初めて見たのは中野冠山(広島県)の麓だったと思います。集落の裏手の山際に咲いていた姿を思い出します。
| ハクサンチドリ |
華やかな姿をしたラン。群れ飛ぶ千鳥をイメージして名付けたものでしょう。たくさん千鳥ではなく白山千鳥です。
| ヒオウギアヤメ |
見るからに涼やかな花ですね。ぱっと見、普通のアヤメですが、高山に咲くことと葉がアヤメに比して幅広であるところが相違点だそうです。
| ワタスゲ |
ワタスゲです。高山の湿原を代表する花です。この白いワタスゲが風に揺れる風景は夏の高原の風物詩ですね。とはいえこの状態は果実の集合体。花は背が低く黄緑色の綿棒のような地味な姿をしています。
| |
見上げると大きな滝が。遠くにあるので音はまったく聞こえませんが、結構な落差がありそうです。どうやら白馬乗鞍岳の山腹、天狗原の平坦面の縁から流れ落ちているようです。
| エンレイソウ |
日が射してきましたね。その光を浴びるエンレイソウには既に実ができています。葉はまだ生き生きとしていますね。どんどん光合成をして栄養を実に送らなければならないですから。
| ツマトリソウ |
これはツマトリソウ。花冠の直径2㎝弱の小さな花です。名前の由来は「妻を娶(めと)る」とかそんなことに関係しているのだろうと思っていましたが、調べてみると鎧の装飾模様の一種「褄取威(つまどりおどし)」からだとか。「褄」とは尖った先端部分のこと。肩当ての角の部分を地色とは違う色で装飾してあるものだそうです。ツマトリソウは花弁の先端部が薄桃色に彩られているものがあって、それが褄取威を連想させるからだそうです。うん、まあ創造力が豊かだこと。
| コバイケイソウ |
降り注ぐ日射しに負けないようにすっくと伸びているのはコバイケイソウです。この花はよっぽど甘い蜜を出すのでしょう。いつもアブが集まっています。
| オオヒョウタンボク |
ヒョウタンボクと名の付く花はたくさんあって、いずれもスイカズラ科の木本です。これはオオヒョウタンボク。中部地方の高山となぜか広島県の帝釈峡に分布しているという変わり者です。ヒョウタンボクの仲間の花には写真のような上下に開いた唇形のものと、ラッパのような漏斗型のものの2種類があります。花の形は全然違うのに名前には共通してヒョウタンボクが付くという不思議。これはきっと果実の形が共通している(ひょうたん型)からでしょう。
| コガネイチゴ |
名前にイチゴが付くことからも分かるとおり、バラ科の植物です。面白いのは葉の形。小葉が5個あるように見えますが、じつは3個で、左右にある小葉が深く裂けてそれぞれ2個に見えるからなのです。で、何が黄金(こがね)なのかというと、果実に光沢があるからだそうです。野イチゴのような赤い果実です。
| キヌガサソウ |
おお、キヌガサソウだ。これが今回のお目当てのうちの一つです。しばしば大きな群落を作るのだそうで、花自体が大きいから、いきおい群落も立派な感じになります。花冠の大きさは野球のボールほどもあり、輪生する葉は直径50㎝くらいはあります。花被片の数は株によってばらつきがあり、6~11個。葉の数も同様です。右の写真の二つの株は、左が10個、右が9個ありますね。
キヌガサといえば、カープファンとしては鉄人の方を思い浮かべます。この花とはちょっとだけ印象が違いますが。
| オオバミゾホオズキ |
黄色の花冠に赤い斑点。鮮やかなコントラストですね。「蜜はこの奥にあるよ」とアピールしているかのようです。ミゾホオズキのミゾとは「溝」、すなわち水が流れているようなところに生えているということだそうです。ちなみにあのホオズキ(ほおずき市のホオズキ)とは無関係です。
| ズダヤクシュ |
花の大きさが約2㎜と極小のズダヤクシュ。こんなに小さくてもきちんと花の基本構造を備えているんですからすごいもんです。それれにしても花粉を媒介するのはいったいどんな虫なんでしょうか。
| オオバタケシマラン |
オオバタケシマランの花は葉の下に隠れているのか、それとも雨を避けているのか、面白い位置で咲いています。しかも花柄の途中に関節があって、吊り下げられているようになっているのが面白いですね。関節までの花茎が葉裏に合着しているものとそうでないものとがありました。どうやら開花後に葉から離れるようです。
| キバナノコマノツメ |
全体に小型で、丸っこい葉が可愛いキバナノコマノツメ。名前に「スミレ」の文字をもたない唯一のスミレだそうです。
| ベニバナイチゴ |
濃い紅色の花を下向きに付けるベニバナイチゴ。花弁がシワシワですが、これが満開状態です。果実は渋みが強く「これほどまずいキイチゴはない」と図鑑に紹介されていました。気の毒に…。
| キヌガサソウ |
これは端整な顔立ちのキヌガサソウです。この花を実際に眺めることができて、はるばる栂池まできた甲斐があったというものです。
| チングルマ |
ミズバショウ湿原を散策し終えました。時刻は10時45分、ここまでで1時間半です。次から次へと花が現れるので「超」が付くほどスローペースですな。
チングルマの果実が湿原を渡る風にゆれています。そんな様子を眺めるだけであっという間に時間が過ぎてしまうので、しょうがないですね。《この続きは中編で。》