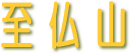
至仏山 ~山上の花畑ふたたび(中編)~
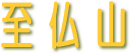 |
(中編) |
【群馬県 片品村 平成25年7月28日(日)】
至仏山、山上の花畑を訪ねる山歩きの中編です。(前編はこちら)
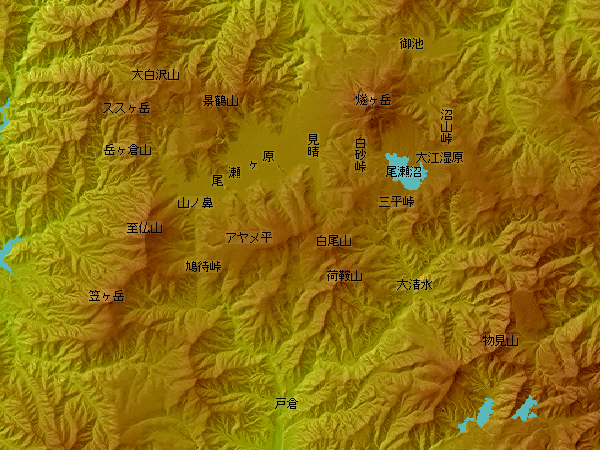 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
|
| 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
鳩待峠を出発したのは9時前。林間の道を抜けて、1935mピークの北側斜面の開けたところまでやって来ました。時刻はすでに10時半です。
| クロトウヒレン |
これはクロトウヒレン。ちょっと地味ですがこれでもキクの仲間です。漢字では「黒唐飛廉」。黒糖ではありません。「飛廉」とはヒレアザミのことだそうです。
この辺りから小至仏山までは花の波状攻撃。おかげでまたまたスローペースに。
| オオバギボウシ |
オオバギボウシは夏の花。ちょっと湿ったところを好む花です。
| アカモノ |
高原の明るい林縁で見かけるアカモノ。
| ゴゼンタチバナ |
標高が上がるとゴゼンタチバナもまだ花を咲かせています。「和」のテイストの花です。
| ツマトリソウ |
ゴゼンタチバナが生える環境ではツマトリソウもよく見かけます。
| マイヅルソウ |
マイヅルソウはもう実を育みつつありました。
| |
草原エリアを抜けて再び林間に入りました。
| ミネカエデ |
カエデの仲間の花序は垂れ下がるものが多いですが、ミネカエデは立ち上がるタイプ。
| モミジカラマツ |
モミジカラマツに花弁はなく、白い線状のものは雄しべです。花弁の代わりに頑張ってアピールしていますね。
| |
オヤマ沢の源流部にあたる小さな流れを横切ります。ここには清水を飲めるように沢からパイプが引かれていました。一口含むと、うん、美味し。
| コガネイチゴ |
コガネイチゴは比較的寒い地方に分布する野イチゴ。何がコガネ(黄金)なのかというと、果実が宝石のように深紅に輝いているからだそうです。
| オヤマ沢田代 |
11時20分、オヤマ沢田代までやって来ました。「田代」とは本来は水田のことですが、転じて湿原を意味します。
スタートからここまで2時間半。かなりスローペースです。正面に見えているのは小至仏山。至仏山の本当の山頂はまだその先です。
| タテヤマリンドウ |
湿原にはタテヤマリンドウが。普通は青紫色をしているのですが、中には赤紫色のものも。
| ヨツバシオガマ |
湿原の草から頭一つ抜け出しているヨツバシオガマ。
| 笠ヶ岳分岐 |
オヤマ沢田代を過ぎるとすぐに分岐が現れました。左に折れると笠ヶ岳方面です。ここは直進です。パラパラと雨が落ち始めてきたのでザックカバーを掛けました。
| ベニサラサドウダン |
そして再び開けた場所に出ました。ここからは森林限界を超えるので、もう森はありません。
ベニサラサドウダン。東北地方南部から中部地方にかけての高所に生えるのだそうです。サラサドウダンの変種とされています。
| ハクサンシャクナゲ |
ハクサンボウフウに続いて出ました、ハクサンの名の付く花。ハクサンシャクナゲです。氷河時代から生き延びている植物だそうです。
| |
|||
| オゼソウ |
これこれ、今回の至仏山登山の目的の花が現れました。その名もオゼソウ。本州ではここと谷川山系のみに分布し、もちろん至仏山のものが基準標本となっています。前回来たときにはわずかに時期がずれていて、一株も見ることができなかったので、とても嬉しいです。
| オゼソウ |
丈の高さは20㎝ほど。すっと伸びる姿に涼しさを感じます。ちなみにユリの仲間です。
| 尾瀬ヶ原 |
尾瀬ヶ原方面。ずいぶんと雲が低く垂れ込めてきましたね。
| コイワカガミ |
コイワカガミの時期はもうそろそろ終わり。よくぞ待っていてくれた。
| イワイチョウ |
yamanekoの好きな花、イワイチョウ。今年初めての再会はここ至仏山になりました。
| シナノキンバイ |
本州中部の高所や北海道に生えるシナノキンバイ。個性派集団のキンポウゲの仲間です。
| ハクサンイチゲ |
これもキンポウゲ科のハクサンイチゲ。高山植物の代表格です。そしてハクサンファミリーです。
| |
この先で木道は切れ、蛇紋岩が連なる山道になります。そして正面の丘を回り込んで稜線の反対側(西側)に出ます。
雨がだんだん強くなってきました。やむなくレインウエアを着ることに。ここで活躍するのかビニールの買い物袋です。
レインウエアを着ようとするときはたいがい靴は泥で汚れています。なのでズボンを履くときには靴を脱がないとズボンの内側が泥だらけになってしまいます。とはいえそうでなくても脱ぎにくいトレッキングシューズ。一刻も早く着たいのにこれはなかなか面倒です。そこでビニール袋の中に靴を履いたまま足を突っ込み、その状態でズボンを履くのです。裾から靴が出たらビニール袋を取れば完了です。
| ハクサンチドリ |
さて、雨の装備を整えたところで、再び歩き始めます。
すると、またまたハクサンファミリーが。ハクサンチドリ、ランの仲間です。
| ガクウラジロヨウラク |
これはガクウラジロヨウラク。さっき見たウラジロヨウラクとは萼の部分の形が異なり、細長くてよく目立っています。ウラジロヨウラクの萼は小さく花弁の基部に張り付くようになっています。
さてさて、中編はほぼ花の紹介で終わりました。これからは山頂に向けての岩場歩きになります。そうでなくても蛇紋岩は滑りやすいのに、雨が降ってきたので余計に注意が必要です。(後編に続く)