
尾瀬ヶ原 〜秋の森と湿原を行く(中編)〜
 |
(中編) |
【群馬県 片品村 平成29年9月24日(日)】
秋の尾瀬。森と湿原を歩く「野山歩き」の中編です。(前編はこちら)
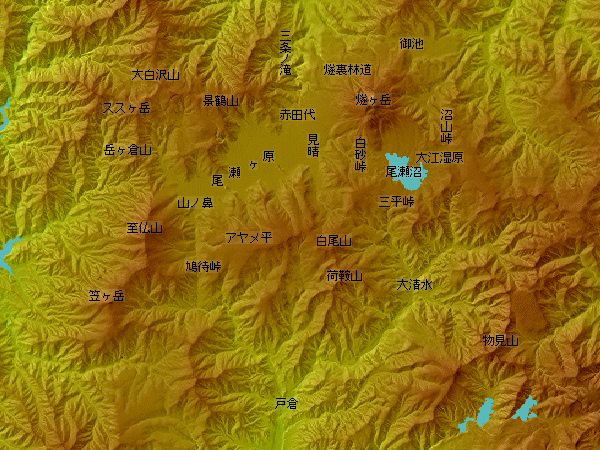 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
|
| 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
7時50分に鳩待峠を出発し、川上川沿いに下ること1時間半。もうすぐ山ノ鼻、というところまでやってきました。なお、ふつうに歩くと1時間かかりません。
ここで橋を渡り、初めて川上川の左岸を歩きます。
| マユミ |
マユミの実。ショッキングピンクです。青空とのコントラストがすごいですね。
| ミズナラ |
その立派さに毎回足を止めてしまうミズナラの大木。木道の左右にあって、尾瀬ヶ原に人々を迎えるゲートのような感じです。
| ルイヨウボタン |
おっ、これはルイヨウボタンですね。黒色に近い濃紺の実を付けています。
| ビジターセンター |
9時30分、山ノ鼻のビジターセンター前に到着しました。
テント場はあらかた撤収済み。まあ、もう9時半ですからね。
至仏山荘前の広場。ここでしばし休憩です。水分を補給し、持参のアンパンを食す。ホッと一息です。
広場の横のミズナラは部分的に紅葉が始まっていました。それにしても同じ木でありながら赤くなったり黄色になったり。カラフルです。
20分ちょっと休憩しました。そろそろ歩き始めましょうか。この林を抜けていくと湿原です。
| エゾリンドウ |
湿原に咲くエゾリンドウ。尾瀬にはこの他に森林内や山地に咲くオヤマリンドウもあります。
| ミヤマアキノキリンソウ |
ミヤマアキノキリンソウは低地に咲くアキノキリンソウに比べ密に花を付けます。
| 至仏山 |
上田代をしばらく歩いて振り返ったところ。至仏山がすそ野を広げ、雄大な姿を見せています。
尾瀬ヶ原は、上田代、中田代、下田代の大きく3つのエリアがあり、それぞれを川と拠水林が隔てています。上田代と中田代を隔てているのは上ノ大堀川、中田代と下田代を隔てているのは沼尻川です。
| アブラガヤ |
尾瀬の湿原を代表する植物の一つ、アブラガヤ。もういい色になっていますね。
| イワショウブ |
湿原の妖精、と勝手に名付けているイワショウブ。yamanekoの好きな花です。
| トモエソウ |
これはトモエソウの花後の姿だと思うのですが。
| オオマルバノホロシ |
オオマルバノホロシの実が色付いています。ナス科の植物で、別名「尾瀬ナス」とも。背後に写っている葉は別のものです。
| ズミ |
深紅のルビーのような輝き。これはズミの実です。実の大きさは1cm弱。バラ科の植物で、言ってみればリンゴの小さいのって感じです。
| 燧ヶ岳 |
進行方向にはもう一人の尾瀬の雄、燧ヶ岳(2356m)が聳えています。至仏山に比べてやや荒々しい感じがしますね。上の写真で見えている湿原の範囲全てが上田代です。
| ウメバチソウ |
先月、木曽駒ヶ岳の千畳敷カールで見かけたウメバチソウが尾瀬の湿原にも。いずれも厳しい環境の中で逞しく生きています。
| 特別な場所 |
人々は談笑しながら歩いて行くのですが、その声も発してすぐに空に吸い上げられるかのように、湿原は静寂の世界です。遙かな空間の広がりと共にこの非日常的な静寂も尾瀬を特別な場所たらしめる要因の一つだと思います。
| エゾリンドウ |
陽が高くなるにつれエゾリンドウの花冠も開き始めます。でもこれがほぼ満開の状態。開ききることはありません。そして、日が陰るとすぐに筆の穂先状に閉じてしまいます。
| 調査隊 |
おや、湿原に立ち入っている人が。脇には「調査中」の幟が立てられています。そこには「尾瀬総合学術調査団」の文字も。調べてみると、これは尾瀬保護財団が学術研究者ら50人で結成した調査団で、約20年ぶりに尾瀬で総合学術調査を行っているのだそうです。地球温暖化などによる影響を調査し、65年ぶりに地形や動植物のリストなども作るのだとか。調査は今年から平成31年までの3カ年だそうです。しかし、湿原に入ってもズブズブ沈み込むようなことはないんですね。場所によるか。
| 上田代 |
上田代をずいぶん歩いてきましたが、振り返って見る至仏山はほとんど変わらない大きさです。湿原の紅葉は「草紅葉(くさもみじ)」と呼ばれ、そのピークまであと数週間といったところでしょうか。本当に黄金に輝くんですよね。
| 池塘 |
湿原にはこういった池塘があちこちに。ただ湿原にまんべんなく散らばっているわけではなく、池塘が集中しているエリアとそうでないエリアがあります。地下水脈の関係とかでしょうか。この地塘には浮島がありますね。
| 水面の紅葉 |
こちらの池塘にはヒツジグサの葉がびっしり。草紅葉より先に紅葉し始めています。
| ヒツジグサ |
ヒツジグサの葉。なんかアートです。
| アカハライモリ |
池塘を泳ぐアカハライモリ。音もなく、スイー、スイーと、空中に浮かんでいるようにも見えます。
| 「逆さ燧」 |
ここは池塘の水面に燧ヶ岳が映る「逆さ燧」が見られるスポット。風もなくさざ波が立たないときにはこんなにくっきりと見えます。
池塘の奥に木立が見えますが、あれは拠水林。拠水林とは、湿原の外(即ち山)から流れ込んできた川の両岸にその川が運んできた土砂が堆積し(=自然堤防)、その土壌を基盤として高い樹木が育ち、それが川に沿って壁のように連なるものを言います。土砂が必要なので、湿原内に源を発する川では拠水林はできません。
写真の拠水林は上ノ大堀川の拠水林で、あそこより向こうが中田代になります。
| 中田代へ |
拠水林を近くで見るとこんな感じ。これから渡る橋が見えていますね。川の規模が小さく自然堤防の幅も狭いので、拠水林の向こう側が透けて見えています。
| 上ノ大堀川 |
橋の上から。水生植物がみっしり生えていますね。
| 中田代 |
10時55分、拠水林を抜けて中田代に入りました。相変わらず広大な湿原です。
| 景鶴山 |
進行方向左手の山々。中央奥にあるピークは景鶴山。その向こうは新潟県になります。ちなみに景鶴山には登山道はないそうです。
| 尾瀬ヶ原三叉 |
中田代に入って10分ほどで尾瀬ヶ原三叉に到着。別名を牛首分岐とも。ここをまっすぐ行くと今日の目的地である竜宮小屋に至ります。一方、ここを左に折れると、ヨッピ橋、東電小屋を経て、赤田代方面へと続きます。
さて、ここで一休みしてから竜宮小屋に向かうことにしましょう。続きは後編で。