
尾瀬ヶ原 〜夏空の下の湿原へ(後編)〜
 |
(後編) |
【群馬県 片品村 平成26年7月12日(土)】
夏空の下の湿原歩き、後編です。(前編はこちら)
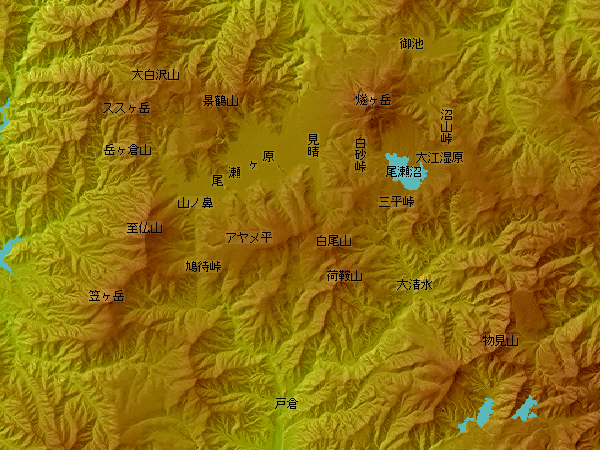 〔今回のルートを大きな地図で〕 |
尾瀬エリア Kashmir 3D |
鳩待峠から山ノ鼻に下って、上田代を過ぎました。
| 尾瀬ヶ原三又 |
8時40分、尾瀬ヶ原三又までやって来ました。この辺りはもう中田代です。直進すると竜宮十字路を経て見晴(尾瀬ヶ原の北東端で数件の山小屋が集まっているところ。)へ。左に折れるとヨッピ橋を経て東電小屋方面へ。ここは左折。ヨッピ橋まで行ったら右に折れて竜宮十字路に向かいます。
| |
分岐を折れてすぐのところで振り返ると至仏山がさっきとたいして大きさが変わらないままありました。随分歩いてきたはずなのに。手前にあるこんもりとしたところは牛首と呼ばれる丘です。
| ノアザミ |
尾瀬で最もポピュラーなアザミ。ノアザミです。尾瀬にはもう一種、オゼヌマアザミというものがありますが、葉の刺があまりに鋭く、触ると痛いので、木道の際に生えているものは刈られてしまうのだそうです。
| |
木道を歩いて行くとこんな楽園のようなところも。この風景の中を歩けただけでも今日尾瀬にやってきた甲斐があるというもの。
| ニッコウキスゲ |
尾瀬を代表する花の一つ、ニッコウキスゲ(ゼンテイカ)。なんかハツラツとした感じがしますね。
| ワタスゲ |
夏の風に吹かれるワタスゲ。もう朝露は消えてしまっています。ところで、ワタスゲといえばこの白いフワフワしか記憶にありませんが、これは種子に付いている綿毛であって、この前には花の時期があるはずです。調べてみたら、スゲと名が付くだけあってカンスゲなどと同じ姿をしていることが分かりました。むしろより背が低くて目立たないくらいです。ちょっと意外。
| |
ここはでニッコウキスゲが歓迎してくれています。沿道で小旗を振って声援を送ってくれているみたい。
| |
燧ヶ岳がだいぶん大きく、そして少しだけはっきりと見えてきました。夏の山って感じです。
| |
一面のヤマドリゼンマイ(大型のシダ)の中を突き進む。正面の拠水林をくぐってその向こう側に出ます。この写真、なんか合成みたいです。
| サワラン |
この辺りにもサワランが群生していました。めったに逢える花じゃないんですけどね。
| |
9時20分、ヨッピ橋の分岐に到着。直進するとすぐにヨッピ橋が現れます。ここは右折しますが、とりあえず橋までは行ってみましょう。
| ヨッピ橋 |
数年前に来た時はもうちょっと簡素な造りだったような。確か補修工事もしていました。
この橋が架けられたのは昭和の初めのことなのだとか。以来雪解け時期の増水でいく度となく流されたそうで、現在では鉄骨の頑丈な橋になっています。
| |
歩いてきた方角を振り返ると、至仏山が随分遠くになっていました。右から張り出している山裾は景鶴山のもの。
| |
ヨッピ橋からは分岐を右に折れて竜宮十字路にむかいます。
写真左に見切れている濃い緑色は沼尻川(尾瀬沼から流れ出している川)の拠水林。正面の山の稜線はアヤメ平や富士見峠辺りになります。
| ウラジロヨウラク |
この壺を逆さにしたような花はウラジロヨウラク。ツツジの仲間ですが、見慣れたツツジの花とは随分かけ離れた姿をしています。
| トキソウ |
トキソウをアップで。自然の造形には感嘆させられます。きっとこの形が合理的なんでしょうね。
| アブラガヤ |
この背の高い植物はアブラガヤ。今は緑色ですが、9月の紅葉の季節になると黄金色になり、湿原の草紅葉(くさもみじ)に彩りを添えます。
| 竜宮十字路 |
ヨッピ橋から20分ほどで竜宮十字路に到着しました。写真は十字路を通り過ぎて来た方向を振り返ったところです(奥のこんもりした緑のずっと向こうにヨッピ橋がある)。正面中央の山が景鶴山です。
ところでなぜこの辺りを竜宮というのか。それはこちらに。
| チングルマ |
チングルマはもう実を付けています。このふさふさの根元に種子があります。
| |
景鶴山をアップで。標高は2004m。以前は登山道も拓かれていたようですが、現在では登頂はもちろん立ち入りも禁止だそうです。
| リュウキンカ |
さあ、ここからは山ノ鼻に向かって戻って行きます。木道の間から顔を出しているのはリュウキンカ。本来はもっと早い時期に咲く花ですが、寝ぼけて出遅れたのかもしれません。春に咲くミツガシワを10月に見たこともあるので、尾瀬ではよくあることなのかも。
| クロバナロウゲ |
この花はクロバナロウゲ。 これも木道の間に咲いていました。中部地方以北の亜高山帯の湿原に生えるバラの仲間だそうで、yamanekoも初めて出会いました。
| |
日も高くなり燧ヶ岳がもうだいぶんクッキリと見えるようになりました。時刻は9時45分です。
| |
湿原の中の小さな川を覗くと思いのほか魚の影が濃いようです。餌や栄養分は乏しい環境だろうに。
| ヒツジグサ |
ヒツジグサの葉がびっしり。背景の池塘の黒が葉の緑を際立たせています。なんかアートですな。
| 尾瀬ヶ原三又 |
10時5分、尾瀬ヶ原三又まで戻ってきました。ここはスルーです。
| 昼食 |
今日は朝早くから活動しているので、さっきから腹が鳴っていました。途中のベンチに腰を下ろして昼食です。お昼にはまだ間がありますが。メニューはみてのとおり、助六寿司とゆでたまご。沼田ICを下りたところにあるコンビニで買ったものです。
| 至仏山 |
弁当を食べながら眺める至仏山。雄大ですな。 もう上田代に戻ってきました。
| 燧ヶ岳 |
振り返ると燧ヶ岳が。また来いよと言っています。
| ミズバショウ |
ミズバショウの花。もう葉が巨大になっていますが、こんな時期でも花が残っているものもあるんですね…。いやまて、花は棒の先にみっしりと密生しているヤツだから、正しくは「白い苞がまだ残っている」ということか。
| |
10時40分、山ノ鼻に戻ってきました。木立の中に山小屋の屋根が見えています(山ノ鼻には3軒の山小屋とビジターセンターがあります。)。
| 植物研究見本園 |
さて、ここからは植物研究見本園に行ってみましょう。湿原をぐるっと回る約1kmのコースです。
| |
見本園と言っても特段それらしい施設があるわけではなく、これまでと同様木道が巡っているだけです。きっと、尾瀬ヶ原の植生がコンパクトに収められていて、ここを見て歩けばその概要を理解できるということではないでしょうか。
| ニリンソウ |
ニリンソウ。もう時期が遅いのか、弱々しい印象です。
| |
|||
| ヤナギトラノオ |
ヤナギトラノオの群落が現れました。花は茎の途中に咲くので、一面の緑の中に黄色の花がたくさん埋れているといった感じです。
葉がヤナギに似ているのと、花がオカトラノオに似ていることからこの名が付いたということですが、葉はともかく花はお世辞にも似ているとは言えません。
| |
湿原の所々にこんなものがあります。これはクマ除けの鐘。尾瀬ヶ原には普通にクマが現れるので、この鐘を鳴らして人間の存在を知らせるのだそうです。特に朝夕は注意。
| ギョウジャニンニク |
これはギョウジャニンニクですね。紫色のよく似たやつはヤマラッキョウ。
| |
40分ほど散策したらまた山ノ鼻の分岐に戻ってきました。見えているのは至仏山荘です。
| |
山小屋の前の広場にはテント泊をしている人たちも。大きなテントはなく、ほとんどがソロ用のテントでした。
さあ、鳩待峠に向かって登りはじめます。
| |
森の中の雰囲気も朝方とは違って随分明るくなりました。
| 木道 |
木道は所々で補修工事が行われており(この日は作業はしていませんでした。)、真新しい部材が設置されているところも。写真は東京電力のマークとH26の数字が焼印されています。これは東京電力が今年設置した部材であることを示しています。当然色々な年のものがありますが、見た範囲で最も古いので平成16年というものがありました。耐用年数は概ね10年程度というところなんでしょう。
| |
地味にしんどい上りを続けて行くと、おお峠に着いたではありませんか。
| 鳩待峠 |
鳩待峠に戻ってきました。時刻は12時です。朝ここを出発したのが6時10分ですから、約6時間歩いたことになります。長い距離を歩いた後の最後の登りがちょっときつかったです。
広場にはたくさんの人がいて、これから湿原に向かおうというグループも。さすがにこの時間からの日帰りはないでしょうから、きっと今日はどこかの山小屋に泊まるのでしょう。
| 花豆ソフト |
整理体操をして下山の準備。乗合タクシーのチケットを買うと、定員の9人集まるまで出発しないとのこと。待ち時間で名物の花豆ソフトクリームを食すことにしました。
そのうち乗車人数が集まったとのことで、麓の戸倉に向けて出発しました。車でなにげなく通り過ぎていますが戸倉までの道沿いの渓畔林だって立派なものです。
戸倉の駐車場に着くと明らかに気温が違いました。これが更に下界に降りるとまた数度上がるんでしょうね。
午後1時、東京に向けて出発。高速道路には渋滞もなく順調に走ることができました。
急遽決めた尾瀬ヶ原の湿原歩きでしたが、最高の天気に恵まれ心から楽しむことができました。今年のうちにまた訪れることができれば。楽しみにしつつ日々を送ることにしました。