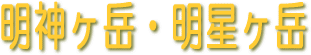
明神ヶ岳・明星ヶ岳 〜秋の箱根外輪山(前編)〜
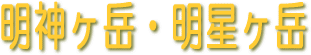 |
(前編) |
【神奈川県 箱根町 平成22年11月3日(水)】
今日は文化の日。祝日です。しかもこの日は「晴れの特異日」で、晴天である確率が高いのだとか。予報でもやはり「秋晴れの一日」と言っていました。そうなるとじっとしているわけにもいかず、秋の山に出かけることにしました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今日向かうのは関東の老舗観光地「箱根」です。箱根は温泉地として有名ですが、実は大規模なカルデラを持つ活火山で、主だった観光スポットはこのカルデラの中にあります(箱根火山の成り立ちはこちら)。今日はそのカルデラの外輪山を歩きます。
午前6時、新宿発の小田急に乗ってまずは小田原に向かいます。この時間、まだロマンスカーは走っていないので、急行に乗車。終点の小田原までは1時間30分の道のりです。
小田原駅からは箱根登山バスに乗り換えて、箱根湯本を経由し、早川沿いにカルデラの中に入っていきます。カルデラの中に降った雨が外輪山の切れ目を辿ってカルデラの外に出るその流路が早川です。下車は登山口最寄りの仙石バス停で。混んでいなければ40分で到着します。
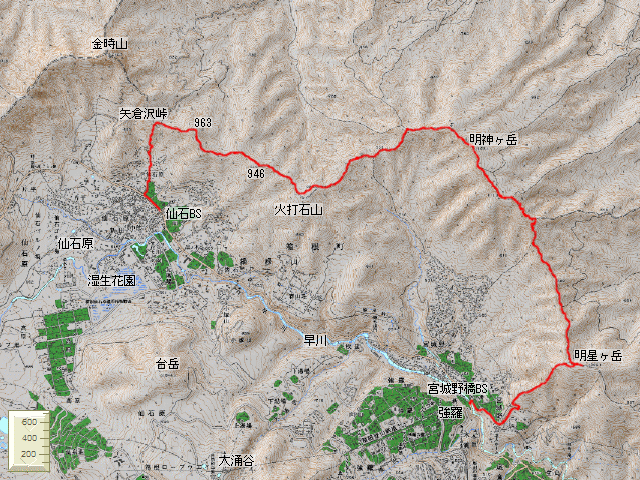 |
|
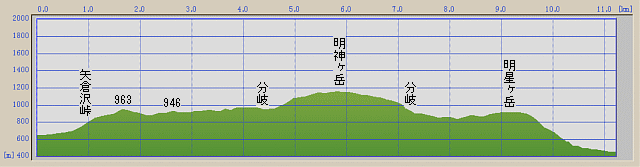 Kashmir 3D |
今日のコースは、仙石バス停から住宅や保養所などの間を抜けて登山口に向かい、そこから外輪山の稜線に向かって登っていきます。金時山との鞍部である矢倉沢峠で稜線に出て、そこからは東に向かって歩きます。途中にある火打石山はピークを北側に巻いてやり過ごし、やがて宮城野に下る分岐を過ぎたら、その先にある一段高くなっている(標高差は約200m)尾根が明神ヶ岳です。
明神ヶ岳からは更に稜線を辿り、大きく下りきると宮城野への分岐。その分岐では下らず、引き続き尾根道を明星ヶ岳に向かって緩やかに上っていきます。明星ヶ岳から麓の宮城野までの道は急降下。早川にかかる宮城野橋からバスに乗って、小田原へ戻っていくというものです。
| 金時山 |
小田原からは特に渋滞もなく、8時20分頃に仙石バス停に到着。近くのコンビニで食糧を調達し、なんだかんだしているうちに出発は9時前になってしまいました。
民家の間を歩いていると、これから取り付く外輪山がのしかかるように迫ってきます。上の写真のピークが金時山で、その稜線を右に辿った鞍部が矢倉沢峠です。
| ムラサキシキブ |
秋の野の宝石、ムラサキシキブです。この実を見ると梅仁丹を思い出します。色は若干異なりますが。
| センブリ |
石垣の隙間に生きているセンブリ。こんな環境で世代交代を繰り返しているとは。天晴れです。
| 登山口 |
バス通りに近いところにこそ民家はありましたが、そこから山に向かってまっすぐに延びる小径沿いには、いろいろな会社の保養所が並んでいました。不景気で福利厚生費が切り詰められる中、保養所の運営も大変でしょうね。
で、10分ほど歩いたら本格的に山道に。
| |
朝日が梢から漏れて、マーブル模様を作っています。日陰は少しひんやり。落ち葉を踏みしめて一歩一歩登っていきます。
| ホトトギス |
縦に並ぶのはホトトギスの果実。三つの稜がソリッドで、槍の穂先のようです。
| |
火山灰土の山道を黙々と登ります。
| 矢倉沢峠 |
9時40分、矢倉沢峠に到着しました。小休止している間に2組の登山者に追い越されましたが、いずれも金時山に向かって歩いていきました。ここから明神ヶ岳に向かうのはちょっとアプローチが長いので、宮城野から直登する人が多いようです。
さて、これからは尾根道歩きです。天気は良いのですが、箱根上空には雲が湧いたり消えたりして、日が陰ったり照ったりしています。
| What's this? |
このひょろ長いものは何の種子? 初めて見た気がします。さく果が3つの部屋に分かれているので単子葉植物らしいですが。 で、いろいろ調べた結果、ツルボの種子と判明。ふーん、こんなだったのか。
| リュウノウギク |
峠からじわじわと登っていきます。リュウノウギクが登山道脇のあちこちで揺れていました。
| 振り返ると |
10時、963mピークに到着しました。振り返ると北側の外輪山が屏風のように連なっています。右の尖っているのが金時山。そこから左に長尾山。乙女峠を挟んで、電波塔があるのが丸ノ岳です。矢倉沢峠は手前の日陰になっているところあたりです。
| 紅葉 |
陽が射すと紅葉が映えます。
| 仙石原 |
カルデラの中にある仙石原。植物の宝庫、箱根湿生花園もここにあります。
| リンドウ |
さて、再び歩き始めましょうか。リンドウがきれいに咲いています。今日はリュウノウギクとリンドウの一日になりそうです。
| ノブキ |
控えめな花のノブキ。葉は革質でテカテカです。
| ハコネメダケ |
ずっとササの原を歩いてきましたが、ところどころこんなに伸びているところもありました。トンネルみたいです。これはハコネメダケといって、箱根の外輪山に自生する種で、メダケ属とクマザサ属とのハイブリッドなのだそうです。
| ノコンギク |
淡い紫のノコンギク。秋の野に似合う花です。
| 946mピーク |
10時25分、946mピークまでやってきました。ササの背丈も低く、展望がよさそうです。
| 丹沢山塊 |
思ったとおり360度の眺望です。上の写真は北の方角(南は逆光なので。)。遠くの山並みは丹沢山塊です。右手には丹沢を代表する鍋割山(1273m)や檜洞丸(1601m)が見えます。写真左の突出した峰は道志渓谷の最高峰、御正体山(1682m)です。
| 明神ヶ岳の稜線 |
東には明神ヶ岳の稜線が見えました。ここからS字に稜線を辿っていきます。
| |
尾根道は上ったり下りたりの繰り返し。いい運動になります。
| 巻き道 |
途中、道は稜線を離れ、火打石山のピークの北側を巻いていきます。落葉広葉樹の明るい森です。
| マユミ |
おお、これはマユミの果実。まだ開裂しきっていないので、全体的に淡いピンク色に見えます。
| |
まだ立冬の手前なので「小春日和」といってよいか分かりませんが、日向はそんなポカポカの陽気です。
| |
巻き道から稜線に出ました。今度は逆に稜線の南側を歩いていきます。ススキがいい風情を醸しだしていますね。この道沿いは日当たりが良いらしく、歩くにつれ草原に咲く花が次々と現れました。ここからはそのラインナップのご紹介。
| リンドウ |
リンドウはどれもよく開いています。
| アキノタムラソウ |
ちなみに、「春の」と「夏の」もあるそうです。
| アキノキリンソウ |
こっちも「秋の」麒麟草。奥の株はこれから咲くようです。
| シオガマギク |
「塩竃菊」ですがキクの仲間ではなく、ゴマノハグサ科。そういえば似たようなのに「秋明菊(シュウメイギク)」がありますね。こちらはキンポウゲ科です。
| ヤマラッキョウ |
まるで園芸種のようなポップな姿。名前は野暮ったいですが。
| キアゲハの終齢幼虫 |
可愛い幼虫を見つけました。キアゲハの幼虫です。これから最後の冬を蛹で越して、来年の春には華麗な変身を遂げ、野山を舞うでしょう。それにしてもペットにしてもいいくらいの可愛さですね。
| ワレモコウ |
ワレモコウ。深い血のような赤色をしていますが、昔は止血剤として利用されていたそうです。それにしても、この花がバラの仲間だなんて。
| ヤマトリカブト |
ヤマトリカブトの毒性は強く、この花粉が混ざった蜂蜜を舐めても中毒を起こすほどだそうです。
| ミヤマガマズミ |
見た目は美味そうなんですが…。鳥たちのご馳走です。
| コウゾリナ |
「剃刀菜」と書いてコウゾリナと詠みます。「かみそりな」が転じたものだそうです。
| 明神ヶ岳 |
花を見ながら歩いているうちに明神ヶ岳の尾根が眼前に迫っていました。今いる尾根より約200m高いところにある尾根です。写真中央よりやや右が明神ヶ岳のピーク。この角度からだと分かりにくいですね。
さて、全行程のちょうど中間点くらいまでやってきました。続きは後編で。《後編に続く》