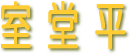
室堂平 ~天上の地で一足早い秋を(前編)~
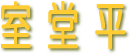 |
(前編) |
【富山県 立山町 令和4年9月10日(土)】
「室堂平」 立山黒部アルペンルートの中程にあり、立山や剱岳への登山の拠点となっている場所です。また、ここは高山植物の宝庫でもあり、登山者以外にも多くの人が訪れる場所でもあります。その数、年間90万人以上なのだとか(「年間」と言っても雪のない数か月ですですよね!)。
今回、yamanekoも12年ぶりに室堂平で野山歩きをすることにしました。(前回の様子)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
立山黒部アルペンルートに長野県側からアプローチする場合、起点は大町市の扇沢になります。そこまではマイカーで行けますが、そこから先は、電気バス、ケーブルカー、ロープウエイ、トロリーバスと乗り継ぐことになります。多くの観光客にとって、途中の黒部ダムとともに、この乗り物を乗り継いで行くこと自体も観光の目的になっているのです。ちなみに室堂平から先の富山県側は前回往復したことがあるので、今回でアルペンルートを完走(完乗?)することになります。
麓の大町温泉郷に前泊し、ドリーム号Ⅲで扇沢へ。到着したのは午前10時でした。空気は少しひんやり。既に標高は1400mです(室堂平は2400m)。
扇沢出発は10時30分。往復の乗車券は事前にネット予約(若干割引あり)しておいたので、スマホでQRコードをかざすだけで発券。これは混雑時には便利です。ちなみにこの日は土曜日でしたが、係の人曰く「今日は土曜日にしては決して多くはなく、皆さんラッキー」とのことでした。ハイシーズンは相当な人出なのだそうです。ちょうどシルバーウイークの直前で、加えて台風が通過した直後のタイミングだったからかもしれません。
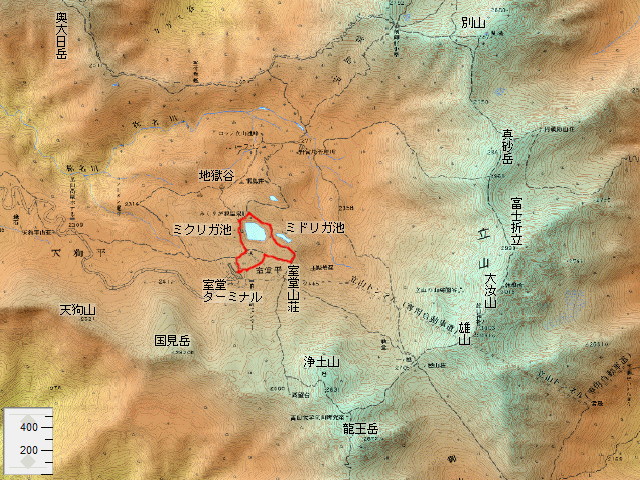 |
Kashmir3D |
10時30分、扇沢を出発。バスはいきなり長いトンネルに入りました。黒部ダムの天端を歩く区間と大観峰のロープウエイを除きずっとトンネルの中の移動です。
そして、室堂ターミナル到着は11時55分でした。
| 立山 |
ターミナルで昼食を済ませて外に出ると、この風景です。正面に立山がどどーんと。標高3千mの山が目の前に。この瞬間にはるばるここまでやって来て良かったと思いました。早速観察を始めましょう。
| ヤマハハコ |
これはヤマハハコか。小さな頭花が寄り集まって花序を作っています。いつも比較的乾燥したところで出会うような気がします。
| 室堂平 |
あらためて室堂平越しの立山連峰を。(写真にマウスポインタを乗せると山名表示) 室堂平、広々としていますね。もう秋の色になりつつあります。ちなみに「平」といいつつも結構起伏があり、正面の丘の向こうは大きく落ち込んでいたりまた高くなったりしています。
| 隠れ剱 |
山並みの端。手前の山は剱御前で、その奥に剱岳が見切れています。「岩と雪の殿堂」 剱岳は多くの登山者の憧れでもありますね。
| 室堂ターミナル |
振り返ると室堂ターミナル。冬場の豪雪にも耐えられるようになのか立派な造りになっていますね。ここ立山は世界有数の豪雪地帯とのことで、吹き溜まりなど多いところでは積雪20mにもなるのだそうです。ちょっとしたビルの高さです。そして、初夏にはそれが全部融けると考えると逆にそれもすごいです。
| ミヤマアキノキリンソウ |
ミヤマアキノキリンソウ。別名をコガネギクと言います。標高の低いところに生えるアキノキリンソウよりも頭花が大きいです。
ミヤマは「深山」で、山深いところ、標高の高いところという意味で付けられる名前です。
| ネバリノギラン |
植物のラインナップがやっぱり高山っぽいですね。これはネバリノギラン。若干紅葉(?)気味です。
| 大日ブラザーズ |
左が大日岳で右が奥大日岳。これらも室堂平を囲む山々です。こことの間には地獄谷の低地があり、その標高差は200mほど。景色の奥行き感が日常と違いますね。
| アオノツガザクラ |
壺型の白い花、アオノツガザクラの花です。高さはせいぜい20cmほどですが、これでも立派な樹木なんです。
| イワカガミ |
この花殻は…、根元に残る葉を見るとイワカガミのようです。まさに名前のとおりテカテカで光を反射しています。
| タテヤマアザミ |
タテヤマアザミ。ここ立山が基準標本の産地なのだとか。根生葉がないのが特徴の一つ。
| タカネヨモギ |
これはタカネヨモギ。葉は細かく裂けていてコスモスの葉みたい。まあ、ヨモギっぽいと言えないこともないような。花はもう枯れていますが葉はまだ緑色なんですね。
タカネは「高嶺」で、高山という意味で付けられる名前です。高山に生えるヨモギに似た植物ということですね。
| ウメバチソウ |
ウメバチソウは今が盛り。いきいきしています。
| オヤマリンドウ |
オヤマリンドウもちょうど花の季節のよう。紫紺の花です。よく似た植物にエゾリンドウがありますが、エゾリンドウは湿地を好み、オヤマリンドウは草地に生えています。
| チングルマ |
チングルマご一行様。花茎の上に白鬚のような花序を揺らしています。凜とした立ち姿は樹木であることの矜持か。花が淡く赤味を帯びるタテヤマチングルマという種があるようですが、今の状態ではこれがそうなのかは分かりません。
| ミヤマトウキ |
生薬で有名な当帰(トウキ)。その仲間で高山に生育するのがミヤマトウキです。右の写真は果実。
| イワイチョウ |
イチョウの葉っぱが落ちているのかと見間違うようなイワイチョウの葉。落葉しているわけではなく、ちゃんと生えている状態です。
スタートからここまで約200mにもかかわらず既に30分経過しています。
| ミヤマアキノキリンソウ |
ここのミヤマアキノキリンソウはまだいきいきとしていますね。生育箇所の近いでしょうか。風当たりとか湿気とか。
| タテヤマリンドウ |
秋色の草原の中でタテヤマリンドウの青い花冠は鮮やかです。低地に生えるハルリンドウの変種なのだそうです。タテヤマ(立山)の名が付く植物は他にもいくつかあって、さっき見かけたタテヤマアザミもそのうちの一つ。他にはタテヤマイワブキとかタテヤマキンバイとかも。
| タカネニガナ |
ニガナによく似たこれはタカネニガナ。高山に咲くニガナの仲間ですね。もしかしたらクモマニガナかもしれません。クモマは「雲間」という意味で、こちらも高山に生えるという意味があります。このような低地に生えるものと区別する修飾語的に付けられる言葉は、標高が高くなるにつれて「深山」→「高嶺」→「雲間」となっていくようなイメージ。言葉の意味としてもそうですよね。
| ミヤマキンバイ |
地面に張り付くように生えているのはミヤマキンバイです。花は低地の野山で見かけるミツバツチグリに似ていますね。葉は若干違いますが。
| ヨツバシオガマ |
花期を終えてもなおキリッと姿勢を保って立つヨツバシオガマ。次の世代に命をつなげたでしょうか。
| イワイチョウ |
ちょっと分かりにくい写真ですが、イワイチョウの花茎。花の時期はもう過ぎています。
| 秋の空 |
室堂平には時折涼しい風が吹き渡っていました。なにしろ標高2400mですから。
| ウサギギク |
ちょっと遠くなので分かりにくいですが、ウサギギクですね。根生葉の形がウサギの耳に似ているから付いた名だそう。このウサギギクも立山が基準標本の産地なのだそうです。
| 剱御前小屋 |
ちょっと視線を上げてみると。別山と剱御前の鞍部に山小屋があるのが見えました。地図で確認すると剱御前小屋のようでした。(望遠で目一杯寄って撮っています。)
| 雄山神社 |
立山(雄山)の山頂には立派な建物が。雄山神社の社務所です。(こっちも超どアップで。) 左手のピークの上にちょこんと見えている三角屋根が雄山神社の峰本社です。
| ミクリガ池 |
丁字路に突き当たりました。正面の低地を覗き込むと青々とした池が。ミクリガ池です。
丁字路を右折して正面に立山を見ながら進みます。非日常の風景の中にいることをあらためて感じる次第です。
| ワレモコウ |
風に揺れるワレモコウ。もう花穂がだいぶん伸びています。色も薄くなりかけていて、花期も終わりです。
| キオン |
これはキオンですね。キオンは低山でも見られますが、丈も高く華奢な印象で、高山のもののような逞しさは感じられません。「気温」の差が原因か。
| イワオトギリ |
足下で控えめに咲いたイワオトギリ。か弱そうな感じがしますが、ここ立山の厳しい環境の中でずっと命をつないできていると考えると、何やら「尊さ」といった類いのものを感じました。
| ミネウスユキソウ |
ミネウスユキソウがありました。茎頂近くの総苞葉がまるで薄雪をまとったかのように見えますね。本来の花は茎頂に何個か寄り集まって付いている頭花。筒状花の集合体で、ちょうど開花の時期でした。
| ヒメクワガタ |
クワガタというと昆虫の方を思い浮かべますが、植物にもクワガタの名を持つものがいくつかあります。これはヒメクワガタ。高さ20cmに満たない小柄な花です。ヒメ(姫)の名が付く所以でしょうね。
| オヤマリンドウ |
いい具合に色付いていたオヤマリンドウ。花冠はこの状態から大きく開花することはありません。慎ましやかな花です。
さて、ここまで1時間をかけて300mほど進みました。時速0.3kmです(牛歩か)。この後は池の畔の方まで行ってみたいと思います。まだまだ面白そうなものに出会えそうです。(後編に続く)