
三毳山 ~冬晴れの尾根歩き(後編)~
 |
(後編) |
【栃木県 栃木市 令和4年12月10日(土)】
カタクリで有名な三毳山での野山歩き。後編です。(前編はこちら) もちろん今はカタクリの花の時期ではありませんが。
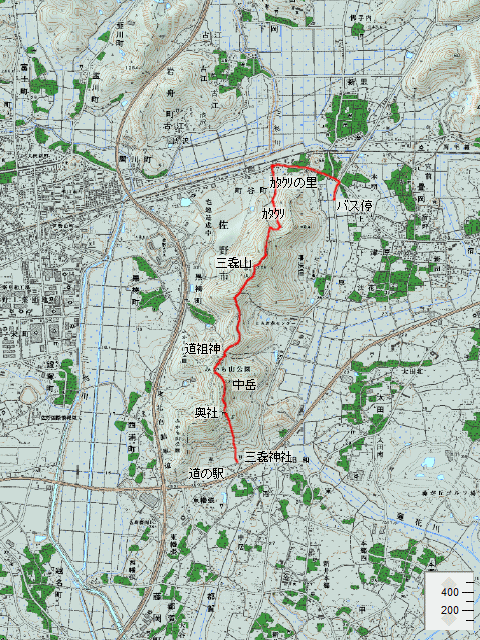 |
Kashmir3D |
9時50分に三毳山南端の三毳神社をスタート。奥社まで直登し、そこから稜線を歩いて中岳を超えました。
10時40分、鞍部になっているところで周回道路を跨ぎます。ここが三毳の関所で、昔はここを東山道が通っていたそうです。
| 三毳の関 |
道路を越えると広場があり、東屋もありました。日向ではベンチでお茶をしている人もいたりして、長閑な風景です。関所があったということですから、ここ三毳山の東西で支配者が異なっていたということでしょうね。
| 道祖神 |
広場には道祖神も建っていました。道中の安全を祈願するとともに、外部からの災厄や疫病が侵入するのを防ぐ塞ノ神の役割もあったようです。側面に彫られた文字を読んでみると、かろうじて「弘化」という文字が読み取れました。弘化は江戸時代後期の年号。今から170年ちょっと前に建てられたもののようです。
| 花籠岩 |
関所跡から進むことしばし。平らなステージのような岩が現れました。看板には「花籠岩」とあります。解説によると、僧が五穀豊稔、村内安穏を祈願して一週間経を唱えたところ、村民が競って花籠を捧げたという故事から来ている名前なのだそうです。確かに岩の上に立つと見晴らしも良く、祈願しているところが麓の村から見えたかもしれません。でもまてよ、そんな昔に「一週間」という期間の概念があったのか?
| 花籠岩からの眺め |
花籠岩からの眺めがこちら。写真右手に東北道の佐野SAが見えています。遠くの山並みは赤城山から皇海山、日光白根山などです。
さて、尾根歩きを楽しみましょう。身も心も解放されるような気持ちよさです。
| コゴメウツギ |
これはコゴメウツギの葉ですね。ウツギといいつつバラ科の植物です。和芥子色に黄葉していくのがいいですね。yamanekoの好きな黄葉です。
関所跡から傾斜が増していましたが、ここでまた周回道路を跨ぐと更に傾斜が増して、三毳山山頂に向かって一気に登っていく形になります。
ここも直登です。そろそろ軽く汗ばんできました。
| 花センターへの分岐 |
右手に下って行く道との分岐が現れました。その道を行くと麓にある「とちぎ花センター」に至ります。大温室などがあり、今から16年前の初夏に行ったことがあります。(こちら)
山頂に向かって黙々と。
おお、視界が広がりました。通信アンテナがあるということはここが三毳山の山頂ですね。
| 三毳山山頂 |
11時10分、三毳山の山頂に到着しました。リュックを下ろして眺望を楽しみましょう。
| 西側展望 |
山頂からは西側の展望が開けています(東側は通信施設があって見えません。)。正面奥の大きな山塊は赤城山です。写真右端には日光白根山の姿も。
| 日光白根山 |
その日光白根山をアップで。山頂溶岩ドームは完全に真っ白になっていますね。ここからだと北西に約57kmほど離れています。
| 男体山・女峰山 |
日光白根山から少し東(右)に視線を移すと男体山や女峰山が望めました。ここからの距離は約50kmです。こうやって遠くの山々を眺めるのも山登りの楽しみの一つですね。山の名前が分かるとより印象に残ります。
| カタクリの里へ |
山頂に平地部分はほとんどなく、通信施設のフェンス脇に腰かけて菓子パンを食しました。そして山頂での滞在時間15分で下山開始です。
| 分岐 |
しばらく下ると分岐が現れました。直進すると引き続き稜線を下る道。右折すると谷間に向かって下る道です。その先にカタクリの里(群生地)があり、そこを通って下山することもできます。
花の時期ではないものの、ここはカタクリの群生地のある谷間に向かいました。
| カタクリの里ゲート |
下って行くとフェンスが現れました。えっ、行き止まりか。
ゲートの張り紙を読むと、3月中旬から下旬までの間ここのゲートを閉じるのだとか。カタクリの開花期間中は登山者が通行しないようにしているようです。なので、今は鍵が開いていて、中に入ることができました。
| ヤブラン |
足下に何株かヤブランが。葉が青々としていますね。黒く輝いているのは種子です。
| かたくりの里 |
ここがカタクリの里。北に向いて開いた谷一面にカタクリが咲くようです。確かにこの谷がピンク色に染まるところを想像すると感動ものですね。
谷の底の方にモミジが紅葉していました。急にそこだけカラー写真になっているみたいでした。
| 秋の名残 |
秋の名残。これから雪の季節に向かいます。
| かたくりの里入場ゲート |
再びゲートが現れました。谷全体がフェンスで囲まれていて、花の季節にはここのゲートでカタクリの里への入退場を管理するのだと思います。
ゲートを出ると里の風景です。人間様の生活圏に戻ってきました。
| 管理センター |
かたくりの里の管理センターです。室内に電気は付いていましたが、入口には「閉鎖中」とありました。
時刻は11時50分。ここからは県道を歩いてコミュニティバスのバス停に向かいます。
| 「円仁誕生地入口」バス停 |
ダンプがゴーゴー行き交う道路を歩いてバス停にやって来ました。バス停名は「円仁誕生地入口」です。円仁とは平安時代初期に活躍した慈覚大師のことで、最澄や空海とともに唐に留学したこともある当代きってのインテリ僧。その生誕の地がここから畦道をたどって三毳山の山裾に至ったところにあることから、バス停の名前になったようです。
2、3時間に1本のバスに待ち時間5分で乗り込み(もちろん時刻はあらかじめ調べていました)、出発地点の道の駅に向かいます。乗車時間は6分。料金は200円でした。
| 三毳山 |
バスを降りた後、道の駅では食堂で佐野ラーメンをいただきました。ネットには味が落ちたとか書いてありましたが、yamanekoにとってはまた食べたいと思うくらい十分に美味でした(味の評価は単に好みの問題では)。そして、駐車場のドリーム号Ⅲのところに戻って、軽く整理体操をして、三毳山を後にしました。
上の写真は、佐野藤岡ICに乗る前に三毳山の南側に回って撮ったもの。南北に長い山なので、ここから見るとこんもりとした小山に見えますね。今日は楽しませてくれてありがとう。
さて、おそらく今日が今年最後の野山歩きになると思います。もっぱら低山の山登りとはいえ怪我もなく楽しむことができ、何よりでした。
来年も小さな感動を求めてあちこち出かけたいと思います。そのためにも健康第一で。