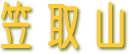
笠取山 〜多摩川源流、再び〜
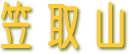 |
【山梨県 甲州市 平成21年10月17日(土)】
多摩川の最初の一滴が生まれるところ、笠取山。ちょうど1年前の10月の第二土曜日、輝くような紅葉の中を歩いた山です。
そのときの楽しい山歩きを再び、ということで、今回は会社の仲間をさそってやって来ました。
ところが当日の天気は曇り。降水確率こそ10%ですが、この天気では紅葉の美しさも半減かも。とはいえ、それぞれ都合を合わせて計画したので、予定どおり出発です。笠取山もその日の天気なりの姿を見せてくれるでしょう。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前6時、集合場所の荻窪駅北口に集まったのはyamanekoを含めて4人。同年配のMさん、Aさんと、若者B君です。ここからAさんのステップワゴンに乗って、青梅街道をひたすら西へ。青梅市街を抜け奥多摩湖を過ぎると、辺りは深山の趣です。
| 作場平 |
8時45分に登山口の作場平に到着。スタート時刻も1年前とほぼ同じです。ただ、曇天のためなのか、駐車場には数台の車しか停まっていませんでした。(去年は満車でした。)
装備を整えて、ストレッチをして、登山口で記念撮影。左からAさん、Mさん、B君です。
| 森の中へ |
なんかいい雰囲気でしょう。静かな朝の森。柔らかい地面を踏んでゆっくりと歩いていきます。そういえばMさんとAさんは利尻山メンバー。B君とは去年高尾山に登っています。
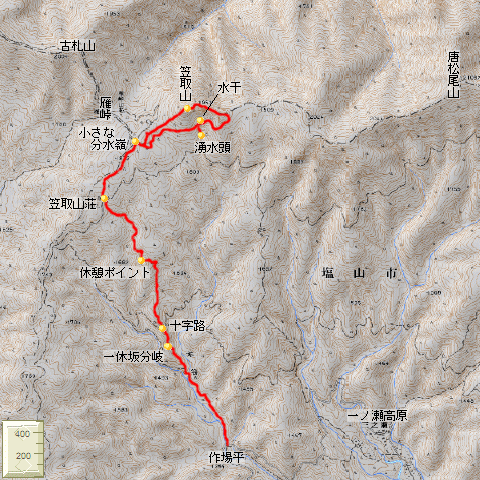 Kashmir 3D |
本日のルート |
今日のルートは、作場平から川沿いにさかのぼり、途中から川筋を離れ笠取小屋を目指して登っていきます。笠取小屋からは稜線の道となって、最後にそそり立つような笠取山のピークへ。山頂で昼食をとった後、反対側に下って、多摩川の最初の一滴が滴る「水干(みずひ)」を訪れる予定です。(このルートも去年と同じなんですがね。)
| マムシグサ |
晩秋の色合いのなかでちょっと目立っていたマムシグサの実。
| 若い多摩川 |
この小川はまだ若い多摩川。清冽な水が勢いよく流れています(正式にはここではまだ一ノ瀬川で、奥多摩湖より下流が多摩川と呼ばれることになっています。)。さあ、ここからは谷筋を離れて山腹を登っていきます。
| 一休坂分岐 |
しばらくいくと分岐があり、まっすぐ行くとヤブ沢峠。右手に折れると一休坂です。ここでちょっと休憩して一休坂に向かいます。
| ヤマウルシ |
一休坂に入ると紅葉が一段と見事になってきました。背景が白い空なので鮮やかさに欠けますが、これも侘び寂の趣があって亦良し、ですか。
こんな道を登っていきます。幸せ幸せ。一年のうちでもこんな山歩きができるのはこの時期だけ。四季っていいなあ。日本の自然って素晴らしいなあ。
| アサノハカエデ |
浅く裂けた葉身に粗い鋸歯。比較的よく目立つ葉脈。長い葉柄。これ、アサノハカエデの特徴です。
| 錦の森 |
一休坂の急な道に息は上がっています。でもちょっと足を止めて見上げると、こんな素晴らしい風景。30mくらい上空から見下ろすと、きっと錦の森に包まれた自分が見えるでしょうね。
| 木漏れ日 |
少し陽が差してきました。やっぱり明るくなると気持ちが前向きになってきますね。いいぞ、いいぞ。
| 落葉 |
休憩ポイントで拾った落ち葉三種。左:モトゲイタヤ、右:ハウチワカエデ、下:ヤマナラシ。
小さな流れを渡って、さらに登っていきます。もう稜線がだいぶ近くなってきました。
| マユミ |
マユミの葉。風が吹くと葉のつけ根を支点にクルクルと反転して日の光を反射していました。薄桃色の実は葉が落ちた後も枝に残っています。
| 笠取小屋 |
10時30分、笠取小屋に到着しました。ここまでで1時間半、去年よりペースが速いようです。どうりでしんどかったはずだ。ここで休憩です。でも長居をすると汗が冷えてくるので要注意。上着を脱ぎ着してこまめに温度調節することが重要です。
| コスギゴケ |
コスギゴケの絨毯の上に赤い実。ナナカマドでしょうか。
| 小さな分水嶺 |
稜線上にある「小さな分水嶺」に到着。この小さな丘は多摩川、荒川、富士川の3水系の分水点になっているのです。正面に笠取山が見えていますね。これからあそこに登るんです。
読みにくいですが、右の面に「多摩川」、左の面に「富士川」と彫り込まれています。向こう面には「荒川」です、念のため。
振り返ると歩いてきた道。稜線なので遮るものがなく、晴れていればずっと向こうに大菩薩嶺が見えるはずです。
| 笠取山のピーク |
さあ、最後に待ちかまえている急坂にとりつきます。ここから先はただ無心で。
| 山頂 |
で、10分後。ゼーゼー言いながら山頂に到着しました。汗がどっと噴き出してきます。でも山頂を吹き抜ける風でみるみる体温低下。時計を見るとまだ11時過ぎですが、とりあえず風の当たらない窪みを見つけて、そこで弁当にしましょう。
| 山頂からの眺望 |
おお、素晴らしい眺め…、うん。 あのうっすらとみえる稜線の向こうから登ってきたのです。
| サラサドウダン |
弁当を食べながらサラサドウダンの紅葉を愛でる。至福ですな。これでもう少し暖かかったら言うことないのに。
| 下山開始 |
昼食を終えるとさっそく動き始めました。というのもじっとしていると寒いのです。山頂からいったん反対側(東側)に向けて下っていきます。
ずいぶん下った後、唐松尾山からの登山道と出会ったら、反転して西に向かって行きます。水干はちょうど山頂直下にあるのです。
| 水干へ |
どうです、いい感じの登山道でしょう。yamanekoはこういう感じの山道を歩くのが大好きです。
12時、水干に到着しました。写真奥にある小さな窪みの天井から最初の一滴がしたたるのですが…、去年同様、今回も干上がっていました(若干湿ってはいたのですが。)。んー、残念。
でもご安心。水干から谷を約60m下ると、こんこんと湧き出しているところがあるんです。(上の写真)
水干で滴った最初の一滴は、いったん山中に染み込んだ後ここで再び湧き出して、流れとなって下っていくのです。流れをさかのぼってたどり着く最も遠いところがここになります。みんな手のひらですくってすくって飲んでいました。
| 大ミズナラ |
多摩川の源流を堪能したら、本格的に下山です。
上りは息が上がりますが、下りは下りで関節にダメージが。衝撃を和らげるため、歩幅を小さくしてゆっくりと下山するのが基本です。途中、一休坂の十字路のところにある大ミズナラで元気をもらって、また一歩一歩下りていきました。ヒザをかばいなら。
| 余韻の中で |
再び紅葉の中を歩いていきます。すでに体のあちこちに張りや痛みが出始めていますが、それも楽しい山歩きの余韻です。
| 渓流 |
作場平が近づいて、道も緩やかになってきました。水干に端を発した多摩川の最初の一滴は、紅葉の谷を下る間に「渓流」と呼べる姿になっていました。
去年とまったく同じ時期に登った笠取山。天気の相違はあったものの、紅葉は去年よりちょっと早く時期を迎えていたようで、山の印象も少し異なっていました。カレンダーは同じでも年によって微妙に前後するんですね。あたりまえか。
ところで、2年連続で「最初の一滴」を見ることができませんでした。再リベンジするには梅雨時とかに訪れた方がよいのかもしれませんね。