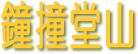
鐘撞堂山 ~木々とともに陽を浴びて(後編)~
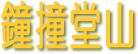 |
(後編) |
【埼玉県 寄居町 令和2年3月15日(日)】
早春の陽を浴びながらの野山歩き。後編です。(前編はこちら)
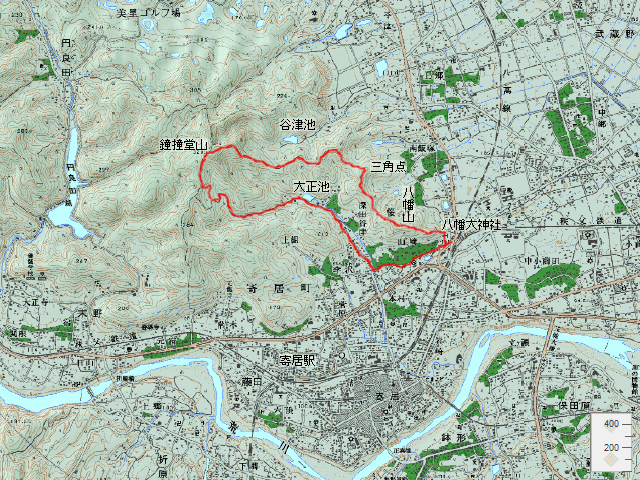 |
Kashmir 3D |
秩父鉄道桜沢駅近くの八幡大神社からスタートし、尾根道を歩いて市町境(寄居町と深谷市との境界)の稜線に出てきました。お昼は過ぎてしまいましたが、鐘撞堂山の山頂まではあと1km弱です。
| カタクリ |
市町境の稜線の右手(北側斜面)にカタクリの保護区域が現れました。ここは深谷市が整備している「鐘撞堂山ふるさとの森」の一部。「ふるさとの森」は一つの谷戸の内側を稜線までの斜面も含めてエリア内としています。
| 後ろ姿 |
ここの群落はまだ咲き始めといったところ。北側斜面ということで日差しも弱く、花被片を開いている株はごくわずかでした。ところで、カタクリの群落はどこでも大抵北側斜面なんですよね。
小さなピークで小休止です。ここには「八幡山⑦」の張り紙。いや、ここは「鐘撞堂山」の方が明らかに実態に即しているんじゃないでしょうか。
| 谷津池分岐 |
緩い鞍部。小広くなっています。ここは谷津池分岐と呼ばれていて、右手に下っていくと「ふるさとの森」内にある谷津池に至ります。
| ガマズミ |
ああ、これは展開途中のガマズミの若葉ですね。まだシワシワが強いです。これからこのシワが伸びて大きく広がっていきます。
これは日差しが陰って閉じてしまったところでしょうか。開花時より清楚な感じがします。
おっ、階段が現れました。地図を見てもここから等高線の間隔が狭まっているのが分かります。
次に少し緩やかな山道に。
そしてまた階段。汗が出てきたのでアウターを脱いでリュックにしまいました。
| タチツボスミレ |
里山のスミレといえばタチツボスミレ。可燃な姿をしていますが、結構過酷な環境でも花を咲かせる、たくましい一面も持っています。
うっ、かなりの斜度の階段が。大腿四頭筋にビンビンきます。
階段が終わるとぐっと山頂が近づきました。急傾斜は終わったようです。荒い息を収めてから出発しましょう。
| 谷津池 |
東の方を見ると眼下に谷津池が。この谷戸が「鐘撞堂山ふるさとの森」で、ここだけ深谷市が寄居町に貫入している形になっています。この谷戸を囲む稜線の外側は寄居町ということなんです。遠くに見える街並みは熊谷とか籠原あたりでしょう。
| 寄居町市街地 |
さあ、山頂まではあとわずか。寄居町の市街地を左手に見ながら上っていきます。いつのまにか頭上に雲が広がってきました。
寄居町は秩父の山域を下ってきた荒川が平地に出たところに広がっていて、扇状地と河岸段丘の地形になっています。荒川の中流域の始まりがここ寄居町になるのです。
| サンシュユ |
山頂の南斜面は園地的に植樹がなされていました。今満開だったのはこのサンシュユでした。
| ヤマザクラ? |
このサクラは? 形態的にも葉の展開と同時に開花している点でもヤマザクラと思いますが、ひょっとしたら植栽された園芸種かもしれません。
| 鐘撞堂山山頂 |
13時ちょうど、鐘撞堂山の山頂に到着しました。スタートから2時間15分の行程でした。目の前にあるのは登山者用滑り台、ではなく展望台です。
| 堂平山 |
真南には堂平山。秩父の山々の前衛に位置していています。ここからだと直線距離で15kmほどです。yamanekoも登ったことがあります(こちら)。
| 昼食 |
さて、遅くなりましたが昼食にしましょう。メニューはコンビニで買ったのり巻きと唐揚げです。
食後、再び陽が差し始めまたので展望台に行ってみたら立ち入り禁止になっていました。「柵が危険なため」とのこと。残念です。
| 花園・東松山方向 |
南東方向には今日登ってきた尾根が延びています。その右手の谷戸が帰りのルートになります。
それにしても関東平野は広いですね。正面の平地は花園やその奥は東松山あたり。さらにずっと奥になると大宮とか上尾とかになります。
| さいたま新都心 |
さいたま新都心のビル群も望遠レンズで捉えることができました。ここからの距離は50kmほどです。
| 東屋 |
昼時を過ぎたこの時間、東屋には人もまばらでした。山頂でのんびりするにしても、この季節は日向の方がいいですよね。
鐘撞堂山らしく半鐘が設置されていました。もともとこの山の名の由来は、戦国時代この山が見張りの出城だったことで、有事に鐘をついて味方に知らせる役割があった所だからということです。もちろんこの半鐘は近年になって設置されたものでしょう。
| 北西方向 |
そこからは北西側の展望が開けていました。榛名山、浅間隠山、浅間山が概ね横一列に並び、その奥に草津白根山があるという位置関係になります。榛名連山の麓に見える市街地は高崎ですね。
あと、北方向に尾瀬の燧ヶ岳も見えていると教えてくれる登山者の方がいて、木立の隙間から双眼鏡で確認することができました。これは教えてもらわなければ分からなかったでしょう。
| 下山開始 |
ということで、ひととおり景色を楽しんだあと下山開始。時刻は13時45分です。いったん登ってきた方とは反対側の稜線沿いに下っていきます。
ほどなく分岐が現れました。直進すると円良田湖を経て波久礼駅方面に至るのですが、ここは左手に山腹を下っていきます。
そういえばここにも例の張り紙がありますね。「大正池②」だそうです。大正池はずいぶん遠くにあるはずですが。と、ここでなんとなく分かりました。張り紙の「八幡山」や「大正池」は登山道のコース名なのではないでしょうか。確かに、ガイドブックなどでは八幡山コースや大正池コースという名前で呼ばれています。だったらちゃんと「コース」を付記してくれればいいのに。
| ニオイタチツボスミレ? |
これはニオイタチツボスミレ? ちょっと自信がないです。
| キリ |
しばらく下っていくと大きなキリの木がありました。以前この辺りに民家があったのかもしれません。枝先に付いているラグビーボール型のものは去年できた果実。それよりも小さく丸いものは今年の春に咲く花芽です。
キリはもともと中国原産で、古い時代に日本に渡ってきたものといわれています。下駄や箪笥の材料として有名ですね。キリは日本の樹木の中で最も軽いのだそうです(小ネタ)。
| ハコベ |
路傍のハコベ。ナデシコ科の小さな花です。花弁が10個あるように見えますが、実は二つに深く裂けた花弁が5個あるというのが正解です。
| ??? |
そのハコベのすぐ近くにあったこれ。これが何だか分からないのです。花冠だけ見るとゴマノハグサ科のオオイヌノフグリに似ているのですが、ご覧のとおり白色。あと花冠の中央部の雄しべや雌しべの様子も少し違うような気がします。何だろう。
下山の道もずいぶん緩やかになってきました。
| 林道へ |
車止めが現れました。その先で林道に合流します。
ほぼ平坦な歩きやすい道。この先の「深田谷津」という谷戸
に続いています。
| 大正池 |
深田谷津に入ると少しずつ民家が現れ出しました。やがて大正池に到着。堤に石造りの顕彰碑のようなものがありましたが、彫られている内容は不明。おそらく農業灌漑用にこの池を造った人たちを顕彰したものだと思われます。あと、トイレが綺麗に整備されていて、地元の方の大正池に対する思いがなんとなく分かりました。
大正池から流れ出る天沼川沿いに歩いて行きます。下るにつれ深田谷津集落が見えてきました。
| コブシ |
谷戸を出たあたりの民家の庭先で凄いコブシに出会いました。何ですかこの花付きの良さ。こんなに花いっぱいのコブシを見たのは初めてです。
あとは集落の中の舗装路を歩き、スタート地点の八幡大神社に戻るだけです。写真は、山崎地区から見る鐘撞堂山。ここからはピークは望めないんですが、方角としてはこの向きになります。
そして15時ちょうど、八幡大神社に到着しました。リュックを降ろすと、適度の筋肉の張りと疲労感。今日は明るい日差しを浴びながらの楽しい野山歩きとなりました。
さあ、これから春本番です。