
陣馬山 〜新緑満開のハイキング(前編)〜
 |
(前編) |
【東京都 八王子市 平成31年4月20日(土)】
初夏のような陽気の一日。東京に戻ってきてから初めての野山歩きです。
場所は東京都と神奈川県の都県境に位置する陣馬山。前回登ったのは平成21年でしたから、ちょうど10年前ということになります。前回は珍しく息子が付き合ってくれましたが、その息子も独立して久しく、今回は妻と二人で登ります。(前回の様子はこちら)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前9時20分、JR高尾駅に到着。山々が萌え出すこの時期、ここから小仏峠や陣馬山に向かう登山客で駅前のバス停は長蛇の列となります。所定の発車時刻に2台、3台と複数編成で発車したり、臨時便が運行したりと、京王バスも稼ぎどきを逃しません。利用する側としては、ありがたいことです。
yamaneko達も臨時便に乗り込み陣馬山に向かいましたが、車内は激混み。平日の通勤電車と遜色ない状況でした。
| 陣馬高原下バス停 |
乗車時間30分ちょっとで終点「陣馬高原下」バス停に到着。陣馬山に高原なんてあったかなと一瞬考えましたが、昭和の頃に京王電鉄が陣馬山をリゾート開発し、山頂エリアに庭園などを整備したと聞いたことがあるので(今もそれらしい名残があります。)、その一帯を陣馬高原と称したのかもしれません。陣馬山といえば山頂に立つ白馬のモニュメントが有名ですが、これも一連のリゾート開発によって建てられたもののようです。
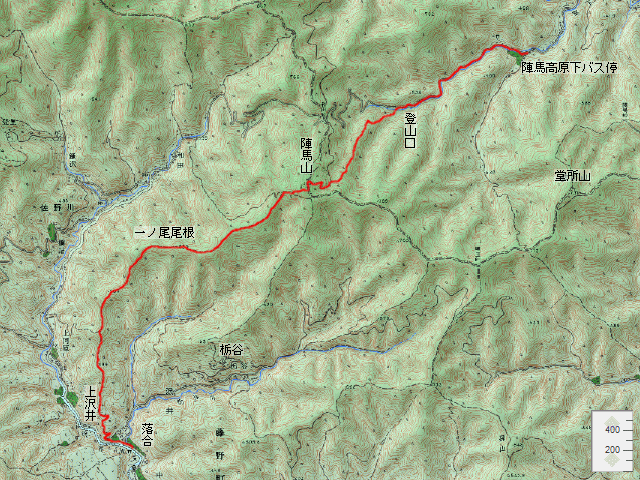 |
Kashmir 3D |
今日のルートは、ここから車道をしばらく歩き、山道に入ったら急登を一気に山頂まで登ります。下山は西の神奈川県側へ。一ノ尾尾根を歩いて落合集落まで下り、そこからバスでJR藤野駅に向かうというものです。
| ミツバアケビ |
ストレッチを終えていざ出発。と、すぐにミツバアケビの花を見かけました。濃い葡萄茶色の萼片(花弁のように見えるやつ)が3個あるのが雌花。その先にある小さなぶつぶつっとしているのが雄花達です。雌花の中心にある短い棒状のものが雌しべで、これがあの甘く美味しいアケビの実になる部分です。
小さな集落の中ほどから延びる道に入っていきます。この道は和田峠を経て神奈川県の上野原や藤野に至る道で、道幅は広くはないですが車で走れる道になっています。
| フウロケマン |
小さな渓谷沿いの道。きらめく水面をバックにフウロケマンの黄色が眩しく映ります。
| ムラサキケマン |
こちらはムラサキケマン。両方ともケシ科で、花冠の形は後ろに距が突き出た特徴的なもの。言ってみればちょんまげのような形をしています。
| コクサギ |
コクサギの葉は展開したばかりで見た目にもしっとりしているのが分かります。面白いのはこの葉の付き方。枝の元から先にかけて右、右、左、左、右、右…と変則的です。
| ツルカノコソウ |
ツルカノコソウはオミナエシの仲間。と言われれば「なるほど」と思える姿をしています。見た感じツル性ではありませんが、花期が終わるとランナー(走出枝)を伸ばしてその先に新しい苗を作るので、その様子をツルに見立てたのだそうです。
| マルバネコノメ |
マルバネコノメです。もう花の時期は終わりで、花冠の中心に茶色の実ができています。このマルバネコノメもこれからランナーを伸ばします。
| カテンソウ |
小さな小さなカテンソウの花。手前のものは雄しべが伸びた状態。というのもカテンソウの雄花は雄しべの花糸が内側に屈曲していて、それが弾けるように外側に開く際に花粉を飛ばすシステム。これだと風がなくても花粉を遠くまで飛ばせるのだそうです。写真奥の花冠が弾ける前の状態です。
満開のヤマザクラ。里ではすっかり終わってしまった桜の開花ですが、この辺りは今が盛りのようです。
| エイザンスミレ |
エイザンスミレは、細く裂けているような葉で見分けることが比較的容易なスミレです。エイザンとは比叡山のことだそうです。
木漏れ日の中を歩いていきます。ときおり車やロードバイクなどが通り過ぎていきますがそれもたまにのことで、基本、鳥の声を聞きながらの静かな野山歩きです。
| 登山口 |
スタートして40分、左側に登山道の入口が現れました。この先、小さな沢を渡って、そのあとは尾根沿いに登って行くことになります。
同じバスに乗っていたたくさんの登山者はもうみんな先を行っているのでしょう。前後には誰もいません。たまに下りてくる人とすれ違うだけです。
| シロバナエンレイソウ |
これはシロバナエンレイソウですね。大きな3つの葉の中央に花茎を伸ばし、白磁色の頭花を付けます。「シロバナ」の付かないエンレイソウの花冠は葡萄茶色をしています。エンレイソウは漢字では「延齢草」と書くので、何らかの薬効があるのかもしれません。容姿からは「艶麗草」でもいいような気も。
| フタバアオイ |
ハート型の葉が並んでいますね。これはフタバアオイでしょう。花は椀状か盃状で俯いて付くのが特徴。萼片が反り返っているのが分かりますね。花弁はありません。昔、商店街の街灯でこんなのが並んでいましたね。
| ヒトリシズカ |
杉林の中を登っていきます。だんだん息が荒くなってきますが、ヒトリシズカ達が「ゆっくり登ったら?」と声をかけてくれます。
写真を撮りながら登るので、どうしても妻が先行する形になるのですが、妻は素晴らしく目がいいので、あれこれ見つけてくれてありがたいのです。ただ、夫の素行にも目ざといです。
これは根を踏まずに歩くというのはなかなか難しいでしょう。木漏れ日の斑と相まって目が変になりそうです。
| タチツボスミレ |
陽が差すところにはこんな可愛い花が咲いていました。
| ヤブレガサ |
若いヤブレガサ。今は根生葉が1個だけですが、株が充実してくると根元から花茎を伸ばしてその先端に花穂を付けます。
| リョウブ |
透けるようなリョウブの若葉。これに出会うのが春の山を歩くときの楽しみの一つなんですよね。
尾根の反対側は広葉樹林。道はそちらに向かっています。
広葉樹林はまぶしいくらいの明るさです。別世界ですね。
| 昼食タイム |
時刻は12時。山頂まではまだちょっとありますが、ここいらで昼食にしましょう。って、ここで12時を迎えるなんて、どんだけスローペースなんだ。
| カワラハンノキ |
お腹いっぱいになって、まったり。見上げると青空をバックに新緑が鮮やかです。カワラハンノキですね(ミヤマカワラハンノキかも。)。
| ミヤマシキミ |
昼食を終え、再び歩き始めます。さっそくミヤマシキミに出会いました。これは雄花ですね。早春から咲き始める花で、もうそろそろ花期は終わりです。
| モミジイチゴ |
モミジイチゴの花は下向きに付くので、写真を撮るときにはたいが逆光になります。
| 分岐 |
午後1時、分岐が現れました。ここは右手へ。
斜面をトラバース気味に歩いて行きます。
| ナガバノスミレサイシン |
正確にはシロバナナガバノスミレサイシンか。スミレサイシンが日本海側に分布するのに対し、ナガバノスミレサイシンは太平洋側に分布し、その区分けは明確だそうです。
| ダンコウバイ |
まだ葉が出てくる前に黄色の花を付けるダンコウバイ。花柄はほとんどなく、枝から直接咲いているように見えます。
| 合流点 |
和田峠から上がってくる道との合流点が現れました。ここは左手に登っていきます。
さあ、気持ちのいい山頂まではあと少し。これまでと同様、のんびりと行きましょう。続きは後編で。