
陣馬山 〜新緑満開のハイキング(後編)〜
 |
(後編) |
【相模原市 緑区 平成31年4月20日(土)】
新緑が「満開」の陣馬山登山。後編です。(前編はこちら)
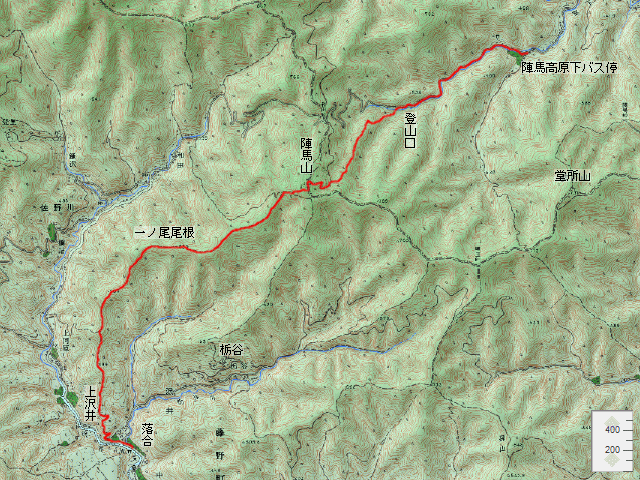 |
Kashmir 3D |
10時20分にスタートして山頂直下の分岐までやってきました。時刻は午後1時10分。普通の人ならとうに山頂に着いている頃ですが、何かを見つけるたびにこれは何だとかあれじゃないかとか頻繁に立ち止まりながらの登山なので、この時刻になってもまだ到着していません。yamanekoの野山歩きはいつもこんな調子で、だいたいコースタイムの1.5倍で見積もっています。
| ニリンソウ |
分岐の脇にニリンソウの小群落がありました。可憐な花です。若葉は山菜として食用とされますが、この葉とよく似たトリカブトの葉を誤食する事故が絶えないそうです。おお恐い。
| 園地跡 |
分岐にはこんな広場がありました。満開のツツジはおそらく植栽のものでしょう。かつてはここが整備された園地であったことが伺えます。京王電鉄のリゾート開発の名残ですね。
| マルバスミレ |
これはマルバスミレですね。
なかなかスミレの種を覚えられないのは、難しいがゆえに敬遠しているからと自分でも分かっています(反省)。図鑑じゃなかなか区別がつかないんですよね。例えば、スミレを見分ける際の最も基本的なポイントとして「地上茎」があるタイプかないタイプかというのがありますが、花柄と茎との違いが分かっていないとこの入り口から迷ってしまいます。
山頂が近いせいか、林内の見通しが良くなってきました。こんな気持ちのいいところを歩けるなんて、休日の過ごし方としては最高ですね。
| ヘビイチゴ |
ヘビイチゴ。ミツバツチグリやキジムシロに似ていて間違えやすいです。花の後には真紅の実を付けますが、見た目にも毒々しく、実際食べて美味しいものではないそうです(毒はありません。)。
13時25分、山頂部に出ました。ご覧のように公園化しています。最寄りの和田峠まで車で来れば小さな子供連れでも簡単に上がってくることができますから。
山頂はここから一段上ったところです。
| 生藤山 |
その山頂に向かう階段から眺めた北側の風景。なかなか雄大ですね。正面のピークは生藤山。東京都、神奈川県、山梨県の3都県の境に立つ山です。
| 陣馬山山頂 |
そして山頂へ。陣馬山といえばこの白馬のモニュメントですよね。これも京王電鉄の建立です。もう昼ごはんは食べてしまっているので、ここではしばらく休憩するのみです。
山頂で30分ほどまったりして、下山開始です。生藤山を正面に見ながら下っていきます。左奥の山は奥多摩の三頭山でしょう。
見事なヤマザクラ。木の精か、そうでなくても天狗くらいは棲んでいそうな大木です。
| ヤマザクラ |
満開のヤマザクラを見上げるたびに思います。今年も野山に春が来た、万物に生気が満ちる春が来たと。
| ヤマザクラ |
そして、ひとしきり眺めた後には、ちょっと寂しいですが、この季節をあと何度楽しむことができるだろうかとも考えてしまいます。もっと早くからこのヤマザクラの良さに気付けていれば良かったなあ。
| ヤマブキ |
山頂からは一ノ尾尾根を麓の落合集落まで下っていきます。下山路は基本的には明るい木立の中の尾根道になります。これはヤマブキ。そろそろ花期は終わりですね。
| 一ノ尾尾根(和田分岐) |
しばらく行くと和田分岐が現れました。ここを右手に下ると和田集落に至り、早くバスに乗りたい人はこの道に入ります。yamanekoたちは直進です。
尾根の左側はスギやヒノキの植林地、右側は落葉広葉樹を中心とした雑木林です。
| ニガイチゴ |
これはニガイチゴですね。同じ時期に咲くモミジイチゴとの相違点は、花弁が細いことと花が上を向いて付くことなどです。名前に反して実は甘く美味しいんですよね。
| ミミガタテンナンショウ |
まだ若いミミガタテンナンショウ。短期間に伸びてがっしりとした姿になります。今は観音様のような立ち姿をしていますね。逆光を受けてちょっと神々しく見えます。
| ジュウニヒトエ |
ジュウニヒトエでしょう(ツクバキンモンソウではないですよね。)。まだ背が低く、10cmほどです。これから倍近く伸びるでしょう。
| クサイチゴ |
クサイチゴ。名前には「草」とありますが立派な樹木なんです。この実も甘く美味しいです。
| 休憩ポイント |
時刻は2時55分。休憩スポットのようなところが現れたので、製作者の意図どおり休憩することにしました。ちょうど妻もふくらはぎが張ってきたと小休止希望です。
おやつなどを食べてしばらく休んだ後、再び歩き始めます。ここまで緩やかに下ってきた尾根道でしたが、この辺りから下り勾配が急になって、ときおりつづら折れも出てくるようになってきました。
午後の日差しは角度が浅く、柔らかです。木立を抜けて入ってくるとより穏やかに感じます。
| チゴユリ |
チゴユリ。午前中登ってきた北斜面側にも何株か見かけましたが、いずれもまだ開花していませんでした。日当たりが関係しているのでしょうか。チゴユリの花は控えめに俯いて咲くのが特徴です。
| ニホンカナヘビ |
伐採された丸太の上で日向ぼっこをしていたニホンカナヘビ。ヘビと名が付いていますがトカゲです。体温が上がっていないのか動きは鈍く、1mくらいまで近づいても逃げませんでした。子供の頃、よく意味もなくトカゲを捕まえました。トカゲを腕の上に乗せるとひんやり冷たいんですよね。トカゲにとってはいい迷惑ですが。
| シュンラン |
シュンランですね。花被片が緑色なので林床では見落としがちなのですが、むしろ細く放射状に株立つ葉の様子が目立つので、目が慣れてくると見つけられるようになります。
| カンアオイ |
カンアオイかな。株元に開花状態の花を見つけました。
| ダンコウバイ |
ダンコウバイの幼木。去年芽吹いたものでしょうか。先割れスプーンのような特徴的な形の葉が可愛いです。
| ヤマツツジ |
ヤマツツジの花は淡い朱色。ミツバツツジなど紫色のツツジをよく見かける中で、山中でこの花に出会うとちょっと新鮮な感じがします。
| オトコヨウゾメ |
これはオトコヨウゾメですね。ガマズミの仲間ですが、花序の花の密度が小さくまばらな感じがします。それにしてもオトコヨウゾメとはちょっと変わった名前ですね。ただ、由来は定かではないようです。
かなり下ったところで上沢井集落が現れました。時刻は3時50分です。
陣馬山の山頂方向に振り返るとこんな里山風景が。左に見えているピークはここまで下ってきた一ノ尾尾根の一つ南側の尾根です。驚くのはその中腹にある栃谷集落(マウスオーバーで表示)。ずいぶん高いところにあるのがわかります。今でも生活している人がおられるようです。前回(10年前)陣馬山に登った時にはあの集落を通るルートで下山しました。
| ホタルカズラ |
静かな集落の中を下っていきます。これはホタルカズラ。青い色が目を引きました。この花は、さっき山頂から見えていた生藤山でよく見られる花とのことです。
| 上沢井集落 |
春の午後。長閑な時間が流れまています。子供の頃を過ごした町はここまで田舎(失礼)ではありませんでしたが、なんとなく懐かしい心和む風景です。
自然観察会などで話を聞くと、子供の頃自分が野山で体験した遊びや発見などを必ずしも同年代の人が同様に体験しているものではないということに軽く驚くことがあります(同年代どころか明らかに年配の方でも。)。高度成長期に少年時代を過ごした我々ですが、その時代を片田舎で過ごしたか都市部で過ごしたかで、自然との関わりの濃淡が違ってくるということでしょうね。逆に今の子供達では情報や物資の地域間格差がほとんどないので、子供の頃の経験も大差ないのかもしれません。
急なつづら折れを下ると車道が見えてきました。和田峠から下ってくる県道522号線です。やれやれ、無事に下りてくることができました。長い下りだったので足首とつま先が若干痛くなりましたが。
| 陣馬登山口バス停 |
車道に合流して歩くこと約100m。終点の陣馬登山口バス停に到着しました。時刻は4時5分。時刻表を見ると、この日は4時台に臨時便が出るようで、待ち時間は20分ほど。登山客を見越してのことでしょうが、ありがたい限りです。通常は2時間ちかく間隔が開く時間帯でした。
バスに乗車後は5分ほどでJR藤野駅に到着。ここから中央本線に乗り、八王子経由で帰途につきました。