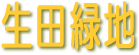
生田緑地 〜多摩丘陵の秋・11月〜
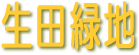 |
【川崎市 多摩区 平成20年11月30日(日)】
生田緑地の観察も11回目。季節は巡り晩秋となりました。今日は朝から素晴らしい青空。小春日和の一日になりそうです。
| 小田急線 |
今日はいつもよりちょっと早く家を出て、久しぶりに電車で向かいました。新宿から小田急線の急行で、代々木上原、下北沢、経堂、成城学園前、登戸、そして向ヶ丘遊園駅まで、約20分のぶらり旅です。
駅からはしばらく線路に沿って歩いていきます。上り下りの電車がひっきりなしに通り過ぎ、踏切の警報音が途切れる間もないほどです。
| 北入口 |
午前10時30分、住宅街の路地を抜け、生田緑地の北入口に到着しました。日陰はシンと冷えていますが、ほどなく朝日に照らされて暖かくなると思います。
| コブシ |
毎回観察しているコブシ。先月とは一変して、葉が全部落ちてしまっていました。果実にも種子がまったく残っていません。でも、枝先には来年の小さな葉芽が。ちゃんと準備しているんですね。
| アシ |
午前中の日射しを受けて眩しく輝くアシの穂。風もなく静かな空間です。
| 定点写真 |
いつもの定点写真の場所。「秋深し」といった感じですね。おそらく来月にはここの木々たちも葉が落ちてスケルトンになっているでしょう。
| 稲ハデ |
刈り取られた田んぼの隅に稲ハデがまだ残されていました。yamanekoの田舎でいうところの「なだら」です。
| 残り柿 |
鳥たちの冬の食糧。田舎では民家の庭先や畑の脇に柿の木があって、晩秋になってもすべて採り尽くすことなく鳥たちのためにあえて残していたものです。あと、枝に1個だけ残っている柿を「留守番柿」といって、こちらは来年もたくさん実りますようにというおまじないとして、採らないように教えられました。
| 谷地の中程 |
谷地の中程にある平坦な場所。2ヶ月前にツリフネソウの大群落があった場所です。谷地の斜面から浸みだし小さな流れとなった水が平坦地に出て湿った原っぱを形作った、そんな地形のところです。
| スプレー画 |
エゴノキの幹にカラフルな模様が。スプレーを吹きかけたような。おそらく藻類か地衣類(藻類と菌類の共生体)だと思いますが、何なのか特定できず。よく見かけるのですが…。ちなみに、地衣類は空気のきれいな場所で付きやすいのだとか。
| ハンノキの林 |
また少し谷地をさかのぼりました。ハンノキの林にも光が差し込んでいます。
| 水面(みなも)の紅葉 |
小さな池までやってきました。ここは春先にはたくさんのオタマジャクシが泳いでいたところ。初夏にはカエルになり、またそれを狙ってシマヘビなども現れたところです。でも今は生き物の影もなく水面も鏡のように静まりかえっています。そこに紅葉と青空が写り込んでいました。
|
||||
| ウド |
谷地の斜面を稜線に向かって登っていきます。そこにちょっと面白いものが。線香花火のようにも見えますが、これはウドの果柄。先端に付いていた果実が落ちてしまった後の姿です。
| 葉 | 茎 |
ウドの葉は2回羽状複葉。茎をはじめとして全体に毛が多いのも特徴です。ウドの若芽は山菜として有名。他にも蕾や若葉、茎も食用になるそうです。でも大きく育った後のものは食用には適さず、かといって木材としても使えないため、ここから「ウドの大木」という言葉ができたということです。
| エノキの落ち葉 |
観察路を覆い隠すエノキの落ち葉。朝露にしっとりと濡れて、歩いてもカサカサ音はしません。
| メグスリノキ |
この上品な紅葉はメグスリノキ。なんともいえない趣のある色合いですね。この木の葉は、単葉で掌状に裂けるカエデの仲間にはめずらしく、3出複葉です。でも対生であることがカエデっぽいところ。名前は、葉や樹皮を煎じたもので目を洗ったことから。通りかかった人から何の木か聞かれたのでそんな話をすると、しきりと感心していました。
| ヒュウガミズキ |
いったん稜線の道に出て、今度は東西の谷地を分けている支尾根を下っていきます。
日当たりの良い場所にヒュウガミズキが。今年の葉をまだ残していますが、一方で冬芽も準備できているようです。来年の春、レモンイエローの小さな花をたくさん付けてくれるでしょう。
| サクラとモミジの広場 |
支尾根をずんずん下りていくと、サクラとモミジの広場に出ます。先月まではまだ青々と葉が茂っていたのに、一月で紅葉も盛りを過ぎたようです。
しばらく紅葉に見とれてまったりしました。さて、今度は東の谷地に下りていきましょう。
| あの倒木は… |
先月観察路に倒れ込んでいたコナラがどうなったのか気になっていましたが、どうやら撤去されることなく、1mくらいの長さに分割されて、観察路脇の空き地に放置してありました。(手すりも修理されていました。) このまま自然に朽ちさせるのでしょう。完全に土に戻るのに10年くらいはかかるかもしれませんが、その間格好の観察材料となっていくれますね。
| 日本人の心 |
倒木の近くにあったイロハモミジ。葉裏から透かしてみる紅葉と漆黒の幹とのコントラストが艶やかで錦絵のようです。遠く万葉集の時代から日本人が愛してやまない風景ですね。(ちなみに万葉集にこのような紅葉を詠った歌は80首ほどあるそうですが、そのほとんどは「黄葉」と書き表されているそうです。)
| 階段を埋める黄葉 | 戸隠不動のイチョウ |
戸隠不動跡までやって来ました。こちらはその黄葉の代表格、イチョウです。ただし、イチョウの日本への伝来は平安時代後期から鎌倉時代と考えられているので、万葉集に詠われた「黄葉」はイチョウのことではないようです。
このイチョウ、右の写真でも分かるとおり、ちょうどこちら向きの面の樹皮が深く傷つき、それを癒そうと左右から樹皮が傷口を巻き込むように成長してきています。これは、今から15年ほど前に戸隠不動が焼失した際に、建物に面していたところが炎に炙られ瀕死の状態になったのだとか。その後力強く復活し、今もわが身を修復しようとしているのです。
| 東屋 |
こちらは正真正銘の「紅葉」。参道脇にある東屋を取り囲むように植栽されたものです。
さて、今日は小春日和の中、十分に紅葉を堪能することができました。いよいよ次回でこの生田緑地定点観察も最後。この艶やかな木々の姿も来月にはきっと寒々とした姿に変わっているでしょうね。