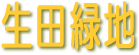
生田緑地 〜多摩丘陵の秋・10月〜
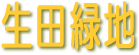 |
【川崎市 多摩区 平成20年10月25日(土)】
10月もそろそろ終わり。山の方だけでなく里にも秋の風景が広がっています。今日はもともと曇りがちな天気であることに加え、歩き始めが午後3時と遅かったこともあって、寂しげに暮れていく里の秋、といった雰囲気を味わってきました。
| 西口駐車場から |
西口駐車場から観察路入口までの尾根道は桜の落ち葉で飾られていました。昨日までの雨で道もしっとりとしています。
| 観察路入口 |
静かな谷地に下りていきます。観察路の入口も落ち葉の絨毯。木製の階段が滑りやすいので注意が必要です。
| ヌルデ |
いい色になりつつあるヌルデ。秋が深まれば真っ赤になります。ヌルデはウルシの仲間ですが、よっぽど敏感な人でなければかぶれることはありません。yamanekoは10数年前、もっとも強いといわれるツタウルシに直接触れてどえらい目に遭って以来、免疫(?)ができたのか、その後ウルシの類にかぶれたことはまったくありません。
| 静かな森 |
今日の谷地はしっとりと落ち着いた雰囲気。風もなく、まるで昨日までの雨で音までも一緒に地面に染み込んでしまったようです。
| ヤブムラサキ |
薄暗い林床に鈍く光るのはヤブムラサキの果実です。サワフタギの果実とともに、この時期の野山で出会うことのできる綺麗な宝石のうちの一つです。
| ハンノキの林へ |
ここまで谷の斜面の中腹をほぼ水平に歩いてきましたが、ここから先は谷地の底へ。この辺りはハンノキの林になっています。
| シロヨメナ |
辺りが薄暗いので舌状花が白く飛んでしまいました。
| 総苞 | 葉 |
シロヨメナの総苞は細長い筒状。葉の鋸歯はやや鋭いです。
| ホトトギス |
先月、ツリフネソウの大群落があった場所にホトトギスが。賑やかな祭りの後の余韻のようにそっと咲いていました。
| カラスウリ |
秋ですね。カラスウリも朱く熟れています。梢の上からモズの鳴き声が聞こえてきそうな写真です。
この果実、見た目は美味そうなんですけどね。
| 実生のケヤキ |
観察路脇の斜面に実生のケヤキが。去年ここに落ちた種子からこの春に芽吹き、なんとかここまで成長したのだと思います。道の脇の斜面ということもあってたまたま日光を取り合う競争相手がいなかったことが幸いしたのでしょう。ただ、これから一本の樹木として成長するためには幾多の試練が待ち受けているでしょうね。
| サクラとモミジの広場 |
ここは春にはサクラ、秋にはモミジで彩られる広場です。モミジはまだ青々としていますね。
| 東の谷地 |
東の谷地に下りてきました。こっちもシーンとしています。
| 倒木が |
東の谷地から戸隠不動跡へ向かう坂道にコナラの倒木が立ちはだかっていました。右手の斜面の上に生えていたコナラが根元からえぐれ倒れ込んでいたのです。観察路の手すりを一刀両断です。近寄ってみると幹にキノコがびっしりと。枯れてしまってからもかなりの期間立っていたのだと思います。立派な大往生です。折れた手すりの断面がまだ新しいことからすると、昨日の雨で地盤が緩んだのかもしれません。ここは往来の邪魔になるのでとりあえず脇に寄せるとして、あえてこの地に放置して、自然に土に戻るよう、その命を全うさせてあげてほしいものです。(その様子を何年にもわたって観察するというのもおもしろいですよね。)
| 戸隠不動参道 |
戸隠不動の参道を入口方面に下ります。いつもながら人気(ひとけ)のない参道です。まあ、本堂をはじめ建造物はすべて焼失してしまっているので、訪れる人がいないのも無理からぬところです。
| バッドランド |
カナダのアルバータ州に恐竜の化石がゴロゴロしているバッドランドという荒野があるそうですが、寄って撮るとそのバッドランドのジオラマのような様相を呈するこの土の盛り上がり。これは何かというと、モグラ塚が雨で浸食されたものです。軟らかい地層の上に硬い岩が乗っているとこういう浸食の仕方をするという模型のようです。
| コブシ |
コブシの集合果です。この1ヶ月の間にすっかり果実が落ちてしまいました。かろうじていくつか残っています。モクレン科には集合果を作るものが他にもあり、例えば渓畔林の代表種であるホオノキもその一つです。
| アシ原の秋 |
夏には両側が壁にようになるほど勢いよく立ち繁っていたアシですが、今では枯れたり倒れたりしています。「侘び寂」の世界を彷彿とさせますね。
| ツリフネソウ(果実) |
先月、大群落を作っていたツリフネソウですが、今ではぱらぱらと残り花があるものの、多くは果実になっていました。このツリフネソウの果実、これがなかなか面白いのです。左の写真は果実が十分に成熟した状態。これにちょっと指で触れるなど刺激を与えてみると、まるではじけるように中の種子をまき散らし、一瞬で縮んだバネのようになってしまいます。これは莢が裂け強く収縮する力を利用して種子を遠くまで散布しようとするツリフネソウの技です。知らずに触ると思わず声が出るほどビックリしますよ。
| 定点写真 |
二つの谷地の合流地点。いつもの定点写真の場所です。少し寒々としてきましたが、それでもまだ緑に覆われていますね。時刻はもう4時を回っていて、もうじき日没です。(写真は明るいですが、これはカメラが自動的に補正したからです。)
| 稲刈り後 |
すっかり稲が刈り取られた田んぼ。切り株から新しい葉が伸びているので、稲刈りは半月くらい前でしょうか。
子供の頃、稲刈りが終わった後の田んぼでよく遊んでいました。稲刈り直後は田んぼに稲ハデ(稲を掛けて干す竹組みの構造物。上の写真の奥に写っている。yamanekoの故郷では「なだら」と呼ばれていました。)が組まれていて、稲がギッシリと掛けてありました。これをバレーボールのネット代わりにして遊ぶのです。稲ハデは普通2段掛けでしたが、山間部に行くと土地が狭いからか5段にも6段にも高く組み上げてありました。これの全面に稲を掛けるので、巨大な壁のようなものが出現することになるのです。
また、何日かして稲が乾燥し収穫され、稲ハデも撤去されると、今度は脱穀した後の籾殻を田んぼの中に小山のように積んで、これに火をかけ焼くのです。この中に濡らした新聞紙にサツマイモを包んで入れておくと、おいしい焼き芋が出来上がるのです。一方、焼かれて灰になった籾殻は、翌春の荒起こし(あらおこし。代かき(しろかき)の前に田んぼの土を全部掘り起こし、土の中に空気を入れる作業。)の際に鋤き込まれ、栄養豊かな土作りに役立つという寸法です。田んぼ一つでこんなにも思い出が。懐かしいなあ。
| セイタカアワダチソウ |
これも秋の代表選手ですよね。なにかと誤解を受け敬遠されがちのセイタカアワダチソウですが、ルーペでその小さな花を見てみてください。ちょっと見直すくらい可憐な姿をしていますから。
| カキノキ |
カキノキは民家の庭先や畑の脇などによく植えられていました。よく登って採っていましたが、この木の枝は折れやすく危ないので、枝先にある実を採るときには枝下から長い竹竿を使って採るのです。竹竿の先端は鉈で二つに割られていて、その割れ目に小枝をはさんでV字型になっていて、そこに実の付いた枝を挟めて捻り切るのです。通販の高枝切り鋏がなかった頃の話です。
秋の野山はなぜか子供の頃を思い出させます。それも遙か遠くのこと。思えば遠くまで来たものです(時間的にも距離的にも、そしてあの頃の少年の心も。)。
さあ、そろそろ日暮れです。駐車場へ急ぎましょう。