
八方山 ~北アルプスの花々(八方・中編)~
 |
(中編) |
【長野県 白馬村 平成24年7月28日(土)】
八方池までの行程の半分くらいまでやってきました(「前編」はこちら。)。ここまでのところ、花は期待以上でしたが、景色の方は…。ガイドブックによるとこの辺りから絶景の北アルプスが望めるはずなんですが。天気相手のことですからしょうがないか。
| ハクサンチドリ |
風景は神様の気まぐれに任せるとして、足下にはこんなきれいな花もあるわけですから、身近にある素晴らしいものに目を向けましょう。
これはハクサンチドリ。ランの仲間です。高さは30㎝弱。園芸種にも負けないあでやかさです。初めて出会ったのは大菩薩嶺だったかな。
| トイレの小屋 |
12時20分、トイレの小屋のあるやや平坦な場所に出ました。標高はちょうど2000mです。
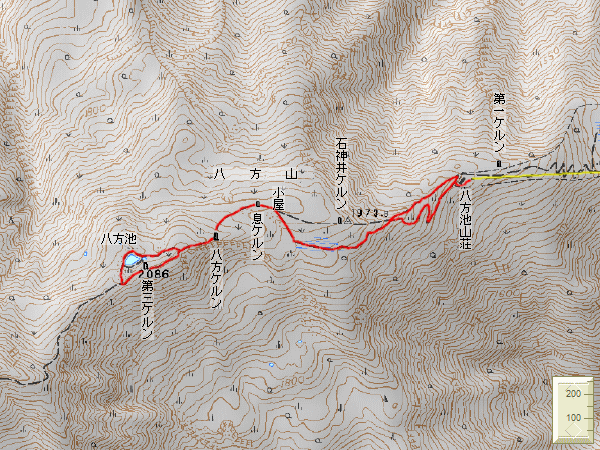 Kashmir 3D |
八方山の山頂はこの辺りになります。地図によると三角点はこの平坦面の東端にあるようで、ここよりも20mちょっと低いです。麓の方から見上げると平坦面の先端があたかもピークに見えるということなんでしょうか。
| 息ケルン |
小屋の前では数人のグループが休憩していました。その向こうには石の塔が。あれは「息(やすむ)ケルン」というそうです。ケルンには道標や墓標の意味があり、この息ケルンはこの地で遭難した我が子を偲んでその親御さんが建てたものだそうです。戦前の話です。
| イワシモツケ |
シモツケが薄ピンク色なのに対してイワシモツケは白い花を付けます。よく似たマルバシモツケとは葉に鋸歯があるかないかで見分けるのだそうです。八方尾根では至る所で咲いていましたが、やや盛りは過ぎた感じか。名前の頭に「イワ(岩)」が付くと、付かないものに比べて標高の高いところに咲くものが多いようです。岩場=高所ということでしょう。
| イワイチョウ |
こちらも「イワ」が付くイワイチョウですが、もちろんイチョウとは無関係。イチョウの高所バージョンではありません。名前は葉の形がイチョウのそれに似ているからとのとこ。でもどう見ても全然似ていません。イチョウの葉は三味線のバチのような形ですが、イワイチョウの葉は腎臓のような形をしているのです。
| ムシトリスミレ |
この花、ぱっと見、スミレですよね。花弁が若干厚ぼったい感じはしますが、姿形はまさにスミレです。ところが、なんとこれがタヌキモ科の食虫植物で、スミレの仲間ではないとのこと。なんで? スミレでないことは良いとして、なんでここまでスミレに似せる必要があったのか。つくづく造形の神は楽しんでいるとしか思えません。
蛇紋岩にはマグネシウムが多量に含まれ、これには植物の吸水作用を妨げる働きがあるのだとか。なので、蛇紋岩質の場所ではこれに耐え得る特殊な植物が優勢に分布するのだそうです。ムシトリスミレも蛇紋岩質のところでも苦にせずに生える特性を持っているそうです。
左の写真は花冠を正面から見たところ。なんか剛毛が生えていますね。よく見ると花弁が合着していて、ここはスミレと違うところ。上手く化けたつもりが細かいところで化けきれなかったということか。右の写真は根生葉です。この肉厚な葉の表面から粘液を出していて、ここに虫が触れると葉を閉じて巻き込み絡め捕られてしまうことに。既に犠牲者がたくさんいました。
| 蛇紋岩 |
これが蛇紋岩です。表面が摩耗すると青黒く光って滑りやすく、山岳事故の原因になったりもするので、要注意です。
中学校の理科で岩石の分類を習ったときには蛇紋岩はあまりクローズアップされなかったような気がします。火成岩といえば玄武岩や花崗岩、堆積岩といえば砂岩や凝灰岩というように代表的に示される岩石ではありませんでした。それからン十年の時を経て、こうやって植物を見て歩くようになってようやく意識するようになった蛇紋岩。植物好きには気になる岩石なのです。そういう意味では石灰岩なども特殊な植生を育む岩石として気になります。
| 八方ケルン |
足場の悪い登山道を一歩一歩上っていきます(妻は元気のようです。)。背後に見えるとぼけたモアイ像のようなものは八方ケルン。息ケルンの2倍ほどの大きさで、目鼻のように見えるのは「八方ケルン」とか書いてあるプレートです。ケルンの遙か後方にトイレの小屋が見えていますね。そこから稜線の向こう側に向かって登山道が延びています。そこをトコトコと歩いてきたのです。
| ハッポウウスユキソウ |
こんな岩陰にもハッポウウスユキソウが。いい感じですね。
| オヤマソバ |
オヤマソバはタデ科の高山植物。ソバといっても麺にする蕎麦とは違います、と書こうと思ったら、その蕎麦もタデ科でした。知らなかった。これまで蕎麦が何科かなんて考えたこともありませんでしたが、そういえば蕎麦の花は確かにタデ科の特徴を備えています。ほほぅ。今更ながら知の喜びを感じました。
| タカネナデシコ |
カワラナデシコが平地に生えるナデシコでタカネナデシコは高山に生えるナデシコ。分かりやすいです。この花はまず雄しべが成熟し、その雄しべが朽ちた後に雌しべが成熟するという、自家受粉を避けるシステムを採用しています。写真のものは、ちょっと分かりにくいですが、雌しべが成熟している時期です。
| ホソバツメクサ |
なんとこのホソバツメクサもナデシコ科。タカネナデシコとはずいぶん見た目が違いますね。尾瀬の至仏山で出会った以来の対面です。
| シモツケソウ |
シモツケとシモツケソウは名前は似ていますが違うもの。大きな相違点としてはシモツケが木本であるのに対し、シモツケソウは草本です。名前に「ソウ(草)」が入っていますしね。花もシモツケソウの方が華奢な感じがします。
広いガレ場に出ました。目的地の八方池が見えます。道はここで二手に分かれ、右に行くと山肌を下って八方池に向かいます。一方、そのまま尾根の道を行くと唐松岳に至るのですが、yamanekoは尾根道を100mほど行き、八方池の真上から斜面を下って池の畔に出る道を辿ります。要は時計回りに八方池を巡ろうということです。
| ミヤマムラサキ |
では尾根道の花を。
ミヤマムラサキ。高山の砂礫地に生える可愛い花です。藤間紫となんか語感が似ています。
| タカネバラ |
これはタカネバラです。ちょっとくたびれ気味か。登山道を外れていたので近づけませんでした。ちなみに「高値」ではなく「高嶺」のバラです。
雲がなければ八方池越しに北アルプスの主稜線が一望にできたでしょう。今日はかろうじて天狗沢の雪渓が時折見える程度。それもまた次の瞬間には流れる雲が覆い隠してしまいます。
| 第三ケルン |
八方池を見下ろす尾根道に第三ケルンが建っています(妻はますます元気です。)。ケルンが多いということは事故も多いということなんでしょうね。
| タカネマツムシソウ |
高山植物には「タカネ」とか「イワ」とか「ミヤマ」とかが付くものが多いですね。長い年月をかけて高山の気候風土に適応するよう変化した結果、元の種に対して独立した名前を持てるほどの特徴を備えるようになったのでしょう。このタカネマツムシソウは元の種より背が低いのですが、これは風が強い尾根で生きてきた証ですね。
| カライトソウ |
カライトソウ。これがバラの仲間だっていうんですから、植物の世界も奥が深いですな。長い毛のようなものは雄しべの花糸。小さな花がたくさん寄り集まっているのです。それぞれの花に花弁はなく、雄しべの根元に白い萼片が4つあるのみです。
| タカネイブキボウフウ |
セリ科の植物は見分けが難しいです。これはタカネイブキボウフウだそうです。
| 八方池 |
午後1時、八方池の真上までやって来ました。水面が鏡のようです。ここに逆さアルプスが映っていたら…。もういいか。
これから写真の左側に回って湖畔に下り、そこから正面の小高い丘に上がって右手に下りて行きます。池の畔にはどんな花が咲いているでしょうか。(続きは後編で。)