
八方山 〜北アルプスの花々(八方・後編)〜
 |
(後編) |
【長野県 白馬村 平成24年7月28日(土)】
八方山、花の山歩き。後編です(「中編」はこちら。)
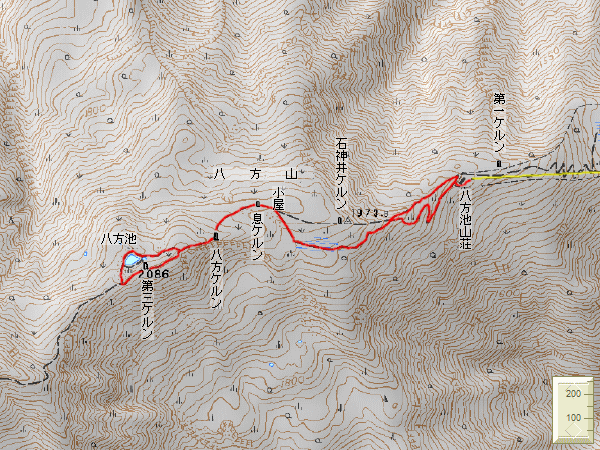 Kashmir 3D |
これから尾根道を離れ、急な斜面を下りて八方池の周りを巡ります。
| チシマギキョウ |
岩場で風に揺れるチシマギキョウ。同じ高山植物でよく似たイワギキョウという花がありますが、花冠の縁に細い毛が生えているのがチシマギキョウです。まるで和紙を破いたような感じです。
| ミヤマアズマギク |
これは濃い色合いのミヤマアズマギクです。チシマギキョウの青紫、ミヤマアズマギクの赤紫。それぞれ自然が作り出した色とは思えない、いや自然だから作り出せる鮮やかな色をしています。
| イワイチョウ |
イワイチョウも元気です。いつも書いていますが、yamanekoの大好きな花です。
| ハクサンシャジン |
ツリガネニンジンの高山適応型とされるハクサンジャジン。もう秋の気配か。
| テガタチドリ |
テガタチドリはランの仲間。根が手のひらのような形をしているから「手形」チドリというのだそうです。
池の畔に下りてくるまでにざっとこれだけの花たちに会いました。
| 天狗沢 |
池の畔で休憩していると、一瞬だけ明るい日射しが。わずか2、3分でしたが、北アルプスの峰々を望むことができました。これぞ「夏山」です。(その後、下山までの間に再び日が射すことはありませんでした。)
| クガイソウ |
つかのまの陽光を身に受けるクガイソウ。漢字で書くと「九蓋草」。「蓋」は天蓋(高僧などに後からさしかける傘状の覆いのこと。)を意味し、その天蓋のように輪生する葉が何層にも重なっている様子を例えた名前です。
| クモマミミナグサ |
ミミナグサの高山適応型にはミヤマミミナグサもタカネミミナグサもありますが、さらにクモマミミナグサというのもあります。「深山」に「高嶺」に「雲間」。これでもかといったネーミングです。雲間は「雲が湧き出るような高い場所」ということでしょう。これより高いところのものがあったらあとはテンジョウ(天上)ミミナグサしかありませんね。
| ミヤマウイキョウ |
ミヤマウイキョウは細かく切れ込んだ葉が特徴。至仏山以来のご対面になりました。
| 八方池 |
1時35分、丘の上に到着。八方尾根の南側は雲の中です。この池、ほとんど尾根に近いところにありますが、雪解け水と雨水だけで涵養されているということでしょうか。
| ハクサンシャジン |
ハクサンシャジンの花冠。萼が針のように細くなっています。
| ミヤマアキノキリンソウ |
これはミヤマアキノキリンソウ。もう何にでも「ミヤマ」を付けることに違和感を感じなくなってきました。別名をコガネギクといい、なんかこちらの方が新鮮に感じます。低地に生えるアキノキリンソウより頭花が大きく、全体にがっしりした印象を受けます。
| ミヤマカラマツ |
ミヤマカラマツの花には花弁はありません。白く細長いのは雄しべの花糸。先端部は葯です。ぷっくりとしていて何か美味しそう。左の写真に写っているギザギザの葉は別の植物のものです。
| ウラジロヨウラク |
ツツジの仲間のウラジロヨウラク。一般的にイメージするツツジとはかけ離れた姿をしていますが、ツツジ科にはこのような鐘型の花を付けるグループがあるのです。ヨウラクとは「瓔珞」と書き、玉や貴金属を編んで首などにかける装身具のこと。きっとこの花冠の形が飾りに似ているということでしょう。ウラジロは葉の裏が白っぽいからです。
| ミヤマタンポポ |
うーん、野山のタンポポとの違いが分からない。強いていえばでかいということか。この厳しい環境では、綿毛を飛ばしても発芽するものはわずかでしょうね。
八方池をぐるっと回って元の尾根道に戻ってきました。これから下山です。蛇紋岩地帯での事故は下りに多いとのことですから、一層注意が必要です。
| タカネアオヤギソウ |
帰り道でも花は見逃しません。
これはタカネアオヤギソウか。これと形がそっくりなものにタカネシュロソウというものがあります。生息地も一緒で、違うのは花の色だけ。花が緑色なのがタカネアオヤギソウ。紫褐色なのがタカネシュロソウです。写真のものは花の縁がすこし褐色になっていますが、中間型か。
| ミヤマコゴメグサ |
ミヤマコゴメグサもあちこちに咲いています。次はどこで出会えるのかな。
| ミヤマママコナ |
これはミヤマママコナ。ママコとはご飯粒のこと。花冠にご飯粒のような突起がありますね。写真では分かりにくいですが、あの白い突起の奥の両側に黄色い斑紋があるのがミヤマママコナの特徴。低山に生えるママコナにはこの黄色の斑紋がありません。
| ヤマブキショウマ |
シモツケソウやカライトソウがバラ科だということにも驚きましたが、このヤマブキショウマもバラ科。なんだかバラの概念が崩れてきそうです。ウメもサクラもバラ科だし、そう考えると私たちが思い浮かべるバラは、バラ科の中でも決して多数派ではないということですね。
| 八方池山荘 |
そうこうしているうちに八方池山荘が見えるところまで下りてきました。リフト乗り場も見えます。ちょうどあの山際辺りが男子滑降のスタート地点ですね。
| オニアザミ |
オニアザミの頭花はずっしりと重たそうです。この重厚感が「オニ」と付く所以か。
| エゾシオガマ |
何がどうなっているんだか花冠の形がよく分からないエゾシオガマ。でも上から見たらスクリュー状に付いているのが分かります。
| タカネマツムシソウ |
終点が近づいてきました。タカネマツムシソウともお別れです。
2時50分、無事にリフト乗り場まで下りてきました。滑らないようにと気が張っていたので、とりあえずソフトクリームでも食べて休みましょう。
一休みしたらリフトを乗り継いで下界に下りて行きます。リフトは下るときの爽快感がいいですよね。
いやー、八方山は期待を裏切らない花の山でした。次から次に現れるので忙しいくらい。ホント楽しい一日を過ごさせてもらいました。今日はこの後、隣の小谷村に移動して一泊。そして明日は栂池高原で再び花三昧の予定です。明日こそはスカッと晴れてくれよー!