
御殿山 ~温暖な照葉樹林を歩く(前編)~
 |
(前編) |
【千葉県南房総市 令和7年2月24日(月)】
列島に強い寒気が居座り続けています。例年であれば木々の枝では冬芽が膨らみ始め、早咲きのカワヅザクラはもうあちこちで開花している時期なのですが、今年はまだまだです。いつものフィールドを歩いていても、冬芽たちはただじっと耐えている感じですね。もう3月の声を聞こうかというのに。
そんな寒い時節に野山歩きに向かうのはやはり温暖な地域。関東地方でいえば房総半島でしょう。今回はそのうちでも特に暖かい南房総の里山を歩いてみることにしました。目的地は嶺岡山系にある御殿山(364m)です。ガイドブックによるとのんびり歩くのにはぴったりの山のよう。更に、妻の希望で下山後には花摘みに行くことにしています。のんびり三昧ですね。ちなみに、花摘みはこの時期の南房総の人気のレジャーです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前7時過ぎ、ドリーム号Ⅲで出発。保土ヶ谷バイパスから首都高神奈川3号狩場線、湾岸線と走り進み、川崎浮島JCTで東京湾を横断するアクアラインへ入りました。
| 海ほたるPA |
アクアラインの延長は約15kmあり、川崎側からの3分の2ほどを海底トンネルで、残りの木更津側の3分の1を海上橋梁で走り抜けることになります。その両者の分岐点、つまりトンネルから海上に出た地点に人工島の海ほたるPAがあります。時刻はまだ午前9時でしたが、立ち寄ってみることにしました。写真は4階(1階から3階は主に駐車場、4階、5階は商業施設)のデッキから木更津方向を眺めたところ。手前にトンネル出口があり、そこから一直線に高速道路が延びています。海ほたるにはこの時間からたくさんの人が訪れていましたが、展望デッキは吹きっさらしの寒風でみんな肩をすぼめていました。
| 駐車場 |
海ほたるで早くもお土産をゲットし、一路房総半島へ。千葉県上陸後は館山自動車道をひたすら南下し、鋸南富山ICで一般道へ降りました。
10時30分、今回の野山歩きの起点となる駐車場に到着しました。広いスペースにきれいなトイレまであって、御殿山登山をする人にとってはありがたい施設です。駐車場のすぐ上に高照寺というお寺があって、元々はそちらのための駐車場なのかもしれません。
| 枝垂桜 |
駐車場の脇にあった枝垂桜。もう蕾がほころびかけています。さすがは温暖な南房総です。
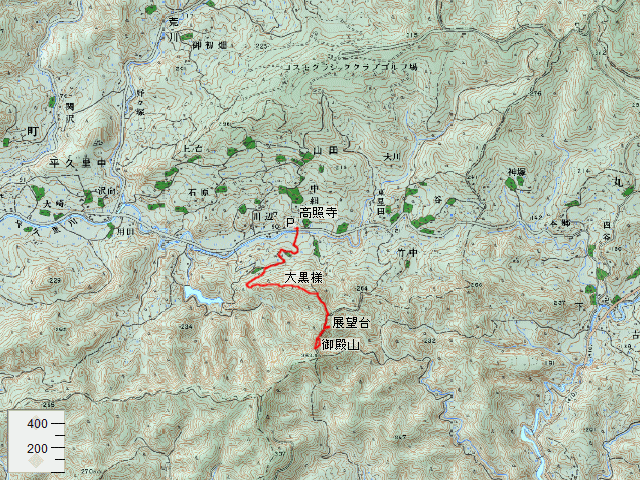 |
Kashmir3D |
今日のルートは、駐車場から目の前の平久里川を渡って、農地の中の道を山に向かってまっすぐに歩きます。まずは正面の峰林山に登り、この里を見下ろす「大黒様」へ。そこから稜線沿いに奥に向かいます。何回かアップダウンを繰り返すと御殿山に到着。復路は来た道を戻ります。
| 峰林山 |
駐車場から望む峰林山。まずはこの山に向かって歩いていきます。山頂の木立が切れているところに大黒様がある模様。御殿山はこの山の奥の方に位置しています。
| 登山口 |
「御殿山→」の標識がありました。ずいぶん立派です。人気の山なんですかね。ここで平久里川を渡って行きます。
峰林山に向かって真っすぐに伸びる道。ここが登山ルートですが、奥に民家もあるので生活道路です。この時間、既に下山してきている人もいました。
山の麓まで行って振り返るの図。向こうの山の麓に駐車場があり、そこから歩いてきました。
さあこの辺りから上り坂になります。急がず一歩一歩登っていきましょう。
| テイカカズラ |
テイカカズラの蔓が垂れ下がっていました。テイカカズラの葉はおもしろく、木々の上の方まで達している枝に付く葉は3cmから7cmと大きく、全縁で、革質で光沢がありますが、林床を這う蔓の葉は2cm程度で、浅い鋸歯があり、葉の表面の脈に沿って斑が入っています。なので両者はまったく別の植物の葉に見えるのです。
| 白梅 |
日陰にあるウメにも花が付いていました。今日はまだ花らしい花には会えないでしょうから、このウメをじっくり楽しみました。
休耕田に置かれていたイノシシ用の罠。ゲージの中の餌が新しかったので現役で使われているものだと思います。この辺りの農家さんは獣害に頭を悩ませているんでしょうね。
| キヅタ |
キヅタに実ができていました。今はまだ色が薄いですが、熟すのは5月から6月で、そのころには紫黒色になります。さっき見たテイカカズラもツル性の常緑樹でしたが、このキヅタも同じです。そういえば寒い地方でツル性の植物はあまり見かけない気がしますが、どうでしょうか。
| 二ホンズイセン |
民家前の道端に二ホンズイセンが咲いていました。この家の方が手入れをされているのでしょう、花を楽しめる花木が道に沿って並んでいました。
| アブラチャン |
このアブラチャンもその並びにあって、枝に花を付けていました。アブラチャンは葉が展開する前に花を咲かせるので、まさに早春の花といった感じがします。
民家を過ぎてほどなく、大きなウメの木がありました。花の数がものすごく多く、一見サクラの木に見えるほどでした。
| 伊予ヶ岳 |
さっきの民家が見下ろせるほどの高さまで登ってきました。西側の山の向こうに特徴のあるシルエットの山が。あれは伊予ヶ岳で、嶺岡山系の山の一つです。伊予ヶ岳には17年前に一度登ったことがあります。(こちら) あれからもう17年もたったのか、というか17歳も年を取ったのか!
| 樹齢400年欅 |
斜面にしっかりと根を張っていた大きなケヤキ。看板には「樹齢400年欅」とありました。400年前というと江戸時代初期。その間にこのケヤキが見下ろす里の様子はずいぶんと変わったでしょうね。ここにぽつんと立っているということは何かの境界を示すものだったのでしょうか。案外埋蔵金が埋まっていたりして。
根元の洞には石造りの祠が。うむ、ますます怪しい。人が掘り返さないようにあえて祠が置いてあるのでは。やっぱり徳川埋蔵金ですね、これは。
コンクリ舗装の道を登っていきます。なかなかの斜度です。
| アリドオシ |
アリドオシです。まだ小さな株で、高さ10cmほどでした。成長すると高さ60cmほどになります。葉の付け根に長い刺があり、それがアリを突き刺すほど鋭いということでアリドオシという名になったとのことです。
正月の縁起物としてセンリョウやマンリョウの寄せ植えなどが売られたりしますが、このアリドオシも冬でも緑色の葉と赤い実を付け縁起が良いということから、同じ流れで「一両」と呼ばれたりします。他にもヤブコウジを「十両」、カラタチバナを「百両」と言ったりしますね。ただ、センリョウやマンリョウがその植物の標準和名であるのに対し、一両、十両、百両はあくまで俗称です。
| ノササゲ |
これはノササゲの実か。鞘が裂けて反り返り、中の種子が露出しています。その鞘の色がうっすらと紫がかっているように見えますが、秋の頃ノササゲの実は鮮やかな紫色をしていて、その名残がこの色なのだと思います。
| サラシナショウマ |
この花殻はサラシナショウマのもの。完全にドライフラワー化しています。
山腹を辿る道から稜線に出ると折り返すようにして更に高度を上げていきます。舗装路は終わりましたが、まだ道幅は広めです。
道の表面には岩の砕けたような細かい砂利が散らばっていて、きつい傾斜とも相まってズリズリと滑って歩きにくいです。
| サルノコシカケ |
足を止めて小休止。傍らの大きな木を見上げると、サルノコシカケが生えていました。触るとカッチカチで、こんなに硬くてどうやって成長していくんだろうと疑問が湧きました。不思議です。ところで、この大きな木、樹皮と葉の様子からその場ではキハダと思っていましたが、よく考えると葉が茂っていたのでキハダということはないですね。何の木だったんだろう。
| フウトウカズラ |
これはフウトウカズラの実です。温暖な沿岸部に生えるツル性の植物で、あちこちの木にとりついていました。コショウ科に属していて、コショウの果実も似たような状態で実るそうですが、フウトウカズラの実には辛みはないそうです。
| スギ |
スギの雄花が熟し、木全体が赤茶色になっています。スタンバイOKですね。
| ??? |
木の根元に生えていたこれは何だ? 高さは20cmほどで、この姿で冬越しをしているようです。見た目からはトウダイグサ科の何かみたいな気がしますが。逸出した園芸種か?
少し傾斜が緩やかになってきたところで、行く手に切り開かれた明るい場所が見えてきました。あれが大黒様と呼ばれる場所だと思います。
| 大黒様 |
11時30分、大黒様に到着しました。やっぱり大黒様が祀られていました。出発からまだ1時間ですが、日当たりもいいのでここで休憩です。
その大黒様が見下ろしている風景がこちら。低くなだらかに続く山々と長閑な里が広がっています。
嶺岡山系は、安房勝山から安房鴨川まで半島先端部を東西に貫く山地で、断層活動によってできたものだそう。地殻変動により太古の海洋底を作っていた岩石(主に蛇紋岩など)が断層から絞り出されるように出てきてそれが隆起したものとのことです。地盤は悪く、地滑りや山崩れの頻発する地質なのだそうです。それにしても、硬い岩石を断層の隙間から絞り出すって、いったいどのくらいのパワーが働いたと考えればいいのか、ちょっと想像がつきません。
西北西の方向にはさっき見た伊予ヶ岳。南峰と北方を持つ双耳峰です。その左奥にあるこんもりした山は津辺野山という山だそうです。
| 駐車場 |
眼下にはドリーム号Ⅲを停めた駐車場が見えました。その右上にあるのが高照寺ですね。
| 担ぎ上げられた神様 |
こちらが大黒様。乗っている俵も含めて90cmほどの高さがあります。砂岩で作られていて、風化の具合から江戸時代中期のものと考えられているそうです。近くに建っていた解説板によると、昔、麓の川辺という集落(駐車場があった辺り)の人が、集落に幸福が訪れるようにと石工に像の制作を依頼し、出来上がった大黒様を集落の中に安置したそうです。すると、「世の中に縁起を担ぐという言葉があるが、どうせ担ぐなら仲間で山のてっぺんまで担ぎ上げたらよかんべ」という話になり、早々翌日にはこの峰林山の山頂まで担ぎ上げ、安置したのだそうです。以来この集落の生業は繁盛したのだとか。
大黒様を過ぎるとアップダウンを繰り返す稜線の道になります。道幅も狭くなりました。yamanekoの住む多摩丘陵ではもっぱら落葉広葉樹の森が広がり、この季節は林床も明るいですが、温暖なこの地では常緑広葉樹の照葉樹林が優勢で、森の中に日が差してきません。同じ南関東でも様子がずいぶん違いますね。
| フユイチゴ |
林床にはフユイチゴの葉が見られます。常緑で、冬でも生き生きとした緑色をしています。花のように見えるものは花冠の基部にある萼です。
| 石碑 |
しばらく行くと石碑が立っていました。正面に大きく「〇大日如来尊」と彫られています。〇は多分太陽を示すマークのような意味だと思います。その左右にも小さめの字でなにがしか彫られていましたが、よく読めませんでした。この稜線の道を御殿山を超えて更に進むと、大日山という山があり、山頂には大日如来像が安置されているそうなので、この辺りには大日山に続く道々に同じような石碑が立っているのかもしれません。
さて、目指す御殿山まではあと少しです。(後編へ続く)