
弁天山 ~浅い春の野辺を行く(前編)~
 |
(前編) |
【東京都 あきる野市 令和3年3月14日(日)】
3月に入って平年の気温を大きく上回る日が続いています。なにか「暖冬」とかの緩い言葉で言い表すのはもう違うような気がしてきます。そのうち冬と呼べるような時季自体がなくなってしまうのではないでしょうか。
そんな暖かい早春の一日、なまった体をほぐしがてら近場の山に登ることにしました。目的地は五日市にある弁天山(292m)です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前9時30分、ドリーム号Ⅲで自宅を出発。国道16号線から八王子で新滝山街道に入り、東京サマーランド前へ。そこからしばらく秋川沿いに走った後、山田大橋という立派な橋で対岸に渡り、五日市街道を通ってJR武蔵五日市駅までやって来ました。ここは五日市線の終点です。
| 武蔵五日市駅 |
里山風景の中にある終着駅にしては立派な駅舎。駅前のコインパーキングが今日のベースになります。
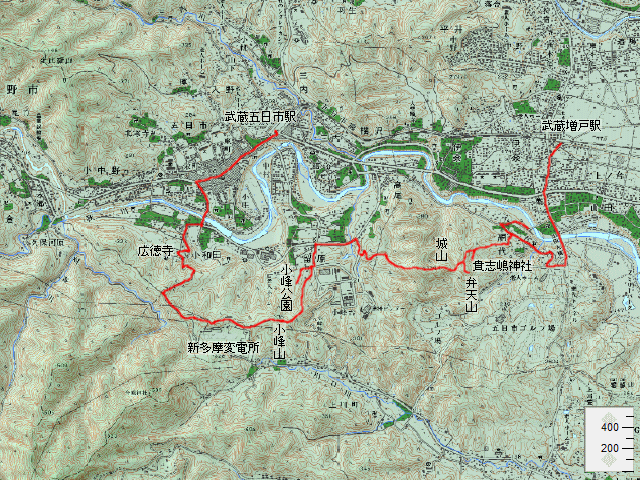 |
Kashmir3D |
今日のルートは、武蔵五日市駅から檜原街道を西に向かい、上町という交差点を左折して秋川の川縁に下りて往きます。川を渡ったらその先にある小和田集落を通って正面の山へ。稜線に出たら東進し、小峰山を過ぎたらいったん麓に下ります。そこからしばらく里を歩いて今度は城山、次いで弁天山に登ります。そこからは網代集落に下り、最後は川を渡って武蔵増戸駅でゴールというもの。武蔵五日市駅へは電車で一駅戻ります。
10時30分、武蔵五日市駅をスタート。
檜原街道を西に向かってしばらく行くと、左手にぱっと展望が開けました。河岸段丘の縁から眺める形なのでよく見渡せます。今日は写真の正面の山々を右手から回り込む形で歩いて行きます。ここから見て一番高いピークが城山で、その奥に弁天山がある(ここからは見えていない)という位置関係です。眼下の道路は今日のルート上で後に立ち寄ることになる小峰公園の脇を通り、八王子市に至る都道32号線です。
| 川に向かって |
上町交差点を左に折れて坂を下っていきます。段丘崖を下るので結構な斜度です(写真では分かりにくいですが。)。
見えている民家は秋川河畔の集落。これから川を渡って、正面に見える稜線に登っていきます。その奥にある三角形のピークは今熊山ですね。今から7年前に登ったとこのある山です。
| 秋川 |
秋川に架かる橋の上から。この時期、水量も少なく静かな佇まいを見せていますが、一昨年秋の台風19号では暴れ川へと変貌し、流域に大きな被害を出しました。
秋川を渡ると小和田集落。長閑な田園風景です。右手の丘の中腹にまっすぐ道が延びていますが、これからあの道を上がっていきます。
その坂道のとっかかりの辻に石碑が並んでいました。このような石碑にはいくつかの種類があるようで、いわゆるお地蔵さんの他、馬頭観音、千手観音、庚申塔や道祖神など、主に江戸時代になって様々な信仰が入り交じって造られていったそうです。お地蔵さんが6体並んだ六地蔵というのもよく見かけます。
ゆっくりと坂を上っていきます。早くもうっすら汗ばんできました。
| ウメ |
ウメが満開です。サクラと異なり花柄がほぼないので、枝から直に咲いているように見えますね。なので、さわさわと風に揺られるような風情もありません。逆に寒風にも毅然と対峙するといった凜々しさを感じたりします。
| セントウソウ |
おっ、これはセントウソウですね。小さな花ですが、比較的薄暗いところに生えていることが多いので、白い花序がよく目立ちます。漢字では「仙洞草」と書くらしく、「仙洞」とは仙人の棲むところという意味があるそうです。そんなに深山に咲いているわけでもないんですけど。
| オオアラセイトウ |
代わってこちらは日向を好むオオアラセイトウ。別名を「諸葛菜」といいます。蜀の軍師、諸葛孔明は、戦で荒廃した占領地の経営のため、戦後直ちに兵たちに救荒作物を植えさせたそうで、結果その地の民の人心を掴んだのだそうです。そして、後にこの作物を「諸葛菜」と呼んだということです。ただ、このオオアラセイトウのどこを食べれば食糧事情が改善するのか疑問です。もしかしたら同じ名前の違う作物なのかもしれません。よくあるパターンです。
坂道の途中に休憩スペースがありました。秋川河畔の集落が下の方に見えています。
| カンゾウ |
これはカンゾウの若芽ですね。美味しい山菜として有名です。(写真からはヤブカンゾウかノカンゾウかは判別不能。)
11時10分、中腹にある廣徳寺の前までやって来ました。室町時代に創建された臨済宗のお寺だそうです。奥に見えているのは(黒っぽい影になっていますが)「總門」と呼ばれる山門。閉まっていたので境内には入りませんでした。中には立派なイチョウの木があるそうです。
廣徳寺を過ぎると山道になります。
| アオキ |
アオキの実が鮮やかな色に熟していました。果肉が薄いからなのか鳥たちに好んで食べられるということはないようで、冬の終わりとか食べ物が少なくなる頃になって食べに来るのだそうです。
| カンスゲ |
これはカンスゲですね。ちょっと触っただけで花粉がフワッと煙のように舞いました。
東側の眺め。ここから大きく右手を迂回する形で歩いて行き、正面に見える尾根の更にもう一つ奥にある尾根の向こう側に下りて行きます。
一旦森を抜け、明るい陽射しを受けながら歩く道になりました。
| アセビ |
アセビの葉も一生懸命に陽射しを受けようとしていますね。
| マルバウツギ |
マルバウツギの果実。昨年のものですね。そういえばマルバウツギのこの姿はよく目にするのですが、中にどのような種子が入っているのかは見たことがありません。今度見かけたら揺すってみたいと思います。もう空っぽなのかもしれませんが。
道は再び木立の中へ。この辺りが鞍部となり、左手に向かって尾根筋を歩いて行きます。
| 分岐 |
分かりにくいですが、道がY字に分岐しています。右手にいくと今熊山に至ります。今日は左の明るい尾根道へ。
| 新多摩変電所 |
突然 巨大な変電所が現れました(といってもここに変電所があるのは知っていましたが。)。山の中に隠されているような立地です。ここは東電の新多摩変電所。何やらよく分かりませんが東京では豊洲とここにしかない「超高圧変電所」とのことです。遠くにいてもジリジリジリ…としびれるような音が聞こえていました。装置がいちいち物々しく、しかも何の装置なのかも分からないので、いきなり異世界に連れてこられたような気分になります。
そんなショッカーの基地みたいな変電所を横に見ながら尾根道をなだらかに登っていきます。
山道のど真ん中を塞ぐように鎮座していた大きな岩。もともと一塊だったものが砕けたようにも見えます。おそらく石灰岩だと思います。
| 小峰山山頂 |
11時50分、小峰山の山頂に到着しました。誰もいません。麓には都立小峰公園があって、看板の地図を見ると、その敷地の南端であって、かつ、最高点に位置しているようです。
ここは特にとどまることなく尾根道に沿って下って行きます。
| 馬頭観音 |
ほどなく馬頭観音の石碑が現れました(写真奥から下りてきました。)。馬頭観音があるということは、その昔は人々が行き交う街道とか生活道路だったということでしょうね。
| 桜尾根へ |
石碑の前が分岐になっていて、ここを斜め左に向かって下る桜尾根という小径を辿っていきます。すなわち小峰公園の敷地の中に入るということです。
木々が葉を展開させる前なので、こんなに明るい山道です。道の左に広場があるので行ってみることに。
広場は休憩スペースになっていて、ベンチもあったので、ここで昼食をとることにしました。時刻はちょうど12時ですし。遠くに見える街並みは五日市の中心部のようです。
| 豪華メニュー |
今日の昼食はこちら。おむすびとあんパンとお茶です。早春の陽射しの下で食べるとご馳走ですね。
| 武蔵五日市駅 |
正面の木立の隙間から、ドリーム号Ⅲを駐車した武蔵五日市駅が見えました。あそこからここまで歩いてきたのか。ずいぶん遠くにあるように見えましたが、地図で確認してみると、直線距離で1.5kmしかありませんでした。
昼食をさっさと済ませ、再び坂道を下ります。その下りきったところに八坂神社という神社がありました。
| 八坂神社 |
創建年代は不詳で、江戸時代には牛頭天王社だったと解説板にありました。地域では「天王さま」と呼ばれているようです。
武蔵五日市駅を出発し、秋川を渡って小峰山に連なる尾根を歩き、山頂を越えて麓に下りてきました。イメージとしては今回の野山歩きの半分が終わった感じです。さあ、ここからはしばらく里道を歩き、今度は城山、弁天山に登ってまた反対側に下っていきますが、それは後編で。