
磐梯山 〜紅葉輝く宝の山(後編)〜
 |
(後編) |
【福島県 北塩原村、磐梯町、猪苗代町 平成21年10月12日(月)】
紅葉の磐梯山。後編です。(前編はこちら)
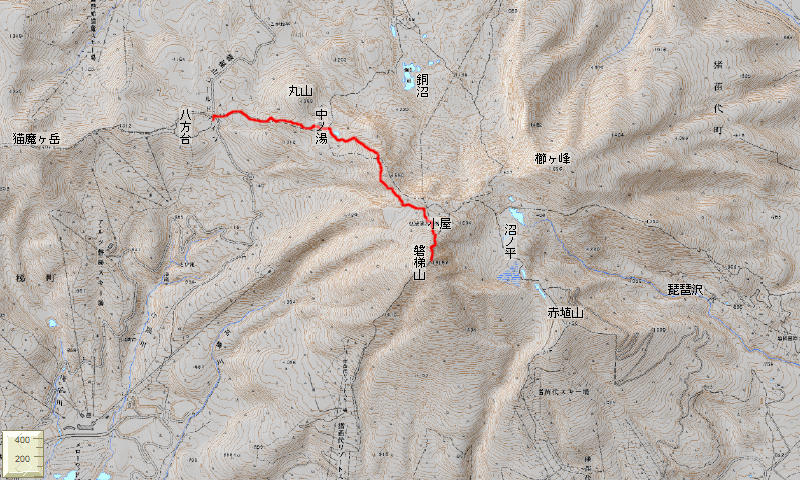 |
八方台の登山口を出発して2時間半。弘法清水小屋に到着しました。普通の登山者ならとっくに山頂に着いているでしょうが、もともとスローペースであるのに加えて、あれこれと観察しながら登っているので、人の2倍くらいは時間がかかってしまいます。
ここでしばらく小休止して若干の体力回復を図り、残るは山頂までの最後の上りです。ここからの標高差は約190m。360度のパノラマを楽しみにして頑張りましょう。
| 秋晴れ |
空を見上げるとこんな感じ。天気予報どおりの素晴らしい秋晴れです。
| ミヤマハンノキ |
ミヤマハンノキの果穂。種子を出し切ってマツボックリ状に開いています。右は雄花序の冬芽です。
この木は本州中部から北海道にかけて分布するヤシャブシの仲間。今日は穏やかな日差しを浴びていますが、ここで生きていくのも過酷でしょうね。
| 沼ノ平 |
登山道の東側は大きくえぐり取られた地形をしていて、眼下の沼ノ平まで一気に落ち込んでいます。その縁に赤埴山のピークが。ここからだとずいぶん低く見えますね。さらにその向こうの麓には長閑な田園風景。裏磐梯から流れ下ってきた長瀬川が造った河成平野で、きれいに圃場整備されているのが分かります。
| 山頂直下の壁 |
同じ場所から右手に目をやると、山頂下の断崖が壁のように迫ってきていました。この山体にものすごい力が作用したのがひしひしと伝わってきます。
| おお、あれは |
上の方から賑やかな声が聞こえてきました。おお、いよいよ山頂か。
| 岩だらけの山頂 |
12時15分、山頂に到着しました。ちょっと風がありますが、いい天気なので寒くはありません。
山頂はゴツゴツとした岩で覆われています。これは噴火した溶岩が冷える過程で細かく割れて形作られたもの。安山岩だそうです。磐梯山の山頂には三等三角点があることになっていますが、国土地理院のサイトでは現況は「不明」とされているそうです。山頂には小さな社が置かれている石の塚(写真手前)ともう一つその奥にも塚があり(登山者が片手を置いているところ。)、噂では奥の方の塚が三角点があったところだということです。(三角点は落雷で破壊されたとも聞きました。)
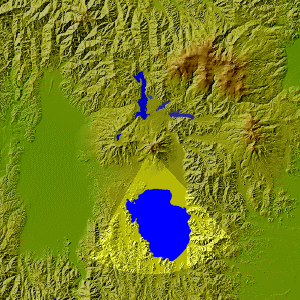 |
さあ、楽しみにしていた360度の眺望です。
登ってくる途中ではまったく見ることのできなかった南の方角。全国第4位の広さを誇る猪苗代湖が一望です。5万年くらい前には湖の水位が今よりも高く、現在平地の部分も呑み込むほどの大きさだったとか。その後湖から流れ出る唯一の川の日橋川(写真では湖の右端)の急激な浸食によって今の水位にまで下がったと考えられています。
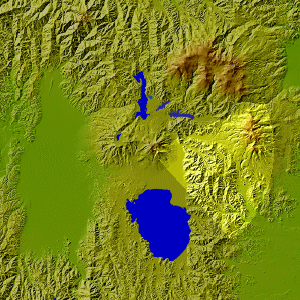 |
東の方向は、さっき見た沼ノ平越しの田園風景。赤埴山は手前の丘に遮られてここからは見えませんね。正面の山並みの向こうは郡山盆地が広がっているはず。左奥には安達太良山のゴツゴツとした山塊が望めます。安達太良山には2年前に残念な想い出があるので、近いうちにリベンジしたいと思います。今度は初夏にでも。
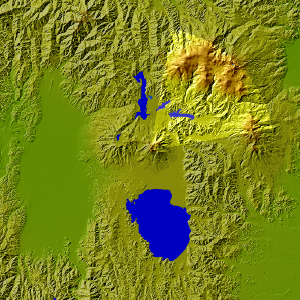 |
北東の方角はというと、目の前に櫛ヶ峰がどーん。明治の噴火で小磐梯が崩れ去った跡が見てとれます。その向こうには秋元湖が見えています。最奥の山塊は山形県との県境をなす吾妻連峰。東吾妻山、中吾妻山、西吾妻山と居並び、最高峰は2035mの西吾妻山です。あの山々の向こう側は米沢です。
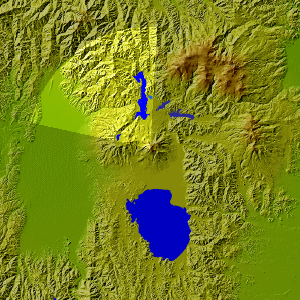 |
北西の方角は、これまで登ってきたルートを一望することができます。上の写真でちょうど雲の影が落ちている辺りを登ってきたことになります。写真左には猫魔ヶ岳。化け猫伝説があるのだとか。おぉ怖っ。写真右には檜原湖です。
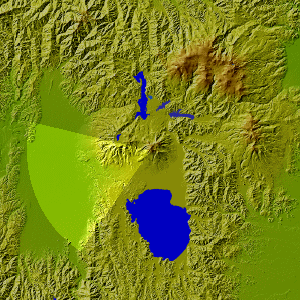 |
そしてこちらが西の方角。猪苗代湖畔から会津盆地へと抜けていく地峡が望めます。遠く広がる会津盆地は標高190m。一方猪苗代湖畔は標高520mなので、その差330mもあるのです。裏磐梯の川は磐梯山の東側を回っていったん猪苗代湖に注ぎ、そこから会津盆地に下って、さらに新潟へ、日本海へと流れ下ります。
| 取材ヘリ |
山頂からの展望を楽しんでいると、どっかのテレビ局の取材ヘリがやってきて、山頂の周りをぐるぐると旋回していきました。思いっきり手を振っておいたので、夕方のニュースあたりで映ったかも。でもテレビの画面ではこの感動は味わえないぞー!
| タダ弁 |
たっぷりと景色を楽しんだ後は昼食です。これがホテルが用意した弁当。おにぎりとおかずがぎゅっと詰まっている感じで、ボリューム満点です。実際におにぎり自体の米密度も高かったです。これにペットボトルのお茶もタダで付いてくるのだから、かなり得した感が高いと思います。
| 記念写真 |
昼食後は山頂で記念写真を。あまりに空が青いのでいっぱい撮ってしまいました。でも写真嫌いのyamanekoは写っていません(撮るのは好きなんですけどね。)。
| ホソバノヤマハハコ |
午後1時、下山開始です。登山道脇でホソバノヤマハハコが午後の光を浴びていました。
| 弘法清水小屋 |
膝に負担をかけないようにゆっくりと下ってきたつもりですが、それでもあっという間に弘法清水小屋まで下りてきました。結構立派な(?)小屋で、食品や土産物も売っていました。ここまで荷物を上げるのはやっぱり人力でしょうね。
遠くに安達太良山が見えていますね。ここもいい眺めです。
| サラサドウダンツツジ |
燃えるようなドウダンツツジの紅葉。「秋だぞーーーー!」って叫びたくなるなるような開放感です。
| カシャ! |
どこを見ても撮りたくなるような風景ばかり。こりゃ、やっぱり下りも時間がかかりそうですぞ。
| モザイク |
これもサラサドウダンツツジですが、このモザイク紅葉もいい味わいを出しています。「日本の秋」の色といった感じでしょうか。
| カジカエデ |
猫魔ヶ岳をバックにカジカエデの紅葉。遠赤外線でも出していそうな暖かさを感じます(感じませんか。)。
| 枝越しに |
枝の下に入って葉裏の紅葉を。日差しが透けて、葉っぱ自体が発光しているかのようです。
| ダケカンバ |
ダケカンバはあらかた葉を落としていました。これはこれで絵になりますね。(というより、バックが青空ならたいがいは絵になるということかも。)
| ムシカリ |
これはムシカリの葉。カラフルだなぁ。
| 秋の日は |
日差しが少し斜めになってきました。とはいえ時刻はまだ2時。 ♪秋の夕日〜に〜、照る山〜も〜み〜じ〜、 鼻歌を歌いながらの楽しい下山です。
| カジカエデ |
しつこいくらいに紅葉です。とはいえ、これはまだこれから。燃えるような赤を見てきた後なので、黄緑色が新鮮ですね。
| オオバギボウシ |
樹木ばかりでなく草本も紅葉します。これはオオバギボウシの葉。形といい色といい、いい味を出しています。
| 黙々と |
ブナの林の中を黙々と下っていきます。でも下れば下るほど、この気持ちいい山歩きが終わりに近づくということで、ちょっと残念な気持ちも。こんな紅葉の山歩きはそうそうできるものではないですからね。
| 中ノ湯 |
2時25分、中ノ湯まで下りてきました。午後の光を浴びた湯治宿の跡は何か山の分教場といった雰囲気を漂わせています。yamanekoの故郷はそれほど山奥ということではなかったですが、それでも子供の頃の秋の日を思い出しました。
| 満足感に包まれて |
傾斜も緩やかになり、紅葉を満喫した山歩きもそろそろ終わりが近づいています。
| 八方台駐車場 |
2時45分、八方台駐車場に到着。あー、とうとう終わってしまいました。ふくらはぎの張りも膝の痛みもなんのその。本当に楽しい一日でした。
これから装備を解いて、ドリーム号に乗り込んで猪苗代湖畔まで下りて、そこから高速道路を延々と東京に向かって走ります。どうせ渋滞が待っているでしょうから、今日のこの山歩きの余韻を楽しみながらゆっくりと帰りたいと思います。
| 猪苗代湖畔から |
猪苗代湖畔から見上げる磐梯山は、噴火の爪痕など微塵も感じさせないほど秀麗な姿をしていました。