2025年7月2日(水)
①
小山内裏公園もすっかり夏の花に入れ替わりました。これはタケニグサ。竹ほどではありませんが、あっという間に伸びて人の背丈をゆうに超えます。

②
ネムノキの花序。髭のようなものは雄しべで、これは10数個の花が寄り集まって咲いている状態です。
③
ヤブミョウガ。花序には両性花と雄花が付き、両性花では花柱がトゲのように突き出しています。ミョウガの仲間ではなくツユクサ科。
④
イヌゴマの花序は唇形花を何段か輪生させます。茎の断面は四角形で、稜に沿って下向きの刺が並んでいます。触るとざらつく感じで、痛いほどではありません。

⑤
クサレダマ。茎が細いせいか大体しな垂れていて、この野草見本園では直立するものは見たことがありません。(図鑑ではどの写真も直立していました。)
⑥
今日は穂状の花序を持つ植物が多いです。これはチダケサシ。乳茸をこの茎に刺し連ねて持ち帰ったということから名が付いたそうです。茎が頑丈なんでしょうか。全体的に淡いピンク色に見えるのは雄しべの葯の色です。
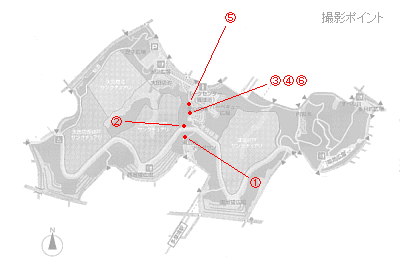
|
|
|
|
2025年7月9日(水)

①
ツユクサはもうかれこれ2か月くらい前から咲いています。日々入れ替わりながら一夏咲き続けます。青い花弁の付け根に黄色い小さな花のようなものが見えますが、これは客寄せ用の仮雄しべ。花粉は作りません。長く突き出して先端に褐色の葯が付いているのが本物の雄しべです。
②
これはタチアオイ。中国原産で古くから観賞用に植えられてきたものだそうです。これは民家の庭から自然に逸出したものか、それとも誰かが植えたものか(それはやめましょう)。
③
もう今日にでも開花しそうなヤマユリ。蕾の大きさは小ぶりのサツマイモくらいあります。ササの添え木に支えられていますね。
④
内裏池の畔でアキノタムラソウが咲き始めていました。軟毛を生やした唇形花を数段輪生させています。花冠の中の黒っぽい点に見えるものは葯。初め上唇に沿って付いていますが、花粉を出し終えたものはうなだれたり横を向いたりするのだそうです。
⑤
オオバギボウシ。花序の下部の花から咲いていきます。涼しげですね。咲き進むにつれて花序自体も長く伸びていきます。
⑥
鮎道沿いにあってもほとんど見向きもされないヤブマオ。これは雌花序で、雄花序は茎の下の方に付きます。風媒花の場合上下が逆のパターンが多いように思いますが、どういう戦略があるのか。
⑦
雌花序をアップで。イガイガしていそうで触るのもためらってしまいますが、触っても別にどうこうありません。数個の花が集まって栗のイガのようになっています。
⑧
この変わった形のものはオニドコロの蒴果。雌雄異株で、雌花序は写真のように垂れ下がり、雄花序は逆に上向きに伸びます。

⑨
ヤブカンゾウの花はうだるような夏の日を連想させます。今日はまさにそんな日です。雄しべと雌しべが花弁化して八重咲きになるのが特徴。これが暑苦しさの原因かもしれません。

⑩
一方、ノカンゾウは一重咲き。こちらは花冠の中央に見慣れた姿の雄しべ、雌しべがありますね。
⑪
ミソハギ。漢字では「禊萩」と書き、仏事と縁が深そうな名前です。別名を盆花といい、お盆に仏壇に供えられることの多い花です。と、図鑑には書いてありますが、yamanekoの実家の仏壇に供えられていた記憶はありません。地域的なものでしょね。この花も花期が長く、秋が深まる頃まで咲いていたりします。
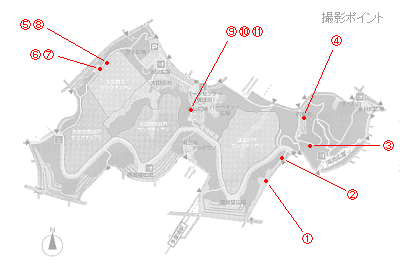
|
|
|
|
2025年7月17日(木)

①
クマノミズキの果実。ミズキより概ね1か月遅れて花を咲かせ、実を付けます。樹形も花も葉も見た目はそっくりですが、葉の付き方が違うので、よく見れば見分けられます。ミズキは互生、クマノミズキは対生です。
②
野草見本園へ。これはミズタマソウ。花の大きさは約5mmとかなり小さいです。花序の下の方にある毛むくじゃらのものは果実で、これに露が付いて水玉のように見えることが名の由来。
③
ヤマトラノオだそうです。yamanekoがよく使っている図鑑には記載がなかったので、こういう植物があることを知りませんでした。関東地方以西の山地で見られるとのこと。見た目はトラノオというよりクガイソウに近いという印象です。
④
ヤマトラノオの花序をアップで。花冠は薄い青紫色で、4弁に見えますが、基部で合着して筒状花になっているようです。この辺はクワガタソウの仲間らしいですね。

⑤
ダイコンソウです。花冠を見る限り大根と似ている点はありませんが(大根はアブラナ科で4弁)、それもそのはず、似ているのは根生葉だそうです。茎からではなく根際から生えている葉のことです。
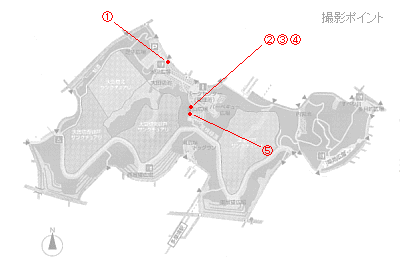
|
|
|
|
2025年7月23日(水)
①
朝から気温30度超え。そんな中でも植物は生き生きとしています。これはヨウシュヤマゴボウの花序。基部に近い方はもう果実ができていますね。秋には黒紫色に熟します。美味しそうですが有毒。

②
エノキの実。少し色づき始めています。秋には赤く熟し、その時には中の果肉も赤くなっています。味は干し柿に似て美味しいのですが、いかんせん小さすぎて食べた気がしません。
③
これはアカメガシワの果実。表面に刺のような突起が密生しています。実が熟す頃には概ねなくなるのですが、「それまで俺に手を出すなよ」と言わんばかりの威容です。

④
ギラギラの陽射しを受け、キツネノマゴも暑そうです。葉も少ししな垂れ気味。ただ、その陽射しのおかげで葉の表面に毛が生えていることがよく見て取れます。
⑤
公園の正面入口にある円形花壇へ。これはオニユリ。百合でありながら鬼って、恐ろしいのか可憐なのか分からないネーミングです。確かに大きく育ちますが、大きさで言うとウバユリやヤマユリの方が鬼っぽいです。花冠の色を鬼の赤ら顔に例えたということでしょうか。
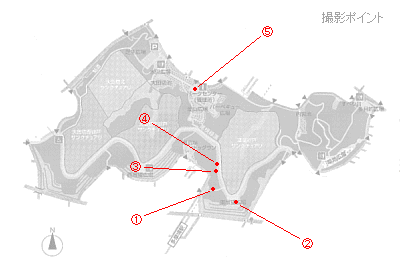
|
|
|
|
2025年7月31日(木)
①
少しでも涼しいうちにと7時過ぎに歩いてみました。
野草見本園のコバギボウシ。既にギラギラの朝日を浴びていて、この花ならではの涼やかさが伝わってきません。

②
ミニビオトープのようなエリアに咲いているコケオトギリ。花冠の直径は8mmほどと小さく、しかも昼前には萎んでしまいます。なかなか目に触れない花ですね。園内では大田切北サンクチュアリ内に自生のものがあるそうです。
③
これはリョウブ。花の時期が終わり、花序には若い果実が連なっています。リョウブは古代から救荒植物として利用され、新芽や若葉は食用とされたそうですが、実にはあまり利用価値はなかったようです。

④
九反甫谷戸へ。この時期ウバユリが林立しています。茎の高さは1.5mほど。なかなかの存在感です。写真の状態が満開です。

⑤
この谷戸にはタマアジサイもあります。写真は花序が展開し始めた状態。その花序を包んでいた球形の総苞がまだ落ちずにちょこんと乗っかっていますね。

⑥
これはツルウメモドキの若い果実。先端に花柱の名残がありますね。初冬には薄褐色の果皮が割れて中の朱色の種子がよく目立ちますが、この時期は生えている場所を知っていないとなかなか認識できないと思います。
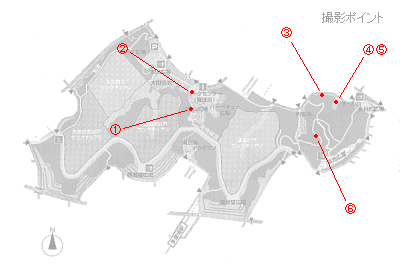
|
|
|
|
| |

