2025年6月4日(水)
①
梅雨入り前でありながら曇りがちの日が続き、今日は久々の陽射しです。まずは野草見本園から。
これはミゾコウジュです。花序の下の方から咲いていき、上の方に数個の花が残っている状態です。名前に「溝」と付くようにやや湿ったところを好んで生えます。

②
テイカカズラ。花弁(花冠の裂片)はスクリューのようにねじれています。花冠の中央に穴が5つ空いていて、その奥に蜜や花粉がある構造。細長い吻をもつ虫を待っているんでしょうね。

③
これはシュンランの若い果実です。立ち上がっているのは熟した後に極小の種子を風に飛ばすため。少しでも高い位置から飛ばしたいんでしょうね。ちなみに熟すのは翌年の花の時期です。

④
ヤブレガサが花茎を伸ばし、若い頭花を何個も付けていました。頭花は筒状花が集まったもので、それ自体蕾のように見えます。開花はこれから。

⑤
ニワトコの実が赤く色づいていました。大きさは3~5mmくらいと小粒です。

⑥
ビヨウヤナギは雄しべの数が半端なく多く、1つの花に100個以上あります。オトギリソウ科で、なんとなく葉の形にその雰囲気があります。

⑦
尾根道に植栽されているアジサイが涼しげな色合いを見せていました。雨が似合う花です。

⑧
ヤマグワの集合果。写真のものは普通サイズのものに比べ1.5倍くらいの長さです。その大きさからぱっと見、マグワかなとも思いましたが、集合果の粒々から伸びている雌しべが長いので、ヤマグワだと思います。黒く熟すと食べごろです。
 |
⑨
クサフジが密に花を付けていました。マメ科特有の蝶形花です。ほぼ雑草の扱いですが、よく見ると優美な花ですね。ただ、周囲にヤブジラミが密生していて、この写真を撮るために大量のヤブジラミの果実を身に付着させるはめになりました。

⑩
アカマツの若葉。今年伸びた枝の先端に付きます。その枝には花粉を出し終えた雄花の残骸が。

⑪
マルバアオダモの果実です。翼果と呼ばれるタイプで、扁平で細長い形をしています。風が吹くとサラサラと揺れます。

⑫
再び野草見本園に戻ってきました。これはキヌタソウ。花の大きさは3mmほどで、星を散らばらせたように花を咲かせます。yamanekoにはルーペがないとピントが合わず、見えません。

⑬
ようやくヒメジョオンが咲き始めました。ハルジオンよりも1か月くらい遅いです。両者は花はそっくりで、花茎の中の髄の有無や葉の基部の形に目だった相違があるので、そのへんで見分けがつきまます。
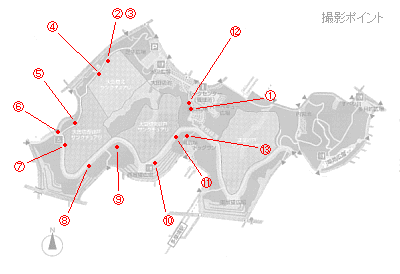
|
|
|
|
2025年6月12日(木) その1

①
きちんと並んだ花序。これはコマツナギです。長い花茎が強くてちぎれにくく、馬(駒)を繋ぐのにも使えるくらいということで名づけられたそうです。花はマメ科に特有の蝶形花。

②
ミズキに遅れること約1か月。クマノミズキが咲き始めました。見た目はほとんど同じ。この開花の時期の違いと、あとは葉の付き方で見分けられます。ミズキは互生、クマノミズキは対生に葉が付きます。

③
ムラサキシキブの花も咲きました。花筒から雄しべが勢いよく飛び出ています。

④
キンシバイはオトギリソウ科で、先日見たビヨウヤナギと仲間同士です。葉の形が似ているということの他にも、雄しべが100個以上と多数あるのもよく似ています。あと生け垣によく用いられる点も。
⑤
オオバコの花序。花は雌しべ先熟で、花序の下から上に向かって成熟していきます。写真のものは、現在、花序の上3分の1が雌性期(雌しべが成熟し雄しべはまだ未熟)、中3分の1が雄性期(雌しべはしおれ雄しべが成熟)、下3分の1が雌しべも雄しべもしおれた状態です。

⑥
マンネンタケ。柄が傘の中央ではなく端に付いているタイプのキノコです。こういう生え方を「偏心生」というのだそう。
⑦
森の奥でオオバジャノヒゲが花を付けていました。ひっそりと咲くという表現がぴったりです。なんだか陶器で作った工芸品のような質感です。

⑧
ヒヨドリバナが蕾を付けています。初秋の花というイメージがありますが、梅雨どきから開花の準備をしているんですね。
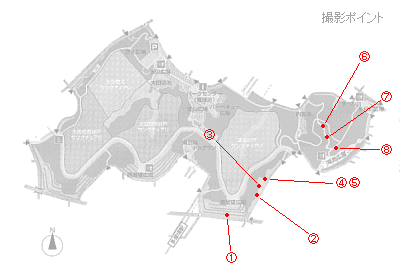
|
|
|
|
2025年6月12日(木) その2

①
おお、ニガイチゴの実が熟しています。漢字では「苦苺」ですが、本当は甘く美味しいです。いったい誰がどういう意図で付けた名前でしょうか。
②
こちらは見たまんまのネーミング、ツリバナです。今は果実になっていますが、1か月前には花が吊り下げられていました。まさに「吊り花」。2個ずつがペアになっていて、アメリカンクラッカーみたいです。

③
これはリョウブの若い花序。暑いさなか、純白の花を付けます。ただすぐに薄褐色に変色してしまって、花序全体が満開の状態にはならないのが普通です。

④
九反甫谷戸へ。今まさに全盛を誇っていたのがこのドクダミでした。花弁のように見えるものは総苞片。その中央から立ち上がる花穂の表面にびっしり付いているのが花です。1個の花は花柱と3個の雄しべで構成されていて、花弁も萼もありません。

⑤
ミツバウツギの若い果実。薄い袋の中に種子があります。残念ながら今年は花の時期を見逃してしまいました。
⑥
これはヒルガオ。コヒルガオやセイヨウヒルガオとよく似ていますが、下の閉じた花の苞の形で判断しました。これは一見萼のように見えますが、萼はこの苞の中に包まれているそうです。
⑦
チガヤ。既に花期を終えようとしています。褐色の斑点のように見えるものはしおれかけの葯。それぞれの花の基部から白い絹毛が生えていて、全体としてもふもふの状態になっています。
⑧
パークセンターの前にオカトラノオが密生していました。ひと月前にシランが咲いていた場所です。オカトラノオは園内のあちらこちらに自生していますが、ここに植えられているものが一番先に咲いたようです。肥料をやっているからか?
⑨
このスタイリッシュな植物はカラスビシャク。高さは40cmほどになり、写真に写っている部分と同じくらいの長さの茎がこの下にあります。かなり細長いです。マムシグサやムサシアブミなどと同じ仲間です。
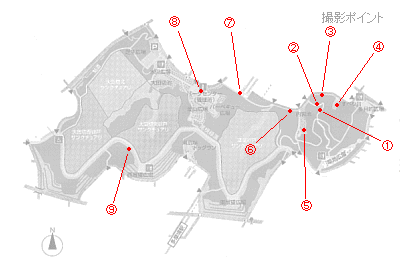
|
|
|
|
2025年6月18日(水)

①
尾根道から里山広場に下りる坂道の脇にオトギリソウの自生地があります。今年も周囲を除草し、ロープを張ってマーキングしました。
②
野草見本園。オオバギボウシが咲き始めました。もう夏ですね。そういえば今週は一時梅雨前線が消滅するなど異例の猛暑になっています。
③
こちらはウツボグサ。花の色は青紫色のものから赤紫色のものまで幅があります。別名をカコソウ(夏枯草)というそうで、夏に花が枯れて黒っぽくなってもそのまま立っている姿からそう呼ばれているとのことです。
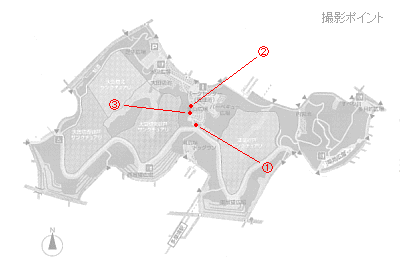
|
|
|
|
2025年6月19日(木)

①
タカドウダイの花。言われなければこれで開花状態だとは気が付きません。花茎の先端に葉が5個輪生し、そこらか5個の花序が伸びだしています。

②
ドクダミの葉に休むアカシジミ。個体数が少ないわけではないようですが、昼間はあまり活動せず、しかも樹上にいることが多いので、あまり見かけないとのことです。
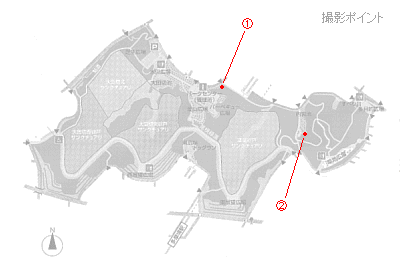
|
|
|
|
2025年6月21日(土)
①
今日は夏至。中天からの陽射しを受けるマムシグサの果穂です。瑞々しいですね。絡みついているのはオニドコロの蔓。

②
ヤブレガサの花が満開です。一つの花のように見えるものは筒状花が10個程度集まったもの。それぞれの花から長い雄しべが伸びだしています。
③
ハエドクソウの花をアップで。唇形花で、花冠の大きさは5mmほどです。根を煮詰めた汁で蝿取り紙を作ったのだそうです。昔、天井から蝿取り紙をぶら下げている家や店がありましたね。昭和の風物詩です。

④
野草見本園のウマノスズクサ。ジャコウアゲハの幼虫の食草で、今年はたくさんの幼虫がムシャムシャと食べていました。ジャコウアゲハの成虫は春から夏にかけて3、4回発生するそうで、最終サイクルに生まれたものは数か月間さなぎのままで過ごしてそのまま越冬し、翌年の春に成虫になるそうです。

⑤
トモエソウの花冠を真上から見るとスクリューのような形をしています。五つ巴ですね。オトギリソウの仲間です。
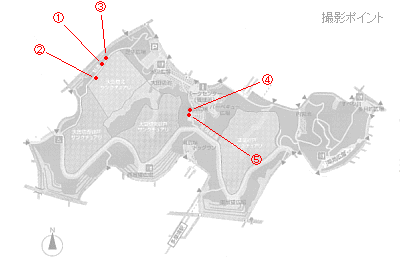
|
|
|
|
2025年6月26日(木)

①
春先から次々に咲き続けているブタナ。花期の長い植物です。もともとヨーロッパ原産で、意図して移入されたものではないようです。昭和初期に札幌で気づかれたのが最初なのだとか。ただ、その時点では各地に帰化していたそうです。

②
クリの枝先に雌花が。この時点でなんとなくクリの様相を呈していますね。丸く膨らんでいる部分は総苞で、この中に雌花が3個包まれているのだそうです。だからクリのイガの中には栗の実が3個入っているんですね。

③
こちらはウツギの若い実。お椀型で真ん中に花柱が残っているのが分かります。こんな形の独楽(こま)がありますよね。回すと倒立するやつ。

④
ナンテンの花冠は多くの花被片で構成されていて、最も内側に並ぶ6個のみ黄色の花弁状。外側のものは白色です。黄色の花被片が開くタイミングで白色の花被片がいっぺんに落ちてしまうのだそうです。この時期、ナンテンの木の下は落ちた細かい花被片で白なっていることが多いです。

⑤
リョウブの花が咲き始めました。まだ若いので花序もまっすぐに伸びています。根元から順に咲いて行くので花序全体が満開状態になることはありません。夏が来たことを教えてくれる花です。

⑥
九反甫谷戸の入り口にオカトラノオの群落があります。リョウブと違って花序は最初から湾曲しています。多摩地方ではよく似るノジトラノオも見られます。相違点は葉が細いことと茎に淡褐色の短毛が多く生えていること。写真のものはオカトラノオです。
⑦
園東側の通称「調整池」にやって来ました。今ヒメガマが花期を迎えています。ヒメガマの特徴は茎の先端部にある雄花穂とその下の雌花穂との間に隙間があり茎が露出していること。ガマやコガマは両者が接しています。

⑧
ナワシロイチゴの実。1か月前に一面に開花していたものが、今一斉に実をつけています。名前は田んぼの苗代作業をする頃に実を付けるからだとか。昔の田植えは6月というイメージで、一応それとは合致しているようです。現代では早いところでは3月末に田植えのニュースを聞いたりしますが、農業経営の必要上、耐寒品種が普及したということでしょうか。もともとイネは南方の植物ですが。
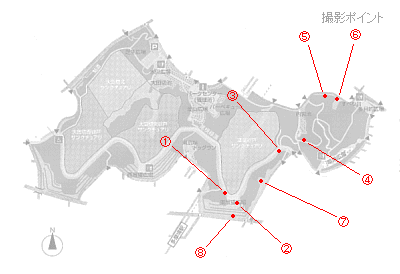
|
|
|
|
| |

