2025年2月5日(水)

①
サンクチュアリ内での作業中に見かけたジャノヒゲの種子。鮮やかな紺碧をしています。この種子を食べる生き物がいるのか、その者にはどんな色に見えているのか、興味があります。

②
ユズリハの枝先に冬芽が集まって付いていました。ユズリハは葉柄が赤いのが特徴の一つですが、冬芽も赤いんですね。

③
ヤツデは太い幹の先端に花序を付けます。白い部分が今シーズンに伸びた部分で、現在は若い実が付いている状態です。この花序の大きさは写真のもので約80cmくらい。なかなか存在感があります。

④
先月、カジイチゴの自生地を整備しました。その後どうなっているか見に行ってみると、若い葉をたくさん展開させていました。こんなに寒いときから伸ばしていることに驚き。耐寒仕様なのか、葉は硬く頑丈そうです。

⑤
エノキの高いところに寄生しているヤドリギ。地上10mくらいの場所にあって、しかも細かい枝が茂るその先にあるので、なかなか観察しづらいです。株の大きさは直径1mくらい。去年半分くらい脱落してしまったので、ちょっとスカスカになった気がします。
⑥
ニワトコの冬芽です。ツルっとしているように見えますが、よく見ると細かな毛に覆われているようです。これも防寒対策か? あまり効果はなさそうですが。

⑦
カワヅザクラが3個ほど咲いていました。この公園で毎年一番早く咲く株です。蕾も次の出番を待っているか、ほころび始めていました。
⑧
尾根道に植栽されているアジサイの冬芽。先端はガラスペンのようなシルエットです。白い部分は葉がついていた痕。維管束を目や口になぞらえて羊の顔とか小人とか言ったりします。

⑨
野草見本園へ。ここではしばらく花の姿が見られない時期が続きましたが、立春を過ぎたということもあり、フクジュソウが開花していました。まだ訪れる虫は少ないでしょうね。
⑩
ソシンロウバイが開花しています。咲き始めてもう2週間くらいは過ぎていますが、まだまだ蕾はたくさん付いています。先日からの冷え込みで開花している花はほとんど傷んでいました。一方、これから開くものは生き生きとしています。
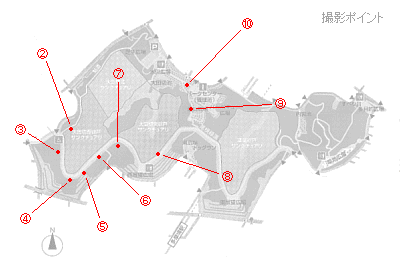
|
|
|
|
2025年2月12日(水)

①
ようやくウメが咲き始めました。今年はかなり遅いです。やはり先日来の最強寒波のせいでしょうか。ただ、例年この時期に1回はある積雪が今年はまだないのですが。

②
ウバメガシの冬芽。枝の先端に冬芽を付けます。真ん中のものを頂芽、その左右のものを頂生側芽というのだそうです。枝の先端だけでなく途中の葉の腋にも冬芽は付いていますが、植物には「頂芽優勢」(先端に近い芽ほど開芽しやすい)という性質があるそうで、種によっては枝の先端のものだけが開芽するものとか、枝の途中の冬芽も開芽するものとか、いろいろあるとのことです。ウバメガシは頂芽も頂生側芽も開芽するようですが、日当たりなどの条件によってすべてが開芽するわけでもないとのことです。

③
内裏池です。水に落ちた枯れ枝にヤマガラがやってきて、何度も水を飲んでいました。

④
尾根道のヤマハンノキ。こちらも寒さのせいか花序がまだぎゅっと締まった状態でした。
⑤
厳しい冬の寒さを緑の葉で耐え忍ぶスイカズラ。漢字では「忍冬」と書きます。昔の人のネーミングセンスってときに唸らされるものがありますね。安易なものも多々ありますが。

⑥
日陰でも緑の葉を茂らせるランヨウアオイ。むしろ日陰の環境の方が生きやすいようです。こちらは漢字では「乱葉葵」と書きます。葉の表面に白斑が出て、その模様が葉によって様々であることによるのだそうです。

⑦
ジョウビタキ(雌)です。羽にある白斑が特徴です。日本では冬にやって来る渡り鳥。ただ、近年各地で繁殖例が報告されているそう。これは、日本の夏が冷涼化しているということではないでしょうから、北国に戻れなかったものがやむを得ず日本で繁殖しているといううことなのでしょうか。

|
|
|
|
2025年2月15日(土)

①
エナガが数羽で枝にやってきて、しばらく枝の間をチョロチョロした後、また揃ってどっかに去っていきました。その間にカメラに一瞬目線をくれました。

②
ミズキが冬芽を膨らませつつあります。小枝がみな一様に上を向いていて、「春が来たら一気に開くぞ」という意気込みが感じられます。展開したばかりの葉は透明感があり、陽を透かして本当に瑞々しいです。
③
鮎道で作業中、小山内裏公園に隣接するマンションの屋上にオオタカが停まって、しきりに鳴いていました。オオタカの生活史は、1月後半から3月が求愛期、4月から5月が抱卵期、5月から6月が巣内育雛期、6月から8月が巣外育雛期だそうです。過去に公園のサンクチュアリ内で営巣した例もあるので、今回は新居の下見に来たのかもしれません。

④
白梅に一足遅れて紅梅も咲き始めました。今年はどの株も花数が多いようです。ウメはサクラと異なり花柄がほとんどないので、花が風に吹かれて揺れるということはありません。それがウメ独特の凛々しさにつながっているように思います。

|
|
|
|
2025年2月18日(火)

①
セツブンソウが咲いているとの情報に野草見本園に行ってみると、ありました。なんとも可愛いサイズのセツブンソウが。花冠の大きさは普通なのですが、茎の長さが3cmほどしかありませんでした。長引く寒波で成長できなかったのでしょうか。

②
ホオノキの冬芽です。どれも天に向かって伸びています。大きさ、形とも習字の筆のようです。
③
ダンコウバイの冬芽はもう芽吹き直前です。ダンコウバイは葉が展開する前に花が咲くので、まずは丸っこい花芽から。来週には冷え込みも緩むそうなので、きっと咲き始めるでしょう。花が終わって本格的は春が来たら葉芽が展開します。

④
園内に白花のヤブツバキがあるのを知っている人は多くはないのでは。目線よりちょっと高いところに花を付けるので、気が付きにくいのです。花冠の大きさは野球ボールほど。普通のヤブツバキより大きいです。

⑤
センニンソウの果実、先端からブラシのような毛を伸ばす舟形の果実が、5個星形につながっています。ユキヤナギの垣根に覆いかぶさるように蔓延っていました。
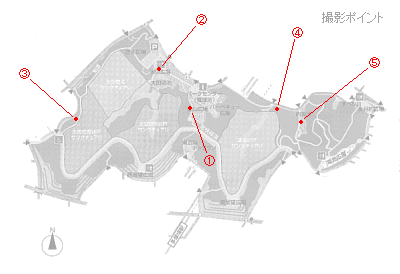
|
|
|
|
2025年2月20日(木)
①
キハダの冬芽です。この冬芽は葉柄の基部で作られ、秋に葉が落ちると顔を出します。植物の芽は葉の付け根の腋に付くものが多いですが、こういうパターンもあるんですね。
ところで、初期の仮面ライダーにこんな顔をした怪人がいませんでしたっけ。
②
そのキハダの全体像。高さ20mにもなる高木で、フレームに入りきりません。冷たい風を受けながらも春の準備をしているんですね。
この木はキハダの変種のオオバキハダではないかという話を聞いたので、春になって葉が展開したら確認してみたいと思います。違いは葉の裏の主脈に生える細毛の様子。主脈の基部にだけ生えていればキハダ、主脈に沿って一様に生えていればオオバキハダとのことです。

③
尾根道に植栽されているヒイラギナンテン。中央部からこの春に咲く花序が伸びています。葉が少し紅葉しているのは寒さ対策か(葉に糖を溜めこんで)。冬に葉を落とす植物の紅葉とは若干意味合いが違うように思うのですが。

④
ヤブサンザシの保護活動をしました。この公園にヤブサンザシがあることを初めて知りました。図鑑には「個体数は少なく、見る機会のあまりない樹木」とありました。本来、成木では株立ちし1mくらいの高さになりますが、ここの株は樹勢が衰え気味でした。写真は幼木で高さ20cmくらいです。

|
|
|
|
2025年2月26日(水)

①
昨日からガラッと季節が変わりました。野山の木々や草花も慌てているでしょうね(ただ、来週はまた寒波が戻ってくるとか)。野草見本園の外にもフクジュソウが咲いていました。暖かい陽射しを全身で受け止めています。

②
ヒサカキの花芽。もう開く準備を始めているようです。この花が開くと独特の臭気を漂わせ、中にはそれを嫌う人もいますが、yamanekoは野山に春を告げる匂いとしてむしろ気に入っています。

③
藪に紛れてヒヨドリが食事中。嘴の先で咥えているのはアオキの実です。ヒヨドリはこの実を好んで食べるようで、時々こういう場面に出会います。

④
これはトウグミの冬芽。厳しい冬を乗り越えて春に葉を展開する準備をしています。雌雄異株らしく、この木が実を付けているのを見たことはありません。美味しいらしいのですが。

⑤
ヤマハンノキの雄花序が伸びていました。つい先日までは固く締まっていたのに、昨日からの陽気で開いたのかも。花に花弁はないのでこれを開花と呼んでいいかわかりませんが、伸びて開いた隙間から花粉を飛ばします。

⑥
公園西側の尾根道沿いにはたくさんアセビが植栽されています。まだ開花していない株の方が多く、この株はフロントランナーです。花は壺型で口を下にして付いていますが、これが実になる頃には揃って上を向きます。考えてみれば不思議です。何か意味があるんでしょうね。

⑦
カワヅザクラがようやく咲き始めました。これもフロントランナーの株です。やはり今年は寒波が長く止まったからでしょうね。例年ならもう開花している樹木が一様に足踏みをしているようです。
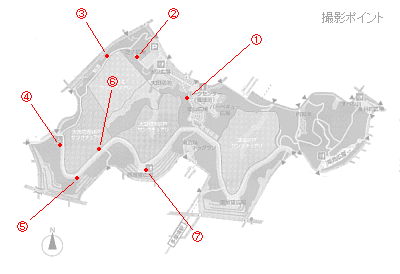
|
|
|
|
| |

