2025年1月4日(土)

①
南広場脇のクロモジの冬芽。尖っているのが葉芽で丸っこいのが花芽です。この状態で冬を越えて、4月頃に展開します。
②
これはキヅタの果実です。去年の花が結実したものですが、熟すのは今年の初夏の頃です。キヅタは耐寒性があり、雑草よけのグラウンドカバーや壁面緑化などに使われています。

③
年を越してもきれいな黄葉を見せているのはユキヤナギ。春の訪れとともに白く小さな花をたくさん付け、それが風に揺れる姿には胸がすく思いです。ああ、春が来たなと。

④
マユミの枝を見上げたところ。青空をバックに桃色の果実が映えていますね。この枝を弓の材料としたことから「真弓」の名が付いたといいます。

⑤
高さ2mほどのヤツデ。葉は天狗の羽団扇のような形をしていて、存在感があります。茎頂の果序を含め全体として円錐形を形作っています。昔は民家の裏手によく植えられていましたね。

⑥
園の西端、鑓水口近くまでやって来ました。ここは、去年、間伐や笹刈りなどyamanekoたちが林床整備を行ったところ。いい感じになっています。
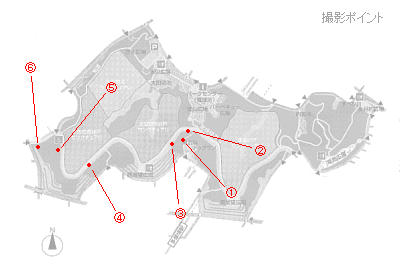
|
|
|
|
2025年1月8日(水)

①
去年、園路脇の藪の中にフッキソウの群落を見つけていたので、開花期を前に笹刈りをしました。成長しても30cmほどですがこれでも樹木に分類されるのだそう。自生のものなのか公園開設当初に植栽されたものなのかよく分かりません。

②
フッキソウの群落に中にあったマンリョウ。こちらは明らかに自生ですね。鳥が種子を運んで来たものでしょう。

③
内裏池の谷戸を遡った先にある雑木林を整備しました。冬の間に林床まで陽が差し込むようになって、春には様々な植物や昆虫が出てくると思います。
④
夏場、「猛威」と形容するのが相応しいくらいはびこっていたクズ。ここではミズキを完全に覆い隠すほどでしたが、冬を迎えて葉を落とすと、残っているのはなお頑丈なツルと痩せた果実でした。名前のイメージだけでなくその繁殖力からもとかく嫌われがちなクズですが、人間への貢献度はかなり高く、根からは葛粉や葛根湯、茎の繊維からは葛布などが作られました。要ははびこるのは人間の管理(手間)不足なんですね。
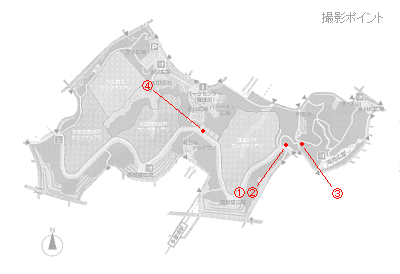
|
|
|
|
2025年1月14日(火)

①
ススキの小穂をアップで。基部から放射状に生えている毛がススキの穂のフワフワの正体です。小穂の先端から細長く伸びているのが芒(のぎ)で、ススキの芒はまっすぐ伸びずに折れ曲がるのが特徴です。イネやコムギなどイネ科の植物の多くには小穂に芒がありますが、ススキによく似た姿をしているオギには芒はありません。

②
早実グラウンドの境に植栽されているトサミズキの冬芽です。ぷっくりと膨らんですぐにでもほころびそうですが、花期は3月です。土佐に特産することからトサミズキの名が付いていて、自生地は狭い地域に限られているそうです。

③
去年の夏に整備した園路。むせ返るような草いきれの中で作業しましたが、木々が葉を落とす冬にはこんなに明るい場所になっています。

④
コゲラです。枝を螺旋状に登りながらコツコツとつついていきます。中に虫がいるところでは音が変わるのか。それとも感触が違うのか。いずれにしても微妙な変化を感じ取っているんでしょうね。

⑤
ナンテンが紅葉していました。葉は3回奇数羽状複葉という形をしていて、写真に写っているたくさんの小葉をもって一つの葉を構成しています。

⑥
サザンカに入れ替わり立ち替わりメジロがやって来て密を吸っていました。今日は温かいので(3月下旬並み)鳥たちの動きも活発です。
⑦
サワフタギの冬芽。円錐形で2mmほどとごく小さいです。この小さな器官が春になると伸びだし、たくさんの葉や花を形作ります。

⑧
ヤマツヅジですが、この株は何故だか春に展開した葉が黄葉し枝中に残っていました。本来ならこの時期この葉は落葉し、夏に展開した葉(写真中央の緑色の葉)だけが残って越冬するはずです。

⑨
これはアワブキの冬芽です。ベルベットのような細かい毛に覆われています。この公園にアワブキが自生していることを始めて知りました。花期は6月なので、開花が楽しみです。花が付けばですが。
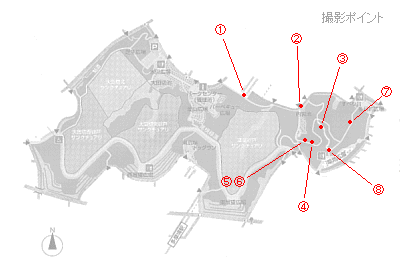
|
|
|
|
2025年1月22日(水)

①
大田切池にダイサギが来ていました。そろりそろりと餌を狙っているようです。普通には「ダイサギ」として話をすればよいですが、これは亜種チュウダイサギというやつだと思います。
実はダイサギには大小あって、ちょっと前までは大きい方をダイダイサギ(またはオオダイサギ)、小さい方をダイサギと言っていました。それが10数年前から大きい方を亜種ダイサギ、小さい方を亜種チュウダイサギと呼ぶことになったのだそうです。これらとは別種でチュウサギやコサギというのもいてややこしいので、みんなひっくるめて白鷺でいいですよね。
②
イヌコリヤナギの冬芽です。米粒大の褐色の冬芽が左右に対生しているのが分かります。その対生の冬芽が上下で90度ずれて付いていますね。十字対生というやつです。

③
ここはカタクリの自生地。鮎道の途中にあります。カタクリはなぜか北向き斜面を好むんですよね。今は何もないですが、あと二月で花を咲かせるでしょう。そのときのために今年も落ち葉掻きをしました。

④
ヤマツツジの夏葉。夏に展開してそのまま越冬する葉です。春葉は秋に落葉します。夏葉は小さくて数も少ないのですが、何か特別な役割があるのでしょうか。
⑤
これはダンコウバイの冬芽です。シュッとしているのが葉芽、ぷっくりとしているのが花芽で、早春に花を付けます。

⑥
ヤブツバキ。赤い花の方に目が行きがちですが、葉の方もなかなか特徴的。厚く硬く光沢があって、多少の湾曲もあり、強い日差しや潮風などに耐えられるようになっています。西日本の沿岸部に広がる照葉樹林の中心的な樹木です。ペラペラの葉を付ける樹木よりもたくさんのエネルギーを使うでしょうが、秋に落葉することもなく長持ちするでしょう。

|
|
|
|
2025年1月29日(水)

①
アラカシの堅果。ほとんどは枝から落ちていて、かろうじて残っていたものです。ブナ科の樹木の果実では花が咲いた年の秋に成熟するものと翌年の秋に成熟するものがあり、アラカシは前者です。成熟時期の違いのほか、殻斗(帽子)の形状、果実の模様など、樹種によって数パターンの組み合わせがあります。

②
これはシャクナゲの冬芽。おそらく園芸種ではないかと思います。重なる芽鱗の様子が何だかタケノコみたいです。
③
内裏池で久しぶりにカワセミを見ました。オスのようです。アシの茎に停まって、根気よく狙いを定めていました。この池に魚はいないと思いますが、何を狙っているのだろうか。

④
多目的広場のハリエンジュ。この時期、マメ科に特有のえんどう豆のような果実を付けています。痩せた果実で同科のネムノキなども似たような形状。とても食べ応えがある感じではありませんね。ただ、この姿がむしろスタンダードであって、えんどう豆のぷっくりとした姿と比較すると、えんどう豆がいかにう改良されたものかが分かります。

⑤
サザンカ(の園芸種)の花冠をアップで。野生種のサザンカは花が純白なので、これが園芸種であることはすぐに分かります。おそらくタチカンツバキという種ではないでしょうか。花冠の中央にはたくさんの雄しべがあり、中心には雌しべの花柱が見えます。雄しべの数を数えてみたらなんと65個もありました。こも数の多さはいったいどういう意味があるのか。密生させることによって、訪れた虫の足場になるようにしているのかも。この雄しべ群の上に乗っかるとすると、自家受粉は避けられそうですね。(yamaneko説)

|
|
|
|
| |

