2022年3月5日(土)

①
南広場。イチョウの枝から芽が伸び始めています。メリメリと音がしてきそうな感じ。

②
クリスマスローズが咲きました。高い木立の下の半日陰の環境ですが、毎年ここで元気に咲いています。

③
園の正面入口へ。ようやくウメが満開となりました。今年の冬は寒い日が続きましたからね。

④
早春の使者、オオイヌノフグリ。そよ風にみんな揃って揺られていました。その姿の可愛いこと。
⑤
大田切池へ下りていく途中のカワヅザクラ。咲き始めです。

⑥
これはハコネウツギの果実。去年実って既に種子を出した後ですね。

⑦
ロニセラが五分咲き程度になっていました。春の陽射しを透かすカーテンのよう。花の形はスイカズラにそっくりです。

⑧
イヌコリヤナギ。キャップのような固い芽鱗が取れて、ふわふわの雄花序が顔を出しまています。

⑨
大田切池に張り出したエゴノキ。水面(みなも)からの反射にも暖められています。
⑩
サルトリイバラの蔓がアートのようだったので。

⑪
南広場に戻ってきました。見上げるとヤマハンノキの雄花序が完全に開花状態。高いところから花粉を飛ばすと、ずいぶん遠くまで広がるでしょうね。

|
|
|
|
2022年3月12日(土)
①
キブシの花穂がほぐれ始めてきました。まだ全体に固そうですが、いずれ珠暖簾のようにぶら下がります。

②
尾根緑道沿いの植栽にはいくつが種類がありますが、これrはアジサイ。若々しい葉が展開し始めています。

③
ヤブツバキ。まだいきいきと頑張っています。

④
カワヅザクラが満開を迎えていました。今年はずいぶん遅かった。

⑤
尾根道の西端から鮎道へ。木漏れ日がもう春です。

⑥
カタクリの保護エリアへ。葉がちらほら伸び始めていました。気の早いやつは写真のように花茎を伸ばしていました。蕾も膨らんできて、もうすぐ咲きそうです。でもエリア全体ではまだ芽吹き始めといったところ。

⑦
モミジイチゴもようやく咲き始めたところです。

⑧
こちらはシュンラン。右の花茎はまだ見るからに固そうです。

⑨
これはカンゾウかな(ちょっとシュっとしすぎか?)。ちなみに、生薬のカンゾウは、マメ科の別のもの。

⑩
大田切歩道橋からの入口近くのフサザクラ。ここ数日暖かかったので、蕾がほころび始めていました。開花は来週あたりか。

⑪
春の野辺といったらホトケノザ。よく見るとオリンピックの聖火トーチのような形をしています。

⑫
野草見本園へ。
これはエヒメアヤメか? ヒメシャガともちょっと違うような。そもそも開花時期は4月中旬頃だと思いますが、本物か?

⑬
シロバナタンポポですね。これも植栽だそうです。自生地は関東西部以西だそうで、このあたりは自生はないのかもしれません。

|
|
|
|
2022年3月19日(土) その1
①
キブシが咲きました。なんとも言えない薄緑色です。この花序は雄花ですね。

②
南広場では桜が満開になっていました。品種は不明。

③
マルバウツギの芽吹き。去年の果実との共演です。

④
野草見本園へ。いました、春の使者カタクリ。

⑤
パークセンターの横の花壇でサンシュユが満開になっていました。花火みたいです。

⑥
大田切池に向かって下って行きます。コブシも咲き始めましたね。純白で、輝いています。

⑦
コガモ。繁殖地はシベリア方面だそう。もうじき長旅に出るのかい。

⑧
これはクマシデの花穂が伸び始めたところ。どこかメカっぽい?

⑨
「つくし誰の子、スギナの子」 つくしも最近あまり見かけなくなったような。

⑩
芝生広場。今日は家族連れが一組と中国ゴマ回しの動画撮影をしていた女性が一人だけ。静かでした。
(その2に続く)

|
|
|
|
2022年3月19日(土) その2

①
藪の中で静かに佇むシュンラン。多摩丘陵に本格的な春が来た。
②
これはヒサカキ。葉裏に隠れるように咲きます。花には独特の匂いがあり、これを嫌という人もいますが、yamanekoは待ちかねた早春の香りとして、好きな匂いです。

③
芝生広場から鮎の道に上る小径。

④
この一週間でフサザクラが満開になっていました。季節の進み具合に驚きます。

⑤
ウグイスカグラ。まだ他に花のない2月頃から咲き始めるので、いつもその頃に撮影して、花の盛りにはスルーすることが多かったです。この姿が本来の花の姿なんですね。

⑥
モミジイチゴです。下向きに咲くので、いつも背景は空になります。
⑦
カタクリも咲き始めました。
ああ、今年もこの季節がやってきたか。(しみじみ)

⑧
スタイリッシュな二人。まさにスプリングエフェメラル。

⑨
ヤブツバキをアップで。雄しべの密集度がすごいです。鮮やかな赤と黄。案外ポップな花です。

⑩
尾根道にやって来ました。アセビも綺麗に咲いています。豪奢ですね。
⑪
こちらも尾根道に植栽されているジンチョウゲ。辺りに芳香が漂っていました。「春よ来い」に歌われているとおり、春を呼んできてくれたようです。

|
|
|
|
2022年3月27日(日) その1

①
ユキヤナギ。花が雪のように白く、その花穂がヤナギのようにしな垂れることから付いた名前です。流れの際に生えることが多く、大水の時には茎が折れ株を守る戦略をとる植物です。
②
紫色が鮮やかなキランソウ。これが咲くと春本番です。
 ③ ③
ヤブザクラです。小山内裏公園には何種類かの自生の桜がありますが、これはそのうちの一つ。

④
花冠の後ろ側の萼片は5個で、その根元がくびれた槍の穂先型をしています。

⑤
野草見本園へ。これはヒトリシズカです。白い糸状のものは雄しべ。葯は花糸の先端ではなく、花糸の根元に付くという変わり者。花被(花びら)はありません。

⑥
ニリンソウも咲き始めましたね。この時期、野草見本園を訪れるたびに新しい花が咲いています。

⑦
パークセンターの横に生えている大きなヤナギ。これはフリソデヤナギという園芸種だそうです。

⑧
トンネル上の歩道を歩くと、この時期は黄色の垣根が見られます。これはおそらくシナレンギョウ。花冠の裂片の幅が狭く、また、枝が直立するのがレンギョウやチョウセンレンギョウとの違いとされています。

⑨
早実グラウンドとの境の道を行きます。白花のヤブツバキ茂みの奥に隠れるように生えています。

⑩
モミジの若葉。早くも展開中です。今年は冬が寒かったせいか、春先の植物の生長の順番がバラバラみたいです。

⑪
内裏池の前までやって来ました。植栽のトサミズキ。房が垂れ下がるように花序を伸ばしています。
(その2に続く)
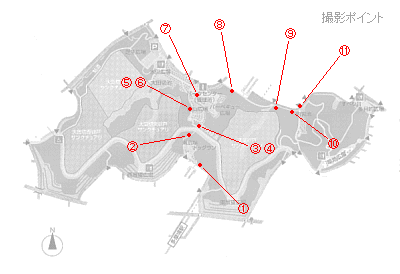
|
|
|
|
2022年3月27日(日) その2

①
内裏池の谷戸を奥に向かうと自生のタマノホシザクラがあります。周囲には接ぎ木で増やした株もいくつかあり、それぞれ大きく育ってきています。

②
花冠は下を向くので、どうしてもローアングルに。背景はまさに花曇りです。

③
名前の基となった星形の萼片。さっき見たヤブザクラの萼片とは明らかに形が違っています。

④
タチツボスミレ。最もポピュラーなスミレです。名前は立ち上がったツボスミレという意味だそう。

⑤
ミチタネツケバナ。ヨーロッパなどを原産地とする帰化植物です。

⑥
ミツバウツギの芽吹き。葉とともに花芽も姿を見せています。

⑦
ニワトコも葉と花芽を展開し始めていました。ニワトコの枝や幹を煎じて水飴状にしたものを湿布薬としたことから、別名を接骨木(せっこつぼく)というそうです。

⑧
これはコナラの若葉。軟毛が密生しているからか、銀色に輝いて見えます。

⑨
木立の上の方から、コココココーン、と聞こえてきたので探していると、いました。アオゲラです。逆光の中、ほぼ垂直に見上げるようにして写真を撮りました。

⑩
草地広場へ。クスノキに新しい葉の芽が伸びつつありました。常緑樹なので現役の葉があるうちに次の葉が伸び出します。

⑪
満開のコブシ。これから春がぐんぐん進んでいきます。

|
|
|
|
| |

