2017年12月2日(土)

①
今年も師走になりました。小山内裏公園の紅葉ももう終わりに近づいています。イタヤカエデはバナナ色です。

②
植栽のアジサイ(韻)。日当たりの良いところにある株はこんなに紅葉します。

③
公園の西端に向かう尾根道です。
④
鮎道へ。こんなところで日がな一日過ごすのも良いかも。寒いですが。

⑤
ダンコウバイの黄葉。この公園ではここでしか見かけません(サンクチュアリ内は知らない。)。

⑥
ジャノヒゲの実(種子?)。自然界にあるのが不思議に感じる色をしています。

⑦
芝生広場脇にあるメタセコイア。これも紅葉ですね。褐葉か。

⑧
芝生広場から大田切池に下りて行く巻き道。通る人も少なく、気持ちの良い小径です。

⑨
野草見本園のツワブキ。この時期の数少ない花の一つです。

⑩
ドウダンツツジの紅葉。陽を透かしてカラフルな感じに。

|
|
|
|
2017年12月7日(木)

①
マルバウツギ。陽当たりの悪いところに生えているので、黄葉もあまり進みません。花は可愛いのですが、今年は少ししか付きませんでした。

②
尾根道沿いに植栽されているサザンカ。

③
コゴメウツギの黄葉は素朴な色合い。冬の訪れを感じます。
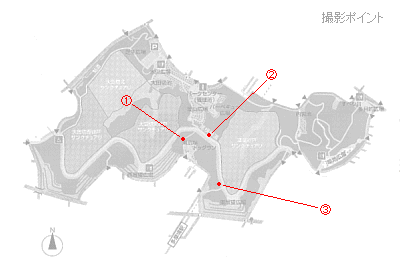
|
|
|
|
2017年12月9日(土)

①
今日は今年最後のガイドウォークに参加。冬晴れですが空気はシンと冷えています。
このフクロウのシルエットは、ウスタビガの繭です。
②
スギヒラタケが干からびたような感じのキノコ。何でしょうか?

③
枝から枝に飛び移る瞬間をキャッチ。内裏池にやって来ているカワセミです。

④
池の対岸の林縁にカラスザンショウが実を付けています。メジロなどが食べに来るそうです。
⑤東屋の脇の紅葉に黄葉。今年最後の輝きかな。

⑥
多目的広場のナンテン。この辺りはもう日が陰っていました。

⑦
キボシカミキリ。甲が一部割れていたし、寒さにかなり弱っていました。もうじき命を終えるのかもしれません。

⑧
ツバキの葉裏で越冬するウラギンシジミ。一般的に、成虫で冬を越す昆虫でも死亡率は高いそうで、春を迎えるものは多くはないのだそうです。

⑨
ヤブムラサキの葉は触るとフワフワした手触り。果実の萼の部分もモフモフしています。

⑩
秋も深まり、ゴンズイの実もずいぶん少なくなりました。

⑪
枝先でドライフラワー化していたクヌギ。

⑫
サイハイランの葉ではないかとのこと。ただ葉が2枚出ないと花は付けないそうです。再来年以降に期待か。

|
|
|
|
2017年12月13日(水)

①
大田切池が今シーズン初めて全面凍結しました。寒いはずです。

②
シロダモの冬芽。周囲の硬い葉も元はこのような冬芽の中にありました。

③
ジュウガツザクラ。季節外れに咲いてしまった桜のようですが、本来この時期に咲きます。寒さに負けるな。

④
ソシンロウバイの蕾です。もうじき花の時期になります。

⑤
尾根緑道に植栽されているコムラサキ。いい具合に枯れていますね。

|
|
|
|
2017年12月16日(土)

①
小山内裏公園にも色が少なくなってきましたが、そんな中でガマズミの実はよく目立っています。

②
クマシデの果穂。もうドライフラワー状態です。

③
ヤマハンノキ。春まだ浅い3月上旬に開花します。開花といっても棍棒状の雄花序がほぐれるように伸びて、鱗片の隙間から花粉を飛ばすのです。

④
燃え立つようなコナラの黄葉。

⑤
林の中の梢に何かの巣が懸かっていました。もう空き家でしょうね。

⑥
夏場、薄暗いほどに繁っていた森が、今はこんなに明るく開けた空間に。

⑦
ニシキギの実。やや干からびたような状態になっていました。

⑧
エノキに7、8羽ほどのイカルの群れが訪れていました。乾燥し硬くなったエノキの実をパキッ、パキッと割って、しきりに食べていました。

⑨
群れが去った後、木の下にいってみると、イカルが割ったエノキの実の破片が一面に散らばっていました。
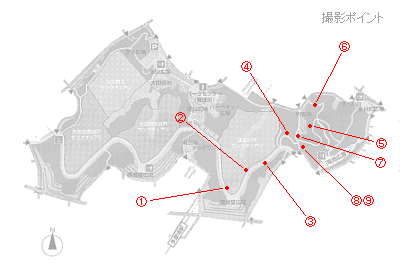
|
|
|
|
2017年12月21日(木)

①
キンキンに冷えた朝の空気。ようやく陽が差してきました。(明日が冬至)
遠くに大山が見えます。

②
この時期、マユミの朱色にホッとします。

③
尾根道沿いに植栽されているアジサイの冬芽。冬至は陰極まって陽に転ずるめでたい日とされています。アジサイもまだ遠い春に向けてちゃんと準備をしているんですね。

④
マルバウツギの黄葉は和テイスト。来年はたくさん花を付けてほしいです。

|
|
|
|
2017年12月23日(土)
①
南広場、ドッグランの縁に植えられているコウテイダリアですが、花期は短く、もう実を付けています。下の方に萎れた花が残っていますね。

②
パークセンターの花壇にあるベニバナミツマタ。名前のとおり枝が三つ叉になっています。

③
ヤマコウバシは枯れ葉になっても枝から離れることはありません。

④
九反甫谷戸。こんなに明るいのは冬だけです。夏には薄暗い谷戸をウバユリが一面埋め尽くします。

⑤
九反甫谷戸から小径をたどり尾根上へ。ここは多摩丘陵の主稜線で、多摩丘陵の浸食が未発達だった太古の昔には、この高さの台地が広がっていたとのことです。

⑥
ピーヨ、ピーヨ。鋭い鳴き声はヒヨドリです。褐色の過眼線がブーメラン状でかっこいい。

⑦
残り柿、なんですが、今年はちょっと残り過ぎ。残念ながら渋柿だそうです。
⑧
周りの木々の葉が落ちて、この坂道にようやく陽が届くようになりました。そしてモミジも色づきました。

⑨
園の南東側の入口。急な階段を上ると尾根道です。夏場は鬱蒼とした森で、尾根道などまったく見通せないんですが、今はスケルトンですね。
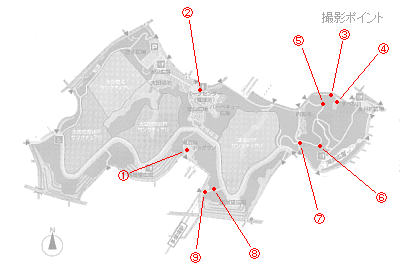
|
|
|
|
2017年12月27日(水)
①
今日は今年最後の谷戸山の会に参加。コナラ、マユミ、ヌルデ、ミズキなど6本を間伐。休憩時間に見たカラスウリ。完全に冬枯れです。

②
作業を終えて尾根道をパークセンターに向けて戻ります。
植栽のサザンカ。赤い花冠になんだかホッとします。

③
東展望台脇にあるこんもりとした林。この時期、林床の隅々まで光が入っています。

④
ガマズミの実。イクラみたい。

⑤
尾根道沿いのコナラにキイロスズメバチの巣が懸かっていました。かなり高いところにあり、葉を落とすこの時期までまったく気がつきませんでした。もう空っぽでしょう。

|
|
|
|
2017年12月30日(土)

①
2017年最後のヤマネコ散歩。
南広場の上にあるこの雑木林。何かというと会員制ドッグランなんです。贅沢な立地ですよね。

②
マンション群の向こう、丹沢山地から富士山がちょっとだけ頭を覗かせています。

③
尾根道沿いに植栽されているアオキ。赤く色づいてきました。

④
ナンキンハゼの種子が青空をバックに輝いています。白いのは脂肪に富んだ蝋質の物質で、ヒヨドリなどが好んで食べます。

⑤
クスノキが春の芽吹きに備えています。芝地広場で。

⑥
残り柿をついばんでいるのはシジュウカラ。それは渋柿だぞ。

|
|
|
|
| |

