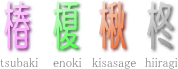2017年8月5日(土)

①
園内のあちこちでキツネノカミソリが咲き始めました。

②
フェンスに絡んで伸びているシオデ。

③
いつのまにかクサギも咲いていました。この木は実の時期にも鮮やかな色彩で楽しませてくれます。

④
オトコエシ。漢字で書くと「男郎花」。「女郎花」はオミナエシです。
⑤
清楚な花。でも名前はヘクソカズラ。

⑥
シュロソウの花は暗褐色。なかなか珍しい花の色です。

|
|
|
|
2017年8月9日(水)

①
ツユクサ。二枚貝のようになった苞の中から顔を出しています。その名のとおり葉に露を乗せていました。

②
尾根道から里山広場に下りていく斜面にはオトギリソウが花を咲かせます。

③
このところぐずついた天気の日が続き、林床は湿り気たっぷり。キノコにとっては嬉しい環境でしょう。
④
涼しげなオオバギボウシ。

⑤
キバナコスモス。パークセンター前の花壇です。

|
|
|
|
2017年8月11日(金)

①
イヌザンショウの実。表面には濃い緑色の斑点が密に付いています(ゴルフボールのディンプルのよう)。

②
エノキの実が若干色付いています。

③
傘を広げる前のキノコ。可愛いです。

④
これはゴーヤの花ですね。

⑤
ドッグランの柵沿いに植えられていた百日草。鮮やかな色合いです。

|
|
|
|
2017年8月12日(土)

①
今日はガイドウォークに参加。朝方まで降っていた雨も上がり、日が差してきて暑いです。
これはミンミンゼミ。名前のとおり、ミーンミンミンミンと鳴きます。

②
アベリアの花を訪れたトラマルハナバチ。

③
8月上旬。キツネノカミソリの時期です。

④
ヤブソテツの葉で休むムラサキシジミ。こんなに派手な姿ですが、羽を閉じると薄茶色一色の目立たない姿になります。

⑤
ミツバウツギの実。

⑥
ウワミズザクラの実は美味しそうに熟しています。ツキノワグマの好物だとか。

⑦
オオカマキリと対峙するアカボシゴマダラ。両者間合いを計って微動だにしません。

⑧
コバノカモメヅルの花。小さく目立たない花です。

⑨
エノキの葉に停まっていたナナフシ。レンジャーの人に聞いたところニホントビナナフシではないかとのこと。

⑩
ヒグラシの雄。本来朝夕に鳴きますが、日中でも日が陰ったりすると寂しそうに鳴き始めます。

⑪
ツリバナの若い実。熟すと割れるところが筋になっていますね。

⑫
公園の正面入口脇にあるハギ。ミヤギノハギか?

|
|
|
|
2017年8月18日(金)

①
ナンキンハゼが実を付けました。花の様子からは想像できない姿です(花はこちら)

②
北米からの帰化植物のオオニシキソウ。花は極小です(3mmほど)
③
これぞキノコといった姿のキノコ。名前は…分かりません。

④
早くもヤマボウシの実が色付いていました。こんなに赤いのは周囲を見渡してもこの株(植栽)だけでした。

⑤
シュロソウの花。野草見本園で。
⑥
ヤマホトトギスが咲くとそろそろ秋の気配。

⑦
カリガネソウの花。これから盛りに向かいます。

|
|
|
|
2017年8月21日(月)

①
タカサゴユリが咲き始めました。白磁のような曇りのない白色です。
②
サンショウは実を付けています。

③
こちらはマユミの若い実。

④
クマノミズキの花序の茎が赤く色づき始めています。秋が深まり茎だけになった花序が落ちているのを見ると、まるで赤サンゴのよう。
⑤
スマートな姿のカラスビシャク。確かに柄杓のようにも見えます。マムシグサやムサシアブミなどと同じ仲間です。

⑥
オオブタクサが茂り始めました。秋の花粉症の元になる植物の一つです。

⑦
ノブドウの実。これkらもっと色が濃くなります。カラフルですね。

|
|
|
|
2017年8月25日(金)

①
野草見本園へ。これはノコンギク。これから盛りに向かいます。

②
ツリガネニンジン。「ツリガネ」には花の形からなるほどと思えますが、「ニンジン」とは。きっと根が人参みたいなんでしょうね。

③
ヤブミョウガ。花と実が混在しています。
④
ミズヒキの花。大きさは3mmほどです。この花を見ると秋がそこまで来ているなと感じます。

|
|
|
|
2017年8月27日(日)

①
アオツヅラフジの花。一つの大きさは5mmほどです。
②
同じツルに実になっているものもありました。

③
オトコエシの花を真上から。

④
線香花火のようなセンニンソウの花です。

|
|
|
|
| |