2016年11月3日(木)

①
ツチイナゴ。成虫で冬を越す生活サイクルですが、寒さに強いわけではなく、厳しい寒さが続くと死んでしまうのだそうです。
②
オニドコロの花と実。軍配のようなものが蒴果です。

③
経1cmほどの小さな薄紫色の花。アメリカイヌホオズキです。いわゆる雑草ですが、よく見ると可憐な花です。

④
更に小さなハキダメギクの花。愛嬌のある姿をしています。

⑤
ウシハコベの花も見逃してしまいそうになるほど小さいです。丈自体はハコベに比べて大柄なので「ウシ」の名を付けたのだとか。

⑥
ナギナタコウジュの花穂。この花を初めて見たのは広島県西部の恐羅漢山の麓でした。

⑦
アカシデの果穂がいい感じに朽ちてきています。秋深し、です。
⑧
見上げるほどの高さのトチノキ。黄葉し始めていました。

⑨
隣の日本品質保証機構の敷地に生け垣として植栽されているヒイラギモクセイ。

⑩
内裏池の谷戸にシロヨメナの花です。
⑪
これはイタドリの実ですね。3個の花被片が弓矢の羽根のように合わさって、その中にゴマ粒状の実を包んでいます。

⑫
サクラの紅葉は一斉に赤くならないところに風情あり。
⑬
公園正面入り口のシンボルツリー、ケヤキです。街路樹では電線などがあり伸びすぎないよう毎年剪定されたりしますが、この木は自然の樹形に近いです。
⑭
野草見本園で。ツワブキは今が盛り。葉もつやつやとしています。

⑮
これはコマツナギの実です。これまであまり気にしたこともありませんでしたが、こんな姿をしていたんですね。
⑯
カラスウリの実は格好の被写体なのですが、いかんせん背景がごちゃごちゃしていて残念なことに。

⑰
南広場のトウカエデ。紅葉が始まっていました。
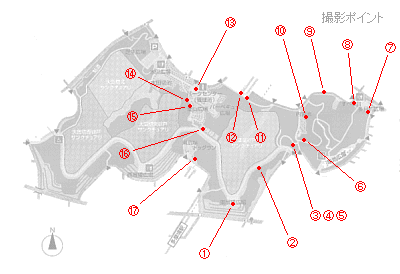
|
|
|
|
2016年11月10日(木)
①
わんわん広場に植栽されているコダチダリア。背丈は4mくらいあります。さすが「皇帝」。

②
野草見本園で。最後まで頑張っているコバギボウシ。寒さにじっと耐えている感じです。

③
いつのまにかカツラはすっかり落葉していました。もっと黄葉を愛でておけばよかった。

④
南広場入口近くにあるイヌザンショウです。実ができていました。
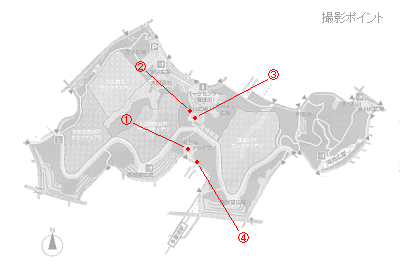
|
|
|
|
2016年11月12日(土)

①
今日は小山内裏公園主催の野鳥観察に参加。これはハクセキレイです。パークセンター前の芝生で。普段はせわしなく動き回るのですが、しばらくじっとしていました。寝起きか?

②
公園の東側に向かいます。キブシには来年の花芽が垂れ下がっていました。既に夏にはできていましたが、その頃は垂れ下がらず枝に沿って伸びていました。

③
早稲田実業高校の王貞治記念グラウンドとの境界に植えられているトチノキ。陽が当たると茶色の紅葉も鮮やかですね。

④
青空を背景にトチノキを真下から。③とは別のトチノキです。

⑤
内裏池までやってきました。ここにはカルガモが1羽とマガモの雌らしきものが2羽が休んでいました。写真はそのマガモらしきもの。レンジャーの方も何かの交雑種ではないかと言っていました。

⑥
カラスザンショウにたくさん実ができていました。普段良く通る南広場のカラスザンショウにはまったく実が付かないのは、この木が雌雄異株だからでしょう。

⑦
草地広場で。クスノキの実が熟し始めていました。鳥たちは好んで食べるそうですが、人間様の口には合わないようです。

⑧
これってカマツカの実ですよね。公園内に自生するところを2箇所だけ知っていましたが、こんなところに植栽されていたとは。実は随分前に食べたことがあります。確かリンゴのような味がしたような記憶が。
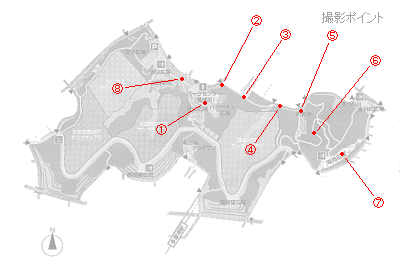
|
|
|
|
2016年11月16日(水)
①
ツタの紅葉です。南広場近くで。

②
ナメコ的な何か。一抱えほどもありました。

③
今朝は尾根道を西側へ。コブシの黄葉も綺麗です。

④
マユミの実。見た目と違いけっこう硬いものです。

⑤
これはセンブリでは。花が開いていないのはまだ陽が差さないからか。西展望台の先で。

⑥
キブシも風情のある紅葉をするんだと、新たな発見。
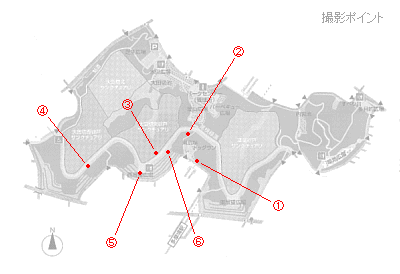
|
|
|
|
2016年11月20日(日)

①
南広場。去年、今年と紅葉は今ひとつな感じです。

②
野草見本園のリンドウ。花が少なくなったこの時期、まだ元気です。

③
カマツカの黄葉。日当たりがいいところだとこんなに鮮やかな黄色になるんですね。
④
大田切池の畔のコブシです。名前の由来となった集合果はまだ中から朱い種子が出てきていません。

⑤
ヌルデ。紅葉のバックに青空は鉄板です。

⑥
深紅の葉はニシキギ。枝に翼があるのが特徴です。
⑦
ムラサキシキブの残り実。芝生広場脇で。

⑧
UFO? 街路灯? コヤブタバコの集合果です。

⑨
渋い黄葉はコゴメウツギ。

⑩
晩秋の鮎道。

⑪
ユキヤナギも紅葉するんですね。この公園に生きるみんな、秋の装いを楽しんでいるみたいです。
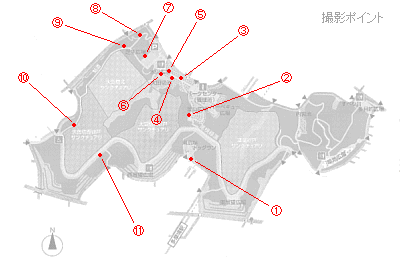
|
|
|
|
2016年11月23日(水)

①
どんよりと曇り肌寒い一日。明日の朝には異例の積雪との予報も。
イヌザンショウ黄葉。レモンイエロー系です。

②
南広場のトウカエデです。ここには数本植栽されていますが、木によって落葉の進み方が大きく異なります。
③
今日はめずらしく南西側の入口から。
ツタの紅葉グラデーションですが、葉が小さいと糖分の生成が十分でなく、紅葉もしづらいということなのでは。
④
晩秋のカラスウリ。いや、もう初冬か。

⑤
ガマズミの葉も黄葉するんですね。これまで枝に葉のない状態で赤い実を見ることが多かった気がします。
⑥
アカメガシワ。葉緑素が壊れ始め、元からあった黄色の成分が見えるようになってきています。

⑦
ミズキの黄葉も同じ仕組み。

⑧
ウワミズザクラも色づいています。多摩丘陵の秋ももう終わりに近いようです。
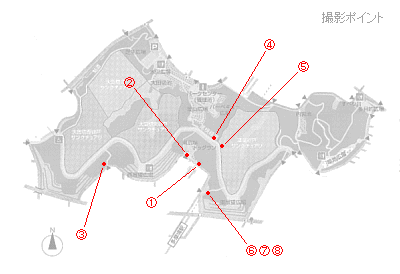
|
|
|
|
2016年11月26日(土)

①
2日前に降った初雪。北向き斜面にはまだ消え残っていました。11月の初雪は50数年ぶりだそうです。
②
野草見本園へ。これはジュズダマ。最近植えられたもののようです。丸いのは果実ではなく雌花の一部が硬く変化したもの。真ん中に柱頭が通る管状の穴が空いていて、子供の頃、そこに糸を通して繋げ、ネックレスを作る遊びがありました。
③
バーベキュー広場にあるヒマラヤスギ。高さ20mくらいはあるでしょうか。紅葉は下から進んでいくようです。

④
モミジバフウは落葉が進み、残った葉がモビールのようになっていました。これはこれで風情あり。

⑤
一枝に様々な彩りを見せるイロハモミジ。もうそろそろ日が傾いてきました。もうじき一年で最も日の入りが早い時期になります。
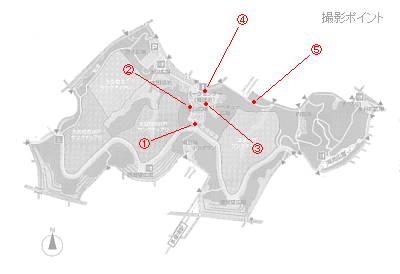
|
|
|
|
2016年11月30日(水)

①
冷え込みの厳しい朝。まだ初冬なんですが。これはトウカエデの果実。たくさん枝に残っていますが、枯れているのか?

②
クロモジの黄葉です。薄暗い林縁にポッと温かみが差したよう。

③
地味な紅葉ですね。これはアカシデ。

④
少し陽が当たってきました。ミズキの枝の上のシジュウカラと目が合ってしまいました。
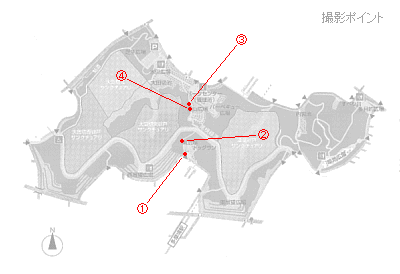
|
|
|
|
| |

