پ@
‚Q‚O‚P‚T”N‚UŒژ‚Q“ْپi‰خپj
پ@
‡@
پ@Œِ‰€‚ج“Œ’[پA‘½–ع“IچLڈê‚ة‰؛‚ء‚ؤ‚¢‚ٹK’iپB‚¯‚ء‚±‚¤‹}‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡A
پ@ƒzƒ^ƒ‹ƒuƒNƒچ‚ھ‚؟‚ه‚¤‚اŒ©چ ‚إ‚·پB‰شٹ¥‚àگگپX‚µ‚’£‚è‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپB
پ@
پ@

‡B
پ@‚±‚ê‚حƒIƒ‚ƒ_ƒJ‚ج—tپBèVپi‚₶‚èپj‚جŒ`‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ؤپA•گ‰ئ‚ج‰ئ–ن‚ة—p‚¢‚ç‚ꂽ‚»‚¤‚إ‚·پB‚و‚ژ—‚½‚à‚ج‚ةƒAƒMƒiƒV‚ج—t‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAچו”‚إˆل‚¢‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBپ@پ©‚»‚جچו”‚جˆل‚¢‚ً‚و‚Œ©‚é‚ئ‚ق‚µ‚ëƒAƒMƒiƒV‚©‚àپB
پ@
پ@

‡C
پ@Œ©ڈم‚°‚éƒgƒ`ƒmƒL‚ج—t‚ھŒُ‚ً“§‚©‚µ‚ؤ‘u‚â‚©‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡D
پ@ƒ^ƒCƒ}ƒcƒoƒiپB–kƒAƒپƒٹƒJŒ´ژY‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB‚ب‚؛‚ةپu–ى‘گپvŒ©–{‰€‚ةپB
پ@
پ@

‡E
پ@Œِ‰€‚ض‚جٹK’i‰ˆ‚¢‚جگA‚¦چ‚ف‚ةƒEƒپƒGƒ_ƒVƒƒƒN‚ھ‘ه—ت”گ¶‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚à‚ج‚·‚²‚¢گ”‚ھ—گ•‘‚µپA‚»‚±‚¢‚ç’†‚إŒً”ِ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@
پ@

پ@
پ@
|
|
|
|
پ@
‚Q‚O‚P‚T”N‚UŒژ‚U“ْپi“yپj
پ@

‡@
پ@–ى‘گŒ©–{‰€‚ةƒgƒ‚ƒGƒ\ƒE‚ھچç‚«ژn‚ك‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ꂼ‚ê‚ج‰ش•ظ‚جگو’[‚ھ‚â‚â‰E‚ة‹ب‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚±‚ë‚ھ”bŒ^پB
پ@
پ@

‡A
پ@‚±‚جگë‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حƒ`ƒ‡ƒEƒWƒ\ƒE‚ج‰تژہپB‰ش‚جژp‚©‚ç‚ح‘z‘œ‚à•t‚©‚ب‚¢ژhپX‚µ‚³پB
پ@
پ@

‡B
پ@ƒLƒٹƒMƒٹƒX‚ج’‡ٹش‚ج‰½‚©پB‰H‚ھڈ¬‚³‚¢‚ج‚إ‚ـ‚¾ژq‚ا‚à‚ب‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپB
پ@
پ@

‡C
پ@چ،“ْ‚حŒژ‚ةˆê“x‚جƒKƒCƒhƒEƒHپ[ƒNپB”ِچھ“¹‚ً“Œ‚ةŒü‚©‚ء‚ؤٹدژ@‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚حƒNƒٹ‚ج‰شپB“Œ“W–]چLڈê‚ج‹ك‚‚إپB
پ@
پ@

‡D
پ@ƒjƒKƒL‚جژہپBڈt‚ة‰ش‚ًچç‚©‚¹‚½–طپX‚ح‚à‚¤ژہ‚ً•t‚¯ژn‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡E
پ@‚©‚ئژv‚¦‚خ‚±‚ê‚©‚ç‰ش‚ًچç‚©‚¹‚é‚à‚ج‚àپB‚±‚ê‚حƒNƒ}ƒmƒ~ƒYƒL‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡F
پ@ƒ€ƒ‰ƒTƒLƒVƒLƒu‚ج‰ش‚ح‚à‚؟‚ë‚ٌژ‡گFپBڈ¬‚³‚ب‰ش‚ھ–§گ¶‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@
‡G
پ@‰ش‚جڈ¬‚³‚³‚©‚ç‚·‚ê‚خ‚±‚جƒLƒkƒ^ƒ\ƒE‚ھˆê–‡ڈمژèپB’¼Œa‚Tmm‚ظ‚ا‚ئ‚©‚ب‚èڈ¬‚³‚¢‚إ‚·پB
پ@
پ@
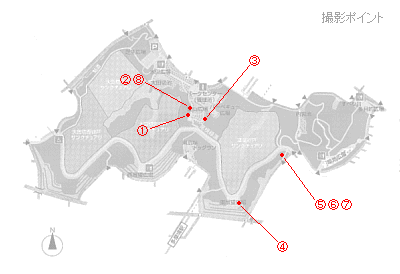
پ@
پ@
|
|
|
|
پ@
‚Q‚O‚P‚T”N‚UŒژ‚P‚O“ْپiگ…پj
پ@

‡@
پ@‰€‚ج“ى“Œ‘¤‚ج“üŒû•t‹كپBƒNƒ}ƒmƒ~ƒYƒL‚ھچç‚«ژn‚ك‚ـ‚µ‚½پB
پ@
پ@

‡A
پ@”ِچھ“¹‰ˆ‚¢‚ةگAچح‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éƒAƒWƒTƒCپB’†گS•”‚ة‚ ‚é—¼گ«‰ش‚ح‚ـ‚¾هQ‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡B
پ@گ¼“W–]چLڈê‚©‚çپB‹´–{‚جژsٹX’n‰z‚µ‚ة‘هژR‚ھ–]‚ك‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡C
پ@گHژ–’†‚جƒKƒrƒ`ƒ‡ƒEپB‘ه‚«‚بƒCƒ‚ƒ€ƒV‚ً‰ء‚¦‚ؤ‚â‚ء‚ؤ‚«‚ؤپA‰½‰ٌ‚àژ}‚ة‘إ‚؟•t‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@
پ@

‡D
پ@چ،“ْ‚ح’JŒثژR‚ج‰ï‚إƒNƒڈ‚جژہگ¶‚ج•c‚ًŒ@‚èڈo‚µ‚ـ‚µ‚½پBڈ¬ژR“à— Œِ‰€ژü•س‚جڈ¬ٹwچZ‚إ‚حژِ‹ئ‚جˆêٹآ‚ئ‚µ‚ؤژ\‚جژ”ˆç‚ًگد‹ة“I‚ةچs‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إپA‘ه—ت‚جƒNƒڈ‚ج—t‚ً•K—p‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ج‚±‚ئپBچ،“ْ‚حپAƒNƒڈ‚ج–ط‚ج‰؛‚إچ،”N‰èگپ‚¢‚½ژہگ¶‚ً‰½ڈ\ٹ”‚©Œ@‚ء‚ؤپi‚»‚ج‚ـ‚ـ‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ؤ‚àŒح‚ê‚ؤ‚¢‚‰^–½پjپA•ت‚ج“ْ“–‚½‚è‚ج—ا‚¢ڈêڈٹ‚ةˆعگA‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚±‚إ‚ ‚é’ِ“x‚ـ‚إˆç‚ؤ‚ؤپAٹeٹwچZ‚ةٹ”‚²‚ئ’ٌ‹ں‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡E
پ@چى‹ئ’†‚ةŒ©‚آ‚¯‚½ƒjƒڈƒgƒR‚جژہپB‘پ‚‚àگش‚¢ژہ‚ً•t‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡F
پ@—رڈ°‚ة‚ح‚±‚ٌ‚ب‰آˆ¤‚¢‰ش‚àƒ€ƒ‰ƒTƒLƒJƒ^ƒoƒ~پBˆê‰پA—v’چˆسٹO—ˆگ¶•¨‚ةژw’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡G
پ@ƒqƒپƒVƒƒƒ‰پBŒo‚T‡p‚ظ‚ا‚جڈ¬Œ^‚ج‰ش‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡H
پ@ƒ„ƒuƒcƒoƒL‚ةژہ‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBژ“‚µ‚ׂج’Œ“ھ‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ•ھ‚©‚è‚ـ‚·پB‚ـ‚¾‚ـ‚¾–¢ڈnپB‚â‚ھ‚ؤ‰ت“÷‚ج•”•ھ‚©Œْ‚چd‚‚ب‚èپA“~‚ة‚ب‚éچ ‚ة‚ح‚R—ô‚µ‚ؤ’†‚جژيژq‚ًکIڈo‚³‚¹‚ـ‚·پB
پ@
پ@

پ@
پ@
|
|
|
|
پ@
‚Q‚O‚P‚T”N‚UŒژ‚P‚R“ْپi“yپj
پ@

‡@
پ@—رڈ°‚ةƒMƒ“ƒٹƒ‡ƒEƒ\ƒE‚ھپB•پ’تپA‚P‚Ocm‚ا‰شŒs‚ًگL‚خ‚µ‚ؤ‚»‚جڈم‚ة‰ش‚ً•t‚¯‚é‚ج‚إ‚·‚ھپA‚±‚±‚ج‚à‚ج‚ح‚ف‚ٌ‚ب’n–ت‚·‚ê‚·‚ê‚ج‚ئ‚±‚ë‚ة‰ش‚ً•t‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ب‚ج‚إ‰J—±‚ج“D’µ‚ث‚إ‰ک‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB–{—ˆ‚حڈƒ”’‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپB
پ@
پ@

‡A
پ@”ِچھ“¹‚ً“Œ‚ضپBƒ„ƒ}ƒnƒ“ƒmƒL‚ح‚ـ‚¾ژل—tپBژ}‚جگو’[‚ج—t‚ج‚فگش‚ف‚ً‘ر‚ر‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡B
پ@ƒ„ƒ}ƒRƒEƒoƒV‚ھژل‚¢ژہ‚ً•t‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBگ¬ڈn‚·‚é‚ئچ•‚‚ب‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡C
پ@ƒqƒپƒRƒEƒ]‚جژہپB‚د‚ء‚ئŒ©پAƒ‚ƒ~ƒWƒCƒ`ƒS‚جژہ‚ةژ—‚ؤ‚¢‚ؤ”ü–،‚µ‚»‚¤‚إ‚·‚ھپA‚ ‚ـ‚肨‘E‚ك‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپByamaneko‚حچ،”N‚àƒNƒڈ‚جژہ‚ح‰½‰ٌ‚©ڈـ–،‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚±‚ê‚ح‰“—¶‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡D
پ@‚±‚جƒ~ƒj‚µ‚ل‚à‚¶‚ف‚½‚¢‚ب‚à‚ج‚حƒtƒTƒUƒNƒ‰‚ج‰تژہپB‚à‚ء‚ئ‘ه—ت‚ةژہ‚éˆَڈغ‚إ‚·‚ھپA‚±‚±‚ج‚à‚ج‚ح‚ـ‚خ‚ç‚ة‚µ‚©ژہ‚ً•t‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپBچ،”N‚¾‚¯‚ب‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@
پ@

‡E
پ@”–ˆأ‚¢گX‚ج’†‚إƒXƒ|ƒbƒgƒ‰ƒCƒg‚ً—پ‚ر‚郀ƒ‰ƒTƒLƒVƒLƒuپB
پ@
پ@

‡F
پ@گAچح‚جƒrƒˆƒEƒ„ƒiƒMپB‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©‰€‚جگ¼’[‚ـ‚إ—ˆ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‹ك‚‚جƒXپ[ƒpپ[‚إ’‹‚²”ر‚ً”ƒ‚ء‚ؤ‹A‚낤‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

پ@
پ@
|
|
|
|
پ@
‚Q‚O‚P‚T”N‚UŒژ‚P‚W“ْپi–طپj
پ@

‡@
پ@”~‰J“ü‚肵‚ؤ‚©‚ç‚â‚ء‚د‚è”~‰J‚炵‚¢“V‹C‚ھ‘±‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@ƒ^ƒPƒjƒOƒT‚ھٹJ‰ش‚µژn‚ك‚ـ‚µ‚½پB‰؛‚©‚çڈ‡‚ةچç‚¢‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡A
پ@”ِچھ“¹‚ةڈم‚ھ‚é‚ئگAچح‚جƒ†ƒٹ‚ھمY—ي‚ةچç‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‰€Œ|ژي‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپB
پ@
پ@
‡B
پ@–ى‘گŒ©–{‰€‚ضپB‘پ‚‚àƒ~ƒ\ƒnƒM‚ھچç‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB•ت–¼‚ًپu–~‰شپv‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ةگ·‰ؤ‚ج‰ش‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ھ‚ثپB
پ@
پ@

‡C
پ@چؤ‚ر”ِچھ“¹‚ضپBƒlƒ€ƒmƒL‚àچç‚«ژn‚ك‚ـ‚µ‚½پB–é‚ة—t‚ھ•آ‚¶‚邱‚ئ‚©‚çپu–°‚è‚ج–طپvپ¨ ƒlƒ€ƒmƒLپB
پ@
پ@
‡D
پ@ƒNƒٹ‚ج‰شپBژ“—Yˆظ‰ش‚إپA•ن‚ج‚و‚¤‚ةگL‚ر‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھ—Y‰شپB‚»‚ج•t‚¯چھ‚ة‚ ‚éٹغ‚ء‚±‚¢‚ج‚ھژ“‰ش‚إ‚·پB‚à‚¤ƒCƒK‚جŒ³‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ثپBƒuƒi‰ب‚جگA•¨‚ج‘½‚‚ح‘پڈt‚ةچç‚«پA‚ـ‚¾’ژ‚ھڈ‚ب‚¢‚ھŒج‚ة•—”}‰ش‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚»‚¤‚إ‚·‚ھپAƒNƒٹ‚ح‚±‚جژٹْ‚ةٹJ‰ش‚·‚é‚ج‚إ’ژ”}‰ش‚ب‚ج‚¾‚ئ‚©پBٹm‚©‚ة‹‚¢چپ‚è‚إ‚½‚‚³‚ٌ‚ج’ژ‚ًŒؤ‚رٹٌ‚¹‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡E
پ@چ،پA”ِچھ“¹‚ة‚ح—lپX‚بƒAƒWƒTƒC‚ھچç‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚³‚ة”~‰J‚ھژ—چ‡‚¤‰ش‚إ‚·پB
پ@
پ@

پ@
پ@
|
|
|
|
پ@
‚Q‚O‚P‚T”N‚UŒژ‚Q‚O“ْپi“yپj
پ@

‡@
پ@ƒJƒ‰ƒXƒUƒ“ƒVƒ‡ƒE‚ج‰ش‚ھٹJ‰ش‚جڈ€”ُ‚ًژn‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBٹJ‰ش‚ـ‚إ‚ة‚ح‚à‚¤‚µ‚خ‚ç‚‚©‚©‚è‚»‚¤پB
پ@
پ@

‡A
پ@‚ق‚قپcپB‚±‚ê‚حƒAƒLƒ„ƒ}ƒ^ƒP‚©پH
پ@
پ@

‡B
پ@”ِچھ“¹‚ًگ¼‚ضپBƒnƒٹƒGƒ“ƒWƒ…‚ةژہ‚ھ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒ}ƒپ‰ب‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ‚و‚‚ي‚©‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡C
پ@گ”ڈTٹش‘O‚ـ‚إ”’‚¢‰ش‚ً‚½‚‚³‚ٌ•t‚¯‚ؤ‚¢‚½ƒGƒSƒmƒLپBچ،‚حژہ‚ھ—éگ¶‚è‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡D
پ@‚¢‚ء‚½‚ٌ’‹گH‚إ‹A‘پAŒكŒم‚ ‚炽‚ك‚ؤژUچô‚ةپB
پ@ƒNƒچƒKƒlƒ‚ƒ`‚جژل—t‚ح‚ب‚ك‚µٹv‚ج‚و‚¤‚ة‚µ‚ب‚â‚©پB‚ز‚ئ‚ء‚ئ‹z‚¢•t‚‚و‚¤‚بگGٹ´‚إپA‚ـ‚¾ڈ_‚ç‚©‚¢‚إ‚·پB‚·‚®‚ةŒْ‚چd‚¢—t‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپB
پ@
پ@

‡E
پ@ƒVƒ‚ƒcƒPƒ\ƒEپB‰ؤ‚ج‰ش‚إ‚·پB–¼‘O‚ج‚ئ‚¨‚è‰؛–ى‚جچ‘پiŒ»“ب–طŒ§پj‚ة‘½‚گ¶‚¦‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚ج‚±‚ئپB
پ@
پ@

‡F
پ@‚±‚ê‚حƒIƒIƒzƒEƒ‰ƒCƒ^ƒP‚©پHƒLƒmƒR‚حچڈپX‚ئژp‚ھ•د‚ي‚èپAگ}ٹس‚جژتگ^‚إ‚ح‚ب‚©‚ب‚©“ء’è‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@
پ@
 |
‡G
پ@ƒNƒY‚ھ”ة‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰ گ·‚ب”ةگB—ح‚إƒAƒپƒٹƒJ‚إ‚ح Japanese green monster ‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚©پBٹm‚©‚ة‘S‚ؤ‚ًˆù‚فچ‚قگ¨‚¢‚إٹg‘ه‚µ‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡H
پ@ƒ\ƒtƒgƒ{پ[ƒ‹‘ه‚جƒLƒmƒRپBƒnƒiƒrƒ‰ƒ^ƒP‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBژP‚ج•”•ھ‚ھ‚ك‚‚ê•ش‚ء‚ؤ‚¨کo‚ج‚و‚¤‚ة‚ب‚èپAƒtƒٹƒ‹‚ج‚و‚¤‚ب‚ذ‚¾‚ھ‚ب‚ٌ‚ئ‚à—D‰ë‚إ‚·پBƒ{ƒٹƒ…پ[ƒ€ٹ´‚½‚ء‚ص‚è‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡I
پ@ƒcƒٹƒoƒi‚جژہپBگجپAƒAƒپƒٹƒJƒ“ƒNƒ‰ƒbƒJپ[‚ئ‚¢‚¤ƒIƒ‚ƒ`ƒƒ‚ھ—¬چs‚ء‚½‚ب‚ پB
پ@
پ@

‡J
پ@ƒIƒJƒgƒ‰ƒmƒI‚ھچç‚«ژn‚ك‚ـ‚µ‚½پB‰ؤ‚ھ—ˆ‚½‚ئ‚¢‚¤ٹ´‚¶‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡K
پ@ƒqƒ‹ƒKƒI‚ح‚·‚ء‚«‚è‚ئ‚µ‚ؤ—ء‚â‚©‚ب‰شپB‚½‚¾چç‚¢‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚ھژG‚ب‚ئ‚±‚ë‚ھ‘½‚¢‚ٌ‚إ‚·‚و‚ثپB
پ@
پ@
‡L
پ@چ،“ْ‚ح‚±‚ٌ‚ب‰ش‚ة‚àڈo‰ï‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒCƒ`ƒ„ƒNƒ\ƒE‚إ‚·پB
پ@
پ@

پ@
پ@
|
|
|
|
پ@
‚Q‚O‚P‚T”N‚UŒژ‚Q‚S“ْپiگ…پj
پ@

‡@
پ@ٹ_چھ‚ة‚و‚ژg‚ي‚ê‚éƒnƒiƒ]ƒmƒcƒNƒoƒlپB‚ع‚آ‚ع‚آچç‚«ژn‚ك‚ـ‚µ‚½پB‘هگ³ژ‘م‚ة“n—ˆ‚µ‚½‚à‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB—m–¼‚حƒAƒxƒٹƒAپB
پ@
پ@

‡A
پ@‘پ‚‚àƒIƒgƒMƒٹƒ\ƒE‚ھچç‚«ژn‚ك‚ـ‚µ‚½پB’è“_ٹدژ@‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‚±‚ٌ‚بژٹْ‚©‚çچç‚«ژn‚ك‚é‚ج‚©‚ئ‹ء‚©‚³‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½پX‚ ‚è‚ـ‚·پB”]“à‚ة‰ش‚جگ·‚è‚جژٹْ‚ھˆَڈغ‚أ‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA‚»‚جƒMƒƒƒbƒv‚ھگV‘N‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡B
پ@–ى‘گŒ©–{‰€پBƒ~ƒ\ƒnƒM‚جگ¨‚¢‚ھ‘‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB ‚ا‚؟‚ç‚©‚ئ‚¢‚¤‚ئژ¼‚ء‚½ٹآ‹«‚ًچD‚ق‰ش‚إپA–ىگ¶‚ج‚à‚ج‚حژR–ى‚جژ¼’n‚إچç‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ًŒ©‚©‚¯‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡C
پ@‚ـ‚¾‚UŒژ‚ب‚ج‚ةƒLƒLƒ‡ƒE‚ئ‚حپBڈH‚جژµ‘گ‚إ‚·‚ھپB‹Œ—ï‚ج—§ڈH‚ـ‚إ‚إ‚à‚ـ‚¾‚P‚©Œژˆبڈم‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ@
‡D
پ@ƒNƒTƒŒƒ_ƒ}پB‚±‚ê‚àژ¼’n‚ةچ炉ش‚إ‚·پB‚±‚ج‰ش‚ًŒ©‚é‚ئ‰ھژRŒ§‚جŒï‚ھŒEژ¼Œ´‚ًژv‚¢ڈo‚µ‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡E
پ@ƒچƒEƒoƒC‚ھژہ‚ً•t‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBˆêŒ©”ü–،‚»‚¤‚ة‚àŒ©‚¦‚ـ‚·‚ھپA‰ؤ‚ً‰ك‚¬‚é‚ئچ•‚ٹ£‘‡‚µ‚ؤƒJƒTƒJƒT‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡F
پ@’©‚ج‘ه“cگط’rپB‹َ‹C‚ھگں‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@
‡G
پ@ƒlƒWƒoƒi‚à—§”h‚ب–ىگ¶ƒ‰ƒ“پBڈ¬‚³‚ب‰ش‚ھ—†گùڈَ‚ة•ہ‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پB‚إ‚àپA‚½‚ـ‚ة‚ـ‚ء‚·‚®•ہ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚â‚آ‚à‚¢‚é‚ٌ‚إ‚·‚و‚ثپB‚±‚جڈêچ‡پA‚ـ‚ء‚·‚®‚ج•û‚ھ‚ذ‚ث‚‚êژزپH
پ@
پ@

پ@
پ@
|
|
|
|
پ@
‚Q‚O‚P‚T”N‚UŒژ‚Q‚V“ْپi“yپj
پ@

‡@
پ@گ^‰ؤ“ْ‚ج—\•ٌ‚إ‚·‚ھپA“ْچ·‚µ‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إ‚¢‚آ‚ـ‚إ‚à‰Jڈم‚ھ‚è‚ج‚و‚¤‚ب•µˆح‹C‚إ‚·پB
پ@گ¼“W–]‘ن‚جکe‚ة‚ ‚éƒGƒSƒmƒLپBٹغپX‚ئ‚µ‚½ژہ‚ً‰؛‚°‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚جژہ‚ة‚حƒTƒ|ƒjƒ“‚جگ¬•ھ‚ھٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپAگجپA‚±‚جژہ‚ًچi‚ء‚½ڈ`‚ًگى‚ة—¬‚µ‚ؤ‹›‚ً–ƒلƒ‚³‚¹‚é‹™–@‚ھ‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·پB
پ@
پ@
 |
‡A
پ@ƒnƒGƒhƒNƒ\ƒEپBڈ¬‚³‚ب–ع—§‚½‚ب‚¢‰ش‚إ‚·پBŒج‚ةژتگ^‚ًژB‚é‚ج‚ةژٹش‚ھ‚©‚©‚èپA‰ل‚ئ‚جگي‚¢‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚±‚جژٹْپAژUچôژ‚ة‚حچک‚ة‰لژو‚èگüچپ‚ً‚ش‚ç‰؛‚°‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚ھپA‚¢‚¢‹ïچ‡‚ة‰Œ‚ةàژ‚³‚ê‚ؤگg‘ج’†‚ھ‰لژو‚èگüچپڈL‚‚ب‚é‚ج‚ھ“ï“_‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡B
پ@ƒJƒLƒmƒL‚جژہپB‚؟‚ه‚¤‚ا‚P‚©Œژ‘O‚ح‰ش‚إ‚µ‚½‚ھپA‚à‚¤‚¨“éگُ‚ف‚جŒ`‚ةپB‚ـ‚¾ƒsƒ“ƒ|ƒ“‹…‚ظ‚ا‚ج‘ه‚«‚³‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡C
پ@ƒiƒ“ƒeƒ“‚ج‰ش‚ھچç‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‰ش‚ح’[گ³‚بژp‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‰ئ‚ج— ‚جƒWƒپƒb‚ئ‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚ةچç‚¢‚ؤ‚¢‚éˆَڈغ‚إ‚·پBپu“ï‚ً“]‚¸‚éپv‚ئ‚µ‚ؤ‹S–ه‚ةگA‚¦‚邱‚ئ‚à‚ ‚ء‚½‚ج‚¾‚»‚¤‚إپA‚ب‚é‚ظ‚ا‚ئ”[“¾پB
پ@
پ@

‡D
پ@‘پ‚‚àƒCƒkƒUƒNƒ‰‚جژہ‚ھگF‚أ‚«ژn‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒEƒڈƒ~ƒYƒUƒNƒ‰‚ئژ—‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‰ت•ن‚جچھŒ³‚ج•û‚ة—t‚ھ•t‚¢‚ؤ‚¢‚é‚©”غ‚©‚إŒ©•ھ‚¯‚ھ‚آ‚«‚ـ‚·پB—t‚ھ‚ ‚é‚ج‚ھƒEƒڈƒ~ƒYƒUƒNƒ‰پBƒCƒkƒUƒNƒ‰‚ح‰ت•ن‚ة‚ح—t‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@
پ@

‡E
پ@ƒIƒJƒgƒ‰ƒmƒI‚ج‰ش‚ھ‚¢‚و‚¢‚وگ·‚è‚ًŒ}‚¦‚ـ‚µ‚½پB•—ڈî‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚بپB
پ@
پ@

‡F
پ@ƒٹƒ‡ƒEƒu‚ج‰ش‚حچç‚«ژn‚كپBڈƒ”’‚ج‰ش‚إ‚·پBژل—t‚حگH—p‚ة‚ب‚èپA‚²”ر‚ةگ†‚«چ‚ق—ك–@”رپi‚è‚ه‚¤‚ش‚ك‚µپj‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚ھ‚ ‚é‚»‚¤‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡G
پ@“à— ’r‚ـ‚إ‚â‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB“¯‚¶ƒ‹پ[ƒg‚ً‰½“x‚àچs‚«—ˆ‚µ‚ؤ‚¢‚éƒRƒVƒAƒLƒgƒ“ƒ{پBچک‚ج‚ ‚½‚è‚ھ”’‚¢‚ج‚إچک‹َپi–¾پjه‘هx‚إ‚·پB‚إ‚àƒgƒ“ƒ{‚جچک‚ء‚ؤ‚ا‚±‚¾پH
پ@
پ@

‡H
پ@–ى‘گŒ©–{‰€‚إ‚·پB‚±‚±‚جƒgƒ‚ƒGƒ\ƒE‚ح‚»‚ë‚»‚ë‰ش‚جژٹْ‚ھڈI‚ي‚è‚ًŒ}‚¦‚éچ پBژتگ^‚ج‚±‚ê‚حمY—ي‚بŒـ‚آ”b‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡I
پ@‘م‚ي‚ء‚ؤƒNƒTƒŒƒ_ƒ}‚حچ،‚ھگ·‚è‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB
پ@
پ@
 |
‡J
پ@“yژè‚ج–@–ت‚ً•¢‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚حƒڈƒ‹ƒiƒXƒrپB‘S‘ج‚ة‰s‚چd‚¢ƒgƒQ‚ھ‚ ‚èپAڈœ‘گ‚ة‚ب‚©‚ب‚©ژ肱‚¸‚é–ï‰îژز‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡K
پ@”¨‚ةگA‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éƒTƒgƒCƒ‚‚ج—t‚إڈم‚ةگ…‚ج‹ت‚ھ‚ن‚ç‚ن‚ç—x‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج“®‚«‚ح‚ـ‚é‚إگ…‹â‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB
پ@
پ@

‡L
پ@‚±‚جˆ¬‚茂ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚حƒGƒSƒmƒL‚ة•t‚¢‚½’ژ‚±‚شپBŒ`‚ھ”L‚ج‘«گو‚ج‚و‚¤‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إƒGƒSƒmƒlƒRƒAƒV‚ئ‚¢‚¤–¼‚ھ•t‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ@

‡M
پ@ƒSƒ“ƒYƒC‚ح‚P‚©Œژ‘O‚ة‰ش‚جژٹْ‚ًڈI‚¦پA‚»‚ë‚»‚ëژہ‚ً•t‚¯‚ح‚¶‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBڈH‚ة‚حگ^‚ءگش‚ب‰تژہ‚©‚çگ^‚ءچ•‚بژيژq‚ھٹç‚ًڈo‚µپA‚و‚–ع—§‚؟‚ـ‚·پB
پ@
پ@

پ@
پ@
|
|
|
|
پ@
‚Q‚O‚P‚T”N‚UŒژ‚R‚O“ْپi‰خپj
پ@

‡@
پ@ƒ}ƒcƒˆƒCƒOƒTپBٹ؟ژڑ‚إ‚حپu‘زڈھ‘گپv‚ئڈ‘‚«پAکa‚ج•—ڈî‚ًٹ´‚¶‚³‚¹‚ـ‚·پB‚±‚ج‰ش‚حنس“›‚ھ’·‚پA–¨‚ح‚»‚ج‰œ‚ة‚ ‚é‚ج‚إپA’·‚¢Œû•«‚ًژ‚آƒXƒYƒپƒK‚ھ‰ش•²‚ج”}‰î‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB—[چڈ‚ةٹˆ“®‚·‚éƒXƒYƒپƒK‚ةچ‡‚ي‚¹‚ؤٹJ‰ش‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پA‚»‚ê‚ئ‚à‰ش‚جٹJ‰ش‚ةچ‡‚ي‚¹‚ؤƒXƒYƒپƒK‚ھٹˆ“®‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پB‚ا‚ء‚؟‚¾‚낤پB
پ@
پ@

‡A
پ@ƒAƒLƒmƒ^ƒ€ƒ‰ƒ\ƒE‚ح’·‚¢‰ت•ن‚ج‰؛‚©‚çڈ‡‚ةچç‚¢‚ؤ‚¢‚‚ج‚إپA‚ب‚©‚ب‚©–ٹJڈَ‘ش‚إ‚ج‘S‘ج‘œ‚ًژت‚µ‚ة‚‚¢‚إ‚·‚ھپAچç‚¢‚ؤ‚¢‚é•”•ھ‚¾‚¯‚ًƒAƒbƒv‚ة‚·‚é‚ئ‚±‚ٌ‚بٹ´‚¶‚إ‚·پB‚؟‚ه‚¤‚اڈ¬‚³‚بƒAƒu‚ھ—ˆ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒqƒ‰ƒ^ƒAƒu‚ج’‡ٹش‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@
پ@

‡B
پ@‚±‚ê‚حƒRƒ}ƒcƒiƒMپBچׂ’·‚¢Œs‚ھ‚ئ‚ؤ‚àڈن•v‚إپA”n‚ًŒq‚¢‚إ‚¨‚¢‚ؤ‚à‘هڈن•v‚ب‚‚ç‚¢‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB‚±‚ج‰ش‚à‰؛‚©‚çچç‚¢‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB
پ@
پ@
‡C
پ@‰ؤ‚إ‚·‚ب‚ںپB‚à‚¤ƒ„ƒuƒJƒ“ƒ]ƒE‚ھچç‚«ژn‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBچL“‡Œ§ژOŒ´ژs‚ة‚ ‚镧’تژ›‚إŒ©‚½ƒ„ƒuƒJƒ“ƒ]ƒE‚ھچ،‚àگS‚ةژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBڈ‹‚©‚ء‚½‚ب‚ںپB
پ@
پ@

‡D
پ@ƒlƒ€ƒmƒL‚ھ‚ـ‚³‚ة–ٹJپBڈ_‚ç‚©‚بˆَڈغ‚ج‰ش‚إ‚·پB‚³‚ء‚«‚جƒRƒ}ƒcƒiƒM‚ئ‚±‚جƒlƒ€ƒmƒLپA“¯‚¶ƒ}ƒپ‰ب‚ب‚ٌ‚إ‚·‚و‚ثپB
پ@
پ@

پ@
پ@
|
|
|
|
| پ@ |
 پ@
پ@ پ@
پ@