2015年3月5日(木)

①
早咲きで有名なカワヅザクラ。その中でも他に先駆けて咲いた一輪です。辺りを見回しても咲いているのはこれだけでした。

②
ユキヤナギの枝が伸びやかです。もうすぐこれが真っ白に。

③
歩道の一部にチップが敷かれていてふっかふかです。
昨日、山谷戸の会の人が「シイタケのほだ木が足りない」と言っていたそうですが、どうやらチップにされていたようです。
④
キブシのの花穂が垂れ下がってきましたね。伸びたばかりの頃は枝に沿っていました。

⑤
花粉を飛ばし終えたヤマハンノキの花穂が役目を終えてあちこちに落ちていました。咲くのも早ければ落ちるのも早いです。咲く前はギュッと目が詰まっていた花穂ですが、それがほぐれるように広がっています。

|
|
|
|
2015年3月8日(日)
①
ヤマハンノキの花。赤いのが雌花、長いのが雄花です。これまで特に気にもかけていませんでしたが、こんな早い時期に咲いていたんですね。

②
透明感のある白。アセビの花です。先の方はほのかにピンク色に。

③
こちらはアセビの去年の果実。花は下を向いているのに、果実は上を向くんですね。いったいどのタイミングで反転するのか。

④
これはノビルですね。漢字では「野蒜」。どこにでもありそうな草ですけど、確かに冬には出ていませんでした。地中に作るミニらっきょうを囓ると春の息吹を感じることができます。
⑤
モミジイチゴの芽吹きです。花と葉が同時に展開しています。

⑥
ヤマモモの雄花。ヤマモモは公園樹としてときどき目にします。子どもの頃、果実を口の周りを赤黒くして食べていた記憶があります。
⑦
植栽のトサミズキ。コウヤミズキとよく似ていますが、花序の軸に毛が密生しているところでトサミズキと分かります。株全体としてはまだ咲きはじめです。

⑧
内裏池にめずらしいお客さん。コサギだなと思っていたのですが、よく見るとくちばしが橙色ではないですか。目先も黄緑色だし、これはカラシラサギではないでしょうか。図鑑によると、「主に旅鳥として渡来するが少ない。」とありました。どこからやって来たんだろう。 ← 専門家は「ダイサギでしょう」とキッパリ。

|
|
|
|
2015年3月11日(水)
①
谷戸山の会で雑木林の間伐。根元で二股に分かれている大きなコナラの片方を切り倒します。
まずは梯子を登って幹の上の方にロープを掛けます。倒したい方向からロープで引っ張るのです。

②
ロープを掛け終わったら木に鋸を入れます。最初に倒したい方向に楔形に「受け口」を切ります。次に反対側に「追い口」を切っていきます。斜面に立っているので鋸を引くのも重労働です。
追い口を入れ終わったらロープを引いて狙った方向に倒します。事故のないように慎重に。
③
スッと伸びたホオノキの冬芽。あの巨大な葉が何枚もこの中に格納されているかと思うと、自然の不思議を感じずにはいられません。

④
これ、何だっけ。よく見る葉なんだけど。

⑤
内裏池にまだ珍客が滞在していました。ここで休んだ後、まだどこかに旅立っていくんでしょうね。(亜種ダイサギは冬鳥で、春に旅立つとのこと。)

|
|
|
|
2015年3月14日(土)

①
今日はガイドウォークに参加。曇天ですが寒さはずいぶん緩んできました。
これはコハコベ。小さな花でも花冠の中は精巧に作られています。自然は手を抜きませんね。

②
尾根緑道を東側へ。今日はいつもより参加者が多目です。
③
ハリギリの樹皮には鋭い刺がびっしりと。経25㎝くらいの成木です。

④
地面に落ちて冬を越したドングリ。これから根を伸ばすところか。

⑤
ホトケノザです。さきほどのコハコベといい、もう冬から早春へと季節は移ったようです。
⑥
ニワトコの枯れた幹に穴3つ。コゲラの仕事にしては穴が大きいような感じですが、アオゲラでしょうか。

⑦
そのニワトコの混芽。中央に花芽があり、その周りに葉芽があります。

⑧
内裏池ににやってきました。カラシラサギ(ダイサギでした。)はもう旅立ったようで、静かな池でカルガモのつがいがのんびりしていました。

⑨
ヒメカンスゲの花です。毛羽だった綿棒みたい。地味な花です。ちょっと触れるとフワッと花粉が飛びました。

⑩
先月落ち葉かきをしたカタクリの自生地で、もう何株か咲いていました。ちょっと嬉しいです。

⑪
ヒイラギナンテンの花。

⑫
カワヅザクラ。先日最初の一輪をみたと思ったら、一週間あまりでもう五分咲き。天気が良かったら敷物と弁当を持って来るべきです。

⑬
まさに桜色。ソメイヨシノよりずいぶん赤みが強いです。

⑭
アオキの実。名前に反して実は赤いのです。ヒヨドリの好物です。

|
|
|
|
2015年3月17日(火)

①
明け方まで降っていた雨のせいで空気が湿気をたっぷりと含んでいて、その中を朝日が差してきます。今日は暖かいです。

②
コブシが咲き始めました。辺りを見てもこの木が先駆けのようです。春だ春だ。

③
大田切池の畔にコガモのつがいが二組。どこからやって来たのかね。シベリアか、それともカムチャッカか。

④
キブシの花も垂れ下がり始めました。淡い緑色の小さな花。周りの木々にまだ葉がないのでよく目立っています。

⑤
アオキの果実。
むむ? アオキの実は大きくなってから緑色→赤色に熟すと思っていたのですが、これは小さなうちから赤いです。それとも、なりは小さいけれどこれはこれで成熟した果実ということでしょうか。

|
|
|
|
2015年3月20日(金)
①
ユキヤナギが咲き始めました。枝全体が真っ白になって、その枝が炎のうねりのような伸び方をするので、ユキヤナギのことを勝手に「白い炎」って呼んでいます。

②
満開のカワヅザクラもさることながら、地面が緑色になってきたのも春を感じさせるでしょう。
③
キブシもそろそろ咲きそろってきました。でも、この時期に花を訪れる虫はまだ少ないでしょうね。

|
|
|
|
2015年3月21日(土)

①
ウワミズザクラの芽吹き。枝の先端にブラシ状の花穂の片鱗が見えていますね。

②
ウグイスカグラは花期の長い植物。暖かくなってきたからか、それともこの株の個性なのか、ずいぶん花冠が大きかったです。

③
クロモジの冬芽もほぐれてきました。

④
モミジイチゴも咲き始めました。この辺り(園の東側の森)のモミジイチゴは開花が早いようです。

⑤
ミズキの芽吹き。この木は枝が水平に広がり、その枝先が上を向く特徴があります。葉が繁ると何段かの棚のように見えます。

⑥
これはヒュウガミズキですね。植栽です。同じ公園内にトサミズキの植栽もありましたが、こっちの方が開花は遅いようです。

⑦
大田切池の畔のコブシ。4日前に一輪咲き始めたのがもうこんな感じに。

⑧
ヒサカキも咲き始めました。独特の香りをいやがる人もいますが、春の訪れを知らせてくれる香りなのでyamanekoにとっては好きな匂いです。

⑨
鮎道のカタクリ自生地。もうずいぶん咲いてきました。今日は曇り空なのでみんな下を向いています。

⑩
ダンコウバイの花。よく似るアブラチャンとは花柄の有無で見分けると簡単。花柄がないのがダンコウバイです。

⑪
ビワの若葉。ビュッとまっすぐに伸びています。よく見ると細かな毛が密生していて、なんか鳥っぽい。

⑫
ヤドリギの花。高いところに着生しているのでこのくらいの解像度が限界です。

⑬
これはマユミの芽吹き。こんなふうにじっくり見るのは初めてかも。

⑭
オオアラセイトウは別名ショカツサイ(諸葛孔明が占領地で栽培し、戦で疲弊した民を救ったという言い伝え。)。アブラナの仲間で、最盛期には50㎝くらいにもなります。

⑮
コブシの花を近くから。

⑯
植栽のジンチョウゲ。この花も咲き始めが早いです。

|
|
|
|
2015年3月23日(月)

①
キブシの花。花冠の中を覗いてみて雄しべが成熟していたらそれは雄花。雌しべもありますが、機能はしません。

②
こっちは雌花。花冠の中には雌しべの柱頭や子房が成熟しています。雄しべは退化してほとんど見えません。

③
鮎の道のカタクリ自生地へ。かなり咲いてきています。ちょうど1年前、初めてフットパスを歩いていてここのカタクリに出会い、感動。

④
今日は陽射しを受けてきれいに花を開いています。

⑤
なかなかにスタイリッシュ。

⑥
今まさに開こうとしている花も。

|
|
|
|
2015年3月28日(土)

①
尾根緑道沿いの桜。咲き始めです。おそらくヤブザクラかと。

②
ヤブザクラはマメザクラとエドヒガンの自然雑種だそうです。三倍体で実が出来ないので、太古より自生地(多摩丘陵周辺)から分布が広がらないのだとか。

③
ユキヤナギの花穂が奔流のように好き勝手伸びています。今週、急に満開状態になりました。

④
葉が開き始めたアカシデ。ぶら下がっているのが花で、葉より先に開花しています。

⑤
タチツボスミレ。寄り添って咲いています。瑞々しいです。

⑥
いい枝振りのコブシですな。今、コブシはどの株も満開です。

⑦
小山内裏公園の尾根道の西端。木々が萌えていますね。

⑧
クロモジもきれいに咲いています。この株は開花が早い方です。枝は高級和菓子の楊枝に。

⑨
むむ、大きな花穂。これはバッコヤナギか。別名ヤマネコヤナギなんで、ちょっと親近感を覚えます。

⑩
シナレンギョウも咲き始めました。

⑪
ミツバアケビ。三出複葉がモビールみたい。

⑫
こっちはアケビ。小葉が5個あります。ミツバアケビのすぐ近くにありました。

⑬
ガマズミの若葉。表面に細かな毛が密生しています。これからびろーんと広がりますよ。
⑭
うつむくカタクリを下から覗くと、花冠の中央にもう一つの花が。これにはなかなか気がつきません。

⑮
鮎道沿いの自生地は今が盛りの状況。
⑯
これはミミガタテンナンショウ。仏炎苞の口辺部が耳のように張り出しています。
⑰
クマシデの花。雄花序です。笠のような苞の下に雄花を一つずつ付けています。

⑱
こぶしの花冠。クリーム色の棒が雄しべ、緑色のが雌しべです。こんな和菓子が合ったような。

⑲
春ですなあ。ツクシが顔を出しています。もう胞子を出し終えた模様。

⑳
パークセンター脇に植栽されていたベニバナミツマタ。下から覗き込んだ図です。普通、ミツマタの花は黄色ですが、これは園芸種なんでしょうね。ミツマタ同様、なかなか豪奢な花です。
㉑
内裏池のそばにたつコブシ。どっしりとしていて立派です。そして今が満開。

㉒
これはタマノホシザクラか。萼が星形をしています。タマノホシザクラもヤブザクラ同様、マメザクラとエドヒガンの自然雑種とのこと。ヤブザクラとの見た目の違いは、花冠が若干お椀形に開くというところだそうです。

㉓
ここのタマノホシザクラはDNA鑑定してみなければマメザクラとの区別は着かない、という人も。

㉔
ここのアカシデはまだ葉が展開していませんね。花もこれから開くところのようです。谷沿いにあるので日当たりの影響でしょう。

㉕
この可愛い葉はイボタノキのもの。今は柔らかそうですが、すぐに濃緑で硬い葉になってしまいます。

㉖
ウワミズザクラの花序。1週間で長さが4倍くらいに伸びました。

|
|
|
|
2015年3月30日(月)

①
南広場付近。ユキヤナギが荒波のよう。ビッグウェンズデーか?(古いか)
②
早くもシャガが伸び始めていました。花は5月頃といったイメージなんだけど。この花は法面などに植えられているのをよく見かけますが、土壌流出を防ぐ役割なんでしょうね。

③
この絞ったモップのようなものはカツラの雄花。花弁がないのでなかなか気付きにくいです。花が終わると丸い可愛い葉が展開し始めます。
④
野草見本園のバイモ。一見地味ですが、花冠を下から覗いてみると内側に黒紫色の網目状の模様があります。なので別名アミガサユリ。

⑤
まだ3月なのに次々と開花が見られます。これはイカリソウですね。「怒り草」ではなくて「碇草」。花冠の形が船の碇に似ているからでしょうね。本来は赤紫色の花で、白いものをシロバナイカリソウと区別して呼ぶこともあります。
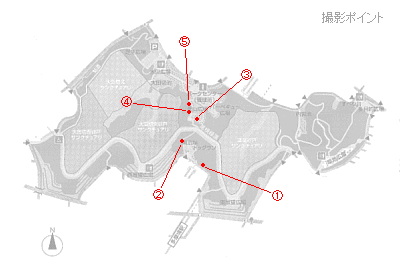
|
|
|
|
| |

