
大小山 ~大天狗小天狗が棲まう山(後編)~
 |
(後編) |
【栃木県 足利市 令和6年12月6日(金)】
大天狗、小天狗が棲むという大小山での野山歩き。後編です。(前編はこちら)
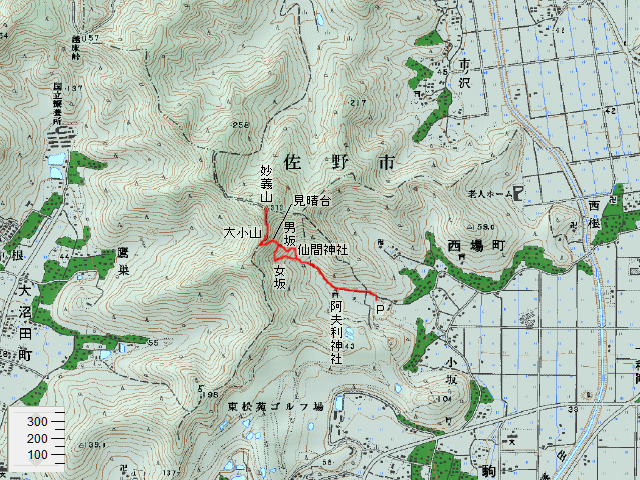 |
Kashmir3D |
登山のベースとなる駐車場を出発したのが11時5分。阿夫利神社に参拝してから山道に入り、男坂の岩場を楽しんだ後、見晴台を経由して12時15分に大小山ピークに到着しました。
| 大小山ピーク |
この岩が露出していることころがピークです。ここまでアクシデントもなく登って来られました。
| 妙義山ピーク |
奥には妙義山ピークが控えています。国土地理院の地形図ではあの妙義山ピークを大小山と記していて、三角点もあちらにあります。
| 赤城山 |
北西の方向には雄大な赤城山の山塊が。存在感ありますね。
もう少し広く見てみると、赤城山塊の手前には足尾山地の南端部分が水平の稜線を見せています。最前列はここ大小山から馬蹄形につながる稜線で、写真左側のピークが大坊山になります。ここから縦走する人も多いそうです。
更に左にパンすると、関東平野の北西端辺りが見渡せました。大坊山からの稜線が渡良瀬川の河畔に下っていく様子が見えます。正面の濃い山影の連なりは群馬県太田市にある金山。広い平野の中にぽつんとあって、利根川や渡良瀬川が運んできた土砂にも埋もれることなく今日まで残った山です。そして、最奥の薄い山影は、写真左が上信国境、右側が上越国境の稜線になります。
大小山ピークからは、木立に遮られて東側の展望は得られません。
この案内板はここを大小山の山頂(282m)としていますね。yamanekoの持っているガイドブックは、ここを大小山の山頂としつつも、その標高は妙義山ピークの314mとしています。それも変ですね。では、国土地理院が大小山山頂とする妙義山ピークまでピストンで行ってみましょう。ちなみに、妻はここに残っておやつタイムだそうです。
| 急降下 |
まずは急激に10mばかり下ります。
| 鞍部 |
すぐに鞍部となり、そこから40mほど登り返します。
今度は岩場の直登です。鎖は掛かっていないので、足場を確認しながら慎重に登ります。
特に難しいこともなく妙義山ピークに到着しました。だれか先客がいるようですね。
| 妙義山ピーク |
12時25分、妙義山ピークに到着。いや、国土地理院の地図に従うのなら大小山の山頂に到着です。標高は314m。大小山ピークから見たときには一旦下って登り返すのに結構時間が掛かりそうに感じましたが、実際に歩いてみるとあっという間でした。
振り返るとさっきまでいた大小山ピークが、と言いたいところですが、ちょうど手前の木立に隠れていました。
さて、妙義山ピークからの眺望は。こちらは360度の眺望です。
大小山ピークからは望めなかった北側です。写真左の雲の下には男体山を始めとした日光連山が見えます。写真中央の台形に見える山は三峰山。佐野市、鹿沼市、栃木市3市の接する辺りに位置しています。右端のとんがりは諏訪岳か。手前の市街地は葛生町(現在は佐野市に編入)ですね。
右にパンして、東方向。さっき見晴台から見た景色と同じ方向になります。写真右半分は真っ平らですね。その方向70km先には霞ヶ浦があり、更にその先には太平洋が広がっているはずです。
もっと右にパンして南方向。東京の都心方向になりますが、さすがに遠い霞の中です。
ぐるっとひと回り眺望を楽しんだところで、弁当が待つ、いや、妻が待つ大小山ピークに戻ります。
この下り傾斜。転げ落ちたらそれなりに大けがをしそうです。
無事に鞍部まで下りて来て、次は大小山ピークへの上りです。なかなかしんどいですな。
12時40分、大小山ピークに戻ってきました。おお、もう弁当を用意して待っているではないですか。お待たせしました。ランチタイムにします。
| おこわ米八の弁当 |
普段はコンビニで調達したカップ麺とおにぎりというのが定番ですが、今日は往きの羽生PAで見つけた立派な弁当です。おかずもご飯も美味しかったです。山で食べれば何でも美味しいのですが。
| 巨大な槍 |
食後、双眼鏡で都心方向を覗いてみると…、見えました。東京スカイツリーです。約70km離れていながらこの大きさ。大地に突き刺さった巨大な槍のようです。それにしても、完成から12年が経過していますがよくまっすぐ立ち続けていられるものですね。
食後の休憩で十分にまったりした後、1時15分、下山開始です。まずは稜線下りから。
| チャート |
落ち葉で隠れ気味ですが、これがチャート。地層が50度くらい傾いていますね。岩石としては極めて固く、ちょっとやそっとでは傷がつかないのだそうです。確かに破砕面が瑪瑙(めのう)とか大理石のような質感ですね。成分は二酸化ケイ素で、太古の海で放散虫の殻などが堆積してできたものだそう。褐色のものから緑がかったものまで色々あるそうで、そういえば10年くらい前に登った行道山(同じ足利市にある)で緑色を帯びたチャートを見た覚えがあります(こちら)。
すぐに稜線歩きが終わり、ここからは山肌を斜めに下っていきます。
滑り落ちないよう最新の注意を払って。事故は下りで多く起こっているそうなので。
| 地平線 |
南東の方向が望める場所がありました。地平線なんて普段なかなか見ることがありません。
鉄製階段を慎重に降ると…
東屋のある見晴台です。ここは素通りで。
| ゴンズイ |
ゴンズイはゴンズイなりに紅葉しています。陽を透かす様子を葉裏から見るのも風情あり、です。
見た目より傾斜がありますが、道幅が広いのでジグザグに下りていきます。多少面倒でもより安全に。
| 分岐 |
1時30分、男坂・女坂の分岐まで下りてきました。真っすぐ行って岩場の縁から崖を下るルートが男坂。右手の日陰になっているところから斜面を斜めに下るのが女坂です。ここは女坂へ。
| 女坂 |
女坂。岩場こそないもののそこそこの傾斜です。でも滑りやすそうなところにはロープが張ってあるのでノープロブレム。
| コアジサイ |
コアジサイの黄葉はレモンイエロー。遅くまで残っていることが多く、冬の野山歩きでこれに出会うとちょっとうれしいです。
| ヤマヤブソテツ |
枯れ葉の季節でもシダの仲間は生き生きしています。これはヤマヤブソテツですね。単なるヤブソテツというよく似たものもあり、その違いは、対になる羽片の数や葉の光沢の有無などだそう。ヤマヤブソテツは羽片が10対前後と少なく、葉の光沢もないとのことですが、どっちがどっちだったか分からなくなってしまいそうです。
| オオバイノモトソウ |
こちらはオオバイノモトソウ。これにもイノモトソウというよく似たものがあり、違いは葉軸に翼があるかないかだとか。あと、こちらは名前のとおり葉が大型です。でも、その場に比較対象がないと分かりにくいですね。
| ムクノキの葉 |
ムクノキの葉が落ちていました。まだ緑色を失っていませんでした。多様な植物の葉にあってこれぞ葉っぱといった模式図のような形をしています。
ズリッ。おお危ない危ない。という感じに写っていますが、この辺りまで下ってくるとそんなに歩きにくくはありません。
| 合流 |
1時45分、男坂から下ってくる道との合流点まで下りてきました。ここからは階段です。
| 獣除けフェンス |
獣除けのフェンスを越えると阿夫利神社はもうすぐです。
| イチョウ |
神社の脇にある大きなイチョウ。寺社林の樹木は伐られることが少ないので大木になっているのをよく見かけます。
| ビワ |
鳳仙寺を過ぎるとそこはもう静かな里です。これはビワの花。冬に咲く数少ない花の一つです。
| チャノキ |
チャノキにも花が着いていました。野山を歩いていてビワやチャノキに出会うと、ああ昔このあたりには民家があったんだなと分かります。
2時10分、ドリーム号Ⅲが待つ駐車場まで戻ってきました。随分車の数が減っています。いや、そもそも今回の野山歩きでは3、4人くらいにしか会わなかったのに、ここに車を停めてみんなどこに行ったのでしょうか。
それはともかく、リュックを下ろして、整理体操をして、帰途につく準備です。今日は紅葉と絶景と岩場登りを楽しませてもらいました。登山道やその途中の施設などもちゃんと手入れがされていて、地域の方に愛されている山なんだなと感じました。感謝です。
帰りの圏央道。桶川辺りから青梅くらいまでまさに夕日に向かって運転する形になり、サングラスを掛けていても眩しくてなかなか大変でしたが、参拝のご利益もあってか無事に家に帰ることができました。