
大小山 ~大天狗小天狗の棲まう山(前編)~
 |
(前編) |
【栃木県 足利市 令和6年12月6日(金)】
今年も年末の声を聞くようになりました。毎年思うのですが、秋が終わると年の瀬に向かって雪崩を打つように時間が過ぎていきます。特に今年は猛暑の影響か秋もなかなか深まらず、ここに来て過ぎ去る日々はより加速度を増しているように感じます。
そんな気ぜわしい師走の日々ですが、いや忙しいからこそ、やっぱり野山歩きを楽しみたい気持ちはふつふつと湧いてきます。まるで無意識に心身のバランスを取ろうとしているかのように(いや単に遊びたいだけ)。今回訪れるのは、栃木県南部、足利市と佐野市にまたがる大小山(314m)です。関東平野の北縁に当たるこの辺りは山と里が接する場所でもあり、昔から山は里の人々の生活と密接につながってきたのだと思います。特に日々山を見上げる生活を送っていると、自然に信仰の念も湧いてきたのではないでしょうか。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前8時前、ドリーム号Ⅲで出発。今回は妻も一緒です。いつものとおり圏央道の外回りに入り(圏央道にはいつもお世話になっております)、埼玉県の久喜白岡JCTで東北道へ。途中羽生PAに立ち寄って弁当や飲み物を調達して、佐野藤岡ICで一般道(佐野バイパス)に下りました。そして田園風景の中を登山口のある足利市西場地区に向けてのんびりと走っていきました。
| 大小山 |
西場地区に入った辺りから望む大小山。まさに山の際まで集落が点在しているのが見て取れます。ん?山頂の下辺りに何か書いてないか?って、yamanekoは事前にガイドブックを読んで知っているのですが、あれは「小大」の文字の巨大看板。山体に文字が掲げられているなんて珍しいですね。昔は右読みだったので「小大」ではなく「大小」と読むのでしょうか。
で、大小とは何のことなのかですが、これはこの山に赤天狗と青天狗が棲むという言い伝えがあり、赤天狗を大天狗、青天狗を小天狗とも呼んだことから「大小」山という名前になったとのことです。ということは、山頂直下の崖に掲げられているあの文字は、山の名前を示すためではなく(つまり「大小」と続けて読むのではなく)、ここに大(赤天狗)と小(青天狗)がいるよという意味で、文字自体が天狗そのものを表しているのではないでしょうか。ここから常に見下ろしているぞと。(yamaneko説)
| 駐車場 |
西場集落の西の端から、離合困難な道を山懐ろに分け入っていきます。その先に登山者用の無料駐車場があるのです。ありがたいことです。 そして、10時50分、駐車場に到着。既に10台以上停められていました。
車を降りると、そこは時折モズの声が聞こえてくるくらいで、静かな山里でした。装備を整え、ラジオ体操をして、さあようやく出発です。
ところで、一般に大小山と呼ばれるピークの標高は282mで、尾根続きでその北側にある妙義山と呼ばれるピークの標高は約30m高い314mとなっています。国土地理院の2万5千分の1地形図では、妙義山ピークの方を大小山と示していて三角点も置かれています。何でこんなややこしいことになっているのか。これはyamanekoの推測ですが、本来、大小山ピークは妙義山ピークを頂とする「大小山」の一部なのではないでしょうか。ただ、大小山ピーク直下の崖に「小大」の文字が掲げられているので、あたかもここが大小山という形で認知されていったのでは。じゃあ、なぜ「小大」の文字は妙義山ピーク直下ではなく大小山ピークの方にが掲げられたのか。これは両天狗を祀る阿夫利神社の背後に位置するのが大小山ピークだからなのではないでしょうか。大体、山の神社は里宮の背後に奥宮があるものです。また、一方の妙義山には文字を掲げるのに適した崖もありませんし。われながら名推理です(自画自賛)。
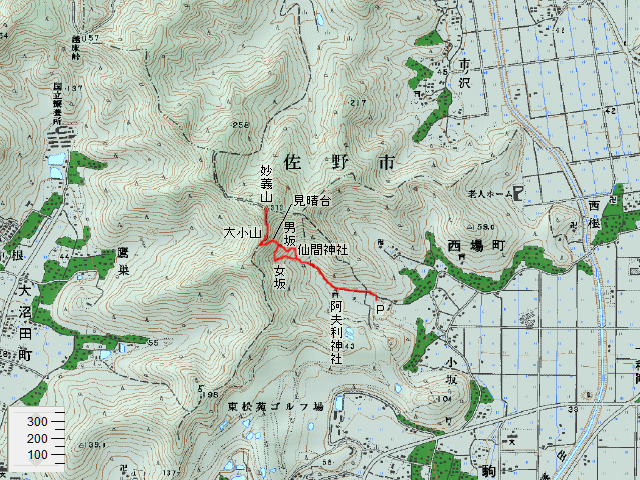 |
Kashmir3D |
今日のルートは、駐車場から谷筋を遡り、阿夫利神社を左に見送って登っていきます。やがて現れる分岐では右手の男坂へ。こちらは岩場が連続する若干スリルのあるルートです。女坂と合流したら、ほどなく大小山の山頂直下にある見晴台に出ます。そこから鉄製階段を登るとすぐに稜線に。見通しの効く尾根筋をひと登りすると大小山ピークにに到着します。そこから一旦鞍部に下りてぐっと登り返すと三角点のある妙義山ピークに。復路は来た道を下りますが、途中女坂を使います。
| 鳳仙寺 |
11時5分、スタート。駐車場を出るとすぐに鳳仙寺というお寺の前を通ります。門から覗くと、人影はありませんでしたが、きちっとしたお寺であることを伺わせる整然とした境内でした。
| タンキリマメ |
道の脇の藪にタンキリマメの実がぶら下がっていました。赤い鞘の中から光沢のある黒い種子が顔を出しています。晩秋の里の風物詩ですね。もう冬ですが。
| エノキ |
エノキが見事に黄葉していました。青空を背景によく映えています。
鳳仙寺から少し上がるとやや小さめの駐車場があり、トイレも併設されていました。車で上がれるのはここまでです。手入れされた駐車場といいトイレといい、近隣の方の登山者に対するもてなしの気持ちが感じられました。
| イロハモミジ |
駐車場の脇にあったイロハモミジです。この紅葉を美しいと感じるのは、ほどなく散り落ちてしまうことが分かっているということもあるかもしれませんね。
| 登山道へ |
さて、ここから谷の奥に向かって登っていきます。ベンチのところから右手に分かれる道もあり、こちらは大小山ピークを踏むことなく妙義山ピークに向かう道になります。
んっ? バス停か? と思いましたが、単なる山火事注意の看板でした。横の案内板には「男坂 女坂 登山口→」とあります。まだ登山口にも達していなかったのか。そして案内板の杭の上にはマガモの人形が。なんで?
| 阿夫利神社 |
すぐに阿夫利神社が現れました。大天狗、小天狗を祀る神社です。まずは参拝を。今日こちらで遊ばせてもらうことに感謝し、そして無事に帰宅できることをお願いしました。家に帰るまでが遠足ですからね。
ドリーム号Ⅲを停めた駐車場からずっとジワジワ上り坂になっていましたが、阿夫利神社を過ぎた辺りから傾斜が急になってきました。長い階段が大腿四頭筋に負荷をかけてきます。
yamanekoの先を登る妻。いつも下山後膝が痛くなると言っていますが、今日はどんな感じか。そんな状況でもたまに野山歩きに同行するということは、妻もこういうのが好きなんだと思います。
| 分岐 |
11時35分、男坂と女坂の分岐が現れました。道がY字になっていて、右が男坂、左が女坂です。ここは男坂方向へ。
| 仙間神社 |
分岐してから更に階段を上っていくと、立派な祠に至りました。ここは仙間神社というそうです。麓にあった鳳仙寺と「仙」の字が共通しますが、「仙」は仙人=天狗を意味するのかな。
| 仙間神社 |
祠はそれを保護する建家の中にありました。この建家、祠ともにまだ新しかったです。前にある門柱(?)も。近年建て替えたのかもしれません。ここでもちゃんと参拝を。
| マンリョウ |
祠の近くにマンリョウが実を付けていました。緑色の葉に朱い実。枯れ色の山中にあって生命力のようなものを感じます。なんかホッとしますね。
階段は仙間神社までで終わり。ここからは山道です。正面の急坂にロープが取り付けてありますね。さっそく男坂の洗礼か。
ロープを使って登ったその先には岩場が続いていました。木の幹に「足元注意」とプレートが取り付けてあります。それらしくなってきたぞ。
この辺りの岩はチャートと呼ばれる岩石のようで、ミルフィーユのようにきれいに積み重なっていました。ただ、本来は水平に堆積したはずの地層がここでは直立していました。
道が落ち葉で隠されています。左手は急斜面。転んだり捻挫したりしないよう気をつけねば。
岩場ではyamanekoが先行してルートを確認。振り向くと妻も黙々と付いてきていました。
更に急な岩場。滑落注意の看板もありました。
妻も両手を使って登ってきています。
黄葉と岩場。なかなか良い取り合わせですね。ここを上がると木立が切れている模様。なんか眺望が開けていそうな雰囲気です。
やっぱり展望台のようになっていました。見えているのは南東方向です。
妻も上がってきて、岩に腰掛けて一休み。今日は天気が良く風もないので、休んでいて体が冷えることもありません。
さて、最後のひと登り。頑張りましょう。妻も鎖を使ってガチ岩登りの様相です。
| 合流 |
登り切ると、そこは女坂との合流地点でした。写真奥からここまで登ってきている道が女坂です。岩場はここまで。合流後は写真右手に向かいます。
ここからは落ち葉の坂道。道幅は広めで、さっきまでの緊張感から開放されました。
しばらく行くと木立が途切れ、見上げると、おぉ「小大」の文字が。思ったよりでかく、崖とともにのしかかってくるかのようです。これは江戸末期に無病息災を願って文字を掲げたのが始まりとのこと。その後何回か架け替えられ、現在のものの大きさは7m四方もあるそうです。
| 残り柿 |
こんな山の中に柿の木が。近くには民家の跡すらないし、鳥が種子を運んだのでしょうか。
| コウヤボウキ |
キクの仲間、コウヤボウキがドライフラワー状態になっていました。葉はまだ緑色をしています。
急な坂を登ると東屋が見えてきました。あそこが見晴台のようです。
| 見晴台 |
おお、なんかただの東屋ではなく、仲間内のたまり場的な雰囲気を醸しています。この山を整備しているグループが使っていたりするのでしょうか。
| 東南東方向 |
そして見晴台からの眺望がこちら。東南東の方向になります。正面の低い山は三毳山。カタクリで有名な山ですね。その左手の山並みは三毳山よりも手前にある唐沢山や諏訪岳などです。三毳山の遥か奥には筑波山の山影が。ここから筑波山までは約55kmほどありますが、案外はっきりと見えました。
| 階段 |
ひとしきり景色を楽しんだら再び歩き始めます。見晴台の広場の端に鉄製の階段があり、ここを登っていきます。
階段の先は斜面を斜めに登っていきました。落ち葉で滑りやすいので油断禁物です。
ほどなく稜線に出ました。写真では分かりにくいですが、正面に案内板が立っていて、山頂へはここを右折と教えてくれています。
ここからは稜線なので左右は斜面です。木々が茂っているので高度感はあまりありません。
| 大小山ピーク |
そしてついに大小山ピークに到着しました。時刻は12時15分。スタートから1時間ちょっとでした。山頂はなだらかな岩の丘になっていて、平らな場所はないようです。さて、お昼ごはんは後にして、まずは眺望を楽しみましょう。(後編に続く)