2025年8月7日(木)

①
ヘクソカズラ。花冠の中央は深紅色で、細かい毛が密生しています。これが受粉に何らかの役割を果たしているとのこと。雄しべが花筒の中にあるので、中に入った虫が簡単に出られないようになっているのかも。

②
フェンスに絡みついたセンニンソウ。ちょうど花の盛りの時期ですね。奇麗ですが、茎や葉に有毒物質が含まれていて、皮膚がかぶれることがあります。

③
野草見本園へ。マツカゼソウが咲き始めました。細い枝の上部に花を付け、ちょっとの風で揺れるので、写真を撮るのには苦労します。

④
階段の擬木の上を歩いていたジガバチの仲間。調べてみるとサトジガバチとかミカドジガバチとか似たようなものが多く、特定には至りませんでした。この仲間は人への攻撃性は低いとのことです。

⑤
いつのまにかヤマユリの盛りが過ぎ、園内でも咲いている姿をほとんど見なくなりました。暑い日々が続く中でも生き物は自らのサイクルをきちんと回しているようです。
⑥
イヌゴマ。ゴマのような果実を作りますが、食用にはならず役に立たないとして「イヌ」が名に冠されています。別名のチョロギダマシも同様で、根がチョロギ(お節料理に添えられる)に似ていることによる名前です。いずれにしても残念なネーミングですね。
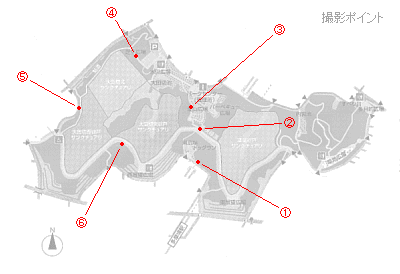
|
|
|
|
2025年8月15日(木)

①
熱帯アメリカ原産のマルバルコウ。明治初期に渡来したものだそうです。見た目は可愛いですが、縦横無尽に繁茂し、農作物、特にトウモロコシなどに被害を及ぼすそうです。
②
キツネノカミソリが咲き始めると夏本番です。ヒガンバナの仲間で、同じように花の時期には葉は見られません。その葉の様子が名の由来なのですが。

③
アオハダの果実。もう赤く色づいています。さすがにまだ熟してはいないでしょう。通常、熟すのは秋(10月前後)です。

④
クサぎの花序。痛み始めている花も見られます。このタイプの花序は集散花序といい、一つの節から複数の側枝が出て、花が集まって咲く形。咲く順番に規則性はあるのでしょうか。
⑤
ミゾソバの花です。花被の裂片の先端が淡い桃色をしていて、透明感があります。じっとりとした空気の中にあって涼やかさ満点。

⑥
テッポウユリに似ていますがおそらくタカサゴユリでしょう。花被片の外側に薄い褐色の筋があるかが見分けポイントの一つ。

⑦
野草見本園へ。
葉の下に隠れるように咲くのはカラスノゴマ。従来の分類では草本としては珍しいシナノキ科に属していましたが、APG体系ではアオイ科に分類されています。手前のイガイガはダイコンソウの集合果。

⑧
線状の舌状花が整然と並ぶオグルマの頭花。この様子を「小車」と例えた名前だそうです。本来は田の畔などやや湿った環境を好む植物です。
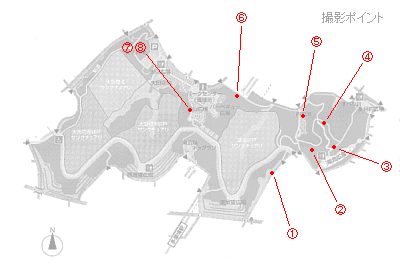
|
|
|
|
2025年8月23日(土)
①
今回は小山内裏公園が企画するサマーナイト観察会の手伝い。その前に自主観察会です。
ホソバシュロソウの花の色は暗褐色で、数ある植物の花の中では珍しい部類です。この色、昆虫にはどんなふうに見えているのか。

②
野草見本園へ。これはキンミズヒキ。花序の下の方から咲いていきます。開花が先端に向かうにつれ、花序自体も伸びて行きます。
③
これはコヤブタバコの頭花。その周囲の花弁状のものは総苞です。花茎の先端になぜか下向きに頭花を付けます。葉が切れているのは草刈りの影響でしょうか。

④
午後6時にサマーナイト観察会スタート。
子供たち大興奮のノコギリクワガタです。コナラの樹液を舐めに来ていました。ただ、そういうところには大概ハチも来ているんですよね。
⑤
6時半頃を境にセミの声とアオマツムシの声が入れ替わりました。
ツクツクホウシの羽化です。幼虫の殻から抜け出て羽を広げているところです。

⑥
こちらはアブラゼミかミンミンゼミの羽化。今まさに殻から抜け出ようとしているところ。体の後部を殻の中に残し、エビ反るようにしてぶら下がったところです。これから上体を起こして前足で殻を掴み、今度は体の後部を殻から出すことになります。その完成形が⑤のツクツクホウシの状態です。

⑦
メマツヨイグサ。夜に咲く花です。写真では光が当たっていますが、暗闇で咲くことになり、その分香りで虫を呼びます。お客さんはもっぱらスズメガの仲間だそうです。

⑧
観察会を終え、公園の外周で咲くカラスウリを見に行きました。こちらも漆黒の闇の中で咲く花です。こんなにあでやかに咲く必要があるのか。
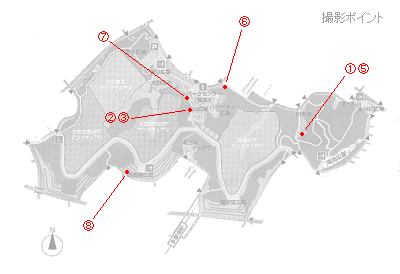
|
|
|
|
2025年8月30日(土)

①
オオニシキソウ。1個の花のように見えるのは花序(複数の花の集まり)。雌花の周りを4個の雄花が取り囲んでいます。花といってもそれぞれが雄しべ、雌しべ単体の状態までシンプルになっていて、雄花は1個ずつが白い花弁のように見えます。中央の雌花が果実を肥大させて、花序から飛び出てぶら下がるようになっています。
②
オオブタクサの花穂が伸び始めていました。今はまだきゅっと締まった状態ですが、これがほぐれていくにつれ花粉を大量に飛ばすという厄介者。秋の花粉症の主犯格です。

③
ヌスビトハギの花はマメ科に特有の蝶形花。花茎の先にまばらに付きます。

④
九反甫谷戸へ。これはイガホオズキの果実。イガイガの萼にすっぽりと包まれていて、果実自体は白い球形をしています。

⑤
秋の七草の一つ。クズ。花期はこれからです。花は花序の下から上に向かって咲いていき、なかなか全体がきれいに咲いている状態のものには出会えません。
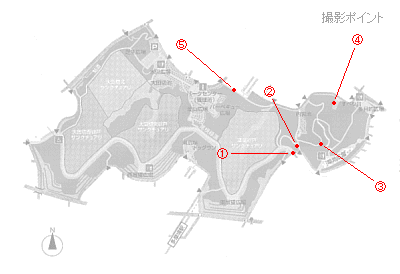
|
|
|
|
| |

