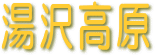
湯沢高原 〜高原が涼しいとは限らない(後編)〜
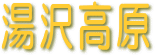 |
(後編) |
【新潟県 湯沢町 令和7年7月28日(月)】
涼しい高原をイメージしてやって来た湯沢高原。着いたとたんにそんな甘い考えを砕かれはしましたが、それでもしっかり盛夏の野山歩きを楽しみます。その後編です。(前編はこちら)
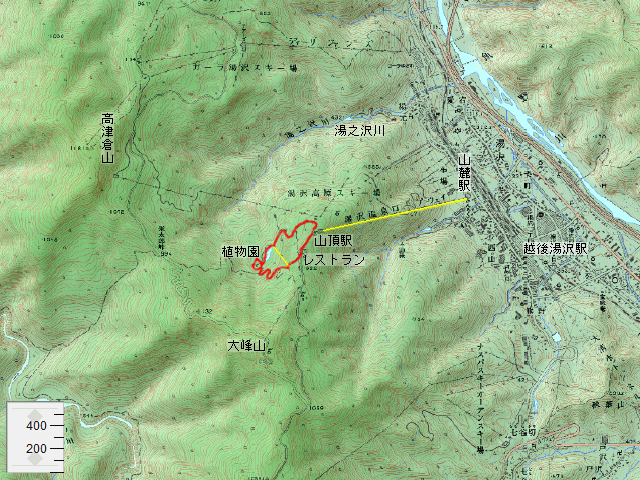 |
Kashmir3D |
越後湯沢の駅近くにあるロープウェイで大峰山中腹の稜線に降り立ち、その先にある湯沢高原パノラマパーク内の植物園((湿性花園、高山植物園)を中心に散策します。
| ガレバハウス |
高山植物園の奥に山小屋風の建物がありました。「ガレバハウス」というジェラート屋でした。ガレバとは「ガレ場」、すなわち山地の岩がゴロゴロしている地形のこと。きっとここがロックガーデンだからでしょうね。
| フシグロセンノウ |
フシグロセンノウです。節が黒いということで「フシグロ」。この節とは茎から花茎が枝分かれする部分のことですが、わずかに褐色がかっているくらいで、いうほど黒くはありません。逆に命名に際してなんでそこに着目したのか。花冠の方がよっぽど目立つだろうに。
| レブンウスユキソウ |
エーデルワイスの仲間、レブンウスユキソウ。「レブン」とはもちろん礼文島のことで、基準標本(学名を付ける際に用いた標本)が礼文島のものだったからだそうです。
| アカモノ |
これはアカモノの果実ですね。子房ではなく萼片が肥大化したものだそうです。甘みがあってジャムなどに加工されることが多いとのことですが、果実の大きさは大きくても1cm程度。ジャム作りには相当な量が必要となるでしょうね。
| イブキジャコウソウ |
イブキジャコウソウ。深山に行かなければ出会えないイメージを持っていましたが、考えてみると低山から高山まで様々なシチュエーションで出会っていました。もちろん伊吹山の山頂でも見ましたし、さかのぼって初めて見たのは島根県の立久恵峡でした。
| キキョウ |
秋の七草の一員、キキョウです。夏の始まりの頃から咲いています。
| シロバナトウウチソウ |
これはシロバナトウウチソウですね。東北地方の山地に咲く花です。こんな姿をしていますがバラの仲間で、葉はよく見るバラの葉に似ています。名前の「トウウチ」は漢字で「唐打」と書き、これは中国の組紐のことだそうです。花穂はたくさんの小さな花が集まり柔らかいブラシのようですが、もしかしたら花が開花する前のぎゅっと締まった状態が組紐に似ているのかもしれません。
| 大峰山 |
高山植物園から大峰山を見上げたところ。暑すぎてセミさえ鳴かないのか無音(だったと思いますが、心象風景か)。それがかえって暑さを増しているような気がします。
| ハマナス |
これはハマナスですね。本来は海岸に生える植物ですが、なぜここに植えた? とはいえ山地でもちゃんと育つことに感心しました。海岸は植物にとって過酷な環境なので、そこで生き延びられているということは大概のところは大丈夫ということか。
| ミソハギ |
「盆花」の別名を持つミソハギ。お盆に仏壇に供える花で、禊萩(みそぎはぎ)が訛った名前だそうです。ただ、yamanekoの故郷ではそのような風習はなかったような気がします。これは全国的な風習でしょうか。
| カライトソウ |
シロバナトウウチソウの仲間、カライトソウです。花穂の様子も似ていますね。漢字では「唐糸草」です。トウウチは中国の組紐、こちらも唐の糸。きっと名前の由来は共通しているんでしょうね。
| オカトラノオ |
オカトラノオも丘陵地や低山でも見かける花です。それにしてもトラの尻尾ってこんなに短かったか?
| リフト乗り場 |
高山植物園をぐるっと回って湿性花園の入口まで戻ってきました。ここにはリフト乗り場があり、楽して稜線上まで連れて行ってくれます。とりあえずこれで稜線に上がり、レストランで昼食をとることにしました。ちなみにこのリフト、無料です。
| やまびこペアリフト |
リフトに乗るのは久しぶりです。記憶をたどってみたら13年前、長野県の八方尾根で乗って以来でした。懐かしっ!
| リフト終点 |
8分ほどで稜線上に着きました。最初にロープウェイで上がってきた地点より標高で80mほど高いところで、距離にして500m弱離れた場所になります。
| レストラン |
正面に見えているのがレストラン「エーデルワイス」です。ついでにそこまでの道ばたも観察してみます。
| ゲンノショウコ |
これはゲンノショウコですね。下痢止めの薬効があり、飲んだらすぐに効くことから「現の証拠」=見てのとおり、という名に。関東地方でゲンノショウコといえば白い花ですが、西日本では紅紫色が一般的だそうです。そういえば広島在住時に見たものはそうでした。
| オオハンゴンソウ |
オオハンゴンソウは「北の国から ’98時代」で印象に残る役割を果たしていました。正吉が「百万本のバラ」よろしくこの花を蛍に送り続けるという泣かせるシーン。広大な富良野の丘で埋もれるようにしてこの花を摘む正吉の横顔。忘れられません。
| 八海山遠望 |
昼食を終えてレストランのデッキで一休み。目の前の道を下って行った先にロープウェイの山頂駅があります。
遠くに八海山のギザギザの稜線が見えていますね。胸のすくような風景です。ここから八海山までの距離は30kmほど。今から13年前に登ったことがあります。ちょうど八方尾根でリフトに乗ったときの前月のことだったと思います。
さて、これからはリフト降り場に戻って、その先からトレッキングルートへ。山肌を下って再び高山植物園に向かいます。
ここから下っていきます。このルートは歩く人もほとんどいないよう。クマに出会わないよう、一応熊鈴をぶら下げました。
| ドクウツギ |
いきなり出ました。いや、クマではなくてドクウツギ。これは果実(正確には肥大した花弁が果実を包んだもの)。黒く熟しているものも見られますね。美味しそうだからといって口にすると死にます。なにしろ株全体に強い神経毒の成分がある中で果実が最も強い毒性を持っているのだとか。おお怖っ。葉の場合だと24gで致死量だそうです。ちなみに、トリカブト、ドクゼリと共に日本三大有毒植物の一つとされているそうです。
| トチバニンジン |
これはトチバニンジンですね。果実はまだ若く、これから秋に向けて朱色に熟していきます。トチバというだけあって葉がトチノキのそれに似ていますね。
| タチカメバソウ |
可愛らしい花を並べるタチカメバソウ。山中の湿ったところに生える花です。yamanekoが自然観察を始めた頃に教えてもらった記憶がありますが、それがどこでのことだったか記憶が定かでありません。なんだか変わった名前の花だなと思ったことは覚えています。「カメバ」は漢字では「亀葉」と書き、葉が亀の甲を連想させるからだそうですが、初めて聞いた時「噛め歯」と理解し、花序が入れ歯みたいに並んでいるからかなと勘違いをしていました。
| ヤマアジサイ |
これはヤマアジサイでしょうね。装飾花の萼片がやや細めですが。それにしても鮮やかな青色です。
| ミヤママタタビ |
葉が白くなるのはマタタビの特徴ですが、葉がやや細身なので、これはミヤママタタビだと思います。ネコを連れてくれば分かるかも。ネコはマタタビは大好きですがミヤママタタビは好まないのだそうです。果実も見た目ほどんど同じなんですが。
| ヤマブキショウマ |
ヤマブキショウマ。葉は2回3出複葉で、その小葉がヤマブキの葉に似ているのだそうです。ショウマは漢字では「升麻」と書き、これはキンポウゲ科のサラシナショウマの根茎から作られる漢方薬の名前。なので、ショウマは本来サラシナショウマのことになるのですが、広く似た感じの植物に〇〇ショウマとして名付けられていたりします。このヤマブキショウマもバラ科で、本来のショウマとは無関係です。
| ノカンゾウ |
田んぼのあぜ道などちょっと湿ったところで見かけることの多いノカンゾウ。奇麗な花なのに世の評価はそれほど高くないようです。道ばたの雑草のような扱いで。
| タニタデ |
この線香花火みたいな花はタニタデです。タデと名が付いていますが、タデ科ではなくアカバナ科。特段タデの花に似ているわけでもないという植物の名前あるあるです。
| オトギリソウの仲間 |
これはオトギリソウの仲間ですね。具体的な種が分からないときは「仲間」で済ませます。
| シロバナウツボグサ |
シロバナウツボグサはウツボグサの白花品。植物の中には本来の花の色ではなく、形は同じで白い花を付ける種がそこそこあります。カワラナデシコとかエンレイソウとかカタクリなどもときどき白花を見ます。
更にトレッキングルートを下り、この先の高山植物園に向かいます。
| ハクロバイ |
ハクロバイはキンロバイの白花品。図鑑にはハクロバイとキンロバイが共存することはまずないと解説されていましたが、なぜなんだろう。本種と変種の関係なんだろうに。
| ゼンテイカ |
これはゼンテイカでしょうか。別名のニッコウキスゲの方が有名かもしれません。漢字では「禅庭花」と書きなんだか意味ありげな名前。ただ、由来はよく分かっていないのだそうです。
| ホザキシモツケ |
ホザキシモツケが咲いていました。亜高山帯の湿原に生える花で、日光の戦場ヶ原が有名な自生地です。
| 湿性花園 |
高山植物園から湿性花園に出て、この先のリフト乗り場から再び稜線に上がります。なにしろリフトは無料ですから。
さっき見た風景です。今度はレストランの前を素通りし、ロープウェイ乗り場まで歩いていきます。
この坂を下るとロープウェイ乗り場。今日の野山歩きの終点です。
2時5分、ロープウェイ乗り場に到着しました。来た道を振り返るとこんな感じでした。
| 上越国境 |
展望デッキから上越国境の山並みを眺めつつ、しばし休憩。方角としては南東方向になります。yamanekoの好きな山、谷川岳を探しましたが、それらしい山は見当たりませんでした。猫の耳のような特徴のある双耳峰なのですが。帰宅後、Kashmir3Dでチェックしてみたら、ちょうど茂倉山のすぐ後ろに隠れていたようです。
しばらく休んでから次のロープウェイで湯沢温泉に下りました。平日とあって観光客も少なめ。ちょっと温泉街をぶらぶらして風情を満喫してから(妻は射的を楽しんでいました)、宿に移動して温泉で疲れをとりました。もっぱら水風呂に入って。