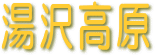
湯沢高原 ~高原が涼しいとは限らない(前編)~
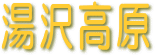 |
(前編) |
【新潟県 湯沢町 令和7年7月28日(月)】
日頃よく使っているウェザーニューズのアプリ。曇りのアイコンはグレー、晴れのアイコンはオレンジ色をしていますが、いつの頃からか同じ晴れでも猛暑日予想の場合は赤色のアイコンが使われるようになっています。描かれている太陽のマークも光の放射部分が直線ではなくかぎ型になっていて、ジリジリとした暑さをうまく表現しています。で、梅雨明け以降、yamanekoが暮らす多摩地方ではその真っ赤なアイコンがずらっと並ぶ状況が続いていて、スマホの画面から異常事態感が伝わってきます。日中外に出かけようものなら真上から降ってくる光線に射貫かれ、地球温暖化、というより熱暑化もここに極まれりといったところです。(いやまだこんなもんじゃ済まないか)
ということで、今月の野山歩きは高原の涼しさを求めて越後湯沢に行ってみることにしました。スキーの聖地に真夏に訪れる形ですが、ロープウェイで稜線に上がると「湯沢高原パノラマパーク」というリゾート施設があり、高山植物園などもあるというyamanekoにとっては嬉しい場所。そもそも新潟県にはあまり行ったことがないのでちょっと楽しみです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前7時半にドリーム号Ⅲで出発しました。圏央道から鶴ヶ島JCTで関越道に入り、ひたすら北上。新潟県に入るとすぐに目的地の越後湯沢です。国境のトンネルを抜けるとそこは雪国…ではなく、多摩丘陵と同じ猛暑が待ち構えていました。そして、午前10時、湯沢温泉のロープウェイ乗り場に到着しました。車のドアを開けると痛いくらいの暑さ。「嘘だろ…」とつい声にしてしまうほどでした。
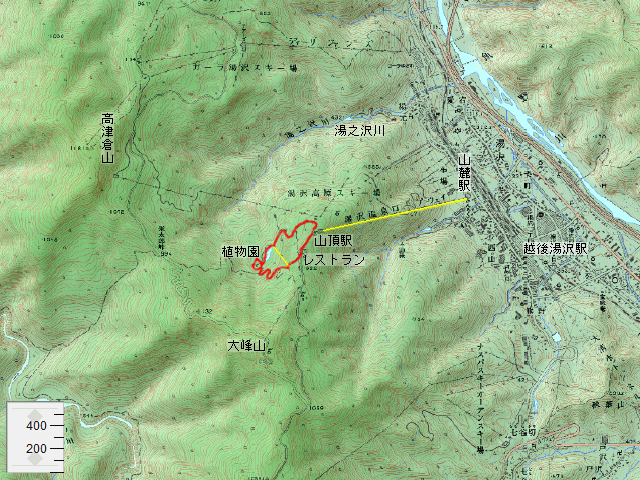 |
Kashmir3D |
今日はまずロープウェイで稜線に上がります。この稜線は大峰山から北東に延びて湯之沢川に下る尾根で、その中ほどに降り立つ形になります。その稜線の反対側斜面に湯沢高原パノラマパークが設けられていて、今日はそこを散策する予定です。
駐車場に車を停めて準備をしていると、頭上をゴンドラが降りてきました。20分おきに出発するダイヤなので、この分で行くとこのゴンドラに乗って行くことになりそうです。
| 山頂駅 |
そしてやっぱりそのゴンドラに乗って山頂駅にやってきました。平日ということもあってか乗客は10人弱。定員166人なんだそうですが。
| 山頂駅 |
山頂駅を出るとこんな感じ。そこには涼しい風が吹き渡り…なんてことはまったくなく、まさに猛暑真っ只中でした。標高は870mくらい。やっぱり1千m超えでなければ涼しさはないか。
| 北方向 |
展望デッキから北方向の眺め。魚野川が造った低地が北に向かって遥かに続いています。南魚沼の田園地帯ですね。
ひとしきり眺望を楽しんでから歩き出しました。時刻は10時50分です。正面に見えているのは高津倉山。ゲレンデが見えていますが、そこに行くにはここから眼下の谷をまたぐロープウェイに乗り換える必要があります。
上がってきた斜面の反対側、西側斜面を少し下ると湿生花園や高山植物園があるはずです。そこまでの道々にも何かあるかもしれません。ただこの猛暑では植物の状態はあまり期待できないかもしれませんが。
| キツリフネ |
まずは車道を下っていきます。脇の法面は道に沿って草刈りがされている途中のようで、今日の作業はこれから始まるといった感じでした。そんな中見つけたキツリフネ。花冠はツリフネソウと同様に吊り下げられる構造で、長い距でバランスを取るようにしてぶら下がっています。距はツリフネソウのように渦巻き状にはならず、先端がわずかに丸まる程度。
| イヌトウバナ |
路傍に咲いていたイヌトウバナ。地味です。おそらく今日の草刈り作業で刈られてしまうのでは。
| ウバユリ |
草むらからにゅっと突き出ているのはウバユリの花茎です。花付きが良いようで10数個の花を付けていました。花冠は満開の状態でもこのくらいしか開きません。
| ヒヨドリバナ |
ヒヨドリバナ。こちらはこれから満開を迎えるところです。優雅に飛ぶアサギマダラが好んでやって来ます。ヒヨドリが鳴く頃に咲くというのが名の由来だそうですが、ヒヨドリは年中鳴いていて、むしろ冬にこそ声高に鳴いている印象なのですが。植物の名前ってけっこう適当だったりしますよね。
| ウド |
このポップな感じのものはウドの若い果実です。果実の付き方がヤツデのそれに似ていますね。同じウコギ科ですし。若芽は春の山菜として好まれ、農家さんで栽培もされていますが、この果実を食べるという話は聞いたことがありません。ネットを見ると一応可食とありましたが。マイナーなのは若芽が有名過ぎるからでしょうか。
車道をだらだらと下って行きます。風はほとんどなく、これで日影がなければ厳しい状況です。
| ウワバミソウ |
ツキノワグマの好物と言われるウワバミソウ。蟒蛇(うわばみ=大蛇)が出そうな山中の湿った所に生えるというネーミングだそうです。そんな植物は他にもたくさんあるでしょうが。写真のものは雌株で、葉腋(葉の付け根)にある白い塊は花序。小さな花が寄り集まって咲いている状態です。
| 湿性花園 |
スタートして20分、湿性花園まで下りて来ました。地形的には山腹の斜面の途中ですが、ちょうどこの辺りが小さなテーブル状になっていて、そこに湿地や池などができているといったところです。右手にはヘメロカリスが咲いていますが、植栽のものでしょう。というかここ湿性花園やこの先の高山植物園も「園」と付くように多くの植物が植栽で、自生のものはあまりないと思います。
| ミズギボウシ |
これはミズギボウシですね。ギボウシの仲間の中では最も葉が細く、ほぼ線形をしています。生えている状況からこれは自生の可能性あり。
| テカリダケキリンソウ |
花の様子からマンネングサの仲間であることは分かりますが、葉の形は見慣れないものです。調べてみるとどうやらテカリダケマンネングサという種のよう。テカリダケとは南アルプス南部に位置する光岳(2591m)のことで、日本百名山の一つ。ここに自生地があるのだそうです。ハクサン◯◯とかタテヤマ◯◯とか、名山の名を冠する高山植物は多いですね。
| オモダカ |
遠目だったので細部は見えませんでしたが、これはオモダカでしょうか。アギナシとよく似ていて、葉が全体に細めとか葉の先端が尖っているか鈍いかとか、見分けポイントが細かいのです。あと、オモダカは水の中に生えることも少なくないですが、アギナシはどちらかというと陸派だとか。
| オオバセンキュウ |
これはオオバセンキュウか。セリ科、特にシシウド属は似たものが多くて分かりにくいです。。
| 湿性花園 |
湿性花園の奥まで歩いて行って振り返った図。写真では涼しげですが、日差しを遮るものがなく、とにかく暑いです。
| 盛夏 |
湿性花園を抜けて高山植物園へ。夏空です。
| キンロバイ |
起伏のある斜面がさりげなく小さな区画に区切られていて、そこで様々な植物が咲いていました。これはキンロバイ。本来は亜高山帯から高山帯に生え、背は低いですがこれでも立派な樹木。花冠の大きさは2cmほどです。
| サンカヨウ |
サンカヨウは果実が熟し始める季節です。コバルトブルーですが表面が粉をふいたようになっていて、やや白みがかっています。葉の形もこの花の特徴の一つ。腎円形と呼ばれる形です。
| サワヒヨドリ |
日当たりの良い湿った環境に生えるサワヒヨドリ。小さな筒状化が寄り集まっています。今日は暑すぎて蝶も来ないか。
| 高山植物園 |
高山植物園はこんな感じのところ。なだらかな斜面になっています。
| クサレダマ |
クサレダマ。漢字では「草蓮玉」と書きます。別名をイオウソウ。花の色が硫黄の結晶に似ているというこじつけ。タマゴヤキソウでも良かったのではとつっこみたくなります。
| ??? |
これは…、ソバナのようでもありますが、やや色が濃いような。何ですかね。
| ヤマホタルブクロ |
こちらはヤマホタルブクロですね。(きっぱり) 身近な公園でよく見る花です。これは高山植物園に意図して植えられたものなのか。それとも周囲の山から入り込んできたものか。いずれにしても堂々と咲いていました。逞しさを感じます。
| ハクサンオミナエシ |
ハクサンオミナエシ。オミナエシの山地型です。オミナエシより背が低く、花序もきゅっとまとまっている感じがします。
| チダケサシ |
高山植物園といいつつ見慣れた花も多いですね。これはチダケサシ。多摩丘陵ではもう花期は終わりました。
| レンゲショウマ |
レンゲショウマの蕾です。なんだかポップですね。開花は8月下旬。なかなか人気のある花で、奥多摩の御嶽山ではシーズンにはどっと人が繰り出したりします。
| ヒメフウロ |
これはヒメフウロ。葉に特徴があり、小葉が細かく裂ける三出複葉となっています。図鑑には塩を焼いたような臭気があると解説されていましたが、焼き塩…どんな匂いだっけ? と考えてしまいました。
| ツリガネニンジン |
ツリガネニンジン、あるいはハマシャジンかもしれません。ツリガネニンジンの仲間も見分けにくいんですよね。そんなときは「…の仲間」と言っておくにかぎります。
高山植物園はロックガーデンのようになっているところもあり、写真のようなデッキもありました。
| ソバナ |
これはソバナですね。漢字では「岨菜」。「岨」は「そば」と読み、切り立った岸壁や岩肌を指す言葉。険阻な岩場に咲くことからこの名が付いたとのことです。yamanekoはこれまで何度も出会っていますが、中でも丹沢の加入道山での出会いをよく思い出します。岸壁を岩に抱きついて横ばいするようにパスしなければならない箇所があり、その手前で一旦心を落ち着けてさあ取りかかるかと踏み出そうとしたら目の前にソバナが。「おお、これこそ文字どおりの岨菜」とハッとしました。あの時味わったスリルとソバナの可憐さがセットで今でも記憶に残っているのです。
| キバナノヤマオダマキ |
夏の山地で見かける浴衣美人。キバナノヤマオダマキです。スッと立つ姿が夕涼みの和装の女性をイメージさせるのです。yamaneko独特の感性ですが。
| ミヤマオダマキ |
濃い青紫色の萼片と白い花弁の組み合わせはミヤマオダマキ。キバナノヤマオダマキが浴衣美人なら、こちらは紺スーツに白ブラウスの新人OLですね。(大丈夫か、この感性)
| ヤマオダマキ |
おっと、こちらは赤紫色の萼片と黄色の花弁。ヤマオダマキです。この色の取り合わせだとしたら…、披露宴に呼ばれレンタルドレスでおしゃれした新郎の女友達といったところか。(設定が細かいですか。)
| オオバギボウシ |
オオバギボウシ。今が盛りと咲き誇っています。これも身近な公園でよく見かける花です。顔なじみに出会った感じ。
| ホソバヒナウスユキソウ |
ホソバヒナウスユキソウは高山帯の蛇紋岩質の岩場に生えるというかなり生育環境が限定されている花です。日本では自生のものは谷川岳と尾瀬の至仏山に見られるそうです。yamaneko的には、霧の中で水滴を身にまとって寒そうに揺れている、そんなイメージです。
| ヒメコウジ |
ぱっと見、アカモノかと思いましたが、よく見ると萼が白いし(アカモノは赤色)、花の形も口がすぼまった壺型(同じく鐘型)。何だこりゃと調べてみたら、どうやらヒメコウジのようでした。北アメリカ北部原産で、アカモノと同じツツジ科シラタマノキ属でした。とはいえ、柑子ってミカンなんだけど。
| コケトウバナ |
あまり見慣れない花です。花冠や葉の様子からシソ科だろうとは推察ができますが。で、またまた図鑑をめくったところ、これはおそらくコケトウバナ。自生のものは奈良県内と屋久島に分布しているとのこと。なんでそこ?
| ヒガシニホントカゲ |
メタリックブルーの尻尾を持つのはヒガシニホントカゲの幼体。全体にぬめっとした光沢がありますが、触るとしっとりとはしているものの滑りはあまり感じません。見た目そっくりなニホントカゲというものもあって、近年まで同一種とされていたそうですが、DNA解析の結果別種と判明し、西日本に棲むものをこれまでどおりニホントカゲ、東日本のものをヒガシニホントカゲとすることになったそうです。
| シナノナデシコ |
シナノナデシコ。ミヤマナデシコの別名をもつとおり、山地の河原や荒れ地に生える花だそうです。本家のナデシコは花弁の先が千々に裂け、ある種妖艶な派手さがありますが、こちらは裂けるというよりちょっとギザギザになっている程度。ただ、「大和撫子」といった場合のナデシコはこちらの方がふさわしいような気がします。
さて、時刻は11時50分。湯沢高原での野山歩きはまだ続きます。(後編に続く)