
夜叉神峠・高谷山 ~白峰展望の尾根へ(後編)~
 |
(後編) |
【山梨県 南アルプス市 令和2年9月22日(火)】
夜叉神峠への野山歩き。後編です。(前編はこちら) さて、白峰三山はどんな姿を見せてくれるでしょうか。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
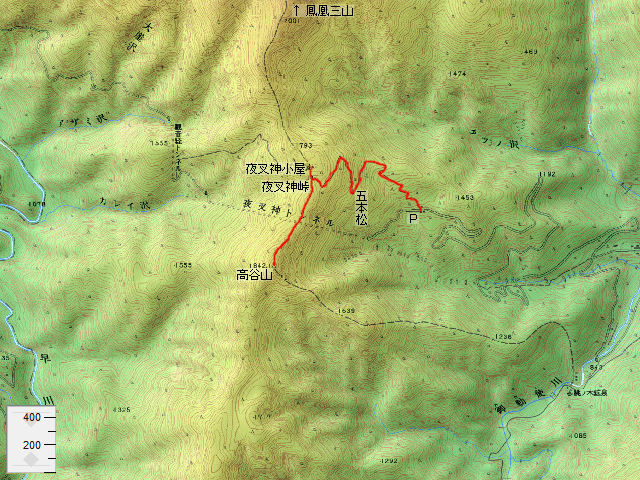 |
Kashmir3D |
標高1400mの登山口を出発したのは午前8時30分。山腹のつづら折りを登り、五本松をすぎて、夜叉神峠のほど近くまでやって来ました。時刻は10時になったところです。
| ハウチワカエデ |
ハウチワカエデ。陽を透かしてまるで新緑のようですね。でも、実際には今は紅葉を待つ季節。夜叉神峠が錦に彩られるまでにはあと1箇月くらいはかかりそうです。
| シラネセンキュウ |
これはシラネセンキュウですね。漢字では「白根川芎」と書き、漢方薬の川芎の元となる植物に似ていて、日光白根山に多く見られたことからこの名が付いたとされています。yamanekoが自然観察を始めた頃に出会った思い出のある植物です。
傾斜が少し緩くなってきました。峠までそう遠くないようです。
早くも紅葉している木が。ナナカマドでした。
登山道の雰囲気が変わってきましたね。
そして水平移動する感じになってきました。
10時20分、夜叉神峠に到着しました。予想に反し、樹木が茂っていて広々とした眺望はありませんでした。展望台は峠を右折して数分のところにある山小屋前にあるようです。
| 峠の句碑 |
峠の脇に石碑がありました。
昔この地で天地を裂くような災厄をなしてたびたび住民を苦しめていた夜叉神があり、これを鎮めるため村人はこの峠に祠を祀って鎮めたのだそうです。その故事を記した石碑かと思いきや、何やら俳句のようなものが刻まれていました。調べてみると、戦後まもなく、地元の新聞社が選定した観光地(夜叉神峠もその一つ)を対象に句を公募し、それを刻んだものだそうです。立派です。
峠には長居せず、左折して高谷山に向かって稜線を辿ります。
おっ、梢の間から南アルプスの稜線が見えました。雲を頂いています。
夜叉神峠と高谷山との標高差は70mくらい。急な上りはほとんどありません。
稜線の明るい森を行く。
きれいな円形のキノコ。いかにも毒がありそうですが…。
東側はカラマツの森。水源涵養保安林として整備されているようです。
| 富士山遠望 |
その梢越しに富士山が望めました。
もふもふの苔。この辺り、霧や雲に覆われることも多いのでしょうね。苔がいきいきしています。
| 高谷山山頂 |
10時45分、高谷山の山頂に到着しました。登山口から2時間ちょっと。ガイドブックのコースタイムは1時間40分です。我々二人以外はだーれもいません。
南アルプス国立公園、いい響きですね。前衛の小山とはいえ、南アルプスの一端に登ったという満足感が湧いてきました。標高は1842mです。
| 三等三角点 |
で、こちらが三角点。周囲をこれだけの樹木に囲まれていて測量できるのだろうか、といつも思うのですが、設置当時は木が刈り払われていたのかも。そして、もしかしたら1回測量したら、目印として石柱は埋めるものの、あらためてこの標識を使って測量を行うといったことはしないということでしょうか。そうであれば納得がいきます。
ちなみに、この標識を損壊させると2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となるそうです。
高谷山の山頂からわずかに望める南アルプスの主稜線。あれはどの山だろうか?
その雄大な眺望が気になるところ。小休止後、展望広場のある山小屋を目指して引き返しました。
| オオミヤマガマズミ |
往きには気がつかなかったオオミヤマガマズミの赤い実。葉よりも上に突き出るように付いています。ミヤマガマズミの変種で標高の高い山で見られるものだそうです。
| フウリンウメモドキ |
オオミヤマガマズミのすぐ近くに生えていたフウリンウメモドキ。こちらは赤い実が葉から下に垂れ下がるように付いています。風鈴の名の由縁ですね。
11時20分、峠まで戻ってきました。そのまま直進して山小屋に向かいます。
峠から夜叉神小屋までは、傾斜はやや急ですが、所要わずか2分。
小屋らしき建物が見えました。
| 夜叉神小屋 |
そして夜叉神小屋に到着。おお、いい感じの山小屋です。
山小屋の前には展望広場。立派な標識が設置されていました。
| 白峰三山 |
どどーん! と、白峰三山。北岳(3193m)、間ノ岳(3190m)、農鳥岳(3026m)、揃い踏みです。ちなみに「白峰」と書いて「しらね」と読むのだそうです。
ちょうど3000mくらいの所に雲がかかっていて、それぞれの山頂は間ノ岳がかろうじて見えているだけでした(あとは心眼で。)。でも、稜線から切れ落ちる谷の深さが半端ない。この威圧感、迫り来る巨神兵か。
| ウメバチソウ |
ちょっと早めの昼食をと腰を下ろしたら、そこにウメバチソウが。草原の花というイメージですが、こんなところで出会うなんて。
| キャンプ場 |
山小屋の横にはテント場がありました。ここで泊まって鳳凰三山に向かう人もいるんでしょうね。
| 下山開始 |
展望広場で約1時間休憩した後、12時20分、下山を開始しました。
復路は往路より早く感じるのはなぜなんだろう。まあ、下りというのもありますが。
苔と茸。しゃがんだままじっと見ていると、時間の流れがゆっくりになったような気がします。
るんるんと下る妻。上機嫌のようです。昔は山仕事や狩りのためにこの道を登り下りしたんでしょうね。その途中で祠に手を合わせ、収穫や安全を祈ったのだと思います。まさに生活の場だったということでしょうね。
| ツリフネソウ |
往きには気がつかなかったツリフネソウ。果実もできつつあるようです。
| 下山完了 |
13時30分、登山口まで降りてきました。怪我もなく戻ってこられて良かった。あの石祠の神様に感謝です。
| ヒュッテ夜叉神 |
ザックを車に積み込み、まずは整理体操。そしてヒュッテ夜叉神で買ったカップアイスを食べながらまったりとしました。峠からの大展望を思い出しながら。ピークが雲に隠されていたのは残念でしたが、山塊の大きさをリアルに感じられたことがなにより感動でした。
さて、帰りの中央道の渋滞を考えると、あまりゆっくりもしていられません。14時、ドリーム号Ⅲで山を下りました。
そして中央道。笹子トンネルの手前から渋滞していました。この辺りから渋滞が始まるとなると、大月から小仏トンネルを越えるまでびっちり渋滞していることが予想されます。
笹子トンネルを越えるといったん流れ始め、河口湖線との分岐まではスイスイ行けました。そしてここで決断を。渋滞していない河口湖線に入り、山中湖、須走、御殿場と走って、東名高速経由で帰ることにしました。距離的にはかなりの遠回りですが、びっちり詰まった中央道の渋滞は高ストレスにさらされることとなるので、あり得る選択なのです。
実際、東名高速は大井松田周辺で若干混んでいた程度で、比較的平穏な気持ちを保ったまま帰宅することができました。そういった意味では、遠回りも悪くなかったということです。ただ時間的にどの程度早く着いたかは分かりませんが。