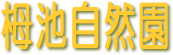
栂池自然園 ~北アルプスの花々(栂池・後編)~
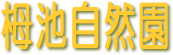 |
(後編) |
【長野県 小谷村 平成24年7月29日(日)】
栂池高原での花巡り、いよいよ後編です。(中編はこちら)
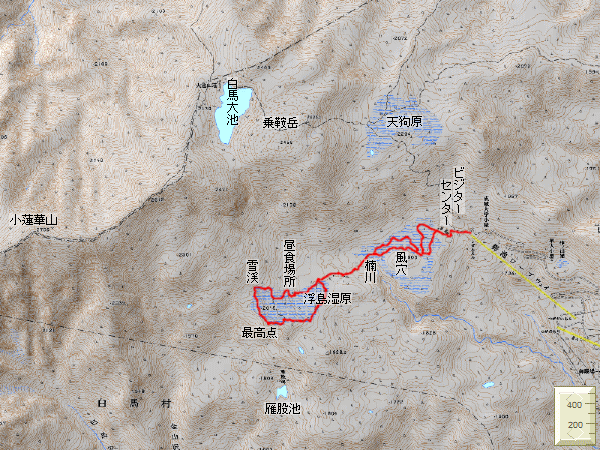 Kashmir 3D |
浮島湿原を過ぎ、栂池自然園の最奥部に近づいてきました。この辺りまでくると観光客っぽい人はほとんどいません。
| モウセン池 |
12時30分、モウセン池までやって来ました。その名のとおりモウセンゴケが群生しています。奥に見える尾根が栂池自然園の最高地点です。
| ノウゴウイチゴ |
ノウゴウイチゴ。聞き慣れない名前のイチゴですね。漢字では「能郷苺」と書き、能郷とは発見された場所の岐阜県能郷村のことだそうです(能郷村は明治時代の2回の合併で西根尾村、根尾村となり、平成16年に本巣市になっています。)。シロバナノヘビイチゴによく似ていますが、図鑑には相違点としてノウゴウイチゴの葉には光沢がないと記述されています。確かに葉はマットな質感です。
| サンカヨウ |
いよいよ尾根に近づいてきました。ここからしばらく湿原とはさよならです。
サンカヨウの花がまだ残っていてくれました。ちょっとした感動です。この花を見るのは何年ぶりでしょうか。初めて見たのは10数年前。広島県と島根県との県境にある猿政山でした。
| ハクサンコザクラ |
雪渓の残る尾根に出ました。その雪渓の途切れるところ、融雪跡一面にハクサンコザクラの群落が。一株は高さ10~15㎝ほどと小さいですが、紫色のくっきりとした顔立ちをしていて、よく目立ちます。突然現れた花畑に一瞬声を失いました。風に細かく揺れる姿も可憐です。
| イワナシ |
おっ、これは。この葉の質感はイワナシですね。ということはこの実はイワナシの実ということか。小さいながらちゃんと梨の味がすると聞いたことがありますが、ちょっと試食するのはやめておきました。
| 尾根道 |
尾根道はこんな感じ。オオシラビソの森です。結構太いのもありますね。
| ヤマハハコ |
これはヤマハハコですね。白い花弁のように見えるのは葉が変化した総苞片というもの。本当の花は中央の緑色の部分です。これから黄色くなります。これがハハコグサに似ているということでヤマハハコという名が付けられたとのことです。
| ハナニガナ |
低山からこんな高いところまで、環境適応能力の高いハナニガナです。
| 雁股池 |
尾根道を歩いていると、ところどころ自然園とは反対側の展望が開けている場所がありました。こちら側は急激に高度を下げています。眼下に見えるのは雁股池。やはり小さな平坦地がいくつもあってそこに池なり湿地なりができているようです。
| 急降下 |
標高2020mの最高地点を過ぎると、道は一気に急降下していきます。一度転がり始めたらそのまま麓まで行ってしまいそうです。
| ミヤマアキノキリンソウ |
野山で見られるアキノキリンソウの高山適応型。本家の方はもう少し花がまばらに付きますが、ミヤマアキノキリンソウはちょっと大きめの頭花が茎頂に寄り集まって咲きます。
| ハクサンオミナエシ |
「ハクサン(白山)」と名が付く高山植物は多くあります。このハクサンオミナエシもそのうちの一つ。昔、登山が一般的でなかった時代に、信仰の山であった白山には多くの人が訪れ、その際様々な高山植物を目にしたでしょう。そしてそこで発見された植物に白山の名を冠したのだと思います。これは同様に信仰の山だった「立山」にも同じことが言えると思います。
| マルバダケブキ |
人が立ち入れない急な斜面にマルバダケブキが咲いています。周囲の植物から頭一つ抜け出して、吹き上げる風に揺られていました。
| ショウジョウバカマ |
道は森の中に入ってきました。ところどころに小さな残雪があり、それが周囲の気温を低く保っているようです。そのせいかまだショウジョウバカマが咲いていました。もう8月がそこまで来ているというのに。
| シラネアオイ |
そしてシラネアオイも。深い森の中に咲く貴婦人のような花です。先月、八海山で見かけたときも感動しましたが、ここで出会ってあらためて感動しました。花そのものの美しさもさることながら、こういった不意の出会いが感動を大きくするのだと思います。
| サンカヨウ |
サンカヨウの花が3輪。まだフレッシュな感じです。ショウジョウバカマとシラネアオイとこのサンカヨウが半径数mの範囲に同時に咲いていたというちょっとした奇跡。いや花の季節が一度にやってくる高山ならあながち不思議ではない風景なのかもしれません。
| オオバスノキ |
オオバスノキ。低山からこんな高い山にまで分布する順応性の高いやつです。スノキとは「酢の木」で、葉を噛むと酸味があるから。自然観察会では定番のネタですね。
| 浮島湿原 |
1時40分、浮島湿原まで下りてきました。急に広々としたところで出てきて、現れる植物もガラリと変わります。
ワタスゲの向こうにはまさに浮島が。ここは楽園か?
| イワイチョウ |
出ましたイワイチョウ。いつ見ても清楚ですね。
| リュウキンカ |
あっという間に楠川まで戻ってきました。川岸に咲いているのはリュウキンカです。普通は春の花ですが、今ここは春であり夏であるわけです。
| |
|||
| オオレイジンソウ |
これはオオレイジンソウです。普通(?)のレイジンソウに比して花はやや大きいくらいですが、茎はがっしりと太く、全体の高さも1mを超えてきます。それにしても虫が入りづらそうな花冠の構造をしていますね。
| タニギキョウ |
水気の多いところを好むタニギキョウ。背丈はせいぜい10㎝。花冠の大きさは1㎝に満たない小さな花です。
| ミズバショウ湿原 |
そうこうしているうちにミズバショウ湿原。帰り道はいつも早い気がします。ときおりこうやって夏の青空が顔を覗かせます。
| オオバタケシマラン |
ここにもオオバタケシマランが。ランという名ですがユリの仲間です。
もうじき散策路も終点へ。天上の楽園もあとわずかです。
| 栂池ヒュッテ記念館 |
2時55分、栂池ヒュッテ記念館まで帰ってきました。雰囲気のある建物ですね。ビジターセンターはこのすぐ隣。
| ベニバナイチヤクソウ |
朝9時過ぎから午後3時過ぎまでの6時間、栂池自然園を十分に堪能しました。売店でソフトクリームを食べて落ち着いてから園を出て、ケーブルカーの駅に向かいます。その道すがらにもこんな花が。これはベニバナイチヤクソウです。帰り道も油断がなりません。
| オガラバナ |
これはオガラバナ。カエデの仲間なんですが、花だけ見るとちょっとそうは見えませんね。オガラとは「麻幹」と書き、皮を剥いだ麻の茎のこと。この木の幹がオガラのように軟らかいのでこの名が付けられたとのことです。
| |
|||
| オニシオガマ |
そしてゴンドラ駅の周辺にもこんな花が。シオガマギクの仲間の中でも特に大型のオニシオガマです。まっすぐに立ち、堂々とした印象です。
| ゴンドラ駅 |
午後4時、ゴンドラに乗って下界に下りて行きます。
この2日間、北アルプスの花を楽しみました。昨日は八方山、今日は栂池高原。歩いた標高はそれぞれ約1800mから2000mまでとほぼ同じで、水平距離も8㎞ほどしか離れていませんが、八方山は乾いた尾根、栂池高原は湿原と環境が違うことから、見られる植物もかなり異なっていました。手帳を見返してみると、八方山ではメモっているだけで49種、栂池高原では69種もあり、そのうち重複しているのはタテヤマリンドウ、イワイチョウ、ゼンテイカなど10種に満たず、ざっと100種以上の植物に出会ったことになります。ほんと飽きない2日間でした。
ゴンドラを下りると4時半過ぎ。宿に戻って温泉に浸かり、オリンピックを見ながらまったりとしました。ああ、これで今年の夏は終わりです。明日からはまた暑い日常に戻らなければ(早く涼しくならないかな。)。