
高塚山 〜南房総春の海(後編)〜
 |
(後編) |
【千葉県 南房総市 令和2年2月9日(日)】
南房総、高塚山での野山歩き。後編です。(前編はこちら)
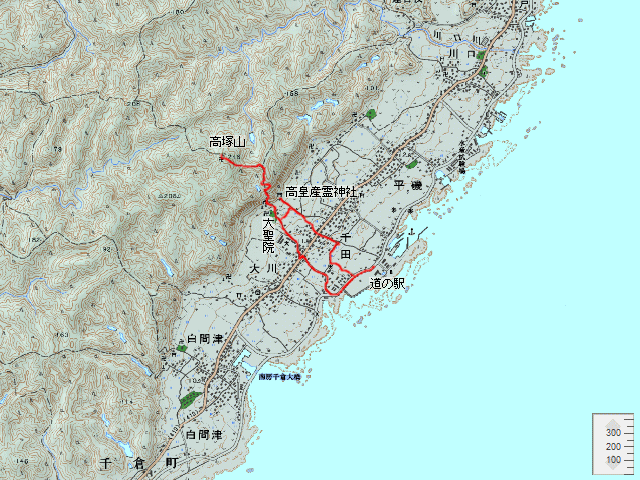 |
Kashmir 3D |
道の駅「ちくら潮風王国」をスタートして、大聖院を経由し、急な崖を登って高塚山の山頂手前までやって来ました。時刻は12時20分です。
山頂が近くなるとまた傾斜が増してきました。あとちょっとなんですが。
| アカガシ |
これはさっきのマテバシイのドングリとは明らかに違うものです。アカガシでしょうか。ドングリの殻斗(帽子の部分)には横縞模様のものと鱗模様のものとがあって、これは横縞ですね。あと、常緑樹か落葉樹か、とか、開花したその年に実が熟すか、翌年に実が熟すか、といった分類ができ、グループ分けをすると興味深いです。(参考まで)
斜度が一段ときつくなりました。あの先が山頂見たいです。
| 山頂 |
12時25分、階段の先に山頂が現れました。なんと山門が潰れています。資料によると、左右に不動明王ではなく風神雷神が鎮座していたということですが、今は見る影もありません。風神を倒すとは、恐るべし台風です。
| 太平洋 |
ここからに眺め、最高です。なんならアメリカくらいまで見えるのでは。肝心の黒潮の流れは…、うーん沿岸に色の濃い帯は見えますが、こんなに近くに流れているとも思えませんよね。
| 奥の院 |
奥に瓦葺の建物がありました。これが奥の院ですね。感謝の気持ちを込めて参拝しました。
| 最高点 |
参拝を終えて奥の院の裏手にまわると、一段高いところがありました。ここが最高点のようです。木立の間から眺望がありそう。
| 西側の眺望 |
おお、これまで登ってきた側とは反対の方角の眺望が開けています。富士山がこんなに大きく見えるとは。房総半島は富士山展望の穴場ですね。今まで知りませんんでした。写真左にある影の濃い山は、州崎(房総半島の南西端)にある大山です。
ひとしきり眺望を楽しんだ後、下山開始。見上げると吸い込まれそうな青空です。
| ヤブツバキ |
ヤブツバキ。照葉樹林でよく見かける木です。激しい台風を耐えきった感じですね。この木には蜜を目当てによく鳥がやってきます。メジロとかヒヨドリとか。yamanekoも子供の頃、花冠を採って根元の萼を外し、蜜を吸って遊んでいました。
| サンショウ |
これはサンショウですね。この時期に若葉を展開しているなんて、いかにここが温暖な場所なのかが分かります。それとも時期を間違えたか。
どんどん下って行き、鳥居のところまで戻ってきました。いつも帰り道は早く感じます。
| タチツボスミレ |
こちらには元気なタチツボスミレが。今日の日差しを春と間違えているかもしれませんね。
明るい森の中を下っていると、何やら倒木をチェックしている年配の方に出会いました。声をかけてみると、その方はこの辺りを中心に野山歩きをしている方で、去年の台風被害の直後から仲間と登山道の復旧・整備をされているとのこと。どおりで倒木が処理され安全に歩けるようになっているはずです。特段地元自治体からの委託ということでもなく、全くのボランティア。定期的に点検に来ているとのことで、台風直後の写真を見せてもらいましたが、よくここまで復旧させたものだと感心しました。よっぽど地元の自然を愛しているんでしょうね。
ボランティアの方にお礼を言って、再び下り始めました。
この辺りの木は微妙に葉が残っていますが、ひょっとしてこれは本来常緑樹のものが去年の台風で葉がちぎれ飛んだ状態ということなのでしょうか。確かに風が強く当たる稜線上の樹木がこの状態になっているような気がします。
小さな入り江を跨ぐアーチ橋が見えます。「南房地倉大橋」というのだそうです。漁港があるので下を船が通るだけの高さが必要だったんですね。
| ツワブキ |
ツワブキです。花茎は枯れてしまっていますが、腎臓形をした特徴的な葉はまだ健在。それでも冬の間はつやつやとした深い緑色をしてるものが、今はやや色があせてきた感じになっています。この葉の様子から「艶蕗(つやぶき)」、ツワブキと転訛したとのことです。
急な階段を下っていきます。斜度は上りより下りのときの方がきつく感じますね。
12時55分、森の出口までやって来ました。なんだかんだでけっこう汗をかきました。
しばし休憩。遠くの水平線にコンテナ船が見えました。望遠でアップにしてみると…、「EVERGREEN」と描いてありました。どうやら台湾の海運会社の船のようです。
大聖院の墓所を通らせてもらって、次に高皇産霊神社に向かいます。
黄色のスイセンは見るからに暖かそうな色合い。あの辺りだけ一段と気温が高くなっていそうな気がします。
| 高皇産霊神社 |
休耕田の畦道を通って神社へ。結構立派な構えのようです。
参道には人の気配はありませんでした。ところで「高皇産霊」とはあまり聞かない名前です。読みは「たかみむすび」。神話では最も古い時代の神とされ、天地開闢の際に現れた3人の神のうちの一人だそうです。調べてみるとyamanekoが知らないだけで、この名前の神社は日本のあちらこちらにあるようでした。ちなみに、「高皇産霊」は日本書紀での表記だそうで、古事記では「高御産巣日」とより読み音に近い文字が充てられているようです。
境内も静寂に包まれていました。綺麗に整備されていてゴミ一つありません。神職の方の居宅が併設されているようでもないので、どなたかが管理されているのでしょう。
| 昼食 |
境内の裏手に山道があり、その入り口に座って昼食としました。カップラーメンと道の駅で買ったクジラメンチです。お湯は水筒で持参しました。
| アオキ |
アオキが芽吹き始めていますね。もう春だ。
休憩を終えて神社を後にしました。道の駅に向かいましょう。それにしても雲一つない日本晴れです。(「日本晴れ」って死語?)
集落の中の小径を歩いて行きます。遠くに花畑が見えます。そういえば、花摘みもしなくては。
振り返ると、今日の野山歩きを楽しませてくれた高塚山の山並。感謝です。ありがとー!
| 観光花摘み園 |
最後に道の駅の前の観光花摘み園でヤグルマギクやキンセンカ、ストックなどを摘んで帰りました。結構な人出でした。
少し陽が傾いてきました。道の駅を後にし、来た道を金谷の港まで戻ります。16時30分発のフェリーに乗る頃には風は少し弱まったようで、帰りの東京湾はあまり揺れませんでした。
今日は一足早く春を感じることができた野山歩きでした。(これからまだ寒い日はあるでしょうね。)