
高尾山 〜ニリンソウに癒され歩く道(後編)〜
 |
(後編) |
【東京都 八王子市 令和7年4月21日(月)】
花の高尾山を巡る野山歩き。後編です。(前編はこちら)
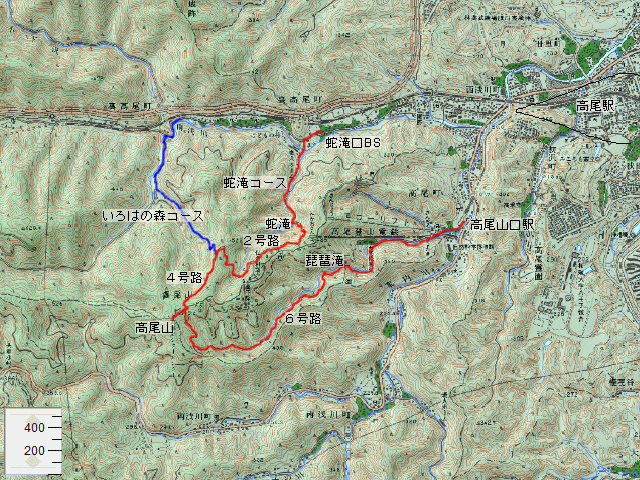 |
Kashmir3D |
9時20分に京王高尾山口駅をスタートし、高尾山の南側の谷筋を通る6号路で登ってきました。この先は、山頂で眺望を楽しんだ後、今度は北側の4号路を歩いて小仏川沿いのバス路線に下る予定です。
眩しい日差し。頭上が開けていることからも山頂が近いことが分かります。
| タチツボスミレ |
これは定番のタチツボスミレでしょうね。今日見かけた3種目のスミレです。あくまでも老眼のyamanekoが認知した範囲でですが。
| カツラ |
ハート形の可愛い葉が枝に並んでいます。これはカツラの葉。ただ、みんながハート形というわけではなく、普通の楕円形の葉を付ける株もあるそうです。カツラは渓畔林を構成する樹木。ここは谷筋のどん詰まりから上がってきたところなので、こういった樹種も自生しているのでしょう。他に渓畔林を構成するものとしては、トチノキ、オヒョウ、サワグルミなどがあります。
| トイレです |
さすが高尾山というか、トイレも2階建て。なにしろ年間300万人ですから。
トイレの前から山頂方向を見ると…。この坂を上ると山頂です。
| 高尾山山頂 |
11時45分、高尾山山頂に到着しました。標高は599mです。おしい!600mまであと1mです。毎年300万人が踏みつけなければ600mを超えていたなんてことは、ないでしょうね。
山頂部は東西に長い形になっています。山頂のモニュメントを過ぎると少し下っていき、右手にはビジターセンターと売店があります。もう木陰で弁当を食べている人もいました。
| 展望所 |
西端まで行くと展望所があります。南西に向いて眺望が開けていて、ちょうど道志の谷筋の奥に富士山が望める形になっていました。
| 心洗われる |
今日は、春霞もなく、くっきりとした富士山の姿を拝むことができました。清々しいです。
富士山の左手に見える山は西丹沢の大室山。右手は道志山塊の赤鞍ヶ岳。その間が道志の谷筋になります。それらの手前に緩やかな稜線を横たわらせているのは石老山です。更にその手前、ここ高尾山との間には相模川が流れています。そう考えるとずいぶんと奥行きのある風景ですね。
ひとしきり眺望を楽しんだ後、近くの木陰に移動し、yamanekoも昼ごはんにしました。いつものとおりコンビニおにぎりです。
| 多摩丘陵 |
展望所から少し引き返したところに南東方向の眺望が得られるところがありました。写真左半分、右ドッグレッグにカーブして奥まで続いている緑のバンドが多摩丘陵です。高尾山の麓の御殿峠に始まり約50km先の横浜まで続いています。写真右半分は相模野台地。相模川が造り上げた河岸段丘でひな壇上の平地になっています。
| 4号路入口 |
12時5分、休憩を終えて再スタートです。まずは、さっきの立派なトイレの手前から北側斜面に下る4号路を行きます。
山腹をトラバース気味に下っていきます。休憩後なので、転ばないように注意です。
| エイザンスミレ |
これはエイザンスミレですね。葉が細かく裂けているのが特徴です。エイザンは叡山(比叡山)という意味だとか。
| ヒトリシズカ |
ヒトリシズカも3人寄ればかしましい? 実際ヒトリシズカは小群落を作ることが多いです。
| ナガバノスミレサイシン |
ハートを縦長にしたような形の葉が特徴的なナガバノスミレサイシン。「ナガバノ」ではないスミレサイシンとははっきりと棲み分けていて、ナガバノスミレサイシンは関東南部から九州までの中央構造線以南の太平洋側に、スミレサイシンは北海道石狩地方から山陰までの日本海側に分布しているそうです。
| ヤマウツボ |
ブナなどの根に寄生しているヤマウツボ。葉緑素を持っていないので全体に白いです。光合成をして自ら栄養を作り出す必要がないんですね。ちなみに、名前のウツボ(靭)は戦の際に矢を持ち運ぶための入れ物のこと。
高尾山の南麓は植林された針葉樹林が広がっていますが、北側は落葉広葉樹の雑木林になっています。こちらの方が気持ちいいですね。
この階段の先でいろはの森コースとクロスするはずです。前を行くのは学生さん風の男女3人組。楽しそうに歩いていました。
| 交差地点 |
いろはの森コースと交差する地点。ここで小休止です。
そして、再スタートしようと歩き始めたところ、さっきの3人組の目の前でツルっと滑って転んでしまいました。「大丈夫ですか?」と声をかけられ恥ずかしい思いをしつつも、立ち上がって照れ隠しに「ここ、危ないですから気を付けて」と言って涼しい顔で歩き始めました。きっと「そちらこそ」と思われていたでしょうね(笑)。
| 通行止め |
そしていろはの森コースに下ろうとしたところ、下から警備員さんらしき人が上がってきて「ここ今から通行止めです」と言って、入口に黄色のテープを張り始めました。どうやら下の方で倒木があったようです。まあ、途中まで下って戻らされるよりも良かったです。
さて、どうしたものかと考え、このまま4号路を進んで、途中から蛇滝コースを下ることにしました。エスケープルートが多いのも高尾山のいいところです。
| 吊り橋 |
ということで、そのまま4号路を下りました。
さっき転んで打った左の尻をさすりながらしばらく行くと森の中に吊り橋が現れました。4号路の名物ポイントです。
| フサザクラ |
その吊り橋を渡りきる直前、目の高さにフサザクラの枝が伸びていて、成長しつつある若い果実を見ることができました。フサザクラという名前ですが桜の仲間ではありません。花も葉も実もこれといった共通点がないにもかかわらず、なぜこの名前?と疑問です。
| タチツボスミレ |
可愛いスミレたち。地上茎があり、細かく裂けた托葉があることから、これもタチツボスミレだと思います。(スミレはみんな同じに見えてしまいます。)
| 分岐 |
12時55分、分岐が現れました。直進すると20m先で1号路に出ます。ここは左手に下りる2号路へ。
| 急降下 |
山頂からここまで、標高差にして120mほど下りましたが、ここから更に急降下です。
| 倒木を活かす |
2号路はマイナーなのか、行きかう人もほとんどいません。すると行く手に倒木が。応急措置なのか、撤去するのではなく、幹にステップが切ってありました。確かに跨ぎにくい太さではありましたが、雨上がりとか足を乗せると滑りやすいのでは。さっき滑って転んだような中高年もいますからね。
| また分岐 |
2号路をしばらく進んでいくとまた分岐が。ここを直進する形で上って行く道が2号路。yamanekoは左に下る蛇滝コースへ向かいます。こういうときに頼りになるのが地図アプリ。分岐で迷うケースがぐんと減りました。ただ、紙の地図も必ず持参するようにしていますが。
| ミヤマシキミ |
ミヤマシキミの花序が満開です。雌雄異株で、これは雄花序です。今朝、6号路を上る途中でミカン科のコクサギを見かけましたが、このミヤマシキミもミカン科です。深山に生えていてシキミに似ているというのが名の由来らしいですが、花は似ても似つかない形をしています。しかも、シキミはマツブサ科。
| キジョラン |
おお、これはキジョランの葉では。漢字では「鬼女蘭」と書き、何やら曰くありげです。ガガイモの仲間によく見られるように、実が熟して裂けると中から種子の白く長い冠毛がわっと出てくるので、これを鬼女が振り乱す白髪に例えたものだそうです。ところで、鬼女ってどこか悲しい存在ですよね。
| シャガ |
シャガはあちこちの山野で目にしますが、本来シャガは果実を作らず根茎を伸ばして分布を拡大するそうなので、種子を作る多くの植物とは違って、自然の移動スピードはかなり遅いと思います(1年で根茎一つ分)。ということは多くは人間の手で植えているということでしょうね。確かにシャガは斜面の土留めとして活用されたりするので。それにしても、種子って効率的に勢力を拡大するための命のカプセルなんですね。
| ホウチャクソウ |
ホウチャクソウに花がぶら下がっています。これで開花状態で、花弁(正確には花弁3個と萼片3個)はほとんど開きません。いったいどんな虫が利用できるのだろうか。と思って調べてみると、どうやらマルハナバチだけを受け入れるようにできているとのことです。雄しべや雌しべも花筒の奥ではなく出口付近まで伸びているようです。へぇー、です。
蛇滝コースに入ってひたすら下ること20分。小さな流れの源頭に至りました。岩場から水が染み出ているようです。これが流れ下って蛇滝になるんでしょうね。
岩場の近くに祠(?)がありました。中には小さな仏像と7柱の祭神の名が書かれた板がありました。いずれも頭に「南無」とあり最後に「神」で終わる名前でしたが(南無青龍大権現神とか)、仏様なのか神様なのかよく分かりません。神仏習合の結果こういうことになっているのでしょうか。
| 青龍堂 |
そこから下ると立派な社が見えました。青龍堂というのだそうです。
| 蛇滝水行道場 |
青龍堂から更に下ると蛇滝水行道場がありました。滝行の道場ということですね。往きにあった琵琶滝にも水行道場があり、高尾山にはこことで2か所あるのだそうです。
水行道場を過ぎると傾斜が緩み、簡易舗装の道になりました。川沿いの道です。
| ミヤマキケマン |
ミヤマキケマン。漢字では「深山黄華鬘」です。華鬘とは仏堂の装飾具の一つだそうです。実際にどんなものなのか知らなかったので華鬘の写真を見てみましたが、特段この花と似ているということはありませんでした。植物の名前って?が多いですね。
| ニリンソウ |
ここにもニリンソウが。ちゃんと二輪咲いていました。今日はいろんなところで癒してくれてありがとう。
| ムラサキケマン |
こちらはムラサキケマン。さっきのミヤマキケマンと仲間同士です。
| 車止め |
車止めが現れました。道はもうほとんど平坦です。
| 圏央道 |
開けたところに出たとたんにこの風景。これまでとギャップがありすぎです。これは圏央道で、八王子JCTからこの谷を橋梁で跨いで、高尾山をトンネルで貫くという巨大インフラの一部です。
バス路線に出て蛇滝口バス停に移動します。ネットで次のバスを調べるとなんと2分後! この正面あたりにバス停があるはずなので、なんとか間に合いそうです。
| 蛇滝口バス停 |
1時44分、バスの時刻と同時にバス停に到着しました。やれやれです。
バスは定刻より3分遅れてやって来ました。満席で座れませんでした。おそらく始点の小仏バス停から満席だったのでしょう。その先に陣馬山方面への登山口があるので、登山客で混む路線なのです。シーズンには同じダイヤで2、3台連なって運行していたりするのです。
結局、終点の高尾駅まで立ったままでしたが、高尾駅からの電車には座れ、乗り継ぎもスムースで、無事に今回の野山歩きを終えることができました。
振り返ってみると今日はずっと道ばたでニリンソウが微笑んでいたように思います。花には本当に癒されますね。野山歩きが止められない所以です。