
高尾山 〜ニリンソウに癒され歩く道(前編)〜
 |
(前編) |
【東京都 八王子市 令和7年4月21日(月)】
yamanekoの暮らす多摩丘陵。早春に始まった草花の開花ラッシュも4月中旬を過ぎて一段落してきた感じです。そうこうするうち、テレビの天気予報でもときどき「夏日」のワードを聞くようになりました。野山では若葉が濃い緑色に変わりつつあるでしょう。yamanekoとしてはこの緑滴る時期の野山を歩かずにはいられません。ということで、今回は登頂者数世界一の高尾山に行ってみることにしました。高尾山は自宅から約10kmと程よく近いのですが、普段あまり訪れることはなく、今回も2年数か月ぶりの野山歩きになります。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前8時過ぎ、通勤時間帯の電車で移動です。八王子駅から中央線で高尾駅に向かい、京王線に乗り換えて一駅、終点の高尾山口駅で下車。駅の電光掲示板に表示された駅名を「たかお
やまぐち」と読んでしまい、一瞬「やまぐち」ってどこだ?と戸惑ったりしつつも、無事にスタート地点に到着しました。平日なので登山者はほどほど、いや、普通に考えれば十分に多いのですが、休日の登山者数が異常なのです。高尾山は。なにしろ年間約300万人だそうですから。
| 高尾山口駅 |
駅前のベンチで装備を整え、ストレッチをして準備完了。降車した人波が途切れたところで、9時20分、スタートです。
| 清滝駅 |
駅から5分ほど歩くとケーブルカーの清滝駅が現れます。ここは登山道の1号路や6号路の基点になっているほか、リフトの乗り場もあり、高尾山登山者の多くが訪れる場所です。
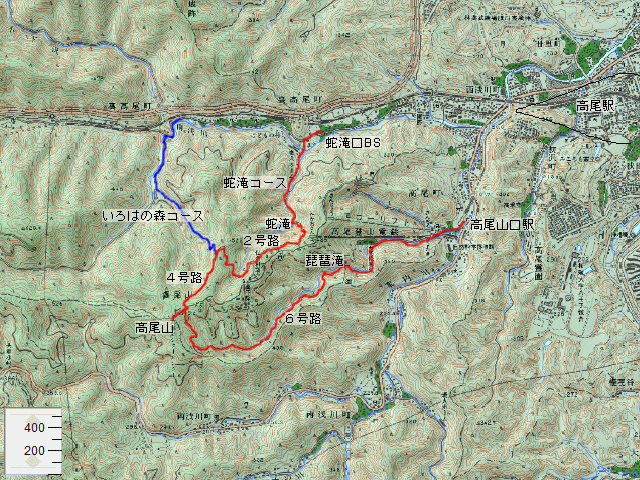 |
Kashmir3D |
今日のルートは、谷筋を遡る6号路で山頂を目指します。下山は4号路を行き、途中からいろはの森コースに入り北斜面となる日影沢を下って、都道に出たらバスでJR高尾駅に戻ってきます。
(ただ、実際には蛇滝コースを下ることになりましたが。)
なお、上の地図は情報が古く、高尾山を貫く圏央道が載っていません。念のため。
| ケーブルカー |
6号路へはケーブルカーを右に見ながら沢沿いの道に入っていきます。
| アメリカスミレサイシン |
路傍に大振りな花冠のスミレが咲いていました。高尾山は「スミレの山」と呼ばれるほどで、様々なスミレを見ることができます。ただ、これは帰化植物のアメリカスミレサイシンではないかと思います。
| ツルカノコソウ |
ツルカノコソウです。ツル性の植物というわけではありませんが、花期が終わるとランナーを伸ばし、その先で新苗を作って増えていきます。
| ニリンソウ |
ニリンソウが咲いていました。道に沿ってそこここに小さな群落を作っています。写真のものは二輪のうちの一輪は花冠が散った後のようです。
右手に東京高尾病院が現れ、ここまでは車の往来があります。この先は歩行者のみ通行可。この時期、6号路は上りの一方通行に規制されていました。
沢沿いの道は少し薄暗いです。ただ、涼しいくらいでありがたいです。
| ヤブタバコ |
左手の岩壁に垂れかかっているのはヤブタバコの葉ですね。水が染み出るような湿った環境を好む植物です。
| ニリンソウ |
こちらのニリンソウは名前のとおり花が二つ付いていました。ちなみに、白い花弁のようにみえるものは萼片です。
| ハナネコノメ |
これはハナネコノメですね。特徴的な赤い葯は既に落ちた後のようです。これはこれで涼やかな感じで好感が持てます。
| 岩屋大師 |
いつの間にか沢は登山道の5mほど下を流れていました。それを橋で跨いだ先に小さな洞穴が。ここは岩屋大師と呼ばれる場所で、弘法大師にまつわる言い伝えのある場所だそうです。
この辺りの登山道は岩場の道になっていますが、浮いた岩がゴロゴロしているわけではないので、それなりに歩きやすいです。、
| コクサギ |
コクサギはミカン科に属する樹木。ミカンの花といえば白色ですが、コクサギの花は薄緑色で葉に紛れて目立ちません。これは雄花ですね。
樹木の葉の付き方には、枝に対して左右に1個ずつ付く「対生」、放射状に付く「輪生」、左右交互に付く「互生」などありますが、コクサギは右、右、左、左、右、右…というふうに付くのが特徴。これを「コクサギ型葉序」といい、ほかにはケンポナシやサルスベリなどでも見られるそうです。
| 琵琶滝 |
スタートから45分、右手に琵琶滝が現れました。登山道からは若干見下ろす感じになります。奥に滝筋が見えていますね。今でもここで滝行が行われるそうです。6号路は一方通行とされていつつも、琵琶滝への往復に限って逆の通行が許されているそうです。
| スギの大木 |
大きな樹木の根元ではその根を踏みつけないよう注意して進みます。樹木保護の意味だけでなく、濡れていたりするとツルッと滑って事故になりかねません。
この季節に森の中を歩く気持ちの良さ。それが水辺の道だったりすると更に癒されます。元気をもらっている感じがします。
| イワボタン |
足元にイワボタンが。さっき見たハナネコノメと同じユキノシタ科の仲間です。花は小さく中央部に数付きますが、今はもう花の時期は終わって種子を作りつつある段階です。
| チドリノキ |
これはチドリノキの葉。モミジやカエデの仲間ですが、葉の様子が旧カエデ科の多くの樹木とは異なり掌状に裂けません(新たな分類ではカエデ科はムクロジ科に統合された)。植物全般からするとこちらの方がオーソドックスなのですが。果実は長い柄を持ち、葉腋からぶら下がります。この様子を千鳥の飛ぶ姿に例えたのがチドリノキの名の由来なのだとか。(写真はまだ若い実)
| ミヤマカタバミ |
ミヤマカタバミの葉はハートを3つくっつけた形をしています。街角で見かけるカタバミの葉よりもかなり大型です。花は3月に咲き終わっています。ここ高尾山には葉裏の毛が少ないカントウミヤマカタバミというのが自生しているそうで、もしかしたらそれかもしれません(残念ながら確認していません)。
標高が上がるにつれ沢の流れとの比高が小さくなり、所々で水辺を歩くことも。水が岩場を流れ下る音は耳に心地よいです。
| ウワバミソウ |
これはウワバミソウの葉。別名をミズナといい、山菜としてはこちらの方がメジャーな呼び名かもしれません。標準和名の方は蟒蛇(うわばみ)が出そうな湿った所に生えるということのようです。ヤマトキホコリによく似ていますが、葉の先端が尾っぽのように長く伸びるているので見分けられます。
| シロミノマンリョウ |
こんなところにシロミノマンリョウが。鳥が種子を運んできたものなのかもしれません。通常、マンリョウの果実は赤色で、従来シロミノマンリョウと区別されていましたが、近年は学名上は同じものとして扱われているそうです。
| ユリワサビ |
山肌から水が染み出しているような湿った環境を好むユリワサビ。花の大きさが1cmに満たない可憐さです。花は4弁で、これはアブラナ科の植物に多く見られる特徴。葉がワサビのそれに似ていますね。ワサビもアブラナ科です。
| ヤマハタザオ |
こちらもアブラナ科に属する植物。ヤマハタザオです。写真では分かりにくいですが花は4弁です。花茎が旗竿のようにすっと伸びるので、それが名の由来になっているのだそう。物干し竿に例えられなくてよかったですね。
| ニリンソウ |
道の畔にはニリンソウが多く見られました。わずかな風に吹かれてみんな揃って揺れる様子に愛嬌を感じます。
流れの脇を歩いていきます。朽ちた倒木は大水のときに流されてきたものでしょうか。
だんだん傾斜が増してきました。こんな場所ではガシガシ登ったりせず、何か面白いものを探しながらゆっくりと歩いていきたいもの。というのは、普段ついつい見逃してしまうものが多く、妻が同行しているといろいろ見つけてくれるので、一人のときはあえてゆっくり歩くよう心がけているのです。
| ヤマルリソウ |
薄青いヤマルリソウ。花冠の直径は1.5cmくらいです。様式化された花のイメージそのままの姿をしています。
| ヤブニンジン |
これはヤブニンジン。日陰を好みます。花をじっくり見ることはあまりないので(小さすぎて)、アップで撮ってみました。うーん、いまいち構造が分からない。
合流する小さな沢を橋で跨いで左手に上っていきます。ここからまた一段と傾斜が増しました。
| コミヤマスミレ |
薄暗く湿ったところに生えるのはコミヤマスミレ。「小宮山」ではなく「小・深山」です。葉の表面には軟毛が密生していて、裏返すと少し紫がかった色をしています。一番の特徴は萼片が反り返っていること。
こういうところを歩くのも変化があって楽しいです。
また橋が現れました。つい渡って左手に行きそうになりますが、そちらは稲荷山コースへのバイパス路。6号路は沢に沿って直進です。「沿って」というより「沢の中を歩いて」というのが正確でしたが。
| 新緑 |
「新緑」。いい響きの言葉です。木々の葉が陽を透かして自ら発光しているかのように輝いています。
沢を離れて山腹を登っていくと、ほどなく階段が現れました。ここまで来ると山頂も遠くありません。
| ツクバキンモンソウ |
階段脇に咲いていたツクバキンモンソウ。シソ科に特徴の唇形花です。その中でツクバキンモンソウは上唇がごく小さいのだそうですが、老眼のyamanekoには見分けは困難です。
| チゴユリ |
多摩丘陵では(というかyamanekoの近所の里山では)既に花期を終えてしまったチゴユリ。1週間ほどタイムスリップした感じでしょうか。
この画角はバリアングル機構のあるカメラだからこそ。さもなくば地表に這いつくばる必要があります。
| ハナイカダ |
葉の真ん中に小さな花を付けるハナイカダ。これは花茎が葉の主脈と合着した結果です。合着している部分が太くなっているのが分かりますね。ただ、合着したとはいえ元々は別の管が通っていたはず。合着後は管も一つになっているのでしょうか。
| ニガイチゴ |
花弁が丸っこいですが、葉の様子からこれはニガイチゴではないかと思います。
階段を登りきると広い場所に出ました。ベンチなどもあり、休憩広場といった感じです。ここで高尾山山頂部を周回する5号路と交差するはずです。
| コバノガマズミ |
コバノガマズミ。花序を見るとすぐにガマズミの仲間とわかりますが、葉が小ぶりでスマート。yamanekoはこちらの方がすっきりとした印象で好きです。この木はまだ5分咲きといったところでした。
時刻は11時40分。山頂も近くなりました。ここから300mほど先で1号路に合流するとすぐ山頂です。1号路はメインルートでありケーブルカー駅からの道でもあるので、きっと人でいっぱいでしょう。急に世界が変わるでしょうね。(後編に続く)