
高尾山 ~大人気の三ツ星の山~
 |
【東京都 八王子市 平成26年10月11日(土)】
秋の長雨も終わり、行楽の季節がやってきました。まだ台風はやってきますが、その合間を狙ってレジャーに繰り出す人も多いようです。この三連休も最終日の体育の日には台風19号が列島を縦断するとの予報。なので秋晴れのうちに出かけようと思います。
行き先は高尾山。紅葉にはまだ早いですが、きっと大勢の人で賑わっているでしょう。引っ越してから時間も距離もグンと近くなりました。昼から出かけても十分です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今日は妻と二人。ドリーム号に乗って町田街道を西進し、南八王子バイパスのトンネルを抜けて高尾山の玄関口の西側に出ます。このバイパスができてから都心方面からの車で渋滞する東側をパスして、空いている西側からアプローチできるようになりました。そして狙ったとおりスムースに駐車場に入ることができました。
| ケーブルカー駅 |
午後1時5分、ケーブルカーの駅前に到着しました。と言ってもケーブルカーで登るわけではなく、ここに起点がある「1号路」を歩いて登るのです。登山道ではありますが、山頂までずっと舗装路です。
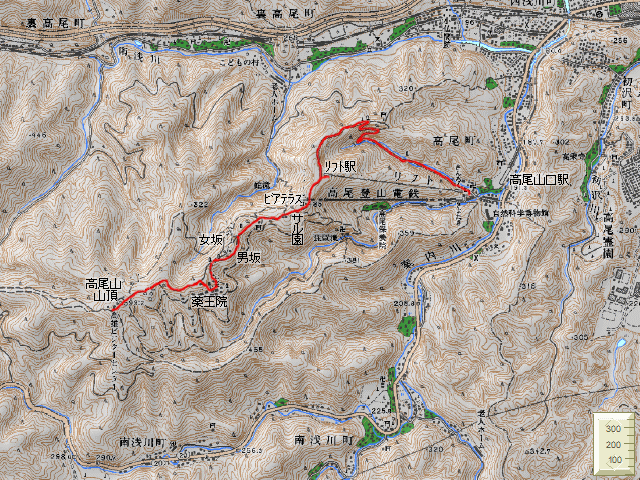 Kashmir 3D |
|
今日のルートは、1号路を歩いて稜線部に登り、リフトやケーブルカーの駅を過ぎて薬王院の境内を通り、そのまま山頂まで至るというもの。麓から登るルートとしては、他に谷筋を登る6号路とその谷を挟んで南側にある稜線を辿る稲荷山コースというのがあります。ちなみに2号路から5号路まではケーブルカー駅と山頂との間のサブルート(というか稜線上の散策路)になっています。
| 1号路 |
登り出しはこんな感じ。普通に舗装路ですね。ここは山上にある施設関係者の車両も通るようです。
| ツリフネソウ |
おっ、ツリフネソウです。周りはもうみんな実になっていますね。触ってみましたが、まだ弾けるほど熟してはいませんでした。熟した果実は触るとバババッと弾けて中の種を撒き散らすんです。
| ヤブミョウガ |
これはヤブミョウガの実。生えている環境が日陰のジメっとしたところなので、なんか地味な印象なんですよね。
| 六根石 |
これは「六根石」というものだそうです。車輪状の石に六根の文字(「眼」とか「耳」とかの五感の感覚器官と「心」の6文字だそうです。)が彫ってあって、これを「六根清浄」と唱えながら回すと、日頃の煩悩が取り除かれるのだそうです。薬王院の参道にはこの六根石が18個あるそうで、1個につき6回ずつ回すと煩悩の数とされる108回回したことになるという仕組み。薬王院も参拝者を飽きさせませんね。
| ツルギキョウ |
おお、これはツルギキョウではないですか。yamanekoは生で見るのは初めてです。なかなか出会うことのない花なんですよね、これが。実は熟すと赤黒くなるはずです。
| |
ジグザグの登山道で高度を稼ぎます。グループありカップルあり、みんな楽しそうです。
| コウヤボウキ |
だんだん花が少なくなっていく季節。コウヤボウキはそんな中でも遅くまで咲いていてくれます。
| |
少し傾斜が緩くなってきました。稜線が近いのか。
| カシワバハグマ |
立派なカシワバハグマ。堂々と立っています。花もちょうど満開。総苞片の部分が長くシーラカンスの鱗のようです。
| |
そのカシワバハグマの花にアサギマダラが来ていました。この蝶は同じキク科のヒヨドリバナやアザミなどに来ているのを見かけますが、この花にも来るんですね。あまり蜜がありそうな感じがしませんが。
アサギマダラは秋に列島を南下し、南西諸島から台湾の辺りまで移動することが知られています。この個体もこれから長旅を控えているのでしょうか。
| |
左手にリフトの山上駅が現れました。ここから先は「原宿か?」というくらい賑やかになります。
| |
リフト駅の前の広場から八王子方面の眺望が開けていました。その先、都心方面は靄っています。
| ビアマウント |
急に人が増えてきました。近くにケーブルカーの山上駅があって、観光客がどっと増えるんです。正面に見える建物は大人気の高尾ビアマウント。山の上にあるビアガーデンなんですが、ここから都心の夜景を見ながらビールを飲むというのがウケていて、この日も行列ができていました。まだ日が高いのに。この人気は都心から電車で1時間というアクセスの良さの成せる技なんでしょう。それにしてもわざわざ飲むためだけにここに来るか。まあ、仲間内でのレジャーにはほどよいのかもしれません。(yamanekoも飲みたかったですが、残念ながら車で来てるので…。)
| サル園・野草園 |
ビアマウントからしばらく行くと、サル園・野草園というのが現れます。10年前に入ったことがありますが、まあその名のとおりの施設でした。
| 浄心門 |
さらに進むと山門が。これは浄心門といい、この先にある薬王院の山門です。この門をくぐると道は男道と女道に分かれていて、男道は急な階段になっています。
| |
薬王院の境内に入ってきました。人が多いですね。山登りの格好をしているのは2割くらいでしょうか。あとは普通の観光客といった身なりの人たちです。この辺りからが薬王院の中心部になります。山腹の地形を利用していくつもの寺社仏閣が何段にも配されていて、それらを巡りながら登って行くとまるで城郭のような印象を受けます。
| |
参道の茶屋で買ったみたらし団子。写真を撮る前に思わずパクッとしてしまうほど美味そうでした(事実うまかった。)。1個の大きさが饅頭ほどもあり、食べ応えもありました。一串3個です。
| 本社(権現堂) |
一段上がると本殿があり、さらに一段上がると本社(権現堂)があります。両方とも立派な建物でしたが、本社の方は神社です。ここからさらに登ると奥の院があり、そのまた一段上に浅間社(神社)がありました。常に神社が一格上なんですね。
| |
浅間社を過ぎると薬王院の敷地外となり、また木立の中の道になります。ここから山頂まではわずかな距離です。
| |
この先が山頂。といっても広場のようになっていて、完全に公園です。
| 高尾山山頂 |
2時55分、山頂に着きました。
山頂はこんな感じ(通り過ぎてから振り返って見たところ。)。うん、公園ですね。
| |
広場の先には富士山の方角に開けた展望台になっています。人だかりができていますね。売店も大賑わい。
| 南西方向 |
展望台からの風景。富士山は中央やや右手の辺りにあるはずなんですが、逆光のうえに靄っていて、判別がつきません。
| |
こちらは東側を見下ろしたところ。写真の左端が南大沢(東京都八王子市)で、右端が橋本(神奈川県相模原市)の市街。直線距離にして4㎞くらいです。写真のちょうど真ん中辺りが都県境。 左手の東京都側が多摩丘陵、右手の神奈川県側が相模野台地で、地形が大きく異なっています。ちなみに台地と丘陵は年代によって区別されているそうで、約13万年~7万年前の最終間氷期の海面が高くなっていた時期に形成された地形面とそれ以下のものを台地、それよりも古くて標高が高いものを丘陵と呼ぶのだそうです。
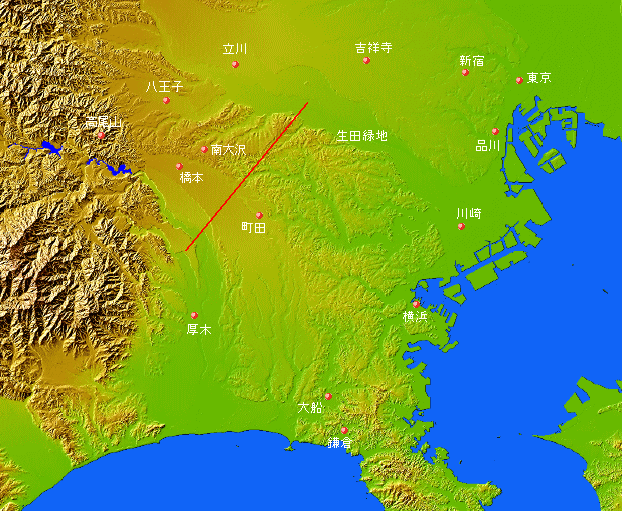 |
Kashmir 3D |
相模野台地は、相模川の左岸に位置していて、主に相模川が運んできた土砂で作られた扇状地が元になっている河岸段丘だそうです。ざっくり3~5段に分かれていて、台地上は関東ローム(箱根山や富士山の噴出物)で覆われています。
一方、多摩丘陵は、 広い平坦面のある台地と違って、その多くが谷戸によって複雑に刻まれています。これはかつて相模川が東に向かって流れていた頃の扇状地が元で、そこが谷戸によって下刻されたものだそうです。下刻前の地形が平坦面だったので、今でも丘陵の頂上の高さは一定に揃っているそうです。
上の地形図の赤腺部分での断面が下の図(高尾山側から見た図。)。
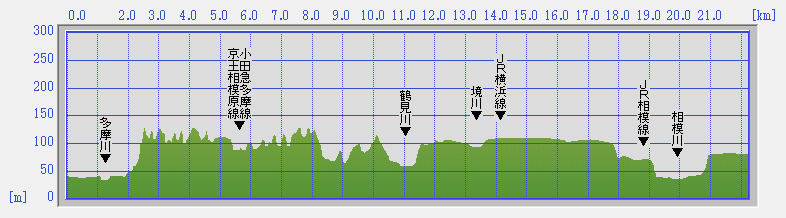 |
Kashmir 3D |
多摩川の右岸から急に立ち上がった多摩丘陵は、細かく刻まれているものの頂上部の高さはほぼ同じ。実際の風景としては一直線の稜線に見えます(こちら参照)。
鶴見川と境川の中間が丘陵と台地との境目で、相模野台地は段々になって相模川の河床まで下りて行きます。
| リフト山上駅 |
満足するまで景色を眺めたら下山です。陽が傾いてきたのでリフトで下りることにしました。
| |
リフトは、乗ってすぐ、斜面に飛び出していくところが楽しいです。ここのリフトは乗車時間が約12分。けっこう楽しめました。
今日はゆっくりと出かけたにもかかわらず、めずらしい花と出会えるなどサプライズもありました。こんなところが近くにあるのも幸せなことです。