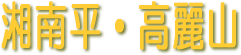
湘南平・高麗山 〜寒中暖あり 展望の山〜
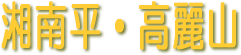 |
【神奈川県 大磯町 平成28年1月24日(日)】
暖冬で年が明けたと思ったら下旬になって強烈な寒波がやってきました。先週は都心でも積雪し、交通機関がガタガタになったりして。今週も西日本方面を中心に記録的な寒波が襲来し、なんと沖縄でも観測史上初めてみぞれが降ったそうです。そんな冬真っ盛りのこの時期ですが、天気がいいとやっぱり出かけたくなるもの。そこで温暖な印象のある湘南、その中でも常夏感のある大磯の小山を歩いてみろることにしました。大磯といえば大磯ロングビーチ。その昔、芸能人大水泳大会で記憶に残っている人も多いのでは。今でも現役で営業しているようです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
極寒の多摩丘陵からJR相模線で南下すること1時間ちょっと。大磯駅に降り立ちました。決して寒くないとは言いませんが、明らかに穏やか感がある、なんというか空気の尖り方が違う感じがします。さすがは湘南。
| 大磯駅 |
大磯駅は 明治20年の東海道本線の国府津までの開通と同時に開業した駅だそうですが、当初ここには駅の設置予定がなかったそうです。当時地元に住んでいた松本良順が海水浴を普及させるため(当時は療養目的)には駅の設置が欠かせないとして国に働きかけ、追加的に設置されたのだそうです。松本良順といえば幕末から明治にかけて活躍した医者で、新撰組とも親交があり、日野の高幡不動にこんな忠魂碑を建立しています。
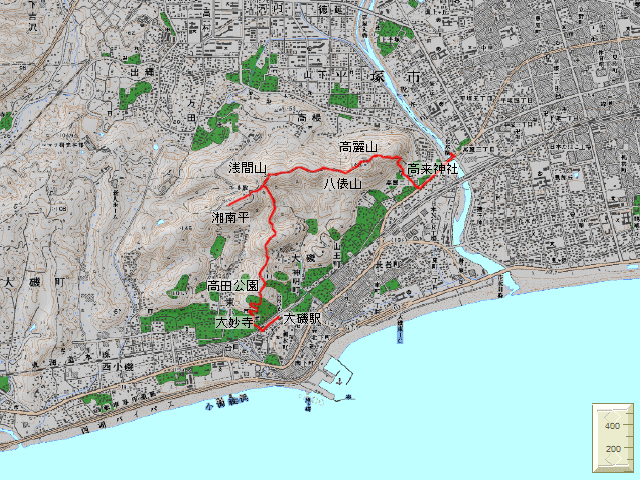 Kashmir 3D |
今日のコースは大磯駅の裏手に位置する丘陵に登り、湘南平で眺望を楽しんでから稜線に沿って東に歩いて高麗山へ。そこから麓の高来神社に下りてくるというものです。
駅横のコンビニで腹ごしらえをして、10時45分、スタートです。初めは線路に沿った路地を西に向かって歩いていきます。
100mほど歩くと左手に現れる大磯小学校の校門が目印。その反対側にあるガードをくぐっていきます。
| 妙大寺 |
ガードの先すぐ右手に立派なお寺がありました。ここは妙大寺といい、先の松本良順の墓所とのこと。ちょっと失礼してお参りさせてもらいました。どちらかといえば佐幕派の松本良順が維新後明治政府で軍医総監まで務めたということは、やはり医師として有能だったんでしょうね。
妙大寺を過ぎて最初の角を右に折れ、坂道を上っていきます。
突き当たりが壁のようになっていますが、道はつづら折れであの上に続いています。
| セイヨウキヅタ |
民家の擁壁を覆い尽くすセイヨウキヅタ。繁ってますね。それにしても陽当たりのいいこと。海に向かった南斜面ですからね。
なんとまだ紅葉が残っていました。やっぱり温暖なんですね。
ここはマチュピチュなのか? 天に向かって登っていくようです。
でそこからの眺め、ドーン。相模湾が一望です。ここに住んでいる人は毎日こんな眺望を楽しんでいるんですね。日常生活は大変かもしれないけど、この眺めがあるならお釣りがくるのかも。
住宅地の最上部近くまで上がると階段が現れました。ここを登っていくようです。
| 高田公園 |
階段の先には公園がありました。高田公園というようです。高田とは人の名で、解説板によると、明治から昭和初期にかけて活躍し、晩年大磯に住んでいた高田保という文筆家を偲んで作られた公園なのだそうです。温暖な土地柄なので晩年をここで過ごす著名人も多いんでしょうね。
| アオキ |
公園の先からは森の中に入っていきました。これはアオキの実。この先もずっと下山するまでアオキの赤い実が目を楽しませてくれました。
| 高麗山遠望 |
小さなアップダウンを超えていきます。正面に見える山が高麗山ですね。
急な階段と左への巻き道が現れました。ここは直進です。
| マルバウツギ |
これはマルバウツギでしょうか。渋い色合いをしています。
一年で最も寒いこの時期。こんな陽だまりの野山歩きが最高です。
| シルト |
ところどころにシルトの岩が露出しています。三浦半島などでもよく目にする逗子層を構成する岩で、砂より細かく粘土より粗い岩。砥石を柔らかくしたような感じで雨に濡れると滑りやすいです。もう砥石なんて使ったことのない人がほとんどなんだろうな。
崩落箇所を巻いて登っていきます。
11時30分、主稜線に出ました。ここは左に折れて、湘南平に向かいます。
| 湘南平 |
ほどなく山上に広がる公園に出ました。ここが湘南平です。ちなみに反対側の北斜面から車で上がってくることもできます。
上空に雲がかかり、周りは晴れているのにこの辺りだけ陽が差していません。芝生の上で車座になって宴会をしているグループがありましたが、ちょっと寒そうでした。
| 展望レストラン |
公園の奥にレストラン兼展望台がありました。そこそこ人が来ているようです。早速登ってみましょう。どんな展望が広がっているでしょうか。ワクワクを抑えながら最上階へ。
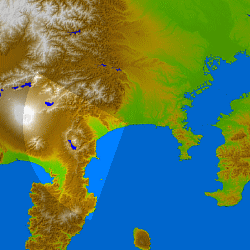 |
おお、これはなかなか。反時計回りにぐるっと360度を見てみましょう。まずは西北西から南南西。純白の山は富士山で、その左側の山塊は箱根山です。山並みはそのまま伊豆半島へと続いています。
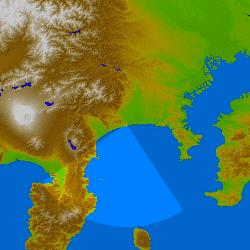 |
南西から南東。正面に広がる相模湾。眼下は大磯の海岸。正面の島影は初島です。 冬の弱い陽を反射して海原自体が発光しているかのようです。
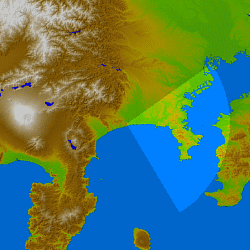 |
南東から北東。真東に向かって湘南海岸が延びています。茅ヶ崎辺りになります。遠く三浦半島や房総半島の山並みも見えていますね。鉄塔は湘南平の東端にあるテレビ塔です。富士山の方から伸びている帯状の雲のせいでこの辺り一帯が日陰になってしまっています。
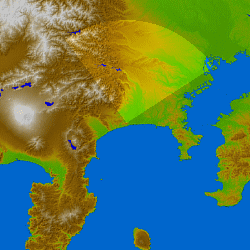 |
北東から北西。北東が都心の方向になります。平坦地が広がっていますが、これは相模川が作った河岸段丘の低地。双眼鏡で見てみると何層かの段丘面に分かれているのが見てとれました。段丘崖に当たる部分がグリーンベルト状になっているにで、それを境に面が異なっているのが分かるのです。 更にその奥には多摩丘陵が横たわっています。
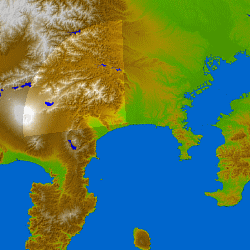 |
最後は北から西方向。堂々たる丹沢山塊。右の尖った山は大山、その左の薄雲を頂いたピークは塔ノ岳です。
ざっとこんな感じで360度。ここからの眺め、最高です。いくつかのスポットをアップで見てみましょう。
| 富士山 |
富士山も驚くほど近くに見えます。今まさにこの時に登っている人もいるのだろうか。極寒の世界でしょうね。
| 箱根 |
箱根の峰々。右端は金時山でその左は明神ヶ岳。いずれも外輪山に当たります。写真左側の山はカルデラの中に位置する冠ヶ岳や神山です。富士山よりずっと古い歴史を持つ山なんですよね。
| 江ノ島 |
こちらは江ノ島。案外こんもりとした島であることが分かります。奥は逗子辺りでしょうか。手前に沖に向かって長く突き出ているのは相模川の河口にある平塚港の防波堤です。
| 新宿副都心 |
新宿の高層ビル群。まるでミラージュのよう。関東平野辺縁のどこからでも見えるランドマークです。
| 丹沢山塊 |
丹沢は懐の深い山塊で、その中に幾多の峰を擁していますが、南側から望んで最も秀麗な姿を見せるのは塔ノ岳です。
展望台からの眺望を充分に堪能した後、12時5分、高麗山に向けて元来た道を歩き始めました。すぐに先ほど登ってきた麓の道からの合流点を通過。いたるところでアオキの赤い実が出迎えてくれています。ここから浅間山、八俵山とピークを踏んでいきますが、山といっても稜線上にある丘程度のものとのことです。
| 浅間山 |
で、ほどなく浅間山に到着。ここには一等三角点がありました。鳥居の奥に鎮座する小さな社は浅間社。江戸時代に富士山を神とする浅間信仰が盛んになった頃、本物の富士山に詣でるのは大変なので、富士山を望める各地に浅間社が建立され、そこにお参りすることでご利益を得ることができるとされたそうです。本物の方は女人禁制であったこともあり、各地の浅間社はずいぶんと賑わったのだそうです。
| ニホンスイセン |
枯野の中にもスイセンの花が。清楚な和装美人といった風情を感じます。
なだらかな起伏の稜線を歩きます。なんだかすっかり曇ってしまいましたね。
| 八俵山 |
12時25分、八俵山に到着。ここがピークであることはようやく看板で知らされました。昔、ここに毘沙門堂が建てられていたそうです。
堀切のようなところを橋で渡ってこの先の高麗山を目指します。高麗山は城郭としての側面も持っているとのこと。先ほどのパノラマで分かるとおり、高麗山からは相模湾や相模平野一体が見渡せることから、古くから軍事上の要衝とされていたそうです。室町時代には北条氏などが陣を構え、その後は相模平野と小田原城を結ぶ狼煙の砦が置かれたのだそうです。
| ヤブツバキ |
ヤブツバキ。この辺りからまた少し日が差すようになってきました。
岩の急坂が現れました。これを超えると高麗山の山頂のようです。右には山頂を巻いて麓に向かう道もありましたが、当然山頂に向かいます。
| 高麗山山頂 |
高麗山の山頂に到着。思ったより広いです。ただ樹木に囲まれていて眺望はなし。山頂はベンチにカップルが一組いるだけで静かでした。比較的新しめの小さな祠がありましたが、昔ここにあったという高来神社の上宮がこれなのかは不明。
ところで高麗山の「高麗」は高句麗のことで、朝鮮半島との関係があるんだろうとは思っていましたが、山頂の解説板に次のように記されていました。
「昔から日本と朝鮮の文化交流は深く、相模国をはじめ東国七州の高麗人を武蔵国に移して高麗郡を置いたと「続日本記」には書かれています。奈良時代のころ高句麗は唐・新羅に滅ぼされ、日本に難を逃れた人も多くその中に高句麗王族のひとり高麗若光もいました。若光は一族をつれて海を渡り大磯に上陸、日本に帰化してこの山のふもとの化粧坂あたりに住み、この地に大陸の文化をもたらしました。高麗若光と高句麗の人たちが住んでいたことから、この地が高麗と呼ばれるようになりました。」日本各地にある「高麗」というところにはこの類のエピソードがあるんでしょうね。それにしても日本には既に大規模な難民受入れの実績があったんですね。
| 参道 |
急な階段を下ります。この階段は上宮への参道だったんでしょうね。 途中現れた男坂と女坂の分岐は迷わず女坂へ。
| アオキ |
路傍にはアオキの実が。一見美味しそうではあります。
| 高来神社 |
12時45分、麓の高来神社に下りてきました。高来の読みは「たかく」ですが、別名を高麗神社ともいいその場合は「こま」となります。おそらく共通の音読み「こうらい」から充てられた名前でしょうね。
上空の雲が去り、急に陽が差してきました。境内の白梅も輝いて見えます。
参拝を終えて参道の中程で振り返ったところ。背後の山が高麗山です。あらためて参道を進み、国道1号線に出たところで左折して平塚方面に歩いていきます。
| 高麗山 |
花水川を渡って振り返ると標高以上に堂々とした高麗山が望めました。歌川広重の東海道五十三次の平塚宿の絵にこの高麗山が描かれています。昔の人も特徴的な姿を意識していたんですね。
さて、ここからはバスに乗って平塚駅へ向かいます。昼食を取っていないので、駅周辺で食べてから、茅ヶ崎乗り換えで相模線を北上し、橋本経由で帰宅です。今日は思わぬ絶景を楽しむことができ、新年最初に相応しい野山歩きになりました。